[#ページの左右中央]
作者――江戸川乱歩氏曰く
私は、最近、従来の「小探偵小説」を脱して、もっと舞台の広い「大探偵小説」へ進出したいと思っている。今回の『黄金仮面』は実にその第一歩である。
本篇活躍の主人公は、例のお馴染 の素人探偵明智小五郎であるが、彼も段々に成長しつつある。今度の小説では相当大きい活躍が出来る筈 だ。相手役の悪魔は恐らく読者を驚かせるに足る人物だと信じている。作者はその驚くべき人物を、果 してよく扱いこなせるかどうかを自 ら危 む程であるが、そこがまた本篇執筆について作者が一層興味を感じている所以 でもある……
私は、最近、従来の「小探偵小説」を脱して、もっと舞台の広い「大探偵小説」へ進出したいと思っている。今回の『黄金仮面』は実にその第一歩である。
本篇活躍の主人公は、例のお
「キング」昭和五年八月号
[#改ページ]
この世には、五十年に一度、
人間社会という一匹の巨大な
で、あのひどく
ある年の春、まだ冬
風評は非常にまちまちで、
ある若い娘さんは、銀座のショウウインドウの前で、その男を見たと云った。
胸をドキドキさせて、遠くの方から
ある中年の商人は、夜、東海道線の踏切を通って、無残な女の
いやそればかりではない。無表情な黄金仮面の口から顎にかけて、
又、一人の老婆は、ある真夜中、自宅の便所の窓から、外の往来をスーッと通り過ぎた
その外数限りもない風説を、一つ一つ並べ立てるのは無駄なことだ。
何かしら恐ろしい天変地異の前兆ではないかと云う者もあった。いや、石が降ったり、古池で赤坊の泣声がしたりする妖怪談と同じで、洗って見ればたわいもない
併し気の弱い人達は、夜更けの一人歩きに、ふとすれ違う洋服男が、オーヴァの襟でも立てていようものなら、若しや「あいつ」ではないかと、
これまでの所、この怪物はただ何かの凶兆の様に諸所に姿を現わすのみで、別に害をする訳ではない。鍍金仏の様な凄味を別にしたら、張りぼての広告人形と選ぶ所はない。で、警察は、この風評を知らぬではなかったけれど、
だが、黄金仮面は不良少年の悪戯やなんかでなかったことが、やがて分る時が来た。四月に這入って間もなくのある日、突如として、このえたいの知れぬ幽霊男は、
その年、四月一日から五ヶ月に
呼び物は色々あったが、建造物では、
国産真珠というのは、「
この真珠陳列場には、二十万円に相当する設備があった。頑丈な厚ガラスの扉には、特別の錠前がつき、その鍵は博覧会事務所に出張している真珠店の信用ある店員が保管し、番人も、一般に募集した少女ではなく、真珠店が
さて、博覧会開催第五日目の出来事である。その日はある高貴なお方の御来場を
大真珠「志摩の女王」の陳列された第一号館の建物は、貴賓
今まで雑沓していた館内が、見渡す限り、
大真珠陳列台の並びの一側には、四人の看守がついていた。真珠護衛係の中年男、その左右に五六間の間を置いて、十七八から二十歳位の少女看守三人、それから向うは、通路が曲っているので、見通しが利かず、つまりその部分はこの四人の持場といった形になっているのだ。
四人は看守控室でも、話友達であった。交代の時も一かたまりになって控室を出たが、その少し前に、誰かが四人の所へお茶を持って来て、
「高貴のお方の御顔を拝むんだ、お茶でも呑んで、心を鎮めて」
といいながら、一人ずつ茶碗を配った。
まだ博覧会が始まったばかりで、場慣れのしない四人の者は、
「オオ、苦い」
少女看守の一人が、思わず呟いた程、お茶は苦かった。
「少し入れすぎたかな」
男は笑いながら、茶碗を集めて向うへ行ってしまった。
間もなく、看守達は館内に這入って、定めの持場についた。陳列台の切れ目切れ目に小さな椅子があって、彼等は
「静かねえ、何だか気味が悪い様だわ」
一人の少女が、真珠の前の男看守にやっと聞える程の声で云った。誰も答えなかった。男看守も、外の二人の少女も、目を細くして、一つ所を見つめたまま、何か考え込んでいる。
「アーアー、睡くなって来た」
話しかけた少女は長い
やがて、途方もないことが始まった。四人の看守が四人共、ポッカリ口を開き、
その時一人の洋服男が、ソフト帽をまぶかに、オーヴァの襟を立て、大きなハンカチで顔を隠す様にして、何か急用でもあるらしく、急ぎ足で、居眠り看守の一廓へ近づいて来た。
外の通路の看守達は誰一人この男を疑うものはなかった。疑いをさしはさむには、彼の態度は余りにも圧倒的で、自信に満ちていたからだ。若い娘達は彼を御警衛の私服刑事と思込んだ。彼女等はそれが御巡覧の先振れでもある様に、
男は居眠り看守の一廓にたどりつくと、よく寝込んでいる四人の者を見廻わして、安心した様に顔のハンカチを取った。ハンカチのうしろから現われたものは、云うまでもなく、ゾッとする程無表情な、金色の顔であった。
黄金仮面はツカツカと、大真珠の陳列台に近づき、ガラスに顔をくっつけて、燦爛たる「志摩の女王」に見入った。彼の黄金の鼻の頭が、ガラスに触れて、カチカチと鳴った。金色の三日月型の口から、異様な呟き声が洩れる。怪物は今、喜びに震えているのだ。
ガラス切断の小道具は、ポケットに揃っていた。何という手際、
アア、日本真珠の誇り「志摩の女王」は、遂に怪物の手中に帰した。彼は
その刹那、ジリリリ……と、けたたましく、建物の高い天井に鳴り響く電鈴の音。
怪物は「アッ」と
盗難防備の秘密装置というのは、この電鈴仕掛けだった。天鵞絨の台座に何かが触れると、
続いて場内に湧起る、少女看守達の悲鳴、逃げまどう足音。だが、そこにいたのは頼み
奇妙な鬼ごっこが始まった。陳列台と陳列台の作る迷路を、
到底逃げおおせることは出来ないと見た怪物は、せめて、最も手薄な追手の方面を目がけて、こちらから突き進んで行った。
そこには、小さい出入口を背にして、一人の警官が立ちはだかっていたが、賊が捨身に突進して来るのを見ると、サッと青ざめて、併し勇敢に大手を拡げた。
二つの肉団が、激しい
だが、警官は到底金属製怪人の敵ではなかった。アッと思う間に、彼は大地に投げ倒されていた。
怪物は建物の外に消えた。ワッと起る追手の
そこは建物の裏手に当り、五六間向うには別の建物のこれも背面が聳えている。左右は行き抜けだけれど、見物人が入り込まぬ為に、両方の端に鉄条網みたいな柵が設けてある。その外は会場の大道路だ。今日は貴賓御警衛の為に、大道路には数名の巡査の姿が見える。
「オーイ、今その柵を越した奴はないか」
一人の警官が怒鳴ると、左右の大道路に立番をしていた巡査が一斉にこちらを向いて、口々にそんな奴は見なかったと答えた。
人々はお互に顔を見合せて立ちすくんでしまった。逃道はないのに、賊の姿が消えたのだ。
「オイ、この正面の建物は何だ」
「演芸館の裏口です。ここから向うが余興場になっているのです」
「開演中かね」
「エエ、ホラ
「まさか、奴、開演中の群集の
「だが、左右の道路へ逃げなかったとすれば、いくら無茶でも、奴はここへ飛込んだと考える外はない。蒸発してしまったんでなけりゃね」
「兎も角
一同は演芸館の裏口から、ドヤドヤと這入って行った。
お話変って、その時演芸場の舞台では、喜劇「黄金仮面」の第一幕目が終った所であった。何も知らぬ数千の見物達は、舞台上の
新時代の幽霊「黄金仮面」のすばらしい人気を当て込んだ
ところが、喜劇に笑いこけていた見物達は、
「皆さん、唯今この裏の陳列場から、有名な大真珠を盗んで逃げ出した
場内のざわめきで、途切れ途切れにしか聞えなかったが、大体の意味は分った。
「そいつはどんな風をしているのです」
勇み肌の職人体の男が、役者を弥次る様な声で怒鳴った。
「そいつは一目見れば分ります」警官は答えようとして、一寸
併し外に適当な呼び方もない。
「金製の面をかぶった奴です。噂の高い黄金仮面です」
ドッと笑い声が起った。突然、今演じつつある喜劇の主人公の名前が出たからだ。ある者は、この巡査も実は役者の扮装したもので、こんなおどかしを云って、あとで大笑いをさせる魂胆だろうと思った。
だが、舞台の警官は一向種を割る様子がない。あくまで厳粛な青ざめた顔で、同じ事を繰り返し怒鳴っている。
その様子を見ると、見物は笑えなくなった。場内はシーンと静まり返った。人々は自分の隣席の見物達を、疑い深い目でジロジロと眺め廻した。自分の腰かけている椅子の下を怖わ怖わ覗いて見るものもあった。
併し、
感興を妨げられて憤慨した見物達が、ブツブツ
警官も結局あきらめて引込む外はなかった。
その騒ぎが一段らくつくと、やがて遅れた第二幕目の緞帳が捲かれた。
舞台は夜の公園の光景である。背景は黒幕、その前一面に深い樹立の体、光線といっては、青っぽい常夜燈がたった一つ。怪談めいた場面である。
先ず数人の仕出しが出て、「黄金仮面」の噂を
で、愈々怪物が姿を現わした。前幕と違って、顔ばかりでなく、全身をダブダブしたマント様の金色の衣裳で包んだ、変な恰好だ。それを見た臆病者の大げさな仕草、当然見物席に
やがて、この幕第一の見せ場が始まる。
と、どこからともなく、シューシューという、変な音が聞え始めた。同時に、仮面の黒く割れた口が少しずつ形を変えて、遂に大きな三日月型の、笑いの表情になった。見物達が思わずギョッとして、耳をすますと、シューシューという音は、怪物の笑い声であることが分った。アア、何といういやらしい笑い声だったろう。いつまでもいつまでも笑っている。そして、見ると、笑いながら彼は血を吐いているのだ。細い細い糸の様な一筋の血が、ツーッと顎を伝って、その末は、顎の先から、ポタリ、ポタリと雫になって落ちているのだ。
喜劇と知りながらも、余りの怖さに、見物は息を呑んで、静まり返って、怪物の顔から目をそらす力もない。
云うまでもなく、脚色者は、例の踏切りで怪物に出逢ったという商人の話を、そのまま劇中に取入れたのだ。又、全身金色の衣裳は、老婆の実見談から思いついたものであろう。
見物中の敏感な少数の人は、
それらの人々は、一秒一秒と時のたつのが恐ろしかった。「今にも、アア、今にも」彼等は外の見物の咳ばらいの音にも、ギクンと飛上る程、おびえ切っていた。
突如、舞台が明るくなった。怪談から喜劇への転換だ。そこへ臆病者の知らせによって、三人の滑稽なお巡りさんが駈けつけて来る。
ある予感に震えていた少数の見物人は、それを見ると、思わずアッと叫び相になった程だが、一般の群集は、反対にゲラゲラ笑い出した。
お巡りさんの一人が、怖々怪物に近寄って、出来る丈け
「コラッ、貴様、その面をとれ。顔を見せろ」
黄金仮面は聞えぬものの如く、ボンヤリ突立っている。電燈に
「聞えんのか。オイ。返事をしろ。顔を見せろ」
いくら怒鳴っても黙っているので、たまり兼ねた一人のお巡りさんが、いきなり怪物に飛びかかって行った。けたたましい靴音、帯剣の
到頭大変なことが始まった。追いつめられた黄金仮面は、金色の衣裳を
「やっぱりそうだ。やっぱりあいつだ」
例の敏感な見物の一人が、真青になって思わず呟いた。だが、見物席全体の哄笑は一層ひどくなった。この役者達のずば抜けた悪ふざけが、彼等の御気に召したのだ。
怪物は椅子と椅子との間の細い通路を正面に向って走り出した。お巡りさん達も舞台を飛び降りて彼のあとを追った。
「
お巡りさんの真に迫った悲痛な叫び声。だが、見物の笑いは止まらぬ。
「やれ、やれ、しっかりやれ」
弥次馬が面白がって、
人々は、この奇妙な追っかけは、見物席を一廻りして、又舞台に戻るものと信じ切っていた。だが、怪物はどこまでも真直ぐに走って行く。
監督席の前を通り過ぎた。その席には二名の警官が、見物と一緒になって笑いこけている。
「君、そいつを逃がすな。オイ、馬鹿ッ、間抜けッ、何をボンヤリしているんだ」
追手のお巡りさんが走りながら気違いの様に怒鳴った。併し監督席の警官には通じない。それもお芝居のせりふの内だと思い込んでいるからだ。
その時、舞台に数名の、明かに役者でない人々が立現われ、ドカドカと見物席に飛降り、お巡りさんのあとから走り出した。その中には、見覚えのある、さっき幕外で見物達に話しかけた警官の顔も見えた。
鈍感な群集にもやっと事の真相が分った。笑い声がパッタリ静まった。一瞬間死の様な
だが、その時分には、怪物はとっくに木戸口を脱出して、会場内の広っぱを、まっしぐらに走っていた。
こんな風に書いていると長い様だが、舞台が明るくなってから、怪物の姿が木戸口の外に消えるまで、
それにしても、何たる奇怪事、何たる大胆不敵のトリックであろう。舞台で喜劇を演じていたのが、恐ろしい真珠泥棒、本物の黄金仮面であったのだ。お巡りさんも役者ではない。真珠陳列場から犯人のあとを追った正真正銘の警官達だ。彼等は演劇の中途で、やっと怪物のトリックを看破し、開演中をも構わず舞台に躍り出した。それが偶然喜劇の筋書と一致したのである。
舞台とお芝居の重複、一体全体何がどうしたのか、舞台監督も、役者も、道具方も、見物達も、思考力が滅茶苦茶にこんぐらかって、余りのことに開いた口がふさがらぬ有様だ。
これは後に分ったことだが、読者諸君の為に附加えて置くと、騒ぎが一段落ついたあとで、所管警察の署長が興行主を呼んで、黄金仮面に扮した役者の身元を
どうして芝居を休んだのかと尋ねると、
「どうも相済みません。慾に目がくれましてね。見も知らぬ紳士でしたが、早朝私を訪ねて参りまして、今日一日外出しないという約束で、五十円現なまを貰ったのです。誠に申訳ありません」
という次第だ。つまり黄金仮面はその役者にばけて、朝から博覧会の演芸場の楽屋に納っていたのだ。貴賓御巡覧の為に場内がひっそりするのを待って、楽屋口を抜け出し、四人の看守に麻酔薬を呑ませて置いて、真珠陳列場へ忍込んだ。そして、何食わぬ顔で、又元の楽屋へ引返し、喜劇「黄金仮面」の主役を演じさえしたのだ。金製の仮面という絶好の隠れ蓑があった。同僚の役者達も、役柄故、彼が楽屋にいる時も、仮面をかぶり続けていたのを、さして怪しまなかった。それに、彼は座頭格で、小さい楽屋部屋を独占していたものだから、不思議と化の皮がはげなかったのであろう。
一見、
やっと演芸館を抜け出した怪賊は、今度は広っぱの大群集と戦わねばならなかった。その方がどれ丈け困難か分らない。実に
四方から迫る警官群、弥次馬の石つぶて、その中を、金色燦爛たる、併し見るもみじめな怪賊は、汗みどろの死にもの狂いで、右に左に逃げ廻った。
人なき方へ、人なき方へと逃げているうち、彼は貴賓御通行の御道筋へ出てしまった。
ふと振向くと、すぐうしろ十間ばかりの所に、丁度一つの建物をお出ましになった貴賓の一行が、しずしずと進んで来られるのと、パッタリ顔を合わせてしまった。
仰天した警衛の警官達が、ソレッと云うと、八方から怪賊の身辺に駈け寄った。そして、彼等が折重なって、今や賊を
見ると、賊の手に光るものがある。ピストルの筒口だ。彼はその時まで最後の武器を隠していたのだ。
人々のひるむ隙を見て、
だが、意外意外、怪人は御一行の前に直立不動の姿勢をとったかと思うと、ピストル持つ手を胸に当てて、うやうやしく
礼を終ると、彼はクルリと廻れ右をした。そして、反対の方角に、
走るに従って、うしろざまに飜る金色の衣、それに折からの夕陽が、まばゆいばかりに照り輝き、怪人の飛び去るあとには、黄金の虹が立つかと見えたのである。
だが、群集がうっとりしていたのは、ホンの一瞬間だ。ハッと正気に帰ると、又しても猛烈な石つぶて。一層数を増した警官隊の追撃。
大道の極まる所に、怪賊
進退
階段が尽きると、百何十尺の空中に、探照燈を据付けた、四方開っぱなしの、火の見
賊は、探照燈係の道具類を入れた木箱に腰かけて、ホッと息をついた。だが、休む
彼は小さな部屋をグルグル走り廻った。だがどこに血路のあろう筈もない。柱につかまって地上を見下すと、
頭の上には、道化師のとんがり帽子みたいな、急傾斜の屋根があるばかりだ。だが、もうこうなっては、その屋根へでもよじ昇る外には、助かる工夫はない。
警官隊の先頭は、已に階段を昇りつくして、頭とピストルの手先が、床の上に現われて来た。愈々最後である。
黄金仮面は遂に驚くべき決心をした。不可能なことをやって見ようというのだ。
彼は両手に屋根の一端をしっかり掴むと、機械体操の見事な手並で、尻上りに屋上に身をのせた。併し、その屋根は、まるで断崖の様な、とんがり帽子型だ。どこに一箇所、足場もなければ手をかける所もない、しかもそこは、目もくらむ百五十尺の高空なのだ。
見るも無残な大努力。彼はさかさまに
さて、向きを換えてしまうと、今度は頂上への、もどかしい
丁度その時、にじむ油汗の為に足の力が抜けた。ハッと思うと、ズルリ、全身が辷った。ワーッと上る群集の叫び声。
だが、何という底力だ。怪人は最後の一寸で踏みこたえた。彼の全身はその努力の為に地上からも分る程波打っている。そして、一休みすると、又頂上へと蠕動だ。
遂に、遂に、彼の右手は頂上の柱を掴んだ。手係りさえ出来れば、もう何の
この離れ業の間、屋根の下の警官隊は、空しく騒ぐのみであった。いかに勇敢な警官も、この切っ立てた屋根へ昇る元気はない。人間業では出来ぬことだ。と云って、ピストルで
頂上の部屋から、
で色々議論の末、結局一同地上に降りて、そこから銃をさし向け、その威力で賊を降服させようということになり、附近の有志が持出した鳥銃や、憲兵隊の鉄砲を借りて、十数梃の筒先を揃え、空砲を放ったりして、しきりに
残る手段は、気長に包囲を続けて、彼が疲労の極、降伏するか、地上に落ちて来るのを待つのみである。
騒ぎの内に、日はとっぷりと暮れてしまった。黄金仮面の光りも失せ、巨人の様な高塔が、おぼろに見えているばかりだ。塔上の探照燈は、今夜に限って光を発せぬ。係りのものが怖がって、昇ろうとせぬからだ。
塔の下には、警察や青年団の
日が暮れて一時間もすると、人々の胸に一種の不安が湧上って来た。怪物は依然として元の場所にいるのだろうか。もう笑い声も聞えて来ぬ。闇の空の豆粒程の人の姿を見極めることは出来ぬ。と云って、どこにも逃げる所はないのだが、妙なもので、暗闇が人を臆病にする。敵の姿が全く見えぬのでは、何だか不安で仕方がない。
そこで一人の警官が名案を持ち出した。博覧会場内には、この塔の
程もなく、強烈な円光が、塔の屋根全体をクッキリと闇の空に浮き上らさせた。
群集は瞳をこらして、頂上の柱を見た。
と、その刹那、ドッと湧起る驚愕の叫声。塔の頂上には、全く予期しなかった大椿事が起っていたのだ。賊の姿が消えたのではない。黄金の守宮は、もとの屋上にへばりついている。だが、だが、アア、これはどうしたことだ。人々は余りの意外な出来事に、空を見上げたまま、
「産業塔」をとり囲んでいた数千の群集は、その時、探照燈の
屋根の頂上の金色の棒から、ブランと下って、巨大な時計の振子みたいに、右に左に揺れている、黄金の守宮、その鍍金仏の様な、仮面の
塔上に追いつめられて、進退
「死んだ」「死んでしまった」
数千の群集の口から、同じ言葉が、どよめきとなって響き渡った。彼等はこの悪魔の死に安堵を感じたのか。イヤイヤそうではない。彼等は激しい失望に襲われたのだ。この金色の英雄の、余りにもあっけない、死を痛む嘆息だ。
警官の一隊は直ちに塔上へ駈上ったが、怪物ならぬ彼等には、足場がなくては屋根へ昇る力はない。イヤ、屋根の出張りが邪魔になって金色の縊死体を見ることさえ出来ぬ。何を慌てているのだ。駈け上る先に、足場を
「誰か、博覧会の建築事務所へ走って、足場の材料を持って仕事師をつれて来る様に云ってくれ給え」
警部が命ずると、隅の暗闇から、博覧会使用人の制服制帽をつけた、背の高い男がヒョッコリ出て来て、モグモグと何か云った。
「私が行って参りましょう」
という様に聞えたが、何となく人間離れのした
「アア、君も昇って来ていたのか。探照燈の係だね」
「ハイ」
「じゃ、君一走り行って来てくれ給え」
探照燈係は、飛ぶ様に螺旋階段を降りて行った。
残った警官達は、イライラしながら、手持無沙汰に
「アア、あいつ、ピストルをこんな所へ落して行ったのだな」
一人の警官がそれを拾い上げて一同に示した。
「ナアンだ。それじゃ、屋根へ昇った時には、あいつ、ピストルを持っていなかったんだ。何もビクビクすることはなかったんだ」
他の警官が呟いた。
「オヤ、変だぞ」ピストルをひねくり廻していた警官が頓狂な声で云った。「オイ、諸君。僕たちがあんなにおどかされた、このピストルは、君、おもちゃだぜ」
検べて見ると、確かにおもちゃのピストルだ。賊は芝居の楽屋にあった小道具のピストルを持出して、さも本物らしく振廻していたのだ。
警官達の間に低い笑声が起った。だが、その笑声は何か気まず
仕事師がなかなかやって来ぬので、又一人の警官が事務所へ走った。そして、愈々足場が出来上ったのは、それから一時間もたった時分であった。
賊の死骸を取りおろす役目は、管内の消防夫
流石商売柄、粂さんは、何の危なげもなく、急傾斜の屋上へ昇って行った。屋根の下へ張り出された足場には、二人の仕事師が死骸を受取る為に待ち構えている。
地上の群集は、待遠しかった足場がやっと出来上り、土地の人気者粂さんの姿が、探照燈の円光の中に現われると、ドッと歓呼の声を上げた。
闇の中空に浮いた、巨大な白いとんがり帽子を、これは
粂さんは遂に頂上に達した。黄金仮面の死体に手が掛る。と見ると、これはどうしたのだ。この消防夫は、気でも違ったのか。金色の死体を革帯からはずすや否や、軽々と一振り振廻して、ポイと、その百五十尺の上空から、地上目がけて投げつけたのである。
黄金の衣裳は、キラキラと不思議な花火みたいに飜って、探照燈の円光をはずれ、闇の中を、流星の様に、群集の目の前の地上に落ちた。
落ちたと見ると、ワッという
賊はまんまと逃げ去った。だが、どこから? どうして? 不可能だ。塔のまわりは群集の
塔内へ潜伏しているのではないかと、厳重な捜索が行われたがどこの隅にも影さえ見えぬ。
警官達は捜索の手段も尽きて、一同塔の階段の下に、ボンヤリ佇んでいた。
「しかも、あいつは
「変だね。これ丈けの群集が、いくら夜だと云っても、真裸体の男を見逃がす筈がないじゃないか」
「オイ、あいつは変装用の衣裳を手に入れることが出来たかも知れないぜ」
警官の一人が変なことを云い出した。さい前、おもちゃのピストルを発見した男だ。
「君は一体何を云っているのだ」
他の一人がびっくりして相手の顔を眺めた。
「あいつは、屋根から頂上の部屋へ降りる時は、如何にも真裸体であったかも知れない。だが、頂上の部屋へ来れば、あすこには、お
「どこに?」
「探照燈係の道具箱の中さ。あの中に、博覧会の使用人の制服が入れてあったというのは、あり相なことじゃないか」
「想像に過ぎない。確めて見なければ、……」
「確める? 無論さ。見給え、あすこへ探照燈係の男がやって来た。あれに聞けば直ぐ分ることだ。オイ、君、君はここの探照燈係だろう」
「エエ、そうです」
相手の制服の男が答えた。
「探照燈室の道具箱の中に、君の着換えかなんか入れてなかったかね」
「エエ、私のではありませんが、もう一人の男の制服制帽が這入ってます」
「その男は」
「今日は病気で休んでいるのです」
何だか話が変梃になって来た。
「では、さっき、塔の上から建築事務所へ仕事師を呼びに行ったのは、一体誰だったのだろう。君ではなかったね」
「エエ、私は一度も塔の上へ昇りません」
「アア、ひょっとしたら。……兎も角、あの道具箱を検べて見よう」
探照燈係を引っぱる様に、一警官が塔上へかけ上った。道具箱を開いて見ると、果して、そこにある筈の制服制帽が消えてなくなっている。
果して、果して、大胆不敵の怪賊は、又しても警官隊と群集を小馬鹿にして、彼等の注意力の盲点を巧みに利用し、まさかと思う探照燈係その人に化けて、まんまと重囲を脱出してしまったのだ。黄金仮面の字引には、恐らく「不可能」という文字がないことに相違ない。
直ちに、警官隊、青年団が八方に飛んで、場内を隈なく捜索したが、無論手おくれだ。あの敏捷な怪物が、一時間以上も危険な場内にウロウロしている筈はない。
警官達は、半日以上の大骨折りの末、やっと塔上に追いつめた怪物を、もう一息の所で取逃がした無念さに、足ずりをしてくやしがった。せめて、探照燈係りに化けた賊の顔を見覚えているものはないかと探したが、塔上の小暗い部屋ではあったし、あとで考えて見れば、怪物は制帽をまぶかにして、
「道理で変でしたよ。僕が建築事務所へ行った時に、まだ誰も知らせに来たものはないといって、皆、変な顔をしていました」
二度目に仕事師を呼びに走った巡査が云った。探照燈係りに化けた賊は、無論、事務所などへ立寄りはしなかったのだ。
翌朝の各新聞は、地方新聞に至るまで、全国的に、すばらしい大見出しで、上野博覧会に於ける前代未聞の大活劇を、詳細に報道した。少々ボンヤリしていたが、粂さんが足場から尖塔へと這い上っている写真などは、新聞効果
だが、少くも東京市民は、その記事を、単なる興味を以て
黄金仮面の下に隠された、賊の正体が何物であるのか、全然不明なことが、一層人々を怖がらせた。又、敏感な読者達は、新聞記事の一警部の談話中に含まれた、一種身震いの出る様な不気味な一節を、どうしても忘れることが出来なかった。その一節というのは、
「探照燈係りに化けた賊は、ただ背が高いという特徴の外に、何も記憶していないが、その時たった一口物を言った、あいつの声を聞くと、何とも云えぬ変な感じがした。言葉も非常に曖昧だったが、それよりも、声の調子が、何といっていいか、どうも我々と同じ人間の口から出たものとは思われぬ様なものであった。云々」
これは
怪物は、大真珠「志摩の女王」を奪い取った丈けで鳴りをひそめてしまうだろうか。イヤイヤ、それは考えられぬ事だ。彼は必ず、再びあの不気味な姿を、どこかに現わすに違いない。いつ? どこへ? そして何を? 彼の目的物が常に財宝に限られているとは
この東京市民の恐怖は、当っていたし、又当っていなかった。というのは、怪賊は果して、僅々数日の後再び聞くも恐ろしい大犯罪を企てたが、その場所は、何という出没自在、意外にも東京から遠く離れた
鷲尾侯は
十九歳の美子姫は、侯爵の
その日、姫は書斎の窓に
思うは、遠き異境に遊学中の
眼に浮ぶは、いつかあちらから送って来た、千秋さんのクリケット遊戯の勇ましい姿、続いて同じ大学の有名なボートレースのこと、そして、かぐわしき洋酒と西洋煙草の香り漂う、漠然たるヨーロッパ大陸の
それにつけても心に懸るは、今日、父侯爵の古美術蒐集品を観賞する為に、東京から
すぐ目の下の塀の外にうろうろしている背広服の男。あれは警察からよこしてくれた私服刑事達だ。一人二人三人、表門
そこへ突然、真青な顔をして駈け込んで来たのは、姫の御気に入りの侍女の
「御嬢さま、わたくし、もうもう、こんなゾッとしたことはございません。どうしましょう。どうしましょう」
「マア、小雪、どうおしなの」
「わたくし、今、御部屋に生ける花を探しに、
「エエ、それで」
「あの小暗い森の中を、何気なく見たのでございます」
「エエ」
「すると、お嬢さま」小雪は震え声で、囁く様に「私見ましたの。アレを……」
「金色の……」
姫はゾッとして思わず立上った。
「黄金仮面……」
「お前、本当に御覧なの」
「エエ、森の茂みの奥から、あの、三日月型の口で笑っている様に見えたのでございますの」
「で、お父さまに申上げて?」
「
心臓のしびれてしまう様な恐怖に、二人はおびえ切った目と目を見合わせて、黙り反っていたが、やがて姫が
「一体そのものは、ここで何をしようと企らんでいるのでしょう。盗みでしょうか、それとも、もっと外に何か恐ろしい目的があるのではないでしょうか」
気の毒な美子姫は、怪物黄金仮面と彼女自身の運命とが、恐ろしいつながりを持っていようなどとは知る由もなく、ただ漠然とした恐怖に、唇の色を失って、打震えるばかりであった。
そこへ父侯爵の姿が見えた。
「アア、お父さま」
「小雪が喋ったのか」
侯爵はその場の様子を見て取って、お喋りの侍女を叱る様に云った。
「お父さま、警察の人達は、そのものを捕えまして?」
「イヤ、残る
とは云うものの、侯爵とても、一抹の不安を隠すことは出来なかった。
「決して、御前さま。幻やなんかではございません。わたくし、いくら何でも、そんな
小雪の抗弁を聞き流して、侯爵は、話題を変えた。
「美子、もう御客さまの見えるに間もあるまい。御出迎えの用意をしなければなりません」
「でも、邸内にまで、そんなものが這入り込んで来ますのに、お客さまをお迎え申上げても、よろしいのでしょうか」
「それは、
侯爵は寧ろ自から慰むるが如く、力をこめて云うのであった。
それから一時間程たって、F国大使ルージェール伯爵は、秘書官と通訳を伴って、大使館紋章入りの大型自動車を鷲尾侯爵邸の車寄せに横づけにして、侯爵、美子姫、執事の
ルージェール伯は、その年二月下旬、信任状を
伯爵は、この国を訪れた外国人の例に漏れず、いやその中でも殊更らに日本古美術の非常な愛好者であった。彼はこの二ヶ月の間、要務の余暇には、京都奈良の博物館、神社仏閣を巡覧して、東洋美術の賞美に日も足らぬ有様であったが、そうした公共の場所丈けでは満足が出来ず、名家の珍蔵にかかる名画仏像等の観賞を思立ち、鷲尾侯爵家は、そのプログラムの第一に選ばれた訳である。
美術館は母屋から離れて、新しく建てられた、コンクリート造り二階建ての、百坪に余る建築だ。先ず三好執事が持参の鍵を以て、入口の大扉を開くと、侯爵を先頭に、大使一行、美子姫、三好老人の順序で、館内に這入って行く。
土蔵風の建物で窓が小さい為に、館内は昼間でも電燈が輝いている。高い天井、冷え冷えとした空気、防虫剤のほのかな匂い、その中に立ち並ぶ
侯爵は先頭に立って、一歩美術館に足を踏み入れた時、異様な恐怖を感じないではいられなかった。
「若しや怪賊は、この貴賓来訪の時を待構えていたのではあるまいか。どういう手段かは分らぬ。だが、この
そう思うと、侯爵は、小暗い物蔭が気になって、伯爵への受け答えさえ、おろそかになり勝ちであった。
だが、ルージェール伯は、思いもかけぬ素ばらしい観賞家であった。彼は日本支那の美術史にも詳しく、通訳官を通じての批評、
一行は徐々に進んで、二階への階段の下に達した。その階段の裏の三角形の暗所に、ふと見るとハッとおびえないではいられぬ一物がある。比較的新しい時代の、金色燦爛たる、等身大の鍍金仏だ。それが、ほの暗い電燈に、異様な光輝を放って、ニョッキリと突立っているのだ。
美子姫は、美術館へ這入った時から、遠くの隅の、その鍍金仏を、目も離さず見つめていた。黄金の顔、……黄金の衣、……若しやあの仏像は生きているのではないかしら、というギョッとする様な妄想に、彼女はおびえ切っていた。
近づくに従って、その大男程もある仏像が、金箔の内側で、ひそかに、ひそかに、呼吸をしている様にさえ思われる。アア、今にも、今にも、あの柔和な口が、キューッと三日月型に曲って、糸の様な血を吐きながら、ニタニタと笑い出すのではあるまいか。と思うと、ゾーッと総毛立って、いきなり大声でわめきたい衝動を感じるのだ。
父侯爵も、娘程ではないけれど、同じ思いに悩まされていた。彼は鍍金仏の前に近々と顔を寄せ、突き通す様な恐ろしい目で睨みつけていたが、突然、ヒョイと手を出して、仏像の腕を力まかせに掴んで見た。若しやそれが、生きた人間の腕の様に生温く、柔いのではないかと考えたからだ。
「アハハハ……」ルージェール伯は、侯爵の心持を察して笑い出した。「では、『金の仮面』と云われている盗賊は、まだ捕縛されないのですね。恐らくその賊は、この仏像みたいな顔をしているのでしょう。キッとそうでしょうね、侯爵」
侯爵は大使の言葉に、臆病過ぎた
その時である。突如として、美子姫の口からほとばしった、絹を裂く様な悲鳴。人々は不意をつかれて、飛び上った。姫の飛び出す程見開かれた両眼が、鍍金仏の背後の小窓に、釘着けになって、顔色は紙の様に白く、今にも卒倒せんばかりである。
見るとその小窓に奇怪な人間の顔。
侯爵はいきなり小窓へ飛んで行って、ガラス戸を開いた。
「君、一寸待ち給え」
侯爵が怒鳴ると、男はクルッと振返って、ニヤニヤ笑いながら一礼した。肩まで垂れた長髪の上に、アイヌの酋長みたいな顔中髭だらけの、薄気味悪い人物だ。
「君は、一体誰です。今何をしていたのです」
侯爵の詰問に、相手の男が答える前に、突然
「
「分った、分った。君の信仰している天理教の教師だね」侯爵は、怪人物の素姓が分ると、安堵して云った。「だが、再びこんな粗相のない様に、君からよく云って置く方がよい」
三好執事は天理教の狂信者で、門内の彼の住居には、時々説教旅行の教師が泊り込んで行く。木場さんというのもその一人で、見ず知らずではあったが、教会の確かな紹介状を持参したので、三好老人は安心して泊めて置いたのだ。どうして覗いたりしたのかと尋ねて見ると、新任のフランス大使閣下の御顔を一目見たかったのだと答えた。
さてそれからは別段の出来事もなく、大使一行の美術品巡覧は主客とも充分の満足を以て終った。
美子姫は毎夜ベッドに這入る前に、
姫が侍女の小雪に手伝わせて、着物を脱ぎ、大理石の浴槽に身をつけたのは、もう十二時を過ぎていた。
純白の大理石に照り
透明な湯の中に、平べったく浮上って見える、ねっとりと白い肌。姫も世の多くの女達の例に
うっとりと物思いに耽っている内に、姫はふと襲いかかる様な深夜の静けさにおびえて、小雪に話しかけようと、うしろを振向くと、いつの間に立去ったのか、侍女の姿は消えていた。
「どこへ行ったのかしら、きっと着換の寝間着を取りに行ったのでしょう」
と心待ちに待っていても、小雪はなかなか帰って来ぬ。
耳をすますと、しんと静まり反った、夜の中に、
浴槽を出るのはおろか、湯の中で身体を動かすことさえ
幻覚だ。でなければ、悪夢を見ているのだ。夢なら覚めよと祈ったが、覚めるどころか、扉の隙間は見る見る拡がって、その向うから、吹き込む
姫は身動きは勿論、喉がふさがって、声を立てる気力もない。だが、目丈けは、目に見えぬ糸で引張られている様に、扉の隙間に固定して動かぬのだ。
アア、今にも、今にも、あの真黒な隙間から、無表情な金色の顔が、覗くのだ。覗くに
姫はその刹那、半ば意識を失って、その黄金仮面の怪物に向って、まるで仲よしのお友達ででもある様に、ニッコリと笑いかけた。極度の恐怖が――泣くことも叫ぶことも出来ぬ程の恐れが、遂に人を笑わせたのであろうか。
怪物は、姫の不思議な笑顔に誘われた様に、窓をのり越えて、ツカツカと湯殿の中へ這入って来た。顔は黄金仮面、後頭部は黒布にすっかり包まれている。身には、例のダブダブの金色外套だ。
姫は生命の危険を感じた。「早く早く、逃げなければならぬ」消えて行く意識を取戻そうと、死にもの狂いの戦いだ。
やっとの思いで、浴槽を出た彼女は、乙女の羞恥も忘れ、むき出しの赤はだかで、よろよろとドアに走った。
だが、黄金仮面は燕の素早さだ。姫が半ばも走らぬ内に、彼は
素っぱだかの、花はずかしい姫君と、全身金色に輝く怪物の、いとも奇怪なる睨み合い。怪物は又しても、例の三日月の唇で、顔一杯の笑いを笑った。と見る間に、パッと飜える黄金マント。彼は一飛びで、姫の白い肉塊を組み敷いてしまった。
怪物は姫のふくよかな胸を狙って、短剣をふりかぶった。か弱き女性の、断末魔の悲惨なる抵抗。もがきにもがく姫の手が、近々とのしかかって来る怪物の顔を、
怪物はアッと叫んで、素早く仮面を被り直したが、
「マア、おまえ!」
姫の
正体を見られた怪物は、物狂わしく短剣を振り下した。針の様な切先が、純白の肌にサッと通る。飛び散る血潮、ギャッといううめき声、そして、宙を
丁度その頃、鷲尾侯爵とルージェール伯とは、まだ寝もやらず、晩餐から引き続いての美術論に打興じていた。書記官も通訳も同席して、聴手の役を勤めている。
この席へ、
「御前さま、大変でございます。お
主客とも色を変えて立上った。侯爵は、客を残して、小雪の案内で湯殿へと駈けつけた。騒ぎを聞いた書生もあとに続く。
湯殿に来て見ると、美子姫は、半身を大理石の浴槽につけて、のけざまに、空を掴んで絶命していた。その胸のムックリと高い乳房と乳房の谷間には、黄金の
侯爵はスリッパのまま浴槽に近づいて、姫の死体を抱えながら、
「オイ、三好を呼ぶんだ。それから波越警部にも知らせるのだ」
と命じた。
書生が走る。やがて波越警部を先頭に、刑事や召使など、殆ど家内中のものが、殺人
調べて見ると、姫は心臓をえぐられて、全くこときれている。
賊の出入口は、庭に面した湯殿の窓の
流石の侯爵も、一人娘の
「三好は、三好はどうしたのか」
侯爵の声に応じて、三好老人の妻女が、おずおず顔を出した。
「三好が、何だか変なのでございます。それから、家に泊っています木場さんも。二人共一間に横になって、グーグー寝込んだまま、いくら起しても目を覚まさないのでございます。どなたか、一度見に来て下さる訳には……」
「眠っているって? それは変だ」侯爵の頭に麻酔剤という考えがひらめいた。「波越さん、一つ見てやって下さいませんか」
警部が三好老人の住居へ駈けつけて見ると、
色々手当を加えたが、薬が利き過ぎたのか、両人共、夜の白々あけまで目を覚まさなかった。
一方ルージェール大使一行は、この思いもかけぬ椿事に滞在どころではなく、夜があけるのを待って、侯爵に
波越警部は、朝裁判所の連中が来着するまでに、この不可思議な兇行の動機なり、犯人の手掛りなりを掴もうとあせった。もう一度足跡を綿密に検べ廻ったり、短剣の指紋を探したり、小雪を捕えて姫の日常を尋ねているかと思うと、三好老人の住居へ飛んで行って、
「三好執事の家に泊っている木場という天理教の教師は、御見知り越しの人物でございましょうか」
警部が意味ありげに尋ねる。
「イヤ、昨日見たのが初めてです。三好も見知らぬ男の様です。ただ教会の確かな紹介状を持っていたので、泊めたと申すことです」
「では、あの男をここへ引出して、一応質問を致して
「いいですとも、わしもあの男は何だか妙な奴だと思っていた位です」
そこで、やっと麻酔から覚めた長髪
「君は昨夜十二時頃、どこにいたのですか」
警部が、臨時被告の住所姓名其他を
「十二時少し前、三好さんと御茶を呑んでいました。それからあとは、御承知の通り、何も知りません。犯人は
「君は、お茶を呑んだのが十二時前だというのですね。併し、三好さんも三好さんの奥さんも、確かな時間は記憶がない。三好さんがお邸から帰って来たのが、多分十二時頃だったと云っています。とすると、あなた方がお茶を呑んだのは、十二時を余程過ぎていたと考えなければなりませんね」
「私も確な記憶はありませんが、若し十二時過ぎであったとすると、どういうことになるのでしょうか」
「君が自分で入れた麻酔剤で睡りこけてしまう前に、湯殿へ忍び込む時間があった。ということになります」
「つまり、私が令嬢の
木場は平気で云ってのけた。
「オイ、君は、まだ、証拠が発見されないと高を
長髪の男は、何の抗弁もしなかった。そればかりか、こののっぴきならぬ証拠に、ひどく驚いている様にさえ見えた。
「それ丈けではない。もっと確かな証拠がある」波越氏はここぞと
警部の手にあるのは、金色の仮面と、金色のマントである。怪賊黄金仮面の衣裳だ。すると、先日来、世の中を騒がせていた怪物はこの男であったのか。
木場は、それを見ると、又一層驚きを増した体であったが、暫らく無言で考え込んでいたのち、
「アア、仕方がない」
と嘆息を漏らしながら、つと波越警部の耳元に口を寄せて、何か一言囁いた。
警部の顔に、サッと上る驚愕の色。
「嘘だ。嘘だ。……」
彼は駄々子の様に
「波越君、君はとうとう僕の邪魔をしてしまった。そんなに疑うならこれを見給え」
木場は、頭に手をやったかと思うと、いきなり長髪をかなぐり捨て、次には、顔中の髭をむしり取った。その下から現われたのは、
「アア、
波越警部の叫び声。驚くべし、天理教の布教師と見えたのは素人探偵明智
一座の人々は、この劇的情景に少なからぬ興味を覚えた。新聞を読むほどの人で、名探偵明智小五郎を知らぬ者はない。鷲尾侯とても、その例には漏れぬ。波越警部は、今し方の失策を忘れたかの如く、やや誇らしげに、この名高い友人を紹介した。
「だが明智さん。肝腎の時に睡らされてしまったのは、少々手抜かりでしたね」
地方の署長が、ある反感を含めて、皮肉に云った。
「エエ、併し、恐らくシャーロック・ホームズだって、僕と同じ失策をやったでしょう。なぜと云って、昨夜、殆どあり得ないことが起ったのです。僕の想像が間違っていなければ、歴史上に未だ嘗つて前例のない椿事が起ったのです。僕はそれを口にするのも恐ろしい程です。無論、僕にもまだ真相がはっきり分ってはいないのですが」
明智は真から恐ろし相に、謎の様なことを云った。
「というと、何だかあなたは、
署長は明智の難解な言葉を、てれ隠しと邪推して、なおも皮肉をやめなかった。
「昨夜の犯人とおっしゃると、お嬢さんの下手人のことですか」
「云うまでもありません」
鈍感な署長は、明智の質問の奥に隠された意味には無感覚で、肯いた。
「多分、存じています。多分という意味は、……波越君、昨夜からの捜索の結果は?」
「皆無だ。君自身が犯人でないとすれば」
「そうでしょう。では、僕は、ハッキリと申上げることが出来ます。この犯人は、数日来私の目ざしていた人物です」
「明智さん、それは誰です。その男の名前を云って下さらんか」
とうとう、侯爵がイライラして口を出した。
「イヤ、侯爵、その前に、あなたにとってお嬢さんの御死亡と、殆ど同じ位重大な問題があります。私は、一刻も早くそれを確めたいのです」
「というのは、アア、若しや君は、……」
「エエ、国宝にも比すべき、御蒐集の美術品です。大使御訪問の折も折、どうしてこうも、様々の兇事が重なり合って突発したのでしょうか。賊は滅多に開かれぬ、美術館の大戸が、
「例えば?」
「例えば、三好さんは何ぜ麻酔剤を呑まされたかということです。失礼ですが、三好夫人は目も耳もうとい御老人です。賊は三好さんの睡っている隙に、隠し戸棚にしまってある、美術館の鍵を取り出して、又人知れず元の場所へ返して置くことも出来たのです。若し賊が、その隠し戸棚を前以て知らなかったとすれば、昨日の様に、たまたま美術館の開かれる日を待って、その隠し場所を確める外はないではありませんか」
「明智さん、来て下さい。美術品を改めて見ましょう」
古美術のこととなると気違いの様な鷲尾侯爵は、もう心配に青ざめて、明智をせき立てた。
侯爵は三好老人から鍵を受取って、明智、波越警部、警察署長の三名を伴い、美術館に這入って行った。
だが、一巡歩いて見た所では、別段紛失した品物もない。
「明智さん、少し取越苦労だったね」
侯爵はホッと安堵して云った。
「ですが、侯爵、この仏像は?」
「藤原時代の木彫阿弥陀如来像です」
「イエ、私の云う意味は、……」
明智は長い間如来像を凝視していたが、何を思ったのか、突如、拳を固めて如来様の横面をはり飛ばした。
「コラッ、何をする。貴様、気でも違ったのか」
侯爵が激怒して駈け寄った時には、已に如来様は台座を辷り落ち、固いコンクリートの床で、粉々に割れていた。
「侯爵、御覧なさい。これが藤原時代の木像でしょうか」
見ると明らかに
アア、何という見事な模造品。賊はいつの間にこの様な石膏像を用意することが出来たのであろう。侯爵は昨日大使を案内した時は、それが決して偽物でなかったことを記憶していた。
明智は何気なく、如来像の底部に当る、石膏の一片を拾い上げて、ひねくり廻している内に、その表面に、
A・Lとは一体何の記号であろう。まさかこんな犯罪用の偽物に、作者が署名をする筈はない。とすると……。
明智は何か、心の奥の奥から、秘密の解釈を探り出そうとするものの如く、じっと考え込んでいたが、やがて、何を思い当ったのか、流石の名探偵も、すっかり
侯爵は侯爵で、絶望の余り、目の前の空間を見つめて黙り込んでいたが、どう気を取直したものか、突然力なく笑い出して、
「イヤ、
と言いさして、侯爵は憤怒に耐えぬものの如く、
「明智さん、君はさっき、娘の下手人を知っていると云いましたね」
と、まるで
「エエ、存じています。侯爵とてもよく御存知の人物です」
「誰です。そいつは一体何者です」
侯爵は日頃のたしなみを忘れて、素人探偵につめ寄った。
「誰です。そいつは一体何者です」
愛嬢の惨死、金銭に替え難き宝物の盗難に、大名華族の大様さを失った鷲尾侯は、噛みつく様に明智小五郎につめよった。
「御急ぎなさることはありません。そいつは決して逃げ出す気遣いはないのです。逃げない方が安全だということを、ちゃんと知っているからです」
明智は落ちつき払って答えた。侯爵を初め一座の人々は変な顔をして明智を見た。何を云っているのだ。泥棒をした上に、人まで殺した犯人が、逃げ去る気遣いはないなんて、そんなべら棒な話があるものか。という心が人々の表情に読まれた。
「決して御心配には及びません。犯人は逮捕されたも同然です。五分間以内に御引渡しすることを御約束します。併し、ここでは何ですから、皆さんあちらの部屋へ御引取り願い
五分間以内に犯人を引渡すとは、何という自信であろう。人々は名探偵のこの自信力に圧倒された形で、いわれるままに母屋へ引取った。その時、侯爵も三好老人も顛動の余り、又一つには已に盗難はすんでしまったのだという油断から、美術館の戸締りをしないで、一刻も早く犯人を見たさに、フラフラと母屋へ引上げてしまったが、その戸締を
引上げたのは、つい今し方、明智小五郎自身が、令嬢殺しの嫌疑を受けて取調べられた、広い応接間である。
誰も椅子に腰を卸そうとはしない。ただ早く犯人が見たいのだ。
「あと三分で、御約束の五分ですよ」
又しても警察署長が、不愉快な敵意をこめて云った。
「三分ですって? そいつは少し長すぎますね。三分どころか、一分、イヤ三十秒で充分です」
明智の小気味よい
「君、冗談を云っている場合ではないぜ」
友人の波越警部が、少々心配になって、小声で注意した。僅か三十秒の間に、あの兇賊黄金仮面を逮捕しようなんて、神様にだって出来ないことだ。
「閣下、令嬢づきの召使をここへ御呼び下さいませんでしょうか」
明智は波越氏の注意を黙殺して、鷲尾侯爵に声をかけた。
「小雪に何か御用ですか。あの女には
侯爵は明智の力量を危んでいる。三十秒などという手品師めいた断言が、少し
「私は犯人を御引渡しする約束をしました。それについて是非必要なのです」
「では……」と侯爵は、不精不承に
やがて、友達の様に懐しんでいた美子姫の惨死に、悲歎の余り目を泣きはらした、
「明智さん、この小間使を問い訊して、それから犯人を探すのじゃあ、三十秒は、ちと無理ですぜ。ホラ、そういう内に、三十秒は過ぎてしまった」
警察署長は行きがかり上、追求しないではいられぬのだ。
「過ぎましたか」明智が平然として答えた。「だが、僕はちゃんと御約束を果したのです」
「ホホウ、こいつは奇妙だ。で、その犯人は?」
「あなた方の捕縛を待っています」
「どこに、一体その男はどこにいるのです?」
「男ですって?」明智は妙な笑いを浮べて云った。「男なんていやしませんよ。ここには小雀の様に震えている、小雪という少女がいるばかりです」
「小雪? すると君は……」
「そうです。気の毒ですが、この小間使が令嬢殺しの犯人です」
余りに意外な指摘に、人々は寧ろ滑稽を感じた。一座に低い笑い声が起った。だが、その中でたった一人笑わぬ人物があった。外ならぬ小雪だ。
まさかまさかと高を括っていた彼女は、今この名探偵に星を指されて、一
「アッ、いけない」
明智がある予感におびえて叫び声を立てた時には、もう遅かった。しかも、外の一座の人々は、まだ笑いやんでいないのだ。
小雪は隅のテーブルに走り寄って、金の仮面とマントをとると、手早くそれを身につけて、アッと驚く人々の前にスックと立ちはだかった。
可憐な小間使の姿はかき消す様に失せて、そこには兇賊黄金仮面が、三日月型の唇でニヤニヤと笑っていた。
不思議な錯覚が、一瞬間人々を躊躇させた。小娘とは分っていながら、黄金の扮装が、何かしらひどく恐ろしいものに見えたのだ。
流石に波越鬼警部は、真先に幻覚を払いのけて、金色の怪物に飛びかかって行ったが、小雪の方では、人々の躊躇している間に、逃走の身構えが出来ていた。彼女は金色の燕の様に、鬼警部の手の下を潜って、ドアの外へ飛出してしまった。
廊下を幾曲り、ヒラリヒラリと金色の虹が飛び過ぎるあとを、波越警部を先頭に、署長や刑事連中が、追駈ける。
母屋を離れた怪物は、疾風の様に庭を横切って、まだ開いたままの美術館へと飛込んでしまった。
追手にしては、何を小娘が、どこまで逃げられるものかという油断があった。逃げる方では死にもの狂いの一か八かだ。そこに思いがけぬ開きが出来た。
小雪は美術館へ飛込むと、中から重い
「そこへ這入れば袋の鼠です。慌てることはない」
おくればせに、明智小五郎と共にかけつけた鷲尾侯爵が叫んだ。
「併し裏手の窓は?」
波越氏は、もうその方へ駈け出し相にしながら聞返す。
「大丈夫。窓には皆鉄格子がとりつけてあります。女の腕で、あの格子を破ることは出来ません」
「では、ここの鍵を。……三好さんはどこへ行きました」
「部屋にウロウロしていました。どなたか、呼びに行って下さい。併し、ナアニ、慌てることはない。もう捕えたも同じことですよ」
黄金仮面
金色の小雀は、異常なる精神力で、僅に追手を逃れて美術館に駈け込んだが、一難去って又一難、追手を防ぐ為に締めた
外には
小雪の顔は恐怖と焦燥の為に醜くひん曲っているのに、それを覆った黄金仮面は、相変らず三日月型の無表情な笑い顔。その笑い顔のまま、彼女は、丁度網にかかった鼠の様に、
どこにも出口のないことは分り切っている。だが、じっとしてはいられぬのだ。今にも、三好老人がやって来て、鍵で
いくら駈け廻っても無駄なことを悟ると、今度は、物におびえた獣の様に、彼女は部屋中で一番暗い隅っこへ、そこにニョッキリ立ちはだかっている、
鎧武者といっても、生人形ではない。
不思議な静寂、ひどい耳鳴りの為に、凡ての物音が消されるのか、屋外の人々は、遠く遠く立去ってしまったかの如く、何の気配も聞えては来ぬ。空漠たる
その時、何とも形容出来ない
彼女の動悸の外に、もう一つ別の調子の
思わずゾッとして、注意をそれに集中すると、分った。分った。その動悸は彼女の指先から伝わって来るのだ。その指先は、櫃の上の鎧武者のお尻に触っている。すると、この鎧武者には、血が通っているのかしら。
鎧の中には、洋服屋の陳列器みたいな、木の棒が立ててある切りだが、そのがらんどうの鎧がどうしてこんなに脈打っているのだろう。と、見ると、何だか、その全体が、モクモクと身動きをしている様に思われて来る。
追手の怖さとは、全く別の恐怖が、彼女の背筋を這い上った。見渡す限り、怪奇な仏像や仏画の幽冥界、その片隅で、虫の食った何百年前の小桜縅がドキンドキンと脈打っているのだ。
小雪の黄金仮面は、怖さに吸い寄せられて、鎧武者の顔を覗いた。
「ギャッ」
と叫んで、小雪が飛びのくと同時に、その鎧が、鎧櫃からヒョイと立上って、物を云った。
「怖がることはない。俺はお前の味方だ」
お化けではない。当り前の人間が、何かの目的で、鎧の中に隠れていたのだ。と分っても、その扮装の不気味さに、小雪はまだ逃げ腰だ。
「あなたは、誰です。誰です」
「名前を云ったところでお前は知るまい。俺は首領の云いつけで、昨夜からこの鎧武者に化けていたのだ。何の目的? そんなことを喋っている暇はない。お前を救わなければならぬ。お前を助けるのも、やっぱり首領の為なのだ。サア、逃げ道はちゃんと作ってある。こちらへ来るがいい」
「アア分った。あなたはあの人の仲間ですね。それで、もし私が捕れば、あの人の秘密がバレてしまうものだから、それが怖いのですね」
「早く云えばその通りだ。つまりお前を助けるのではない。我々の首領の秘密を救うのだ。併しお前にしては、この際、そんなことはどうだっていいじゃないか」
「逃げ道って、どこにあるのです。それをちゃんと私の為に用意して置いて下すったのですか」
「お前の為だって。ハハ……、お前の悪事がこんなに早くバレようなんて誰が思うものか。明智の奴さえ出て来なければ、万事うまく行ったのだ。それに、あのおせっかいめ。……だから俺はあいつの鼻をあかしてやろうと決心したのだ」
気ぜわしく話しながら、鎧武者は鎧兜を脱ぎ捨て、小雪の手を取って、裏手の窓へと走った。
丁度彼等が窓に達した時、ガラガラと大きな音を立てて、背後の大扉が開かれ、追手の群がドヤドヤと踏み込んで来た。だが、不意の暗さに、彼等はまだ窓の二人には気がつかぬ。
「サア、ここだ。お前の為じゃない。俺の逃げ道に、この鉄棒を切って置いたのだ」
鉄格子を握って、一揺りすると、四ヶ所のヤスリ目から、ポッカリとはずれて、大きな穴があいた。二人はそこを
「お前、モーターボートが動かせるか」
「エエ、出来ますわ」
「そいつは幸だ。じゃ、お前一人で、それに乗って逃げ出すんだ」
「でも、どっかへ上陸したら、すぐ捕ってしまいますわ」
「だからよ。それにはちゃんとうまい用意が出来ているのだ。……」
男が何かボソボソと
「マア、これで?」
「ウン、この追手を逃れるには、その位の苦労は当り前だ。お前は人殺しなんだぜ」
「エエ、やりますわ。どうせ絞首台に送られる身体です。死んだ積りでやれば、女でもその位のこと、出来ない筈はありませんわ」
小雪は決然として云い放つと、単身ボートに乗り込んだ。エンジンはいつでも動く様に準備が出来ている。
「オット、それを脱いじゃいけない。さっきも云った通り、そいつの利用法を忘れちゃいけないぜ」
小雪が金色の仮面やマントを脱ごうとするのを、男が止めた。追手の目標になるこの衣裳を、なぜそのまま身につけていなければならないのか、不思議な指図もあったものだ。
「じゃ、しっかりやるんだぜ。俺は又俺で、仕事がある」
男は小雪のモーターボートが、勇ましい爆音を立て始めたのを見送ると、どこへ行くのか、岸伝いに、風の様に走り去った。
この鎧武者の男は、そもそも何者であるか。又彼が首領と呼ぶ人物は一体誰の事なのか。それらの疑問はお話が進むにつれて段々分って行くのだが、ここではただ、鎧武者に化けた男が、昨夜以来ずっと美術館内にいたということ、随って彼は明智小五郎が、置き換えられた美術品の偽物を観破し、それに記してあったA・Lの記号まで読取ったのを、じっと闇の片隅から観察していたということを、記憶に留めて下さればよいのである。
袋の鼠と思い込んでいた獲物が、どうして切り破ったのか、窓の鉄格子を抜け出して、しかもちゃんと出発準備の出来ていたモーターボートで逃げ出そうとは、流石の明智小五郎も、まるで思いも及ばぬ離れ業であった。
まして、追手の警官達は、この解き難き奇蹟に、あいた口もふさがらぬ始末だ。彼等は湖の岸辺に群がって、遠ざかり行くボートを、空しく眺めるばかりである。
遙かにかすむ対岸には、チラホラと百姓家が見えているものの、若し犯人がそこへ上陸してしまったら、事面倒だ。湖水の岸を
「あれの外に、もう発動船はありませんか」
明智が怒鳴った。
「あります。あります。ホラ向うからやって来る。あれは近所の漁師の持舟です」
追手に加わっていた侯爵家の書生が叫んだ。
見ると、何と仕合わせなことには、発動機を取りつけた小さな漁船が、岸伝いにやって来る。操っているのは、所の漁師らしい木綿縞の
「オーイ、その舟を一寸貸してくれ。あのモーターボートを追駈けるのだ。警察の御用だ」
一人の刑事が呼ばわると、御用と聞いて驚いた漁師は、早速舟を一同の前に着けた。
乗込んだのは、警察署長と、波越警部と、明智小五郎と、刑事が二名、運転手の漁師とを合わせて六人の同勢だ。
「こう見えても、馬力はこっちの方が強いんだから、あのボートを追い抜く位造作はありませんや」
漁師は自慢らしく運転を始めたが、その時已に両船の間には、三丁程の
だが、その間に犯人が上陸する心配はない。そんな所へ上陸すれば、すぐ側に県道が通じていて、最も人目につき易い場所なのだ。第一、その様な隙がない。追手の船は瞬く間に、岬の向側まで見通しの利く場所に達した。
見ると、モーターボートは、岬の蔭で方向を転じたと見え、湖水の中心に向って、
爽快なる湖上の追撃戦。
静かな水面を、真二つに切裂いて進む船首。舟全体が見えなくなる程の水煙。見事な尾を引く二条の白浪。命がけのボートレースだ。
漁師が自慢したのは嘘でない。機械力の相違は是非なく、両船の距離は見る見る狭まって行く。
二名の刑事は、黄金仮面の狂暴に備える為、特にピストル携帯を許されていた。彼等は舟が着弾距離に近づくと、そのピストルを高く掲げて、逃げ行くボートを
「オーイ、舟を止めろ、でないと打ち殺すぞ」
だが、ボートの上の黄金仮面は身動きもしない。
追手の舟から一団の白煙が立昇ったかと思うと、湖面に伝わる銃声。
それでも、強情な小娘は、見向きもしない。エンジンにしがみついたまま化石したかと疑われる程だ。
併し、見よ。両船の距離は、二十間、十間、五間と接近して行く。やがて、湖の中心に達した頃には、遂に追手の舟は逃げるボートを捕えることが出来た。
一人の刑事が、敵のボートに飛び移ったかと思うと、いきなり黄金仮面の背後から、組みついて行った。だが……
「ワッ、やられた」
刑事の頓狂な叫び声に、ギョッとした人々の視線が、黄金仮面に集中する。
これはどうしたことだ。そこにあるのは金の仮面とマントばかり、中はもぬけの殻だ。二枚の板を立てて、それに金色マントが着せかけてあったのだ。
黄金仮面の常套手段だ。人なき舟は、向けられた方向に、ただ機械的に進行していたのだ。
では、このボートには、最初から乗手はなかったのか。
そんなことはない。追手の人々は、岸を離れたボートの中に、金色の人の、動く姿を確かに見た。
では、途中水中に身を投じて逃れたのか。
それも不可能だ。この静かな湖面、泳ぐ人影を見逃す筈はない。
上陸したのか。無論そんな
とすると、小雪は人魚と化して湖の底深く姿を消してしまったのか。それとも、霞となって空高く蒸発してしまったとでも、考える外はない。不可能なことだ。
「アア、僕はあの小娘を軽蔑し過ぎていた。何という恐ろしい智恵だろう。諸君、まだ失望することはありません。船頭さん、この舟をさっきの岬の所へ帰してくれ給え。大急ぎだ」
立騒ぐ人々を制して、明智が叫んだ。
「君の考えは、まさかあの岬の蔭から犯人が上陸したと云うのではあるまいね」
進行中の舟の中で、波越警部が念を押す様に尋ねた。
「無論、そんなことは不可能だ」
「すると?」
「たった一つ、残された方法がある。だがあの小娘の考えつけることではない。といって、外にこの不思議な消失を解くすべはないのだから、どんなに不自然に見えようとも、やっぱりその方法を
「共犯者だって? 君は心当りでもあるのかい」
「恐らく僕達の知らない奴だ。そいつがあの美術館の暗闇にじっと隠れて、時の来るのを待っていたのだ」
流石に名探偵の想像は星を指す。
「併し、モーターボートに乗っていたのは、確かに小雪一人だったぜ。すると、共犯者は……」
「用事を済ませて逃げてしまったのさ。どこへ逃げたか。我々にとって、そいつの
明智のこの心配は不幸にも適中した。それがどんな風に適中したかは、間もなく分る時が来る。
やがて舟は岬の蔭に到着した。蔭と云っても、湖の中心からは見通しの場所で、遠くから、そこに何の異状もないことは分っていた。
「明智さん。君の考えは、どうも我々凡俗には理解出来ないね。一体ここまで舟を戻してどうしようと云うのですか。見給え、陸上にも水面にも、人一人隠れる様な場所は一ヶ所もないじゃないか」
警察署長は彼自身定見はないのだけれど、兎も角も、飛入りの素人探偵を敵視しないではいられぬのだ。
明智はそれにも構わず、入江になった浅瀬を、漁師に命じて、あちこちと舟を動かし、群がる水草をかき分けて、何か熱心に探し廻っている。
「アア、あいつが入水自殺をしたという訳ですか。君はその死骸を探しているのですか」
署長が又しても
水面一杯に繁茂した水草の葉の外に、その辺は丁度ゴミの流れ寄る箇所と見えて、
「よし、舟を止めて。……誰か薄い紙をお持ちではありませんか」
明智が妙なことを云い出した。
刑事の一人が極く薄い鼻紙を取り出して、明智に渡すと、彼はそれを細く裂いて、
「君、それは一体何の
余りの不思議さに、波越警部までが、からかい始めた。
「静かに、静かに、今、妙な実験をしてお目にかけるのだから」
明智は生真面目な様子で、細長い鼻紙をヘラヘラと水面に近づけて行く。
人々は、この途方もない明智の仕草に、却って圧倒された形で、黙り込んで、同じ水面を覗き込んだ。
「ホラ見給え、水草の間に、細い竹切れが首を出しているだろう。こいつがどう云う反応を示すか。うまく行ったらお慰みだ」
云いながら、明智は紙切れを、その竹の切口の真上へ近づけた。
すると、これは不思議、その紙切れが、フワリフワリと、下から吹き上げられ又吸い寄せられる様に、一定のリズムで踊り出したではないか。
竹は水中に直立している。疑いもなくその下方から、何かの気体が吹き出しているのだ。
まさか天然
鈍感な人々にも、遂に事の仔細が分って来た。アア、何という悲惨な逃亡者の努力であったか。人々はゾッと総毛立って、青ざめた顔を見合わせたまま、暫くは言葉もない。
云うまでもなく、その節抜き竹の下端には、小雪の口があるのだ。つまり、彼女は水底の岩にしがみついて、身を隠し、竹の管で呼吸を続けているのだ。そうして、騒ぎが静まるのを待ち、人知れず上陸して、
「よし、しぶといあまめ、こうして浮上らせてくれるぞ」
野蛮な刑事がいきなり手を伸ばして、竹筒の切口を押えた。こうすれば呼吸の出来ぬ苦しさに、難なく浮上って来ると思ったのだ。
だが、アア、何という犯罪者の恐怖心であろう。十秒、二十秒、遂に一分間を超えても、小雪は浮上って来なかった。呼吸をピッタリ止められた、水底での戦慄すべき闘い。彼女は
「よし給え。可哀相だ」
余りの悲惨に耐え兼ねた波越警部が叫んだ。
流石の野蛮刑事も、もう手を離したがっていたのだ。彼は警部の言葉をよいしおに、哀れな娘の呼吸を自由にしてやった。
だが、それが丁度、水底の小雪の忍耐力の最大限でもあった。刑事が手を離すと、殆ど同時に、サンバラ髪の少女が、水草の間からポッカリと浮上って来た。
半ば失神した少女犯人は、即座に舟の上に引上げられた。
「アア、もう我慢が出来ない、早く、早く、殺して下さい」
胴の間に横えられた彼女は、手足をもがいて、
「君、僕の云うことが間違っていたら、訂正するんだよ。いいかね」
明智は少女の意識が恢復するのを待って、
小雪は力なく肯いて見せる。
「つまり君は、洋行以前、侯爵邸にいた千秋さんと、何か深い関係を結んでいた。その千秋さんが
小雪は又、大きく肯いて見せた。千秋氏と美子姫の間に婚約の成立していることは已に述べた通りである。
「君は持前の激しい気性から、遂に御主人の美子さんをなきものにしようと企らんだ。何も美子さんが憎いのではない。競争者を除いてしまえば、千秋さんが君に帰って来ると信じたのだ。それには、君の殺人が絶対にバレないことが必要だ。非常にむつかしい仕事だった。丁度その時、黄金仮面の新聞記事を読んだ。そこで、君は恐ろしい計画を思い立った。ね、そうだろう。
で、君は木のお面とマントを手に入れ、それに金箔を押してひそかに黄金衣裳を作り上げた。僕はね、君がその金箔を買った
読者諸君、これで、前夜美子姫が黄金仮面の素顔を一目見て、「マア、お前」と叫んだ意味が判明した訳です。
「僕は噂を聞いて、姿を変えて三好老人の家へ泊り込んだ。そして、何もかも調べ上げていたのだが、F国大使の御来訪と、例の麻酔薬の騒ぎで、非常な失敗を演じてしまった。僕に麻酔薬を飲ませたのは君ではなかった。無論、あの仏像や仏画を偽物とすり変えたのも君の知ったことではない。つまり、君の殺人事件よりも、ずっとずっと大物が突然転がり込んで来たのだ。サア、ここまでに事実と違った点があるかね」
小雪は僅かにかぶりを振った。
「よしよし、それでは、君の殺人罪についてはもう聞くことはない。君の事件は見かけに比べて極く極く簡単なのだ。それよりも聞きたいのは、君の知っているもう一人の犯人だ。つまり美術館の仏像を盗んだ奴だ。君はそいつを見たに相違ない。ね、見たんだね」
波越氏も警察署長も、明智小五郎の一語一語に驚きを加えて、吸い寄せられる様に聞入っていた。明智の方でも、こうして事の真相をその筋の人々に知らせて行く積りなのだ。
小雪が肯くのを見て、明智は言葉を続ける。
「何ぜ僕がそんな疑いを抱いたかと云うとね、外でもない、君のさっきからの見事過ぎる逃走振りだ。君一人の考えで、これ程順序よく、しかもこんなずば抜けた離れ業がやれるものではない。どうしても、誰か君に入智恵をした奴がある。そいつは、何ぜ、こうまで苦心をして君を逃亡させなければならないのか。外に考え様はない。そいつの悪事を君に見られているからだ。君が裁きを受けて、事の
だが、小雪は黙っている。考えを
丁度その時、船尾にうずくまっていた、舟の持主の漁師がけたたましい声を立てた。
「ア、妙なものが流れて来た」
驚いた一同が立上ってその
明智は再び小雪の側にしゃがんで、肝要な質問を続けた。
「サア、小雪さん、どんな片言でもいい、僕の問いに答えてくれ給え。僕が不自由らしく、こんな舟の上で、急いで質問を始めたのは、ただもう一人の犯人の正体が、一刻も早く知りたかったからだ。
明智が驚いて、小雪の肩を揺ぶった時には、彼女は已に生命のないゴム人形みたいに、何の手答えもない死骸になっていた。
余りにもいぶかしき突然の死であった。
「どうしたんだろう。大分落ちついていると思ったのに、何だか変だね」
波越警部が先ず不審を打った。
人々は、うしろから、何かが襲いかかって来る様な、名状し難き不安の中に、言葉もなく哀れな少女の死体を眺めていた。
「アッ、血だ。血が流れている」
誰かが叫んだ。
見ると、グッタリとなった小雪の背中から、舟底へと、真赤な液体がにじむ様に流れ出している。
明智は一刑事の手を借りて、死体を引起した。
「誰だ。誰が小雪を殺したのだ」
二三人が同時に叫んだ。
殆んど有り得ないことが起ったのだ。小雪は殺されている。背中の心臓と
水中から引上げた時には、無論そんなナイフなぞ
だが、舟の上には、皆素性の知れた人々ばかりだ。四人の警察官、明智小五郎、それから舟の持主の漁師。その内の誰が、そしていつの間に、何の遺恨があって、小雪を殺さなければならなかったのだ。
とは云え、外には人影もない水の上だ。どんなに不可能に見えても、下手人は六人の一人に相違はない。
では、若しや……
徐々に徐々に、ある驚くべき真相が、人々の脳裡に浮び上って来た。
不思議、不思議、舟の上には警察の人々、明智小五郎、舟の持主の漁師の外に、誰もいない。場所は岸を離れた湖水の中だ。全くあり得ないことが起ったのだ。
あっけに取られた人々の胸に、漠然と、ある信じ難き考えが湧き上って来た。若しかしたら、若しかしたら……彼等はその異様な想像に慄然とした。
と、突然湖面に響き渡るエンジンの爆音。と同時に起る明智の叫び声。ハッと振向く人々の目に、今まで曳舟にしてあったモーターボートが、非常な速度で、彼等の舟を離れて行く、奇怪千万な光景が映った。ボートを操縦しているのは、いつの間に乗り移ったのか、こちらの舟の持主である筈の漁師だ。
「畜生、あいつだ。あいつが殺したんだ」
出し抜かれた明智小五郎は、憤怒の形相物凄く、エンジンの所へ飛んで行って、運転を始めた。又しても、湖上の追撃戦。
「あいつは、賊の手下だ。小雪に入智恵をしたのもあいつだ。それ丈けでは安心出来ぬものだから、漁師の舟を手に入れて、その舟の持主に化け、味方と見せかけて、僕等を見張っていたのだ。そして、小雪が発見され、何か喋り
明智が運転を続けながら波越警部に怒鳴った。
「
「君はそれが分らないのか」明智は
云われて見ると、あの時、一同がそれを拾い上げたり、中味を検べたりする為に、一方の舷へ集って、しばらく小雪の方をお留守にした。その
そんなことを怒鳴り合っている
「大丈夫、スピードはこちらが早いのだ。賊を捕えるのは
警察署長が、さい前漁師が云ったのと同じ様なことを得意らしく叫んだ。
オヤ、変だぞ。相手は追手の舟の方が早いことをチャンと知っている筈だ。見す見す追いつかれると分っているものを、何ぜあの様に逃出したのであろう。そんな誤算をする様な賊ではない。こいつは、用心をしないと危いぞ。明智はふとそこへ気がついた。
彼は
すると、アア、これはどうしたことだ。舟の底に、もう二寸程も水がはいって、ジャブンジャブンと不気味な音を立てているではないか。昂奮の余り、誰一人足の下の浸水のことなど気づかないのだ。
「誰か舟の底を
明智の声に、人々はやっとそれを悟って、俄かに騒ぎ出し、水の中を手さぐりで、舟底を検べ始めた。
「いけないッ。大きな穴があいている。何かこめるものはありませんか」
刑事が舟底の穴を発見して、青くなって叫んだ。
云う内にも、水は刻々に増しつつある。人々の靴を浸し、已にズボンの裾を濡らし始めた。
「これだ。これをこめ給え」
明智が手早く羽織を脱いで投げた。
刑事はそれを丸めて浸水の箇所を塞ごうとあせる。だが、もう手遅れだ。六人の目方と同じ力で吹き上げる水を、間に合わせのこめ物なぞで防ぐことは出来ぬ。
立騒ぐ間に、浸水は早くも舟の半ばに達し、舟は刻々に沈んで行く。エンジンは動いているけれど、舟足が重くなった為に、速度は半減されてしまった。
場所は深さの知れぬ湖水の真中だ。泳ぎの出来る者も出来ないものも、色を失って、ワッと異様な叫声を立てた。
「畜生ッ、あいつの罠だ。馬鹿野郎。
明智はモジャモジャ延びた髪の毛を掴んでくやしがった。
と、遥かに聞えて来る、賊の高笑い。彼は追手の舟を湖心に近く
追手の一同は、併し、賊の嘲笑を、
金ピカの肩章いかめしい警察署長も、鬼警部とうたわれた波越氏も、名探偵明智小五郎も、こうなってはみじめだ。彼等は沈み行く舟の舷につかまって、辛うじて水中に身を浮かせ、首ばかりを突出して、哀れな呼吸を続けるのが、精一杯だ。
だがそれも長くは保つまい。水泳の達者な明智は別として、その他の人々は、やがて疲労の極、どの様なことに成行くか、いとも心細い有様である。
あとになって考えると、誠に滑稽千万な光景であった。併し、その時は生死の境だ。警察のお歴々も、我を忘れて
「オオ、舟だ。救いの舟だ」
誰かの叫声に、振向くと、侯爵邸の方角から、エンジンの響も高く近づいて来る一艘の小舟。
近づくに従って、その舟には、あとに残して来た警官達が乗っていることが分った。彼等は別の漁船を探し出して、怪賊追撃の第二隊を編成し、応援にやって来たものに相違ない。
結局、一同は少し冷い思いをした丈けで、別状もなくその舟に救い上げられた。小雪の死体も流れ去る
賊はと見ると、騒ぎの間に、モーターボートを湖水の東岸に乗り捨てて、已に上陸してしまった。云うまでもなく、警官隊はその地点を目ざして進んだ。明智を初め五人の者は濡れ鼠だが、そんなことは構っていられぬ。息を
瞬く内に岸に乗りつけた一同は、先を争って上陸する。
「オヤ、何だか紙切れに書いてあるぜ。あいつが我々に読ませる為に残して行ったのかも知れない」
波越警部が先ずそれを発見した。見ると、モーターボートの中に、一枚の紙片。一刑事がボートに飛込んで、それを拾って来た。確かに賊の置き手紙だ。
小雪を殺したのは誰でもない。明智小五郎、貴様だぞ。俺の方には殺す気は毛頭なかった。第一我々の首領は血を見ることが何よりも嫌いなのだ。小雪を逃亡させる為に、あれ程苦労をしたのでも、俺の方に殺意のなかったことは分る筈だ。それを、貴様がいらぬおせっかいをしたばかりに、とうとう、あんな荒療治 をしなければならなかった。即刻手を引くのだ。でないと、俺はもう我慢が出来ん。この次は貴様の番だぞ。
それには鉛筆の走り書きで、こんなことが記してあった。
水に濡れた連中は、あとから来た人達の上衣を借りて、着換えをした。一時しのぎの珍妙な風体だ。
明智は賊の置手紙を叮嚀にたたんで、借着のポケットに納めた。一方は山、一方は湖水を見はらしてうねる細道、右すれば山越し二里にして
賊はその道をどちらへ走ったのかと、迷っている所へ、左の方から一人の田舎女がやって来た。
「オイ、今この道を漁師風の男が通らなかったか。お前と行き違いにはならなかったか」
波越氏が尋ねると、
「通りましただ。わしにぶつかって、
「そいつだ。よっぽど行った時分かね。どの辺でぶつかったのだね」
「つい、そこで。その山の曲り角でぶつかりましただから、まだ遠くは行ってますめえよ」
「よし、諸君、追駈けて見よう。道は一筋だ。それに先へ行けば繁華な町がある。もう逃しっこないぞ」
波越警部は、借着の背広にズボン下ばかりの珍妙な格好で、勇ましく叫んだ。刑事巡査から叩き上げた彼は、職人や土方の風体で捕物に向った経験も
刑事三名と明智とが勇ましい追手の人数に加わった。警察署長を初め残りの人々は、舟でCに先廻りをする手筈だ。
山角を曲ると、見通しの利く真直な道が二三町続いている。だが、そこにはもう賊の姿は見えぬ。五人が、息せき走って行くと、土手に凭れて鼻たれ小僧が遊んでいる。念の為に賊の風体を云って尋ねると、その小父さんなら、さっきここを通ったとの答えだ。
山角を曲り曲り、又二三町走ると、アアいたいた。遙か向うを、トットと急いで行く、漁師体の男、着物の縞柄から脊格好から
「相手に悟られては面倒だ。Cまで脇にそれる道はないのだから、あせることはない。見え隠れにつけて行こう」
波越氏は小声で、はやる刑事達を制した。
「僕は腹が痛くなって来た。とても歩けない。すまないがあとはよろしくやってくれ給え」
明智が突然妙なことを云い出した。
「そいつは困ったね。大丈夫かね。さっきの舟の所まで歩けるかね」
「ウン、その位のことは大丈夫だ。あすこには僕等の為に、賊の乗ったモーターボートが残してある筈だ。君達はどうせCまで尾行するのだから、僕はあいつを拝借して侯爵邸へ帰ることにする」
「そうか。じゃあ
一行は明智を残して前進を続けた。
途中の詳細を記していては退屈だ。結局波越警部の一隊は、賊をCの自動車発着所へ追い込んだ。もう逮捕したも同然である。
賊は発着所の薄暗い隅っこに、小さくなって腰かけ、通行の人々に顔を見せまいと、鼻の頭が膝につく程うつむいている。
波越警部を先頭に、一同ドヤドヤとそこへ踏み込んで行った。と、足音に驚いて見上げる賊と、先頭の波越氏とが、一二尺の近さで、ヒョイと顔を合わせた。
「アノ、ちょっくら御尋ね致しますが、ここに待ってれば日光行きの乗合が来ますだかね」
賊とばかり思い込んでいた男が、さもさも間抜けた口調で、警部に話しかけた。
違う違う。着物は同じだが、顔がまるで違っている。正真正銘の田舎者だ。
追手の一同アッと云ったまま、あいた口が塞がらぬ。
だが、どう見直しても、着物といい、頬冠りの手拭といい、賊のものに相違ない。
尋ねて見ると、何のことだ。賊は舟から上ると、丁度そこを通りかかった旅人を、山の茂みの中へ連れ込み、腹巻の中へ忍ばせていた金時計をお礼に、うまい口実を設けて、服装をそっくり取換えて貰い、旅人とは反対の方角へ走り去った。ということであった。
「別に悪気があってしたんじゃねえだから、どうか勘弁してやって下せえまし。何だったら、この金時計はお返し申しますだで」
田舎親爺は、警察の人々と分ると、青くなって、ペコペコおじぎをした。
アア分った。明智小五郎はこの
「君はずるいぜ。分っていたらなぜ教えてくれなかったのだ」
あとになって、警部が愚痴をこぼした時、明智は、
「だって、別に確信があった訳じゃないからね。若し贋物でなかった場合は大変だ。ただ僕は、あいつの後姿が、何となく気に喰わなかった丈けさ。それに、捕縛するのには、僕なんか大して手助けにもならないしね」
と笑った。
無論即刻、賊の逃去った方角の各警察署へ打電して、逮捕方を依頼したけれど、どこをどう逃げたのか、いつまでたっても、何の報告もなかった。
C湖の大捕物は、かくして何等得る所なく終った。侯爵令嬢美子姫の下手人は分った。だが、その下手人小雪さえも、あの怪賊の為に
二美人の惨死。国宝にも比すべき古美術品の盗難。だが怪物黄金仮面の正体は勿論、その配下の行衛さえ、名探偵明智小五郎の手腕を以てしても、遂につきとめることが出来なかった。
新聞紙が、この絶好の社会種を、鳴物入りで書き立てたのは云うまでもない。
それから十日ばかりは、何のお話もなく過ぎ去ったが、その間とても、噂は噂を生み、おびえきった人々は、
古物商の薄暗い店内に、はげちょろけの仏像に並んで、一体丈けギラギラ光る金色の如来像が立っていたが、あれが黄金仮面ではなかったかと一人が云うと、もうそれに違いない様に、噂はそれからそれへと伝わって行った。
又ある時は、上野の帝室博物館で、場内の掃除女が気絶した騒ぎさえ持ち上った。閉館近い夕暮のこと、仏像ばかり並んでいる陳列室を掃除していると、等身大の鍍金仏が、フラフラと彼女の方へ歩いて来る様な幻覚を感じて、テッキリ黄金仮面と思込み、キャッと悲鳴を上げたまま、気を失ってしまったと云うのだ。
それは兎に角、本物の黄金仮面が、三度目の犯罪を企てていることが分ったのは、四月も終りに近いある日のことであった。
それは、どんより曇った、変に蒸し蒸しする、何となく
我々の主人公明智小五郎の住居について記すのは、これが初めてだから、少々説明をしなければなるまいが、彼は『蜘蛛男』の事件を解決して間もなく、不経済なホテル住居をよして、ここのアパートへ移ったのだが、独身者の彼には、一家を構えるよりも、この方が気楽でもあり便利でもあった。借りているのは表に面した二階の二た部屋で、一方は七坪程の手広い客間兼書斎、一方は小ぢんまりした寝室になっている。
黄金仮面が鳴りをひそめているので、明智は少々退屈を感じていた。その日も、所在なさに、客間のテーブル兼用の大型デスクに頬杖をついて、プカプカ煙草を吹かしている所へ、突然ドアにノックの音が聞えて、見知らぬ老人が這入って来た。
老眼鏡に胡麻鹽髭、折目正しい羽織袴、どう見ても一時代前の人類だ。
老人は一礼すると、一封の紹介状に名刺を添えて、うやうやしく差出した。
名刺には「
「私は大鳥家の執事を勤めて居りまする、
と切口上で云った。
紹介状は実業界にいる友人の自筆で、万事よろしく頼む
老人は長々と何か喋っていたが、凡て前口上に過ぎず、結局「黄金仮面」の事件について、頼みの筋があって、やって来たということであった。
黄金仮面と聞くと、
「詳しくお話し下さい。先ず第一に、警察をさし置いて、なぜ私に御依頼なさるのか、何か特別の理由でもおありになるのですか」
「それでございます。実は大鳥家にとりまして、甚だ外聞を憚る儀が
老人はデスクを挟んで、明智と向き合って腰を卸した。
こいつは面白そうだわい。と思うあとから、ふと変梃な疑問が湧上って来た。危険危険、大鳥家の執事なんて真赤な嘘で、この老人こそ当の黄金仮面の廻し者ではあるまいか。先日賊がモーターボートの中へ残して行った置手紙には「この次はお前の番だぞ」と書いてあった。明智が賊にとって、非常な邪魔者であることは云うまでもない。紹介状の偽造なんて造作もないことだ。ひょっとすると、うまく云って、彼をおびき出し、危害は加えぬまでも、この事件に手出しが出来ぬ様、自由を奪ってしまう計略でないとは云えぬ。
それに気づくと、明智はいきなり鉛筆を取って、テーブルの上の
彼が書いた文字というのは、ある人物の名前であったが、若し読者諸君がその場に居合わせたならば、その人名の余りの意外さ、突飛さに、アッと驚きの叫声を立てたであろう程、実に非常な人物の名前であった。
では、彼は一体誰の名を記したのか。それはお話が進むにつれて、間もなく分って来るのだが、このことは明智が当時已に、黄金仮面の正体が何者であるかを悟っていたという、驚くべき事実を裏書きするものであった。
老人は明かに明智の落書を見た。彼が果して賊の一味であったら、その文字を見て顔色を動かさぬ筈はないのだ。ところが、彼はそれを読んでも、平気なばかりか、却って明智が
「サア、どうかお話し下さい。私はもう充分あなたを御信用申しているのです」
明智がうながすと、老人はやっと要点に話を進めたが、老人の話し振りをそのまま書いたのでは、少々退屈だから、その大意丈けを
大鳥喜三郎氏には、息子さんの外に二人の令嬢があった。姉の
事の起りは今から一週間程前の夜、いつもお母さまの許しを得、行先を告げて外出する不二子さんが、どうしたことか、日暮にふと居なくなったまま、十二時過ぎまで帰らなかった。しかも帰って来ると、誰にも顔を合わさず、ソッと寝室へ這入った様子が、どうもただ事でない。
無論翌日、お母さまからそれとなく尋ねて見たが、ハッキリした返事も出来ない始末だ。
引続いて、そんなことが毎晩の様に起るので、とうとうお父さまのお耳にも入った、捨てては置けぬと、
初めの晩は、不二子さんの行動が実に千変万化を極め、自動車を飛び下りたかと思うと、複雑な露地をグルグル廻って、飛んでもない場所から、又自動車に乗り換えるといった調子で、とうとう中途で見失ってしまったが、次の晩(と云うのは昨夜のことだが)は、今度こそと意気込んだ甲斐あって、おしまいまで尾行を続けることが出来た。
結局行きついた所は、郊外
建物は窓という窓が密閉されていて、少しも光が洩れず、
アア、何たることだ。大鳥家の令嬢ともあろう人が、如何に魔がさせばとて、怪賊黄金仮面と
だが、それ丈けなればまだしも、もっといけないことは、ある日大鳥氏が用事があって土蔵へ這入って見ると、数日
という訳で、大鳥氏としては、いくら黄金仮面逮捕の為とは云え、可愛い令嬢に悪名の立つことは好まぬ。併し打捨てては置けぬ問題だ。と考えあぐんだ末が、出入りの者の助言で、素人探偵として
「で、お嬢さんは、どんなに尋ねても、何もおっしゃらぬのですか」
「左様でございます。平常は誠にお優しいお方ですが、今度丈けは、どうしたものか、まるで人間が変ってしまった様に、お話にならぬ強情で、実に主人も困り切っております」
「恋です。恋の力ですよ。よく分りました。あの賊の最近の動静が分った丈けでも、僕は非常に有難いのです。だが、令嬢のお名前が出ぬ様に、黄金仮面丈けを始末して、絵巻物を取戻すというのは、仲々むつかしい仕事ですね。が、お引受けしましょう。何とかやって見ましょう」
明智のたのもしい返事を聞いて、尾形老人はホッとした様子であった。
「どうかと心配を致しましたが、御快諾を得まして、主人もさぞ喜ぶことでござりましょう。私も一安心でございます。……オオ、それで思い出しましたが、さい前こちらへ参ります時に、玄関の所で、どこのお方か存じませぬが、この手紙をあなた様にお渡し申してくれとことづかりましたのを、つい失念して居りました」
老人は懐中から小型の封書を取出して、デスクの上に置いた。
「ヘエ、妙ですね。あなたが僕の所へいらっしゃることが、よく分ったものですね」
「如何にも、私も何だか
「どんな男でした」
「サア、どんなと申して、洋服を着た会社員とでも云う様な風采の、三十五六の人物でございましたよ」
「フン、私も心当りがない。何だか変ですね。が、兎も角読んで見ましょう」
明智は封を切って、中の用箋を拡げた。そこには、簡単ではあったが、次の様な恐ろしい文句が書きつけてあった。
明智君
大鳥令嬢の問題については、おせっかい断じて無用だ。イヤ、大鳥嬢の問題に限らぬ、所謂黄金仮面の事件から一切手を引いて貰い度い。我輩がそれを命令するのだ。諾 か然 らざれば死だ。我輩は徒 らに人命を絶つことを好まぬ。だが、我輩の慈悲心には、場合によって例外あることを記憶せよ。
大鳥令嬢の問題については、おせっかい断じて無用だ。イヤ、大鳥嬢の問題に限らぬ、所謂黄金仮面の事件から一切手を引いて貰い度い。我輩がそれを命令するのだ。
諸君の所謂黄金仮面より
アア、何たる機敏、何たる傍若無人の振舞であろう。賊は皮肉にも、当の大鳥令嬢問題の依頼人に、この手紙をことづけたのだ。尾形老人は、一方で事件依頼人であり、同時に、その依頼を拒絶せよという手紙の持参人だ。
「どうです。尾形さん。黄金仮面というのは、こうした怪物なのですよ」
老人は答える術を知らず。驚嘆の余り、ただウームとうめくばかりだ。
「だが、僕がこの脅迫状を怖がっていると思ってはいけませんよ。探偵というものは、こんな紙切れは、しょっちう見慣れているのです。何でもないんです」
「ですが、この様子では、あなた様のお命が……」
老人がどもりどもり云った。
「ハハ……、イヤ、その御心配には及びません。アア、一寸お待ち下さい。あなたにお見せするものがありますから」
云ったかと思うと、明智はドアを開けて廊下へ出て行ってしまった。
どこへ行ったのか仲々戻って来ない。老人は見まいとしても、机の上の脅迫状へ目が行く。読返す程、
それが証拠には、隣りの寝室で、カタリと何かの物音がしたのさえ、聞逃さず、若しやドア
イヤ、妄想ではないぞ。賊は人の出入りのはげしい玄関にでもいたのだ。
自然尾形老人の目は、寝室との境のドアに釘づけになっていたのだが、ふと気がつくと、そのドアがジリジリと、少しずつ開いているではないか。妄想がそのまま形になって現われて来たのだ。老人ながら、彼はギャッと叫び相になったのを、やっとのことでこらえた。
ドアが一寸二寸、容赦なく開いて来る。と見ると、その隙間からギラギラと目を射る金色の光。アア、果して果して、黄金仮面だ。あいつが隠れていたのだ。
思わず椅子から腰を浮かして、廊下の方へ逃げ出そうとする老人の目の前に、ドアがパッと開いて、全身まる出しになった怪物の姿。三日月型の唇で物凄く笑っている黄金の仮面。身体を包んだダブダブの金色マント。
老人は腰の筋肉が無感覚になって歩くことさえ出来なくなってしまった。
「ウフフフ……」
黄金仮面の耳まで裂けた口が、不気味に笑った。
「ウフフフ……、どうです、尾形さん。お目にかけたいというのは、これですよ」
「エ、何ですって?」
老人にはまだ事の次第が呑み込めぬ。
「ヤ、びっくりさせて、済みませんでした。僕です。僕です」
仮面をはずしたのを見れば、何の事だ、怪賊ではなくて、明智小五郎の顔がニコニコ笑っている。
「つまり、僕の方にも、これ丈けの用意が出来ていることを、お目にかけたかったのです。怪物に対しては、こちらにも、思い切った策略がなくてはなりません。いつか、僕がこの僕自身の黄金仮面を利用する様な場合も来るに相違ないと思うのです」
明智の説明を聞いて、尾形老人は、又別様の驚異を感じないではいられなかった。
さて、この奇妙な試演がすむと、明智は早速外出の支度をととのえ、老執事と共に
お話変って、尾形執事の留守中、当の大鳥邸では、どんなことが起っていたか。
大鳥氏は、尾形老人の尾行によって、不二子の行先を確め、彼女の恋人が聞くも恐ろしい黄金仮面と分ったものだから、一方明智小五郎の援助を乞うと同時に、再びあやまちを繰返さぬ様、最も奥まった洋室に不二子を監禁した。
二間続きの洋室の一方に、臨時の寝台を備え、部屋の中には
出入口はそのドアたった一ヶ所。窓は幾つかあるけれど、
父大鳥氏は、時々そこへ見廻って来ては、どうかして娘の心持ちを飜えそうと、おどして見たり、すかして見たり、説法をするのだけれど、恋の力の恐しさ、令嬢はまるで人が違った様に強情になってしまって、何の手答えもないのである。
「お嬢さま、わたくしこんな悲しい目を見ようとは、本当に、悪い夢にうなされているのではないかと思う位でございますよ。婆やはそんな大それたお嬢さまに、お育てした覚えはありませんのに。……モシお嬢さま、不二子さま。マア、これ程申上げることが、あなた、お耳には入りませんの?」
かき
不二子さんは、大きなソファに身を沈めて、じっと空間を見つめたまま、身動きもせず、ふてくされた様に押し黙っている。
描いた様な長い眉、睫毛の長い
「お嬢さま、あなたは悪魔に魅入られなすったのです。あなたはお気が違ったのです。本当にしっかりして下さいまし。マア、こんなことがあっていいものでございましょうか」
お豊は、
「婆や、もうもう沢山。どうか私をソッとして置いておくれ。お前なんかに、わたしの心持は、分りゃしないのだわ」
やっと不二子さんが、冷やかな声で、叱りつけるように言い放った。
「マア、それではやっぱり、あなたはあの恐しい男が、思い切れぬとおっしゃるのでございますか」
お豊はびっくりして、目の色を変えて、令嬢につめ寄った。
「お前、それじゃあ、あの人がどんなすばらしいお方だか、知っているのかえ」
不二子さんは、平然として、お豊を驚倒せしめる様な言葉を吐いた。
果して乳母はハラハラと涙をこぼした。
「あなたはマア、何をおっしゃるのです。よくも、よくも、そんなことが……乳母は今日が今日まで、お嬢さまが、そんなみだらなお方とは、ちっとも、ちっとも存じませんでした」
忠義者のお豊は、身も世もあらぬ体で、泣き喋りにかき口説くのだ。
「ホホホホホ、婆や、お前はあの方を知らないからよ」不二子さんは益々恐ろしい事を口にする。「いくら頑固なお前だって、あの人がどんな方だか知ったら、きっとびっくりして、わたしを
不二子さんの、うっとりと、夢見る様な表情を眺めると、お豊は一層ひどく泣きじゃくった。
「マア、あろうことか、あるまいことか……気違いの
「ホホホホホ、お前も、お父さまと同じ様なことを云い出したのね」意外にも不二子さんは平気なものだ。「でも、そりゃ駄目。お前達が、どんなに戸締りや見張りを厳重にしていても、あの方にとっては、そんなものちっとも邪魔になりゃしないのよ。見ててごらん。今にきっとわたしを迎いに来て下さるから」
「何ですって?」お豊は頓狂な叫声を立てた。
「あいつが、あの金色のお化けが、ここへあなたを迎いに来るのですって? あなたは正気でそんなことおっしゃるのですか。あのドアには鍵がかけてありますのよ。そして、青山さんが、あの柔道二段の腕前の青山さんが、廊下に頑張っていますのよ」
「マア、精々厳重にして置く方がいいわ。難しければ難しい程、あの人のすばらしい腕前が引立つ訳なのだから。お前、金色のお化けとお云いだね。そうお化けかも知れないわ。超人はいつだって、神様でなければお化けと間違われるのですもの。でも、なんて素敵なお化けでしょう。黄金仮面! 其の名を聞いた丈けでも、胸がワクワクする様だわ」
アア、何という事だ。大鳥家の一人娘不二子さんは、とうとう気が違ってしまったのであろうか。乳母のお豊ならずとも、誰がこれを正気の沙汰と思うものか。
「わたし、喉が乾いてしまった。婆や、お紅茶を入れて来ておくれ」
暫くすると、不二子さんは、人の気も知らないで、呑気な注文をした。
「そうして、わたしを追い出そうとなさるのでしょう。駄目です駄目です。この部屋から一足だって出るこっちゃございません。お紅茶なら、女中を呼んで云いつけますわ」
乳母も仲々抜りはない。柱の呼鈴を押すと、やがて、廊下に足音がして、ドアの外から女中の声がした。
「お紅茶を二つってお云い。お前だって喉が乾いたでしょう」
「エエエ、お
お豊は半ばやけな調子で、不二子さんの云うがままに、ドアの外の女中へ伝えた。
暫くすると、書生の青山の鍵でドアが開かれ、女中が紅茶のお盆をテーブルの上に置いて立去った。ドアに再び鍵がかけられたことは云うまでもない。
「婆や、暗いわね」
不二子さんが、お豊に目で合図をした。
事実、夕闇が深くなって、部屋の中には、いつの間にか夜が忍び込んでいた。
「マア、ついうっかりして居りました。御免遊ばせ」
お豊は立って行って、一方の壁のスイッチを押した。パッと明るくなる部屋の中。
が、その一刹那、お豊が壁の方を向いている隙に、不二子さんが妙なことをした。
彼女はふところから、小さな紙包を取出すと、それを開いて、紅茶茶碗の一つに、中の白い粉を入れ、手早く
彼女が椅子に戻った時には、令嬢は已に紅茶茶碗を唇へ持って行っていた。
「サア、お前もお飲み」
やっぱり幼い時からお育て申したお嬢さまだ。こんなに口喧嘩をしていても、乳母をいたわって下さるかと、何も知らぬお豊は、ついホロリとして、云われるままに例の白い粉の入っている紅茶茶碗を取上げ、本当に喉も乾いていたので、すっかり飲みほしてしまった。
それから又、三十分ばかり、乳母の意見が繰返されたが、今度は不二子さんは、抗弁もしないで、おとなしく聞いている。そして、乳母のお喋りが一寸とだえたのをしおに、
「わたし、眠むくなったわ」
と云い出した。
「オヤオヤ、まだ日が暮れたばかりじゃありませんか。それに、夕ご飯もまだ差上げませんし」
お豊は、「何てまあ罪のない」と云いたげに、涙の顔を少しほころばせた。
「でも、何だか疲れてしまったし、こうして監禁されていたのでは、床にでもは
不二子さんは甘える様に云い捨てて、グングン寝室へは入って行った。(念の為に申し添えるが、この寝室には廊下へのドアはなく、外へ出るには、やっぱり居間の方の、唯一の出入口による
パチンと、ベッドの枕元のほの暗い電燈が点ぜられた。見ていると不二子さんは、手早く
お豊は、この無邪気な仕草を、あっけに取られて、寧ろほほえましく眺めていたが、仕方がないので、そのまま元の椅子に掛けて、忠実に見張りの役を勤めた。
ところが、そうして十分二十分とたつ内に、妙なことが起って来た。あの忠実な頑固婆さんのお豊が、どうした訳か、無責任にも、コクリコクリと居眠りを始めたのだ。
アア、分った分った。さっき不二子さんが紅茶の中へ入れたのは、眠り薬だったに違いない。そうでなくて、忠義無二の乳母が居眠りなんかする筈はないのだ。
それにしても、不二子さんは、一体全体何の為に、こんな馬鹿馬鹿しい真似をしたのであろう。部屋の中にいるお豊丈けを眠らせて見た所で、ドアには鍵がかかっているし、外の廊下には柔道自慢の青山が頑張っているではないか。いや、それ丈けではない。不二子さんがこの部屋を抜け出す為には、玄関なり勝手口なりに達するまで、幾つとなく部屋や廊下を通り過ぎねばならぬ。至る所に厳重な関所があるのだ。一人の乳母が眠った所で、何の甲斐もないことは分り切っている。
だが、読者諸君、それだからと云って、安心をしてはならぬ。不二子さんには、黄金仮面という恐ろしいうしろ楯がついているのだ。魔術師の様な怪物のことだ。何を考え出すか知れたものではない。何かしら不思議なトリックによって、全く不可能に見えることが、為しとげられるのかも知れない。そうでなくて、不二子さんが、こうまで彼が救い出しに来ることを、信じ切っている訳がないのだ。
それから半時間程たって、外の廊下に怠らず見張り番を勤めていた書生の青山は、例のドアが内部からコツコツノックされているのに気づいた。
彼は乳母のお豊が、自分を呼んでいるのかと思って、ドアにちかづいて、何の用かとたずねて見た。
すると、中からは、意外にも令嬢不二子さんの声が聞えて来た。
「お前青山なの? 早くここを開けておくれ。大変なのよ。婆やが、婆やが」
その惶しい声の調子が、何か恐ろしい事が起っているとしか思えぬので、青山は驚いて、何を考える
ところが、変なことに、誰か中からノッブを押えているらしく、ドアはやっと一二寸開いたかと思うと、バタンと閉ってしまった。
と同時に、青山が真蒼になって、ぎごちなく身構えしながら、ソロソロあとじさりを始めた。
彼は非常なものを見たのだ。
僅か一二寸開いたドアの隙聞から[#「隙聞から」はママ]、ギラギラ光る金色のものが覗いたのだ。中からノッブを押えていたのは、意外も意外、いつの間に忍び込んだのか、怪賊黄金仮面であったのだ。
だが、流石番人を仰せつかった程あって、強情我慢の青山は、真青になって歯を食いしばりながらも、持場を捨てて逃げ出す様なことはしなかった。
「だれだッ。そこにいるのは誰だッ」
彼は一間程離れた所から、ドアを睨みつけ、いざと云えば得意の当身を用いる積りで、拳をかためながら、思い切りの声をしぼって怒鳴った。
だが怪物は恐ろしく黙り返っている。
令嬢不二子さんは、無論賊を歓迎して、彼と共に逃出す積りであろうが、部屋の中には外にもう一人の人物が、見張り役のお豊がいる筈ではないか。そのお豊が声も立てぬのは変だ。若しや彼女は已に怪物の為に恐ろしい目に合ったのではあるまいか。と考えると、豪傑の青山も気持がよくはないのだ。
やがて、ドアがジリジリと開き始めた。
細い隙間から、ピカピカと長い金糸の様に光るのは、確かに黄金仮面の衣裳だ。
隙間が段々に拡がって行くに従い、金糸は見る見る太くなって、黄金の柱が立った。
上部に見えるのは、有名な黄金の仮面であろう。細い目と、例の三日月型の不気味な唇の端が、ゾッとする笑いを笑っている。
青山は、いきなり逃出したいのを、やっとこらえて、
「こん畜生」
と叫びながら、めくら滅法に、怪物めがけて突進んで行った。
だが、こんな青二才の襲撃に驚く黄金仮面ではなかった。彼は無言のまま、ゆっくりと、ドアの隙間からピストルの筒口を差出した。
「アッ」
とひるむ青山。
その瞬間をのがさず、怪物はパッとドアを開け放つと、猛然として廊下へ躍り出し、まるで稲妻の様な素早さで、青山の
「誰か来て下さい。賊だ、賊だ」
青山は怪物のあとを追いながら、家中に響き渡る声で叫んだ。
部屋部屋から、主人の大鳥氏を始め、書生などが、ドヤドヤと現われたが、ピストル片手に、飛ぶ様に走る金色の怪物を見ると、皆々
負けぬ気の青山は、それでも、たった一人で賊を追って、玄関から走り出したが、彼が門に達するまでに、突如響き渡るエンジンの音、賊はちゃんと自動車を待たせて置いたのだ。
青山が運転手を呼んで、賊を追跡する為に、車の用意を頼む頃には、怪物の自動車は、已に遠く遠く走り去っていた。
黄金仮面は不二子誘拐の目的を果さず、身を以て逃れた。不二子は安全なのだ。併し父大鳥氏は、賊を追うことは兎も角として、先ず愛嬢の安否を確めないではいられぬ。
彼は惶しく、さい前賊の逃げ出した部屋へ駈けつけた。
ところが、行って見ると、これはどうしたことだ。肝腎の見張り役、乳母のお豊は、さも呑気らしく、椅子に凭れてコクリコクリ居眠りをしているではないか。
「コレ、婆や、婆や。どうしたのだ」
大鳥氏が揺り起すと、お豊はやっと目を覚して、キョロキョロあたりを見廻している。
「不二子は? 不二子は大丈夫か」
「ヘエ、お嬢さまでございますか」乳母は寝ぼけ声で答える。
「お嬢さまなら、次の間におやすみでございますよ。ホラ、ごらんなさいまし、ああして、よくおよってございます」
お豊が指さすのを見ると、開け放ったドアの向うのベッドの中に、不二子の寝姿が見える。アア、やっぱり不二子には別状なかったのかと、大鳥氏はホッと安堵した。
「マア、わたくし、居眠りをしていたのでございましょうか」
お豊はやっとそれに気づいた様に、頓狂な調子で云った。
「そうだよ。お前にも似合わぬことではないか。お前、あの黄金仮面の賊が、この部屋に忍び込んだのを、何も知らないでいたのだね」
「エッ、何でございますって? あの化け物がこの部屋に。それは本当のことでございますか」
乳母は容易にそれが信じられぬ体だ。いや乳母のお豊ならずとも、誰がこの不思議を信じることが出来よう。窓は皆中から締りがしてある上に、その
大鳥氏とお豊とが、狐につままれた様な顔をして、ぼんやり
「アア、一足おくれました。幸、明智先生の御快諾を得て、御一緒にお出でを願ったのですが、少しの所で間に合いませなんだ。実に残念なことを致しました。併し、お嬢さまには別状もございません様子で」
「アア、不二子はよっぽど疲れていたと見えて、ああしてよく眠っています」
そこで、尾形老人は廊下に待っていた明智を室内に招じ入れて、主人大鳥氏に引合わせた。挨拶が済むと、大鳥氏は明智の為に今夜の出来事を、やや詳しく物語った。そこへ書生の青山も、賊の追跡を断念して戻って来たので、明智は彼に二三不明の点を質問したあとで、意味深い微笑を浮べながら云った。
「すると、黄金仮面が、お嬢さんの声を真似て、青山君にこのドアを開けさせた、という訳ですね」
「マア、そうとしか考えられません」
青山が答える。
「黄金仮面ともあろうものが」明智は皮肉な調子で始めた。
「そんな馬鹿げた真似をするでしょうか。目的も達しない先に、青山君に一目で分る自分の姿を見せて、いきなり逃出すというのは、何だか変ではありませんか。彼はただ逃げ出す為に、苦心をしてこの部屋へ忍び込む様な愚かものでしょうか」
「併し、不思議と云えば、もっと不思議なことがあります。賊はこの全く入口のない部屋へ、どうして忍び込むことが出来たのでしょう」
大鳥氏は名探偵の顔色を読む様にして云った。
「たった一つの解釈があります。それは、賊は一度もこの部屋へ忍び込みはしなかったと考えるのです」
明智が実に突飛なことを云い出した。
「忍び込まなかったものが、どうして逃出したのです」
正直者の青山は、びっくりして、分り切ったことを尋ねた。
「忍び込まなかったものは、逃出すことは出来ません」明智は謎の様に答えた。「ところで、その時部屋の中には、お嬢さんの外に誰もいなかったのでしょうか」
「ここにいるお豊という女が、見張り役を勤めていたのです」大鳥氏が答える。
「で、何も見なかったのですか」
「それが、迂闊なことに、居眠りをしていて、少しも知らぬというのです」
「エッ、居眠りを」
明智が叫ぶ様な声を出したので、一同思わず、隣室の不二子さんの方を眺めた。今の声が彼女の目を覚しはしなかったかと気遣ったのだ。
「まだ日が暮たばかりなのに、年を取った方が居眠りをするというのは、変ではありませんか。アア、ここに紅茶茶碗がありますね。お豊さん、あなたもこれを飲んだのですか」
乳母が飲んだと答えると、明智はその茶碗を手に取って、一寸中を覗いたかと思うと、カチャンとひどい音を立てて、テーブルに置いた。
一同が、又ハッとして隣室を見る。
明智は、さっきの叫声といい、今の仕草といい、なぜか故意にひどい音を立てている様に見えるではないか。
「お嬢さんまで眠り薬を飲まされたのでしょうか。さっきから見ているのに、あの方は身動きもなさらないではありませんか」
それを聞くと、大鳥氏がギョッとして明智の顔を見つめた。
若しや不二子は、殺されているのではあるまいかという恐ろしい考えが、ふと頭をかすめたからだ。
「僕の推察が間違っていなかったら、凡ての謎はあのベッドの中に隠されているのです」
明智は云ったかと思うと、人々の驚くのも構わず、ツカツカと令嬢の寝室へ這入って行って、ベッドの向側へ廻ると、不躾にも、不二子さんの寝顔を覗き込んだ。
「ハハハハハハハ、素敵素敵、僕達はお嬢さんの為に、まんまと一杯かつがれたのですよ。賊は決して忍び込みも、又逃出しもしなかったのです」
明智は気でも違ったのか、若い女の寝室へ這入るさえあるに、その枕元でゲラゲラ笑い出したではないか。しかも、彼の云うことは、何が何だか、まるで意味を為さぬのだ。
「不二子が、どうかしたのですか」
大鳥氏は心配に青ざめて、寝室へ這入って来る。
「どうもしやしません。ホラ、ごらんなさい。これです」
云ったかと思うと、明智はいきなり、不二子さんの頭を、シーツの中から引ずり出した。
「ア、君は、何をするんだ」
大鳥氏がびっくりして怒鳴るのと、不二子さんの頭が、コロリとベッドの下へ転がるのと同時だった。
「ワッ」
という叫声。何かしら途方もないことが起ったのを知った一同は、我先にと寝室へ駈け込んだ。
青山が不二子さんの首を拾い上げた。
「ナアンだ。こんなものですよ」
彼が手に持っているのは、人々の想像した様な、血みどろの人間の首ではなくて、柔い枕を丸めて、それに深々と黒いナイトキャップを冠せた、不二子さんの頭の
胴体はと探って見ると、毛布の下に蒲団の丸めたのが横えてある。
「すると、不二子があの……」
大鳥氏は、余りのことに、あいた口が
「そうです。ここから逃げ出したのは、本当の黄金仮面ではなくて、賊の面と衣裳を借り受けた大胆な変装姿の不二子さんでした」
明智がニコニコしながら説明した。
「無論お嬢さんの智恵ではありません。凡ては蔭にいる黄金仮面の
アア、何という素敵な手品であったろう。怪賊黄金仮面の、人の意表を突くこと、
人々は暫くの間、声を呑んで立ちつくした。
「我子ながら、それ程の馬鹿者とは知りませんでした」やがて、大鳥氏は憮然として云った。「不二子は悪魔に魅入られたのです。併し、いかに堕落しようとも、たった一人の私の娘です。このままにして置いては、死んだ妻に対しても申訳がありません。未練な様でも、娘の行衛を探して取戻さねばなりません。明智さん、あなたのお力をたのむ外はないのです」
「承知しました。
明智の絶えぬ微笑が、一刹那影をひそめ、目の底に異様な光が燃えた。仇敵黄金仮面に対する
その夜更け、戸山ヶ原の例の怪屋の地下室に、いとも奇怪なる、金色の
地下室とは云いながら、そこは、どんな貴族の客間よりも立派に飾りつけられた、居心地のよい部屋である。
桃色の壁紙、深紅のたれ幕、若草の様に柔かい絨毯、深々と身を包む長椅子のクッション、四方の壁を飾る夢の様な油絵の懸額、
朽ちはてて、空家同然の地上の建物は、この地底の天国を覆い隠す、謂わばこの世の目隠しに過ぎなかった。
一つの長椅子に、恋する男女が、身をすり寄せて腰かけていた。
男は黄金の仮面、黄金のマントに身を包んだ例の怪賊。女は邸を抜け出す時の衣裳を相手に返して、派手な模様の和服姿になった大鳥不二子。
不二子は、美しい顔を、怪賊の肩にもたせかけて、うっとりと、異様なる恋に酔いしれていた。黄金仮面は、右腕を、不二子の背中に廻して、力強く彼女を抱きしめていた。
彼等は
彼等は少しも追手を恐れることはなかった。尾形老人は地上の怪屋をつきとめたけれど、その空家同然の怪屋の下に、この様な恋の天国があろうとは、誰が想像するものか。事実、大鳥家の人々は、同じ夜、地上の怪屋を家探ししたのだけれど、地下への秘密の入口を気附かず、賊はこの隠れ家を捨てて、別の場所へ移ったものと信じ、空しく引上げて行ったではないか。それからもう五時間余り、何事もなく
アア、何という異様な取合せであろう。深窓に育った美少女と悪魔の如き怪盗の
「アラ!」
不二子が
黄金仮面は、三日月型の唇をそらして、天井を眺め、じっと聞耳を立てている。何か物音がした。ソッと歩き廻る人の足音の様なものだ。彼の鋭い耳が、いち早くそれを聞きつけたのだ。
コンクリートの天井を隔てていても、あたりが余りに静かなので、どんな物音も聞漏らしはしない。
確かに人が歩いている。頭の上の真暗な部屋の中を、物の怪のように歩き廻るものがある。
不二子にもそれが分った。彼女はおびえて、男の金色のマントにすがりつく。黄金仮面は静かにその手をほどいて、スックと立上った。
彼は不二子を椅子に残したまま、部屋を出て、暗闇の階段を音もなく昇り、秘密の出入口から上の廊下に出た。
地上には月が出ていた。その光が窓から忍入って、部屋部屋をほの白く見せている。
黄金仮面は、足音を忍ばせて、それと覚しき部屋の、ドアの前に立止った。ノッブに手をかけて躊躇した。
コツ、コツ、コツ、……まだ歩き廻っている人の足音、確かにこの部屋だ。
闘争を予期する猛獣のため息。
サッと開かれる
黄金仮面は一歩敷居の中へ踏み込むと、仮面の細い目で、部屋中を見廻した。
ガラス窓を通して、洪水の様に、部屋にあふれる月の光。その青白い月光をあびて、片隅に立ちはだかっていたものは、……流石の怪賊黄金仮面も、ギョッとして、立ちすくんでしまった。
この部屋にはそんな大きな鏡はなかった筈だ。それにも
イヤイヤ、影ではない、もう一人の黄金仮面が、突如として、月光と共にこの部屋に降って湧いたのだ。
アア、何という美しくも異様なる光景であったか。寸分違わぬ扮装の、二人の黄金仮面は、
読者は已に想像されたであろう。そこに立っていたもう一人の黄金仮面は、我等の素人探偵明智小五郎の扮装姿に外ならぬのであった。
血を
お互に身動きもしなければ、物をも云わぬ。糸より細い仮面の両眼を通して、
一人がピストルを取出せば、相手も間髪を
一歩、二歩、しさりはしないで、近づいた。両巨人の左手が、呼吸を揃えた様に、稲妻ときらめいたかと思うと、二つの銀塊が足元に落ち散った。ピストルはお互の右手から叩き落されてしまったのだ。
五分と五分の勝負だ。
兇器を失った二人は、次の瞬間、肉団と肉団とでぶつかり合った。飜える金色の衣、そのさなかに、冷然と笑い続ける三日月の口。
青白い月光の下に、転がり廻る黄金の
地下室の不二子は頭上のただならぬ物音におびえ、長椅子に
組んずほつれつ、肉団の転がり廻る音、けだものの様なうめき声、戦うものの、焔の呼吸さえも感じられる様な気がした。
死にもの狂いの闘争が、やがて五分間も続いた頃、パッタリと物音がやんだ。死の様な静けさ。
暫くすると、俯伏している不二子の身近に、物の蠢く気配がした。ギョッとして、顔を上げると、アアよかった。そこに立っていたのは、いとしの黄金仮面! 恋人は無事に帰って来たのだ。と彼女は信じた。
黄金仮面は無言のまま、不二子の手を取って、部屋の外へ、それから暗闇の階段を地上へと昇って行った。不二子はそれが何を意味するかを知らなかった。ただ、恋人の意志のままに、夢心地で、そのあとに従って行くばかりだ。
黄金仮面は、無言のままなぜか惶しく不二子さんの手を引いて、地上へと階段を昇り、走る様に廊下を通って、玄関から、門外へと出た。
門の側に、ヘッドライトを消した一台の自動車が待っていた。
「いつの間に、車の用意などして置いたのかしら」
と疑う隙もなく、黄金仮面の力強い腕が、不二子さんを車内へと押し込め、運転手に何か囁くと、彼は飛込む様に、令嬢の隣へ腰をおろした。
パッと光るヘッドライト。広い原っぱの遙か向うの枯木の枝が、闇にボンヤリ浮き出した。と同時に、デコボコ道を、車は矢の様に走り出す。アア助かった。もう大丈夫だ。
「私、怖かったわ」
不二子さんは、甘える様に云って、車の動揺につれて、黄金仮面の膝に凭れかかったが、凭れたかと思うと、びっくりした様に、ヒョイと起き直った。
「アラ!」
思わず漏れる恐怖の声。
不思議なことには、恋人の手触りがまるで違うのだ。
恋人同志というものは、顔や声ばかりでなく、身体全体のどんな微妙な隅々までも知り合っているものだが、その恋人の身体が、まるで別人の様に違って感じられるのは、どうしたというのであろう。
「マア、あなたは一体誰です。誰です」
彼女はクッションの隅へ、出来る丈け身を引いて、真青な顔で黄金仮面を見つめたまま、
金色の男は不気味に黙り込んでいた。ゾッとする程不表情な仮面の、糸より細い両眼が、じっと不二子さんの顔に注がれている。三日月型の口がニヤニヤと笑っている。
「早く、早く顔を見せて。……安心させて。……私、怖い!」
不二子さんが叫び続けるので、黄金仮面はやっと口を開いた。
「そんなに僕の顔が見たいのですか」
違う違う。決してあの人の声ではない。
「ヒイ……」
と云う恐怖の
「何も怖がることはありません。僕はあなたの味方です。あなたを恐ろしい悪魔の手から救い出して上げたのです」
男は落ちついた声で云いながら、金色の仮面をはずした。その下から現われたのは、名探偵明智小五郎のにこやかな笑顔であった。
では、怪賊黄金仮面はどうしたのか。明智との戦いに破れたことは分っている。併しまさか明智が賊を殺してしまったのではあるまい。どこかに監禁されているのか。仮令監禁したとしても、それをうっちゃって、怪屋を立去っても大丈夫かしら。その間に、あの怪物のことだ、どうして逃げ出すまいものでもない。
いやそれもそれだが、もっと気掛りなことがある。黄金仮面の正体は
併し、甚だ残念なことには、明智は賊との戦いに勝つには勝ったけれど、きわどい所で、とうとう怪物を取り逃がしてしまったのだ。正体を突きとめる隙もなく逃げられてしまったのだ。
そんなら、なぜ追駈けないのだ。不二子さんを救い出すのは第二として、先ず賊を追かけるのが当り前ではないか。と反問が来るに相違ない。
ところが、それも不可能であった。賊は逃げたのではなくて、煙の様に消えてしまったからである。室内で消えたのなら、どこかに隠し戸がある
二人の黄金仮面が、肉団と肉団とでぶつかり合ったまでは、読者諸君が御承知の通りである。それから
腕力は殆ど互角であった。明智は柔道二段の腕前があったが、敵も少し流派の違う柔道を心得ていた。強さも殆ど同じである。
「妙に癖のある柔道だな。併し馬鹿に強い奴だぞ」
明智は組んずほつれつしながら、そんなことを考えた。
だが、正邪相闘う場合には、どうしても悪人の方に弱味がある。仮令少し位力がまさっていても、勝てるものではない。殊に黄金仮面の場合では、明智の方は、仮面がとれても少しも構わぬに反し、賊の方は、仮面がはずれ、敵に素顔を見られたら、身の破滅なのだ。自然思う存分の働きが出来ぬ。
明智もそれを充分心得ていたので、格闘に際しては、ただ相手の仮面を狙った。一本でも仮面に指がかかれば、もうしめたものだ。それを引きちぎって、素顔をむき出しにしてやろうと、そればかり考えていた。
賊は明智のすばやい指先が、仮面に飛んで来るのを防ぐ丈けで精一杯だった。
その内には、いかな達人でも、身体の方に思わぬ隙が出来る。
チラと見えた大きな隙。
機敏な明智が何で見逃すものか、
「ヤッ」と叫びざま飛び込んだ腰投げが、物の見事に
バンとひどい音を立てて、怪賊の
だが敵もさるもの、投げ倒されると同時に、長い身体をローラーの様に、クルクルクルと転がって、次に来る敵の
ハッとして立直る間に、賊の方でも立直っていた。一間程の距離で、又しても睨み合いだ。
今度は賊の方が攻勢を取った。今にも飛びかかる様に両手を拡げた。明智は身を固めて、それを待ち受けた。双方一分の隙もない。一瞬間、嵐の前の不気味な静けさ。どちらも身動きさえせぬ。聞えるものはお互の呼吸ばかりだ。
と、突然途方もないことが起った。
掴みかかるとばかり思っていた怪賊が、あべこべにあとじさりを始めたかと思うと、アッという間に、窓枠に足がかかる。はずみをつけて、サッと一飛びに、屋外へ飛び出してしまったのだ。
この思いもならぬ逆手には、流石の明智も、張りつめていた気勢を、ヒョイと
しかも、益々不思議なことには、彼が気を取り直して、窓へかけ寄った時には、庭には勿論、低い生垣の外の、何の障害物もない、広い原っぱにも、見渡す限り人の影もなかった。
建物の蔭に隠れたのかと、窓を乗り越し、グルッと
夜とはいえ、降りそそぐ真昼の様な月光だ。どんな隅々でも、どんな遠方でも、人一人見逃す筈はない。生垣も検べて見た。その生垣のほかに、一町四方、樹木らしい樹木はない。あの一瞬間に、広い原っぱを突切って、向うの闇に隠れるなんて、人間業では出来ないことだ。
黄金仮面の怪物は、魔法使の本領を発揮して、地面を突破り、彼の住家の地獄へと、姿を消してしまったのであろうか。
明智は、敵の余りの離れ業に、何とも云えぬ不安を感じないではいられなかった。この様な魔法使のことだから、今の間に、どうかして地下室の不二子さんを盗み出してしまったのではあるまいか。そして、二人は手に手を取って、地獄へと姿を消したのではないかしら。夢の様に青白い月光が、ふと奇怪千万な幻想を起させた。
彼は不安に耐えかねて、賊の捜索を断念すると、急いで地下室へと降りて行った。(その降り口は、さい前怪賊自身が教えてくれたのだ)だが、流石の怪物も、不二子さんを連れ出す程の魔力はなかったと見えて、彼女はちゃんとそこにいた。
令嬢さえ取返せば、明智の目的の一半は達したのだ。慾ばって二兎を追うよりも、一先ず不二子さんを大鳥家に連れ帰るのが
不二子さんが恋人の正体を知らぬ筈はない。この美しい娘さんこそ、賊と語り彼の素顔に接した、日本中でたった一人の証人だ。その不二子さんを取返したからには、もう賊を捕えたも同然ではないか。
と云う訳で、明智の黄金仮面が、相手の気づかぬを幸、怪賊になりすまして不二子さんを自動車へ連れ込んだのである。黄金仮面の変装が、この際ハッキリ役立った訳だ。
お話は再び自動車の中に戻る。
黄金仮面を取り去った明智の素顔を見ても、不二子には、それが何者であるか分らなかった。彼女は明智に会うのは今が初めであった。
「あなたは、僕を御存知ないでしょうね。併し、決して心配なさることはありません。お父様のご依頼で、あなたをお迎えに来た明智というものです」
不二子は明智小五郎の名を知っていた。彼女の恋人である黄金仮面が――あの万能の巨人でさえも、
それと分ると、えたいの知れぬ二人の黄金仮面の恐怖は去ったけれど、其の代りに、今度は、
「この男につかまったら、もう駄目だ」という、現実的な絶望が来た。
恐らく監禁は十倍も厳重になることであろう。恋する人ともこれっ切りお別れかも知れない。それも悲しかった。だが考えて見ると、もっと恐ろしいことがある。
「あの人はどうなったのでしょう。若しや殺されてしまったのでは……」
不二子は袖の間からオズオズと尋ねた。
「あの人って、黄金仮面のことですか。僕は人殺ではありません。あの人はピンピンしています。今頃は
「では、あの人は……」
「エエ、逃げられてしまったのです。……併し僕は決して失望しません。あなたにお願いすれば、あの人は誰であるか、どこに住んでいるか、すっかり教えて下さると信じていますから」
明智はニコニコして、あっさりと、本当のことを打開けた。
「わたくし、存じません。何も存じません」
不二子さんは、身を固くして、叫ぶ様に云った。
「イヤ、今でなくていいんです。お宅に帰って、よくお考えになれば、あなたは必ず白状したくなります。世間の為にあなたの恋を捨てるのが、正しいことだと悟る時が来ます」
明智はやさしい口調で、駄々子をあやす様に云ったまま、黙り込んでしまった。
不二子は益々不安になって来た。明智が怖くなった。この男の落ちつき払った自信力に何とも云えぬ圧迫を感じた。
若しや私は、あの人を裏切る様になるのではあるまいか。みんなから「白状せよ、白状せよ」と問いつめられた時、私はあくまで口を閉じている勇気があるかしら。今度はもう、お父さまや
怖い顔をした刑事達に、柱にしばりつけられ、コチョコチョコチョコチョと、執拗にわきの下を
アア、もう駄目だ。私は白状するに極っている。どうしよう、どうしよう。恋人を
丁度その時、不二子の
「あなた、フランス語はお出来になりますか」
それが、お茶の会などで知合いになった紳士が、話題に尽きて、ふと尋ねて見るといった調子だったので、不二子もつり込まれて、何気なく「エエ少しばかり」と答えてしまってから、ハッとあることに気がついて、飛び上る程びっくりした。
マア、この人は何という怖い人だろう。そ知らぬ顔をしていて、その実何もかも知りつくしているのではあるまいか。
「もう駄目だ」
と思うと、目の前が真暗になった。
「いっそのこと、そうだ、いっそのこと」
彼女は幾度も、幾度も、決心をしては思い返した。そして、とうとう、……
「明智さん、車をとめて下さい。私を逃がして下さい。でないと……」
不二子の震え声が叫んだかと思うと、どこに持っていたのか、ピストルの筒口が、彼女の袖の間から首を出した。
「オヤ、妙なおもちゃをお持ちですね」
明智はそれを見ても、平気でニコニコ笑っている。
「僕をうつのですか。ハハハハ、あなたにうてますか。人が殺せますか。サア、やってごらんなさい」
不二子は引金に指をかけたが、相手のあまりに平気な態度に、不思議な圧迫を感じて、どうしても、それを引く力がなかった。人間の精神力には、無心な兇器をさえ征服する力がある様に見えた。
アア駄目だ、私にはとても出来ない。
又仮令このピストルで明智を殺し得たとしても、女の身で、果して逃げおおせることが出来るかしら。すぐ目の前に運転手がいる。運転手は見逃してくれても、町の人がいる。交番がある。
たった一つ残っているのは、人を
明智は、不二子の顔色がサッと青ざめるのを見た。両眼に異様な輝きの加わるのを見た。キッと結んだ唇に、はげしい痙攣の起るのを見た。そしてピストルの筒口が徐々に方向を変えて、彼女自身の胸に向けられて行くのを見た。
「アッ、いけない。およしなさい」
自分に向けられた筒口にはビクともしなかった明智も、これには色を変えた。何か訳の分らぬことを叫びながら、不二子のピストルに飛びついて行った。
だが、不二子はヒョイと身を
「明智さん、父に一言お伝え下さい。不孝の罪は
アア、何ということだ。この美しい令嬢は、日本中の人がおじ恐れる黄金仮面の悪魔を救う為に、一人の父の歎きをさえ顧みようとしないのだ。あの怪賊のどこにその様な恐ろしい魔力がひそんでいるのだろう。
流石の名探偵も、これには弱り切った。智恵も腕力も、このか弱い少女の決心を飜す力はないのだ、ピストルを奪おうとすれば、その刹那、相手は引金を引くに極っている。この場合、なまじ止めだてすることは、不二子さんの死を早めるに過ぎないのだ。
世の中には、人力の
だが丁度その土壇場に、人力以上のものが出現した。全く予期せぬ救いの手が現われた。
奇蹟だ。殆どあり得べからざることが起ったのだ。
一体全体何物が、どこから救いの手を伸ばしたのか。外でもない三尺と隔たぬ自動車の運転席から、今まで向うを向いていた運転手の右腕が、ニューッと伸びたかと思うと、忽ち不二子のピストルを奪い取ってしまった。
明智にばかり気を取られていた不二子は、不意をうたれて、もろくも敵に武器を渡してしまった。
だが、彼は果して不二子の敵であったか。イヤイヤ決して敵ではなかった。実に驚くべきことには、その運転手は、敵どころか、味方も味方、彼女の恋人、黄金仮面であったのだ。
今までは鳥打帽をまぶかく外套の襟を立てて、後頭部を隠していたので、少しもそれと気づかなかったけれど、ヒョイと振返ったその顔は、まぎれもない黄金仮面、ギラギラ光る金色のお能面が、例の三日月型の唇で、ニヤリと笑ったのだ。
奇蹟だ。彼がいつの間に、本物の運転手を追い出して、この自動車に乗っていたのか。どう考えても不可能なことだ。あの部屋の窓から飛び出して、この自動車の停っていた場所へ来るのには、是非とも見通しの庭を通らねばならぬ。明智はそこを見張っていた。庭には誰もいなかったのだ。
流石の明智も、余りの不意うちにど胆を抜かれた体である。併し、意外も意外だが、今はそれどころではない。このさし迫った危地を、如何にして脱すべきかが問題だ。
というのは、黄金仮面は不二子から奪ったピストルを、そのまま明智にさしつけて、今にも発射しようと身構えているからである。
主客の地位が一瞬にして顛倒した。攻めていた明智が攻められるのだ。
「車を出なさい。すぐ出なさい。出なければ、あなたを殺します」
仮面運転手は、例の怪物独特の、極めて不明瞭な調子で、落ちつき払って命令した。
明智は思わぬ不覚に、歯を噛み鳴らして
「出ませんか」
黄金仮面の催促だ。サア降りろと云わぬばかりに車は
だが、「出ませんか」と云われて、意地にも「ハイ」と車を出られるものではない。明智としてそんな侮辱には耐えられぬ。
とつおいつ、頭を
と、遂に、グワンと音がして、自動車がいびつになるかと疑われる、空気の激動。怪物がしびれを切らせて、とうとう第一弾を発射したのだ。
明智と不二子の口から同時に出た、何とも云えぬ恐怖の叫び声。が、仕合わせと
見ると怪物は第二弾発射の、
「畜生」
明智は遂に断念した。一先ず命を
「サヨナラ!」
憎々しげな捨ぜりふで、車はいきなり走り出す。同時に、又しても不気味なショック。敵は卑怯にも、走る車内から第二弾を発射したのだ。
「オット危い。危い」
明智は快活に怒鳴りながら、ピョンピョンと兎の様に反対の方角へ走り出した。
丸は黄金の衣裳を縫って、危うく脇腹をかすめ過ぎたのだ。
樹蔭から赤いテイルが見えなくなるまで見送ったあとで、明智は又しても、何のことか訳の分らぬ独言を呟いた。
「畜生
彼が謎の様な言葉を吐くのは、これで二度目だ。一度は不二子に「フランス語が出来ますか」一度は今の「モロッコの蛮族」だ。両方とも犯罪事件にどんなつながりがあるのか、少しも見当がつかぬけれど、無論黄金仮面の正体に関する言葉に相違ない。後々に関係のある事
賊の発砲が単なるおどかしでなくて、本当に相手を殺す気であったらしいことが、明智小五郎をびっくりさせた。非常に意外な感じがした。
彼は逃げ出した足を止めないで、元の怪屋へ取って返した。そこにまだ、仕残した用事がある様な気がしたからだ。
月あかりの生垣の外を、ブラブラ歩きながら、何かを発見しようとあせった。賊が庭の真中で煙の様に消え失せた奇蹟、その賊がいつの間にか明智の自動車の運転台に納まっていた、あの不思議な謎を解こうとあせった。
生垣に沿って、浅い溝が続いていた。彼はその溝の外を、何か口の中でブツブツ呟きながら、歩いて行った。
ふと耳をすますと、どこからか妙なうなり声が聞えて来た。確かに人間の苦悶の声だ。見渡した所、どこにも人の影さえなくて、うなり声だけが、耳のそばに聞える。又しても降りそそぐ月光の怪異だ。
「誰だ。どこにいるんだ」
呶鳴って見ると、我が声も月にこだまして、
「ウウ……」
だが、うめき声は、答える様に大きくなった。地から
彼は思わず足元に目をやった。かれた溝が帯の様に続いている。月光はその溝の中にまで
アア、いたいた。二間程向うの溝の中に
駈けつけて引起して見ると、案の定それは彼の傭った自動車の運転手であった。手足の縄を解き、
「旦那ですか。実にひどい目に合いましたぜ。あの屋根から飛び降りて来た、金ピカの怪物は、一体全体何者です」
明智は黄金仮面のことも、彼がその黄金仮面に変装する事も、運転手には知らせてなかった。仮面と衣裳は風呂敷包みにして置いて、怪屋へ行ってから変装したのだし、今は又、さっきの自動車の中へその衣裳を残して来たので、元の脊広姿に戻っていた。
「エ、屋根からだって、あいつが屋根から飛び降りたって?」
明智は運転手の異様な言葉にギョッとして聞き返した。
「エエ、屋根からですとも、まるで金色の鳥の様でした。あんまり変なので夢でも見たんじゃないかと、目をこすっている間に、そいつは生垣を越えて、鉄砲玉みたいに、僕に飛びついて来たのです。何をする隙もありやしません。それに、おっそろしく力の強い奴でね。アッと思う間に、もうぐるぐる縛られていたんです。それから、猿轡をはめて、自動車の見えないここまで担いで来て、ポイと溝の中へ抛り込みやがったんです」
併し、明智は運転手の説明を半分も聞いていなかった。彼は矢庭に生垣を飛び越すと、さっき黄金仮面と格闘した部屋の外へ駈けつけた。見ると、その部屋は一階建てで、屋根のひさしもそんなに高くはない。
「旦那、旦那、あいつはどこの野郎です。僕の車をどこへ持って行ったんです」
運転手は、息せき切って、明智を追駈けて来た。
「君、この窓枠へ手をかけて、尻上りに、あの屋根へ昇れると思うかね。人間業でそんな芸当が出来ると思うかね」
明智が飛んでもない質問をしたので、運転手はびっくりして、目をパチパチさせた。
「僕には迚も出来ない。イヤ、誰だって出来ないだろう。併し、あいつ丈は例外だ。博覧会の産業塔へ昇った奴だからね。梯子乗りの名人の仕事師でさえ
明智は気でも違った様に、喋りつづけた。
「アア、俺は何という馬鹿者だろう。屋根に気がつかぬとは。庭ばかり探し廻って、上の方を見もしなかったとは。君、あいつは庭へ飛び出すと見せかけて、窓枠に手をかけ、一振り振った反動で、足の先で屋根のひさしへ昇りついたんだぜ。そして、僕が庭を探している間、屋根の斜面に平べったくなって隠れていたんだぜ」
「それから、旦那の先廻りをして、表の方へ飛降りたという訳ですね。併し、あいつは一体何者です。旦那は御存じなんですか」
「オヤオヤ、君はまだ気づかないのかね。外に金色の化物があるものか。あいつだよ。あれが黄金仮面だよ」
「エッ、黄金仮面?」
運転手は驚きの余り、白痴の様にポカンと口を開いたまま、二の句がつげなかった。
その翌日、
それ丈けだ。黄金仮面も、不二子さんも、どこへ姿を隠したのか、いつまでたっても、見当さえつかなかった。
同時に、その日から、明智に対する賊の執拗な迫害が始まった。彼等はあらゆる手段を講じて、この唯一の邪魔者をかたづけてしまおうと企らんでいたのだ。
敵は決して姿を見せなかった。併し、明智の行く先々に待伏せしているとしか考えられないのだ。
ある時は、荷馬車の馬が、突然あばれ出して、通りかかった明智を
ある時は、工事中の建築物の足場から、明智の頭の上へ、鉄材が降って来た。
用心して外出を見合わせていると、賊の手は開化アパートの内部にまで伸びて来た。ある日食堂から自室へ取寄せたコーヒーの味が変だったので、一口飲んだばかりで、検べて見ると、毒薬が調合してあることが分った。コーヒーを運んで来たボーイは、一度も見たことのない男であった。しかも、その男は、アパートの雇人ではなくて、その日だけボーイの服装をしてまぎれ込んでいたものと知れた。
それ以来アパート内に私服刑事が
賊は明かに明智を殺そうとしている。先ずこの邪魔者を取除いた上、ゆるゆる次の犯罪に取りかかる計画に相違ない。
明智ともあろうものが、なぜかこの迫害に対しては極度に臆病であった。彼は殆ど外出しないばかりか、自室のドアには内部から錠をおろし、三度の食事の外は、アパートの廊下にさえ姿を見せなかった。
彼の綿密な注意は、郵便物にまで行届いた。返信用の封筒や切手は、皆海綿を用いて、決して口で
自室にとじこもった彼は、昼も夜も読書に余念がなかった。彼の室はアパートの二階の表に面した側にあったので、夜は用心深く締め切ったガラス窓と黄色のブラインドを通して、彼の読書する影が、表通りから眺められた。
机が窓際に置いてあった為に、彼の影は、毎晩同じ窓に同じ形で映っていた。時々廻転椅子の向を変えたり、姿勢をくずしたりする様子が、ハッキリした影絵になって、まざまざと眺められた。
夜の読書は八時から十時までと判で押した様に極まっていた。十時がうつと、電燈を消して彼は寝室へ退くのだ。
賊は手も足も出なかった。こちらからアパート内に入り込むことは、最早絶対に不可能だった。といって明智の外出を待っていては際限がない。夜毎に映る窓の影、それを彼等はどうすることも出来ないのだ。玄関には番人の外に近頃では私服刑事まで張り込んでいる。それに表は電車通りだ。とても人知れず二階の窓へ昇る隙はない。仮令昇って見た所で、抜りない明智のことだ。どうせ相当防備の手段を用意しているに相違ない。ひょっとしたら、あのこれ見よがしの窓の影さえ、賊を引き寄せる恐ろしい罠でないとは云えぬのだ。
といって、そのまま指をくわえて引込む黄金仮面ではなかった。名探偵の用意が行届けば行届く程、彼は寧ろ勇み立って、次から次へと攻撃手段を案出した。そして、遂に、あの
それは賊の迫害がはじまってから、丁度一週間目の夜であった。いつも明智が窓際の読書から寝室に退く、十時に五分前というきわどい時刻、流石の名探偵も、全く予想しなかったであろう様な、思いもかけぬ方角から、賊の最後の非常攻撃が行われ、しかもそれがまんまと効を奏したのである。
十時五分前、一台のありふれた型の円タク自動車が、
外見はその様に何のこともなかったが、若し人あって、箱の中の客席を覗き込んだなら、余りのことに、アッと驚きの叫声を立てないではいられなかったであろう。
規定に従って、車内の豆電燈はついていたし、窓にはブラインドもおろさず、客席は見通しになっていたが、その代りに、まるで引越し荷物の様な、大風呂敷包みが、三つも四つもつめ込まれ、客の姿はその蔭に隠れて、殆ど見えないのだ。
いや見えないばかりではない。その客は、風呂敷包みの蔭に坐り込み、一挺の銃を肩に当て、引金に指をかけ、筒口を開いた窓の隅に置いて、今にも発砲しようという身構えでいるのだ。アフリカの猛獣狩りではあるまいし、自動車の中から、いくら人通りが少いといっても、東京の真中の電車通りで、一体全体何を撃つ積りなのか。
イヤ、もっと恐ろしいことがある。風呂敷の間から、キラリと光って見えたのは、確かに、金製のお面だ。アア、この異様な客こそ、怪賊黄金仮面であったのだ。
車はフル・スピードのまま、開化アパートの前にさしかかった。車上の
アッと思う間に、深夜の大気を揺がして、一発の銃声。だが、誰も驚くものはない。まさかそんな所で鳥打ちを始める奴もないからだ。自動車のタイヤがパンクしたんだなと、そのまま聞き過ごしてしまった。
ただ、アパートの隣室の人々が、ちょっと驚かされた。というのは、明智の部屋の窓ガラスがひどい音を立ててわれたからだ。
弾丸は見事に命中した。ブラインドに映る明智の影が、グラグラと揺れたかと思うと、いきなり机の上にバッタリ倒れてしまった。
しめたッ。うまく行ったぞ。サア逃げるんだ。全速力で逃げるんだ。そして、車は一段と速力を増し、次の淋しい横町へと曲って行った。
それにしても、何とすばらしい射手であったか。二十
ブラインドの影は机の上に倒れたまま、背中の一部を映して、微動さえしなかった。我が明智小五郎は傷ついたのか。イヤイヤ傷ついたばかりなら、声を上げて人を呼ぶ筈だ。身悶えもする筈だ。影が少しも動かず、声も立てぬ所を見ると、若しや、アア若しや、彼は已に息が絶えたのではなかろうか。
その翌日都下の大新聞の社会面に、左の様な激情的な記事が掲載せられた。
咄々「黄金仮面」の魔手!
遂に明智小五郎氏を襲う
アパートの窓に発砲……名探偵は絶命か
昨夜十時頃、開化アパートの書斎で読書中の民間探偵明智小五郎氏は、何者かの為に、屋外より窓ガラスを通して射撃され、絶命したる模様である。聞くところによれば、明智氏は警視庁と協力して、怪賊黄金仮面の逮捕に奇怪! 奇怪! 探偵小説そのままの怪事件
名探偵の死体紛失
それを見たA子さんも小使も非常に驚き、いきなり廊下に走り出て呼び立てたが、あいにく二階に住居せる人々は、まだ一人も帰宅せず、両人は急を告げる為に階段を降りて、階下の事務所まで駈けつけなければならなかった。ほんの二三分、明智氏の死体は開け放った部屋の中に捨置かれたのだが、そのたった二三分の間に、驚くべき椿事が起った。アパートの事務員が駈けつけて見ると、いつの間にか、明智氏の死体が影も形もなくなっていたのだ。明智氏の借受けている二つの部屋は勿論、廊下から階段から、アパート内を煙を吐く自動車
一通行人の奇怪なる陳述
開化アパートの前は、電車通りとは云え、一方川に面した至って淋しい場所だが、午後十時頃には、まだ可成の通行者があった筈である。犯人は如何にして、通行者の目をくらまして、この兇行を演じ得たかが、非常な疑問とされているが、当時アパートの前を徒歩で通りかかったという同区S町○○番地大工職Dの申立てによると、丁度其瞬間にはチラホラ徒歩の通行人があったばかりで、電車も自動車も見えなかったが、そこへ水道橋の方角から、一台の円タクらしい自動車が、非常な速力で走って来て、見る見るアパートの向うの横丁へ曲って行った。その自動車が、アパートの正面にさしかかった時、突然パンクでもした様なひどい音がしたかと思うと、自動車の窓からパッと白い煙が吹き出すのが見えたというのである。この陳述を信ずべきものとすれば、賊は疾走中の自動車からアパートの窓に向って発砲したという、実に奇怪千万な想像説が成立つ訳である。右の本文の外に、明智の死体を発見した会社員夫人を初め二三の人の談話や、被害者の略歴、素人探偵としての手柄話まで掲載されていた。
名探偵明智小五郎が殺された。しかもその死体が黄金仮面一味の者によって、盗み去られてしまった。世論が沸騰しない筈はない。新時代の恐怖「黄金仮面」に配するに、一代の人気者明智探偵の死体紛失だ。かくも激情的な事件が又とあろうか。
素人探偵は果して絶命したのであろうか。若しや重態のまま、賊の巣窟にとじこめられ、死にまさる責苦を味っているのではあるまいか。そして、賊の方では、この名探偵を人質として、更に次の攻撃準備をととのえつつあるのではないだろうか。
よると触るとその噂で持ちきりだ。ある者は明智は已に絶命したと云い、あるものはまだ生きていると主張し、ここかしこで議論の花が咲いた。中にはこれを種に賭を始める者さえあった。
それから一週間程、警視庁のやっきの捜査も空しく、明智小五郎死体紛失事件は何等の進展を示さなかった。明智の行衛は勿論、黄金仮面の所在についても、髪の毛程の手掛りも掴むことが出来なかった。
捜査係長波越警部は、「蜘蛛男」以来無二の親友でもあり、唯一の相談相手でもあった、民間の智慧袋を失って、非常な失望を感じ、その加害者である黄金仮面に対しては、職務以上の憤激を覚えた。
それ丈けに、明智の行衛捜査については、死力を尽したが、武運つたなく、未だに何の手掛りさえ発見出来ないのだ。
彼は今日も、
「オヤ、部長さん、今日は馬鹿に早いぞ」
といぶかりながら、その部屋へ行って見ると、刑事部長の様子が普通ではない。何かしら、ひどく昂奮しているらしい。
「君、それを読んで見たまえ」
波越氏の顔を見るなり、何の前置きもなく、部長は一通の手紙様のものを差出すのだ。
受取って見ると、奉書の巻紙に、叮嚀な字で、左の様な奇怪な文句が書きつけてあった。
来る十五日夜閣下の邸宅に開かるる貴国実業家代表歓迎大夜会には、余 も招かれざる客として、必ず出席致すべく候 。他意あるに非 ず、貴国実業家代表諸公に敬意を表し、併せて余の職業を遂行せん為に候。此段 予め閣下の意を得たく一書を呈し候。
黄金仮面
F国大使 ルージェール伯爵閣下
「黄金仮面! 畜生、とうとう現われやがったな」
波越氏は思わず真赤になって怒鳴った。
「昨日おそくF国大使館から急使があったのです。総監は不在中なので、僕が代って面会した。書記官と通訳です。実業家代表の日程が極っているので、夜会を延期する事は出来ない。仮令延期したところで、賊の方では手を引く訳もないのだから、夜会は予定通り催すことに極めた。ついては、万一の場合に備える為に、警視庁の援助を願いたいという申出でだ」
刑事部長は、極めて無感動な、事務的な調子で、説明を続けた。
「御承知の通り、F国大使の邸宅は、大使館の構内にあるので、事が面倒です。黄金仮面は実に困った場所を狙ったものだ。だが、この重大な事件を抛って置く訳には行かぬので、外務省とも打合わせをした結果、当夜は、警視庁から二十名程の私服刑事を、目立たぬ様に大使邸に入り込ませ、充分警戒する手筈を定めました。そこで、従来の関係もあることだから、御苦労でも、君にその刑事隊の指揮をお頼みしたいのです。一つヘマをやると、国際問題になる重大な場合ですから、出来る丈け手抜かりのない様、慎重にやって貰わねばなりません」
ちょっと考えると、賊の手紙一通で、大使館や警視庁や外務省までが、大騒ぎを始めるというのは、おかしく思われるが、「黄金仮面」の妖しき影は、それ程深く人々の心にしみ込んでいたのだ。殊に当のF国大使ルージェール伯は、読者も知る通り、嘗つて日光の鷲尾侯爵邸で、黄金仮面の魔力を、まのあたり見ている丈けに、この一片の予告状を、可成重大に考えたのも無理ではない。
「奴は来ると云ったら、きっと来ます」
波越警部は、従来の度々の経験で、それを信じ切っていた。
「久し振りで奴にお目にかかる訳ですね。今度こそは、逃がしません。奴を
彼は物々しい決心の色を浮べて、云い放った。
問題の十五日までには、五日間の余裕があった。その間に波越警部は、あらん限りの智恵をしぼって、
庁内をすぐって、優秀なる二十名の刑事隊が組織せられた。彼等は
十四日には、旅行から帰った警視総監が、招待客の一人として、大夜会に出席し、それとなく部下の指揮に当ることが決定された。一盗賊の黄金仮面にとって、身に余る光栄と云わねばならぬ。
さて
麹町区Y町のF国大使館附近には、午後になると早くも、十数名の制服巡査が、配置された。F国実業家代表の一行は、この国にとって、非常に大切な賓客であったから、「黄金仮面」の一条がなくとも、この程度の警戒は当然なのだ。
定刻に近づくに従って、大使館の構内には、続々と自動車が乗り入れられ、大使館表玄関の石段を上る靴の音が、しげくなった。
その石段の上には接待係になりすました燕尾服の波越警部が、私服の二名の部下と共に頑ばっていた。
大使の二名の秘書官(その一人は通訳を兼ねた邦人秘書官であった)が、波越警部と肩を並べて来客の
来客はF国人が最も多く、邦人それにつぎ、他の諸外国の人々も混っていた。それが多くは夫人同伴で、夫々の国語を囁き交しながら入って来る有様は、さながら人種展覧会の感じであった。
知名の人々ばかりであったから、大抵は一目でそれと分ったが、中には秘書官も、波越警部も顔を見知らぬ客があった。そういう人には、鄭重に招待状を要求し、姓名を尋ね、それが日本人である場合は、波越氏と二人の部下が、三方から、ジロジロと鋭い疑惑の視線をあびせかけるという、水も漏らさぬ警戒ぶりだ。
招待者の人数はハッキリ分っていたから、最後の客が到着すると、
さて、か様にして、大使邸にとじこめられた数十人の来客中には、黄金仮面の変装ではないかと疑うべき人物は一人もいなかった。招待状と来客の頭数とがピッタリ一致していた。又、来客達はお互に知合いであって、大ホールのここかしこに一団を為し、親しげに会話を取交わしている様子を見ても、その中に全く誰にも顔なじみのない、盗賊などが混っていようとは考えられなかった。
大食堂の贅沢な晩餐会がすんだのは、午後八時頃であった。そして
警部は接待係に扮していたのだから、晩餐の席へ入り込むことも自由であったが、食卓が開かれて間もなく、食堂の隅の大花瓶の蔭に佇んで、食事中の客の一人一人を、注意深く観察していた時、彼はふと妙なことに気がついた。
それは、彼の外にも、同じ様に、食卓の人々をジロジロと眺めている一人物があったことだ。
その席には、美しい制服をつけた、日本人の給仕達が、作法正しく立働いていたが、その中に一人丈け、無作法にも食事中の賓客の顔をジロジロ眺めている奴がある。しかもそれは、無心に眺め廻すのではなく、ある特定の人物を、細くした目の隅から、さも意味ありげに執念深く観察しているのだ。
特定の人物というのは、第一が主人役のルージェール伯爵だ。伯爵をチラッチラッと盗み見る、其の給仕人の目つきには、何かしら敵意に似たものが感じられた。
二番目には、警視総監だ。余りジロジロ見ているものだから、総監の方でも感づいて、二三度不思議な給仕人を見返したが、給仕人はその
給仕人が盗み見る人物は、食卓のまわり丈けではなかった。彼の目は食卓を離れて、部屋の隅に佇んでいる、第三番目の人物にも、屡々注がれた。その第三番目の人物というのは、外でもない、花瓶の蔭の波越警部その人である。
その給仕人は、挙動がいぶかしいばかりでなく、風采も非常に変っていた。年配は三十五六に見えたが、給仕の癖に立派やかな口髭を貯え、気取った縁なしの近眼鏡をかけているのだ。
警部は予め給仕人等の身元をも充分取調べ、別段疑わしいものもないことは確めてあったので、まさかこの髭の給仕が黄金仮面の変装姿だとは思わぬが、それにしても、何となく気掛りな人物である。
彼は絶え間なく給仕の挙動を注意していた。給仕の方でも警部の存在を、頭の隅でいつも意識している様に見えた。
だが、これという程の出来事もなく、やがて晩餐は無事に終った。そして、奇抜な仮面舞踏会が始まった。
F国大使ルージェール伯爵が、豊かな趣味情操の持主であることは、彼が着任以来、古社寺、博物館は勿論、一私人の邸宅にまで出向いて、古美術を観賞するに、日も足らぬ有様であった一事を以てしても、充分察し得るのだが、伯爵の趣味は、何も古美術品に限られていた訳ではない。彼は素人歴史家であると同時に、素人文学者でもあった。
自然、彼の一挙一動には、普通外交官の思いも及ばぬ、機智と情味が伴った。レセプションなどの場合にも、屡々賓客をアッと云わせる様な、奇抜な趣向が考案された。
幸、F国大使の官邸は、ある富豪の贅沢な大邸宅を譲り受けたもので、多人数の会合にも充分間に合ったので、伯爵の異常な趣味を発揮するには、申分がなかったのだ。
さて、伯爵の今宵の趣向は、偶然にも、甚だ陰欝な種類のものであった。
それらの各部屋には、廊下に向って、壁の真中に、ゴシック風の窓が開き、夫々の窓にすき通る様な色薄絹のカーテンがはりつめてあった。
室内の調度にも、奇妙な工夫がこらされていた。ある部屋は椅子からテーブルから、壁も床も青い布で覆われ、それに準じて、例の窓のカーテンは目も醒める様な青色であった。
その次の部屋は、飾りつけが紫色である故に、窓の薄絹も紫色であった。同様にして三番目は緑、四番目は
どの部屋にも、電燈は勿論、ランプや燭台らしいものもなく、その代りには、各部屋の例の薄絹を張った窓の外の廊下に、赤々と燃え上る、焔の鉢をのせた三脚架が据えられ、その古風な焔が窓の色とりどりな薄絹を通して、各部屋を、キラキラと照らしていた。
伯爵のこの陰欝な、併し詩的な考案は、か様に書き記したのでは、誠に単純なものであるが、実際は計り知られぬ華美な、夢幻的な光景を作り出していた。とり分け、西のはずれの真黒な部屋は血色の色絹を通して暗い掛毛氈の上に落ちる
この部屋にはまた、西側の壁に、巨大な
「いみじくも考案なさいましたね。伯爵。これはエドガア・ポオの『赤き死の仮面』ではございませんか」
英国大使館一等書記官のB氏が、
「アア、気がつかれましたか」伯爵は得意の微笑を漏らしながら答えた。「私はいつも変らぬポオの心酔者なのですよ。しかし、この趣向は、少し陰気すぎはしませんでしたか」
成程陰気には相違なかった。併し、酒気をおびた数十人の舞踏者だ。それに、日頃きらびやかな宴会に慣れた人々にとって、この趣向は、ひどく気の利いたものに見えた。
男達は、無論この様な装飾を怖がる年配ではなかったし、女達も、多少は不気味に思いながらも、物珍らしさに、つい部屋から部屋へと踊り歩いていた。
さて、七つの部屋に踊り狂う、舞踏者達の服装であるが、作者は先程仮面舞踏会と記して置いたけれど、実は仮装舞踏会と云った方が、適当かも知れないのだ。
婦人達は、美しい夜会服に、伯爵から渡された黒い眼隠しをつけている丈けであったが、男達の半数は、外套の下に、思い思いの奇抜な変装を隠してやって来た。
だんだら染めの道化姿もあれば、中世の騎士の装いをしたのもあり、或は日本の簑笠をつけたもの、或は
道化好きの実業家代表の人々も、夫々変装の趣向をこらしてやって来たが、中に一人、日本の
「赤き死の仮面って、どんなお話なの、どなたか教えて下さらない?」
お茶っぴいの米国武官令嬢が、舞踏の切れ目に、突如として、自国の文学をなみした質問を発した。
だが、仕合せなことに、その令嬢は非常に美しかったので、若い男達は、喜んでこの質問に応じた。
「身体中に赤いボツボツが出来て、そこから血をふき出して、全身真赤になって、瞬く間に死んでしまうという、恐ろしい病気が流行したのです」
一人が口火を切った。
「ある公爵がその病をさけて、広い僧院の中へ、家来達と一緒にとじこもったのです。そして、夜も昼も酒宴と舞踏に、歓楽の限りをつくしたのです」
他の一人がそれにつぎ足して云った。
「ある晩のこと、公爵は丁度今夜の様な仮装舞踏会を催しました。僧院の七つの部屋が、今私達のいる部屋部屋の通りに装飾せられたのです。人々はそこで、物狂わしく踊り続けました。ところが、あの黒い部屋の大時計が、十二時をうつと、それを合図に、『赤き死』の仮装をした人物が、突然、舞踏者の中に現われたのです。人々はおじ恐れて道を開きました。仮装者はその中を、よろよろと、七つの部屋を通り過ぎ、西のはずれの暗闇の部屋にたどりついて、そこで全身に血をながして、死んでしまったのです。人々がかけ寄って、いまわしい仮面をはごうとすると、その中は空っぽで、何もありませんでした。つまり『赤き死の病』そのものが、どこからか僧院の中へ忍び込んで来たという訳です。そして、僧院内の人々は、忽ちその病に感染して、身体から血を吹き出して、断末魔のもがきを、もがきながら、死に絶えてしまいましたとさ」
三人目が、お話の結末をつけた。
「君、そんな話をしてはいけませんね」
ルージェール伯がそれを聞きつけて、不気味な物語を打切らせようとしたが、もうおそかった。
いつの間にか、そこへ集っていた婦人達は、この話を聞いて、顔色を変えた。
「マア、気味が悪い。伯爵様は、本当にいけないいたずらをなさいますわ」
一人の婦人が、ゾッとした様に呟くと、それが、奇妙な
それから又、数番の舞踏があったけれど、誰も妙に気乗りがしなかった。奥の部屋の大時計の音ばかりが、耳についた。
黒い部屋に入るものは、一人もなかった。何故ならば、夜も
踊り狂いながらも、女達はふと、燈火ゆらぐ、青い部屋の、或は紫の部屋の、ほの暗い片隅から、顔一面の醜い吹き出ものから、タラタラと血を流した、不気味な仮装者が、ヨロヨロと現われて来る幻想に悩まされた。
そして、遂に真夜中が来た。
人々は青ざめた顔を見交わして押し黙っていた。その中を、大時計の音ばかりが、まるであの世から聞えて来る悲鳴の様な、甲高い調子で鳴り響いた。
十二点鐘が、一年もかかる様に感じられた。だが、長い長い鐘の音がやっと終った。そして、その微妙な
人々は鳥肌立てて、一斉にその方を振り向いた。そしてまだ誰一人としてその存在に気づかなかった一人の異様な仮装者が、彼等の間に混っていることを発見したのである。忽ちこの新しい
「マア、綺麗ですこと。あれ一体どなたでしょうか」
さい前の陽気なアメリカの令嬢が、踊り相手の道化姿の紳士に囁いた。
「あなたは、アレをご存じないのですか」
相手はびっくりして囁き返した。
「エエ、存じませんわ」
令嬢は無邪気に答える。
「アレはね、アレはね、有名な
道化師は、この恐ろしい言葉を虚脱した様な、異様に無感動な口調で、云い放った。
一世紀前の奇怪な物語の中に起ったことが、そっくりそのままの姿で、ここに再現されたのだ。人々は二重焼付の映画を見る様な、何とも云えぬ不思議な気持に襲われた。
あのポオの恐ろしい物語では、黒檀の大時計の十二点鐘が鳴り終ると同時に、誰も見知らぬ仮装者が現われた。今もそれと全く同じではないか。ただ現われた仮装者が、「赤き死」ではなくて、それよりももっと現実的な恐怖、「黄金仮面」であった点が違っているばかりだ。
「いやな趣味ではありませんか。一体あのいまわしい仮装をして来たのは誰でしょう」
「サア、たった今まで、あんな金色の衣裳をつけた人は、一人もいなかった筈ですがね」
人々は、眉をしかめてボソボソと囁き合った。例の黄金仮面からの恐ろしい予告状のことは、ルージェール伯身辺の人々と、警視庁の外には、誰にも知らせてなかったので、それが、若しかしたら、今世間を騒がせている、本当の怪賊ではあるまいかと、疑うものは誰もなかった。皆来客の一人の、人の悪い仮装姿だと信じていた。
そうは信じながらも、あの金色のお能面みたいな、ゾッとする程無表情な顔を見ると、婦人達は申すまでもなく、滑稽なことには、甲冑姿いかめしい男子までが、色を変えて、ジリジリとあとじさりを始めた。
「マスケ・ドル! マスケ・ドル!」
不気味な囁きが、
黄金仮面の人物は、群集のあとじさりの為に広く開かれた通路を、丁度物語の「赤き死の仮面」がしたと同じ様に、ヨロヨロとよろめきながら、部屋から部屋へと歩いて行った。
彼が部屋部屋を通過するに従って、全身を包んだ金色まばゆき大マントが、或は青く、或は紫に、或は橙色に、ギラギラと、夫々の色の焔の様に、美しくも輝いて見えた。
其時、楽師達のいる廊下に立っていた波越警部は、ふと室内のざわめきに気づいた。
「黄金仮面、黄金仮面」という、波の様な呟き声を耳にした。
ハッとして、彼が青い部屋に駈け込んだ時には、怪物は已に二部屋ばかり向うを歩いていた。
「黄金仮面をごらんになりましたか。そいつはどちらへ行きました」
警部が群集に向って慌しく尋ねると、誰かがゲラゲラ笑いながら答えた。
「黄金仮面か、馬鹿なお茶番を思いついたものだね。どこへ行ったって? どこへ行くものかね。あの向うの端の黒い部屋へ入って行ったのさ。赤き死の仮面がした様にね。アハハハ……」
その日本人は、ひどく酔っているらしかった。
警部はいきなり、その方へ走り出した。
彼は、喜びとも恐れともつかぬ感情の為に、胸がはち切れ
次の部屋へ来ると、怪物を追駈けているのは、自分ばかりでないことを発見した。先頭に立って走るのは、主人のルージェール伯爵だ。彼は仮装をしていなかったので、燕尾服の二本の尻尾が、走るにつれて、黒いフラフの様になびいていた。
少しおくれて、もう一人の男が走っている。その男はひどく風変りな仮装をしているので、何者とも分らぬ。日本人かどうかさえ曖昧だ。身体の線の通りに、ピッタリ
そのルージェール伯と、
走りながら、警部は用意の
「何事です。君達はどうしたのです」
舞踏者の群集の中から、いぶかりの声が湧き起った。彼等はこの三人が三人とも、気でも違ったのではないかと疑った。それ程伯爵達の行動は、突飛にも滑稽にも見えたのだ。
「みなさん。注意して下さい」
伯爵は走りながら、群集に向って呼びかけた。
「あの金色のものは、本当の黄金仮面です。私は今夜彼がこの席へ忍び込んで来るという、予告状を受取っていたのです」
その呼声で、部屋部屋のざわめきがピッタリと静まった。そして呼吸の音さえ聞える程の、異様な静寂が七つの部屋を占領した。
人々は誰も、黄金仮面がどんなに恐ろしい奴だかを、よく知っていた。
「アア、危い。伯爵は『赤き死の仮面』を追った公爵の様に、あいつを追っかけているけれど、プロスペロ公は、それを追ったばかりに、黒檀の大時計の前で、命を失ったのではないか」
人々は、何から何まで、ポオの不気味な物語と、そっくりそのままに、進行するのを見て、慄然としないではいられなかった。
一方黄金仮面の怪物は、とうとう黒天鵞絨の部屋に足を踏み入れた。真赤な薄絹を通して、廊下の火焔が黄金の衣裳を燃立つ血潮の色に
三人の追手は、不吉な暗黒と血潮の部屋に入ることを、流石に躊躇して、その入口に踏み止まった。
「フフフフフフフフ」
部屋の中から、例の半ば押し殺した様な、不気味な笑い声が、地獄の底からの様に響いて来た。
ルージェール大使は、躊躇する三人の中で、最も勇敢であった。彼は、二人を入口に残したまま、単身魔の部屋へ躍り込んで行った。
躍込んで行ったかと思うと、バン……という発砲の音、野獣の様なうめき声、そして、ドシンと人の倒れる響。
どちらが発砲したのか? どちらが倒れたのか?
今は一瞬も躊躇すべき時ではない。波越警部と、西洋悪魔に扮した人物は、殆ど同時に部屋の中へ飛び込み、
「いけません。大切の犯人です。殺してはいけません」
警部は相手に通じぬ日本語で、気違いの様に叫んだ。今この怪物を絶命させては、親友明智の生死も、大鳥令嬢の行衛も、分らなくなってしまうのだ。
怪物は、一匹の金色のけだものの様に、黒天鵞絨の床の上に傷つき倒れていた。弾丸は胸をうち抜いたと見えて、黄金マントの胸からと、三日月型の金色の唇からと、糸の様な血潮が、タラタラと流れていた。致命傷だ。しかしまだ全く絶命してはいなかった。
「マスクを、マスクを」
伯爵が叫ぶ。
警部は、怪物の上に身をかがめて、その無表情な黄金仮面に手をかけた。手をかけて思わず見震いした。
アア、この仮面の下には、一体全体何が隠されていたのであろう。今こそそれが分るのだ。世間は、被害者達は、そして警視庁は、どんなにか、この一瞬間を待ち望んだことであろう。それを思うと、波越警部は、指が震えた。歓喜の余り、いきなり号泣したい衝動を感じた。
だが、遂に黄金仮面は取去られた。
その下から現われた顔は、意外、意外、ルージェール伯の
大夜会の始まる前、波越警部と肩を並べて、来客の受附係を勤めていた、あのおとなしやかな通訳官が、この怪物であろうとは、波越氏はあっけにとられて、暫く、伯爵と西洋悪魔の顔を、キョロキョロと見比べるばかりであった。
その時、さい前の
警部は長官の来着に励まされて、気を取直した。
「黄金仮面。F国大使通訳官。犯人は治外法権にかくれていたのだ。分らなかったも無理はない。成程、これで辻褄が合うわい。鷲尾侯爵の盗難も、こいつの仕業とすれば合点が行く。あの時こいつはルージェール伯の随員として、美術館へ入ったのだからな」
警部は素早く頭を働かせた。それから、やや威丈高になって、
「君達はこの犯人を、直ぐ病院へ運んでくれ給え。そして、捜査課へ電話をかけてね、黄金仮面は、唯今取押えましたと伝えてくれ給え」
と命令した。
だが、刑事達は躊躇した。波越氏もギョッとして部屋の中を見廻した。どこからか、異様な笑い声が聞こえて来るのだ。
見廻わしても、誰も彼も真面目くさった顔付だ。笑いの影さえ見当らぬ。だが、たった一人丈け、表情の不明な人物がある。それは例の西洋悪魔に扮した男だ。彼の顔は覆面に隠れて、笑っているのか泣いているのか、少しも分らぬ。
総監も、警部も、刑事達も、伯爵さえも、期せずして、西洋悪魔を見つめた。アア、やっぱりこの男だ。あの押し殺した様な笑い声は、この真黒な悪魔の口から漏れているのだ。
「どうかしたのですか。何がそんなにおかしいのです」
警部が腹立たしげに尋ねた。
「イヤ、ごめん下さい。人騒がせのお茶番が、あんまりおかしかったものですから」
悪魔は明かに日本人であった。
「お茶番だって。何を云っているのだ。君は、これをお茶番だと思うのですか。……君は一体どなたです。覆面をとって下さい」
「アルセーヌ・ルパンは、こんな男じゃありませんよ」
悪魔は警部の言葉にお構いなく、突然妙なことを云って、倒れている犯人を指さした。
「アルセーヌ・ルパンだって? ルパンがどうしたのです」
警部は、こいつ、有名なフランスの紳士盗賊の幻に悩まされている、気違いではないかと疑った。
「黄金仮面と云われている盗賊は、ルパンです。ルパンでなければならないのです」
警部は、この狂人の突飛千万なたわごとを相手にしなかった。その代りに部下に向って、
「こいつの覆面をとれ」
と命じた。
刑事達は、西洋悪魔に走り寄って、有無を云わせず、覆面を引きちぎってしまった。
覆面の下には、縁なし眼鏡が光っていた。豊かな口髭が鼻の下を覆っていた。
「ヤ、貴様、ここの給仕人じゃないか」
波越氏がびっくりして叫んだ。
晩餐の際、伯爵や総監や、波越警部自身を、意味ありげにジロジロと盗み見ていた、あの不思議な給仕人に相違ないのだ。
「
怒鳴りつけられても、不思議な給仕人は、平気な顔をして、警部などは相手にせぬとばかり、ツカツカと警視総監の前に進み出た。
「総監閣下、この瀕死の重傷者に、二三の質問をお許し下さいませんでしょうか」
彼は益々気違いめいたことを云い出すのだ。
総監も面喰ったが、いかめしい顔に、
「許さぬものでもないが、君の姓名は? 一体何の理由で、そういう不躾な要求をするのか」
悪魔に扮装した給仕人は、総監の威厳を物ともせず、顔と顔が触れんばかりに近づいて、
「閣下、僕です。まさか、お見忘れではありますまい」
と、思いもよらぬことを云い出した。
総監はその声がさい前の声とまるで違っていたので、ふとある人物を思い出した。あり得ない事だ。彼は殺されたのではないか。併し、併し、この声音、そして、この顔。総監は半信半疑で、じっと相手を見つめた。すると、不思議なことには、下品な給仕人の顔の下から、徐々に、ある知人の相貌が、浮び上って来た。
「オオ、君は!」
総監はうめき声を発して、思わず一歩あとに下った。
給仕人はニコニコ笑いながら、眼鏡をはずし、口髭をめくり取った。そして、その下から現われたのは、外ならぬ、我等の素人探偵明智小五郎の顔であった。
それを見ると、一座に異様などよめきが起った。時も時、場所も場所、死んだと思っていた名探偵が、こんな所へ姿を現わそうとは、一同アッと云ったまま、相手の顔を見つめるばかりだ。
やがて、気を取直した波越警部が、先ず明智に尋ねる。
「明智君、御挨拶は抜きにして、君がどうして生き返って来たかもあとでゆっくり聞くとして、……今云った妙なことは、あれは一体どういう意味だね」
「黄金仮面はアルセーヌ・ルパンだ。突飛に聞えるかも知れない。僕も長い間迷っていた。だが、二三日以前、やっと思違いでないことが判明した。ルパンは今この東京にいるのだ」
明智も流石に昂奮している。
「では、ここに倒れているのは?」
「真赤な偽物だ。ルパンの常套手段の、お茶番に過ぎない」
アア、この驚倒すべき事実! フランスの紳士盗賊、一代の
「明智君、冗談を云っている場合ではないよ」
総監は皮肉な微笑を浮べて云った。
「アア、閣下はお信じなさらない。ご無理ではありません。併し、犯罪に国境はないのです。世界的美術蒐集家アルセーヌ・ルパンが、日本の古美術品に
明智が
「議論を聞いているのではない。わしは証拠がほしいのだ。動かし難い証拠が見せて貰い度いのだ」
「証拠がなくて、こんなことを云いだす僕ではありません。例えば、ここに倒れている男が、僕の質問に答え得るとしたら。それ丈でも、充分閣下に御満足を与えることが出来ましょう」
「よろしい。この男に質問をして見給え」
やっと総監の許しが出た。
浦瀬は已に断末魔の苦悶に陥っている。ぐずぐずしている場合でない。明智は瀕死の男にかがみ込んで、催眠術でもかける様に、両眼に全精神力を集中しながら、力強い声で、質問を始めた。
「オイ、君、しっかりし給え。僕の声が聞えるかね」
重傷者は、上ずった目を、明智の顔に注いだ。
「ウン、聞えるんだね。では、今僕が尋ねることに答えるのだぜ。非常に重大な問題だ。たった二言か三言丈け、どうか答えてくれ給え」
「ハヤク、ハヤク、コロシテクレ」
浦瀬は苦悶に耐えかねて、血泡のたまった唇を動かした。
「よし、よし、すぐに楽にしてやる。その代りに答えるのだよ、いいか。君は黄金仮面の部下だね。同類だね。もう死んで行くのだ、嘘をつくのではないぜ」
「ウン」
「部下なんだね」
「ウン」
「それから、これが一番大切な点だ。君の口から云ってくれ給え。黄金仮面の正体は? あれは日本人ではないね」
「ウン」
「名前は? その名前を云うのだ。サア、早く」
「ルパン……ア、ア、アル、セーヌ、ルパン」
問答を聞くに従って、流石の総監もこの夢の様な事実を信じない訳には行かなくなった。彼は波越警部と共に、瀕死の男の上にかがみ込んで、彼の断末魔の告白を、一言も聞漏らさじと耳をすました。
明智は息づまる様な質問を続ける。
「それで、アルセーヌ・ルパンはどこにいるのだ。君はそのありかを知っているだろうね」
「ウン」
「知っているね。サア、たった一言、云ってくれ給え。あいつは今、どこにいるのだ」
重傷者は、もう舌が
「浦瀬君、頼みだ。もう一言、たった一言。サア云ってくれ給え」
明智は昂奮の余り、思わず重傷者をゆすぶった。それが、眠りこけて行く瀕死者を、無残にも目覚めさせた。
「ルパンはどこにいる?」
「コ、コ、コ、コ、……」
「何だって? もっとハッキリ、もっとハッキリ」
「コ、コ、コ……」
だが、瀕死者は、同じ片言を繰り返すばかりだ。
「此処だね。此処にいるというのだね」
「ウン、ウン」
「この部屋にいるんだね。サア、どこに、指さしてくれ給え。それが出来なければ、眼で知らせてくれ給え」
浦瀬は最後の力をふりしぼって、右手の指を動かした。そして部屋の一方を指し示した。殆ど白くなった両眼もその同じ方角に釘づけになっている。
アア、何ということだ。世界の侠盗、アルセーヌ・ルパンが、この東京に、この大使邸に、この黒天鵞絨の部屋にいると云うのだ。
一同息を殺した。いつの間にか部屋の入口に殺到していた舞踏の群集も、刑事の一隊も、総監も、波越氏も、明智小五郎も息を殺した。息を殺して、瀕死者の指のさし示す所を見た。彼の両眼の釘づけになった箇所を見た。
そして、そこには、浦瀬の指し示した所には、F国大使ルージェール伯爵が凝然として佇んでいたのである。
百千の目が、黒檀の大時計を背にして立ちはだかっている、たった一人の人物、燕尾服姿のルージェール伯爵に集中された。
死に絶えた様な沈黙、身動きする者もない長い長い睨み合い。
「ワハハハ……、これはいかん。いやに滅入ってしまったぞ。……サア、皆さん舞踏を続けて下さい。伯爵も、どうかあちらへ。跡始末は我々の方でうまくやって置きます」
警視総監は、日本語で云いながら、手真似をして見せた。
「閣下!」
明智が血相を変えて、総監を見つめた。
「この明瞭な事実を、お信じなさらないのですか」
「アハハハ……」総監は腹を抱えんばかりに哄笑した。「君、そりゃいかんよ。いくら名探偵の言葉でも、こいつばかりは採用出来ん。仮りにも君、一国の特命全権大使ともあろうお方が、盗賊を働くなんて、そ、そんなバカなことが、ハハハ……」
「この男が、証人です」
明智は、已に息絶えた浦瀬秘書官を指さした。
「証人? バカな。こいつは伯爵に射殺された恨みがある。それに瀕死の苦しまぎれ、血迷った奴が何を云うか分ったものではない。一秘書官の言葉を信ずるか、F国大統領の信任厚き全権大使を信ずるか、一考の余地もないことだ」
「では、これをごらん下さい。僕は何の証拠もなくて、迂闊にこの様な一大事を口にするものではありません」
明智は云いながら、黒毛糸シャツのふところから、大事そうに一通の西洋封筒を取出して、総監に示した。
総監は明智の一本気が腹立たしかった。彼は一秘書官よりも全権大使を信じたかもしれぬが、同時に、全権大使よりも、更らに名探偵明智小五郎の手腕を信じていた。事実、ルージェール伯こそ、彼の力説するが如く、大侠盗アルセーヌ・ルパンかも知れないと、心の一隅には、深い疑心を生じていた。だが、ここで事をあらだてるには、余りに問題が大き過ぎる。のみならず、手出しをしようにも、警視総監の権限では、一国の全権大使をどうすることも出来ないのだ。
そこで、さりげなくこの場をつくろって、
だが、もう仕方がない。明智は何やら証拠物を持出した。彼のことだ。どんな重大な証拠を握っていまいものでもない。
「待ち給え」
総監は流石に
「みなさん。暫く御引取り下さい。波越君丈け残って、外の刑事諸君も、一度外に出てくれ給え。そして、そのドアを締めて下さい」
明智もそれに気づいて、総監の言葉を外国紳士貴婦人達に通訳した。
入口から覗いていた人々が立去り、ドアが閉まると、総監はその前に立ちふさがる様にして、ジロジロとルージェール伯爵に流し目を与えながら、明智に言葉をかけた。
「手紙の様だが、それはどこから来たのかね」
「
「フン、巴里の
「お聞き及びでしょうと存じますが、元巴里警視庁刑事部長のエベール君からです」
「エベール?」
「そうです。ルパンが関係した、二つの最も重大な犯罪事件、ルドルフ・スケルバッハ陰謀事件と、コスモ・モーニングトン遺産相続事件で、ルパンと一騎打をした、勇敢な警察官として、よく知られている男です。当時の警視総監デマリオン氏の片腕となって働いた男です」
「成程、して?」
「今では職を退いて、巴里郊外に引退していますが、僕は、先年巴里へ行きました時、同君を訪ねて、一日話し込んだことがあります。彼は警察事務にはもう飽き飽きしたといっていましたが、談
「で、そのエベール君から、何を云って来たのだね」
「僕は電報で、ルージェール伯爵の身元調査を頼んでやったのです。伯爵はシャンパーニュの大戦で一度死を伝えられた人物です。そして、彼が巴里の政界でメキメキと売出して来たのは、大戦の後でした。ここに恐ろしい疑いがあるのです。大戦以前のル伯と、戦後のル伯とが、全く同一人であるかどうか。万一別人であったならば、それはアルセーヌ・ルパンではないか。ということを尋ねてやったのです。ルパンと聞くとエベール君、異常な熱心で調査を始めてくれました。戦友を探し出し、伯爵の幼馴染を探し出し、写真を蒐集し、あらゆる方面を調査した結果、大統領を初め戦友達の一大錯誤を発見したのです。ル伯はシャンパーニュで、本当に戦死したらしいことが分ったのです。併し、事は余りに重大です。迂闊に一退職警察官の進言を採用することは出来ません。盗賊に大統領の親書を与え、国家の代表者として、日本皇帝陛下に
警視総監も、波越警部も、云うべき言葉を知らなかった。黄金仮面は稀代の怪賊であったばかりではない。西洋の
「わたしは、あちらへ引取っても差支ありませんか」
しびれを切らせたルージェール伯が、三人の顔を見比べながら、彼の国の言葉で尋ねた。
「失礼しました。伯爵。お察しでもございましょうが、我々は警察の者です。殺された男が、有名な盗賊とは申せ、兎も角ここに殺人事件が起ったのです。被害者の身元も調べなければなりません。又、ご迷惑ながら、大使閣下に二三御尋ねしなければならぬ点もございます。今少々この部屋に御止まりを願わねばなりません」
明智がフランス語で、うやうやしく答えた。
「さっき、この男は、わたしを指さして、何を云ったのですか」
明智が外国語を話すことが分ると、大使は落ちついた調子で尋ねた。
この質問にあって、明智は一刹那困惑の表情を示したが、思い切った様に、ズバリと云ってのけた。
「閣下が、有名な紳士盗賊アルセーヌ・ルパンだと申したのです」
伯爵は、それを聞くと、別に驚いた様子もなく、じっと明智の顔を眺めた。明智の方でも、必死の微笑を浮べながら、大使を見つめていた。
数秒間奇妙な沈黙が続いた。
「ハハ……、このわしが、……全権大使ルージェール伯爵が、ルパンだというのかね。そして、君は、それを信じているのかね」
伯爵は奥底の知れぬ、薄笑いを浮べている。
「若し信じていると申上げたら、閣下はどうおぼしめしましょうか」
明智は必死の気力を振い起して云った。
「あらゆる事実が、それを物語っているとしたら、仮令大使閣下であろうとも、御疑い申上げる外はないのです」
「あらゆる事実? それを云ってごらんなさい」
大使は相変らず、迫らぬ態度を続けていた。
「黄金仮面は滅多に口を利きません。
「それで?」
「黄金仮面は、日本に一つしかない様な、古美術品ばかり狙っていますが、並々の盗賊には、そういう有名な品を処分する力がありません。ルパンの様に私設の博物館を所有するものでなくては出来ない芸当です」
「それで?」
「大鳥不二子さんは、なぜ恐ろしい黄金仮面に恋をしたか。それは彼がアルセーヌ・ルパンだからです。あの気高い令嬢が、若し盗賊に恋をするとしたら、世界中に、ルパン一人しかありません。ルパンはどんな女性をも惹きつける、恐ろしい魔力を持っているのです」
「ルパンがそれを聞いたら、さぞかし光栄に思いましょう。併し、わしには何の関係もないことです」
「鷲尾侯爵家の如来像が偽物と変っていました。その偽物の像の裏に
「…………」
「そして、あの盗難のあった頃、鷲尾侯爵邸を訪れた外国人と云えば、閣下、あなたの外にはなかったのです。僕は当時已に、黄金仮面がアルセーヌ・ルパンであり、ルパンは即ちルージェール大使であることを、薄々感づいていたのです」
「ハハハ……、愉快ですね。このわしが世界の侠盗アルセーヌ・ルパンか。で、証拠は? 空想でない証拠物は?」
「浦瀬の証言です」
「こいつは気狂いだ」
「エベールの調査です」
「ナニ、エベール?」
伯爵は、この時初めて、やや顔色を変えた。
「御記憶でしょう。ルパンの仇敵、元のエベール副長です。彼がルージェール伯爵の身元を調査した結果、何もかも分ったのです。大統領は、閣下を捕縛させる為に、あのエベールを日本へ送りました。閣下は已にF国政府の信任を失われたのです」
伯爵は、遂に絶体絶命となった。返すべき言葉がない。だが、彼は少しも騒がなかった。この様な場合には、千度も出会ったことがあるからだ。騒がぬばかりか、却って高らかに笑い出した。
「アハハハ……、日本の名探偵明智小五郎君、よくもやったね。イヤ、感心感心、アルセーヌ・ルパン、生涯覚えて置くよ」
「で、君は白状した訳だね」
巨人と怪人とは今や対等の置位に立った。
言葉が分らぬ為に、あっけにとられて佇んでいる、警視総監や波越警部をのけものにして、フランスの侠盗と、日本の名探偵は、不思議な対話を続けた。両巨人、互に綿々たる
「俺は少し日本人を軽蔑し過ぎていた様だね。アパートの窓に映っていたのは、君だとばかり思っていた。そして、君は死んでしまったと信じていた。君さえなきものにすれば、今日の様なことも起らないで済むのだからね」
伯爵は煙草に火をつけて、紫色の煙を
「それを褒められては、
明智は、奇妙な西洋悪魔の扮装のまま、伯爵のルパンの前を、右に左に歩きながら、ニコニコして喋り続けた。
「だがね、ルパン君、君を笑ってやることがあるよ。流石のルパンも少し
「浦瀬は日本人だ」ルパンは
「畜生ッ」明智は憤激した。「君にして、白色人種の偏見を持っているのか。実を云うと僕は、君を普通の犯罪者とは考えていなかった。日本にも昔から義賊というものがある。僕は君をその義賊として、いささかの敬意を払っていた。だが、今日只今、それを取消す。残る所は、ただ
「フフン、君に軽蔑されようが、尊敬されようが、俺は少しも痛痒を感じぬよ」
「アア、アルセーヌ・ルパンというのは、君みたいな男だったのか。僕は失望しない訳には行かぬ。第一君は、何の為にこの浦瀬に黄金仮面の扮装をさせたのだ。人々にこれこそあの怪賊だと思い込ませて、一思いに
「フフフ……、耄碌したかしないか、決めてしまうのは、まだちっと早かろうぜ」
ルパンは煙を輪に吐いて、ふてぶてしく空うそぶいた。
「という意味は?」
「という意味は……これだッ! 手を上げろ!」
突如として、ルパンの口から雷の様な怒鳴り声がほとばしった。
彼は黒檀の大時計の前に立ちはだかって、明智を初め三人のものに、ピストルの筒口をむけ、油断なく身構えをした。
相手の態度の余りの急変に、明智さえも、ちょっと度胆を抜かれて、立ちすくんだ程だ。警視総監も、波越警部も、仮令武器を隠し持っていても、それを取出す余裕はなく、筒口をさけて、タジタジとあとじさりをするばかりであった。
「身動きでもして見ろ。容赦なくぶっ放すぞ。ハハハ……これでもルパンは耄碌したかね。俺はまだ日本の警官達に捕まる程間抜けではない積りだよ」
だが、流石の兇賊も、うしろには目がなかった。仮令うしろを眺め得たとしても、時計の中までは気がつかなんだ。
黒檀の大時計の蓋が、音もなく開いたかと思うと、そこから飛び出した人物がある。そして、飛び出すが早いか、彼はいきなりルパンのピストルを持つ手に掴みかかった。
「ハハハ……、フランスの警察官には捕まる間抜けか」
その男は、早口のフランス語で叫んだ。
ルパンは、その声に聞き覚えがあった。ギョッとして振向くと、そこにいかめしい同国人の顔があった。
「ア、貴様、エベール!」
「そうだ。嘗つて君の部下であったエベール副長だ。よもや見忘れはしまい。俺の方でもよく覚えていたよ。明智さん、こいつこそ、ルパンに相違ありません」
「アア、ではあなたは、あの手紙と同じ船で……」
「そうです。上陸すると
「エベール、君は特命全権大使を捕縛する権能を持っているのか」
ルパンが昔の部下を叱りつけた。
「大統領閣下の直命だ。検事の令状も持参している。神妙にしろ」
ルパンは武器を取り上げられた。反対に、波越警部がポケットのピストルを取出して、
流石の怪人も今は最早や万策尽き、進退ここに
「オイオイ、いやにしんみりしてしまったじゃないか。何が悲しいのだ。俺の最後を憐んでくれるのかね。ハハハ……、つまらない取越苦労は御無用に願い度いね。俺は別に捕縛されることを承諾した覚えはないぜ」
アア、何たるふてぶてしさ。この最後の土壇場になっても、ルパンはへこたれない。大口を開いて笑っている。怪物だ。奥底の知れぬ化物だ。
「貴様の承諾を求めているんじゃない。我々は確実にルパンを捕えたのだ。天変地異でも起らぬ限り、ルパンの運命は尽きたのだ」
エベールが、やや感慨をこめて云った。
「天変地異が起らぬ限り? フフン、ではその天変地異が起ったらどうするのだ」
「ホオ、貴様、それを起せるとでも云うのか」
「云うのだ」
「ナニ、なんと云うのだ」
「俺の力で天変地異を起して見せるというのさ」
ルパンはさも自信ありげに、せせら笑った。
× × ×
ドアの外の刑事達は、中の人達が、いつまでたっても出て来ないので、不審を抱き始めた。ドアに耳を当てて見ると、さい前まで微かに聞えていた話声もパッタリやんで、しいんと静まり返っている。変だ。
「波越さん。波越さん」
「総監閣下」
彼等は口々に呼びながら、ドアを叩いた。だが、何の返事もない。
「変だぜ。開けて見ようじゃないか」
誰かが云うと、一同同意したので、手近かの一人が、ソッとドアを開いて、その隙間から中を覗き込んだ。
「アラッ、これはおかしい。誰もいやしないぜ」
「いないって? 一人もか?」
「猫の子一匹いやしない」
そこで、一同ドヤドヤと室に
警視総監と、波越警部と、明智小五郎と、ルージェール伯と、浦瀬秘書官の死骸と、刑事達が知っている丈けでも五人の人物が、密閉された、どこに隠し戸もない部屋の中で、煙の様に蒸発してしまったのだ。溶けてなくなってしまったのだ。
刑事達は狐につままれた様な、夢でも見ている様な、変な気持になって、きょろりと顔を見合わせたまま、突立っている外はなかった。
警視総監が、溶けてしまったなんて、そんなべら棒なことが報告出来るものか。だが、事実、総監ばかりではない、五人の大の男が、あともとどめず溶解してしまったのだ。
「俺の力で天変地異を起して見せる」とルパンが広言したのは、この不可思議な人体溶解術を意味していたのであろうか。といって、いくらルパンの智慧でも、まさか人間を溶かすことは出来ない。では、五人のものはどうなったのか。
お話は再び室内でのルパン対エベールの応対に戻る。
さしもの兇盗も、今や絶体絶命となった。我がピストルはエベール氏の為に取上げられ、反対に敵のつきつけたピストルの前に、彼は身動きすら出来ぬ立場となった。
最早や天変地異でも起らぬ限り、ルパンの逮捕は確実である。仇敵エベール氏は小気味よげにあざ笑った。
「どうだ、アルセーヌ・ルパン。俺の気持を察してくれ、十数年来の
エベール氏が乱暴なフランス語であびせかけた。
「オイ、エベール君。君はさっき俺が約束したことを忘れた様だね」
怪盗ルパンは、この絶体絶命の窮地に立って、少しもへこたれなかった。口辺に異様な微笑を絶やさず、快活に口を利いた。
「約束? ハテナ、何を約束したのだね」
「ハハ……、空とぼけても駄目だ。君はさっきから、それを非常に心配しているじゃないか。ホラ、俺は決して君に捕縛されないという約束さ」
「アア、あの引かれ者の小唄のことか。ナアニ、少しも心配なんかしないさ。捕縛されないと云ったところで、現に捕縛されたも同然じゃないか。君はピストルを取上げられてしまった。我々の方には三挺のピストルがある。それにドアの外には、日本の警官達が山の様にひしめき合っている。如何にルパンの約束でも、こればっかりは信用しないよ。この重囲を逃がれるなんて、神様だって不可能なことだ」
エベール氏はむきになってきめつけた。大きなことを云うものの、内心ひそかに恐れを為しているのだ。彼はルパンというものを知り過ぎる程知っていた。
「ハハハ……、エベール君、少し怖くなって来た様だね。神様には不可能でも、このルパンには可能かも知れないぜ。君はさっき何とか云ったね、そうそう、天変地異の起らぬ限り、俺は
喋っている内に、ルパンは益々快活になって行く。それに反してエベール氏の方は、少しずつ青ざめて行く様に見えた。
「馬鹿なッ。俺は断言する。アルセーヌ・ルパンは確実に逮捕されたのだ」
「ところが、俺は今この部屋を出て行こうとしているのだ」
ルパンが傲然として云い放った。
「ハハハ……、出るなら出て見るがいい。ドアの外は警官の山だぜ」
エベールが青ざめた顔を引歪めて怒鳴った。
「警官の山? そんなものは我輩にとっては無に等しい。『開け、セザーム』俺はこの呪文で、大牢獄の
云いながら、大胆不敵の兇賊は、波越警部と、明智小五郎と、エベール氏とが、一斉につきつけるピストルの筒口を、全然無視せるが如く、悠然とドアに向って歩を運んだ。
「エベール、長官の命令だ。ドアを開け」
ルパンが
「ハハハ……、つまらないお芝居はよせ。そのドアを開けば、貴様の自滅を早めるばかりだ。ルージェール大使の面目を失うばかりだ。その外には、警官ばかりではない、夜会のお客様がウヨウヨしているのだぜ。それとも、たって開きたければ、貴様自身で開いて見るがいい」
「よし、では我輩自身で開くぞ。異存はないのだな」
云うかと思うと、已にドアの前に達していたルパンは、引手を廻すが早いか、サッとそれを開いた。
「ア、いけない」
明智が異様な不安を感じて叫んだ時はもう遅かった。素早い怪盗は、室を飛出して、外からドアを閉めてしまった。
だが、そこには、十数名の刑事が集まっている筈だ。逃げようとて逃がすものか。
「オイ、諸君、ルージェール伯を捉えよ。大使を逃がすな」
波越警部が、
「ワハハ……、オイ、オイ、エベール君、明智君、日本の警官達は一体どこへ行ったのだね。ここには誰もいない様だぜ。夜会のお客様も一人もお出でなさらぬ。ハハ……、では左様なら、君達は暫くそこで我慢していてくれ給え」
カチカチと外からドアに鍵をかける音。
「畜生、ピストルだ。構わぬ、ぶっぱなせ」
エベール氏が、明智の外には通ぜぬフランス語で怒鳴った。怒鳴ると同時に彼のピストルは煙を吐いた。続いて波越警部、明智と、三挺のピストルの
だが、敵は一向倒れた様子がない。
エベール氏と波越警部が、いきなりドアへぶつかって行った。合鍵を持たぬ彼等は、ドアを破って賊を追撃する外はないのだ。
ルパンはどうなったか。彼は微傷だも負わず、ピストルの乱射をあとに、長い廊下を走っていた。実に何とも解釈の出来ぬ。一大奇怪事が起ったのだ。ルパンの行手には、真実人っ子一人見えなかった。ドアの外に密集していた刑事軍、夜会の群集は、一体全体いつの間に、どこへ消えてなくなったのであろう。
イヤイヤ、消えてなくなる筈はない。読者は前章で、刑事達が待ちくたびれて、同じ部屋のドアを、外から開いて見た一条を読まれたであろう。刑事達が室内へ入って見ると、不思議千万にも、そこには誰もいなかった。ルージェール伯も、警視総監も、明智も、波越警部も、偽黄金仮面の死体まで、溶けてなくなった様に、影も形もなかった。
一方ではその様に、部屋の中の人々が消え失せてしまったのだ。
ところが、今度は、ルパンが中からドアを開くと、外の群集が、一人残らず、まるで蒸発した様に、姿を消してしまっていた。これはどうしたというのだ。
まさか、ルパンとて、魔法使ではあるまい。まさか、人々が揃いも揃って夢を見ていた訳ではあるまい。
では作者が飛んでもない
あり得べからざる事だ。理論的にも実際的にも全然不可能な事柄だ。だが、作者が嘘を書いたのでもない。読者諸君が読み違えられたのでは
それは兎も角、ルパンが無人の廊下を走りつくして、突当りの部屋に飛込むと、その暗闇の部屋の中に、影の様な五人の人物が、彼を待受けていた。五人とも燕尾服姿で、三人は外国人、二人は日本人だ。恐らくルパンの部下であろう。
彼等はルパンを加えて総勢六人、全然無言のまま、ガラス窓を開いて、外の非常梯子の足溜りへ出た。そして、一人一人、音も立てず鉄の梯子を降りて行った。
非常梯子の下に二名の刑事が見張りを勤めていることは先に記した。彼等はその時も、忠実にその役目を果していた。
「誰だッ」
梯子を降り立った六人の人影を見て、刑事の一人が叫んだ。と同時に、パッと目を射る一筋の光線。今一人の刑事が懐中電燈を点じて、一同にさし向けたのだ。
「シッ。静かにし給え。怪しいものではない」
ルパンの部下の日本人が、低い声で云った。
「誰です。名をおっしゃって下さい」
刑事は
「大使閣下です。ある重大な用件が生じたので、夜会の座をはずして、外出されるのです。閣下恐れ入りますが、この者達にお顔を見せてやって頂き度いのですが」
云われるまでもなく、刑事の懐中電燈が人々の顔を一巡した。その真中に立っている一人は、確かに大使ルージェール伯爵だ。末輩刑事とて、当の大使館の主人公の顔を知らぬ筈はない。新聞でお馴染の有名な人物だ。まさか、これがあの黄金仮面であろうなどと誰が想像し得よう。
「これは失礼しました。我々は黄金仮面逮捕の為に出張を命ぜられた警視庁のものです。大使閣下とは知らず、
「アア、そうでしたか。それは御苦労です」
云い残して人々は門内に群がる自動車へと進んで行った。それを見ると、二台の自動車がヘッドライトを点じて出発の用意をした。人々は素早く車内に姿を消した。
やがて、深夜の構内に響き渡るエンジンの爆音。地上を辷り行くヘッドライトの光。二台の自動車は、怪しき風の如く大使館を遠ざかって行った。
お話は元に戻って、警視庁刑事の一隊は、黒天鵞絨の部屋の、例の黒檀の大時計の前を、狐につままれた体で、右往左往していた。
彼等の長官である警視総監を始め、ルージェール伯も、明智小五郎も、波越警部も、煙の様に消えてなくなった奇怪事に、悪夢にでも襲われている様な、何とも名状し難い気持で、
すると、突然、どこか遠くの方から、連発されるピストルの音が聞えて来た。続いて人の怒鳴る声、ドアを乱打する様な物音。
十数名の刑事は、それを聞くと、皆歩きまわるのをやめて、ピッタリ、静まりかえってしまった。
「今のはピストルだね。どこだろう」
だが、迷路の様に折れ曲った建物のこととて急には見当がつかぬ。
「聞き給え。何かにぶつかる音は、確かに天井から響いて来る。二階らしいぜ」
そう云えば、成程二階らしい。贅沢な建築の厚い床を隔てているので、物音は
「行って見よう」
一人が先頭に立って走ると、一同ドヤドヤとそれに続く。
長い廊下の突当りにドアが見える。
そのドアに中から誰かがぶつかっているらしいのだ。もう鏡板の一箇所が、メリメリと破れかけている。
「誰だ、誰です、そこにいるのは?」
一人が大声に誰何した。
「警視庁の者だ。アア、君達だね。一体どこへ行っていたのだ。ルージェール伯爵は捉えたか」
波越警部の声が聞えて来た。
不思議、不思議、警部は確かに階下の黒い部屋から出なかった筈だ。それがいつの間に二階へ上ってしまったのだろう。
あっけに取られながらも、刑事達はドアの破壊を手伝った。心利いた一人が
「アラッ、変だぜ。僕達は下にいるのか、二階にいるのか。確か今、階段を上った筈だが」
頓狂な声を立てたものがある。
それも決して無理ではない。開かれたドアの中は、黒天鵞絨の部屋であった。黒檀の大時計も同じ様に動いている。偽黄金仮面の死骸も倒れている。波越警部ばかりではない。総監もいる。明智小五郎もいる。そして、ルージェール大使の姿はなくて、その代りに見知らぬ外国人が一人怖い顔をして突立っている。
これはどうしたことだ。
夢だ。でなければ、気が違ったのだ。
一同青ざめて、顔を見合わすばかりである。
「オイ、君達何をボンヤリしているのだ。大使はどこへ逃げた。あれ程怒鳴っているのに、なぜ捉えなかったのだ」
波越警部が癇癪を起して、再び怒鳴った。
だが、刑事達は、一層驚きを増すばかりだ。なぜルージェール大使を捉えなければならぬのか、さっぱり合点が行かぬ。何者かのえたいの知れぬ妖術で、波越鬼警部まで、気が違ってしまったのではないかと、怪しむ外はない。
「捉えよとおっしゃっても、私共は下の部屋のドアの外に見張番をしていたのです。二階のことは少しも知らなかったのです。併し、大使をなぜ捉えるのですか」
一刑事が不服顔に答えた。
「エ、エ、君は何を云っているのだ。二階だって? ここが二階だと云うのか」
今度は警部の方で、びっくりした。
「そうです。僕等は確かに大階段を上って来たのです。でも、変ですなあ、部屋はまるで同じなんだが……」
刑事達は、妙な顔をして、事の次第を説明した。
「そんな馬鹿なことがあるものか、君達がどうかしているのだ。じゃ、その下の部屋へ行って見よう」
波越氏はなかなか承服しない。
「待って下さい。これはひょっとすると、僕達は飛んでもない目に会わされたのかも知れませんよ」
明智が、廊下に面する窓の、血の色の薄絹をじっと見つめながら、口をはさんだ。
「何ですって?」
「ごらんなさい。あの薄絹の
明智はつかつかとそこへ歩いて行って、いきなり薄絹を引ちぎった。
すると、これはどうだ。窓の外は、さい前までの廊下がなくなって、薄汚い漆喰壁で塞がっているではないか。廊下の
総監も、警部も、エベール氏も、刑事達も、「アッ」と叫んだまま立ちすくんでしまった。
明智は何を思ったのか、部屋の中をグルグル歩き廻っていたが、大時計の前で立止ると小腰をかがめてそこの床を眺めた。
「アア、これだ。ここにスイッチがあるのだ」
彼の指さす箇所を見ると、真黒な絨毯の上に、小さな突起物が出ている。
「スイッチとは?」
総監と波越氏とが同時に聞返す。
「実に驚くべき機械仕掛けです。たった三ヶ月程の間に、誰にも気づかれず、これ丈けの細工をしたとは、やっぱりルパンでなくては出来ない芸当です。
「機械仕掛けとは?」
総監を初め、明智の云う意味が、まだ飲み込めぬ。
「さっき、ルパンの奴、天変地異を起して見せると豪語したではありませんか。そして、事実天変地異が起ったのです。彼奴は自から起した天変地異に隠れて、易々と警官の包囲を
「すると、我々は今、実際二階にいるのだと云うのかね」
薄々事の次第を悟った警視総監が、大きな目をパチクリやって尋ねた。
「そうです。恐らくこの釦を押せば、我々はここにじっとしていて、元の階下へ戻ることが出来ましょう」
明智は云いながら、思い切って、床の釦を押した。
と、何かしら異様な事が起り始めた。人々は身体がしびれた様になって、軽い
だが、その原因が何であるのか、暫くはまるで分らなかった。
部屋は少しも動揺しなかった。天井も壁も床も全く静止していた。だが、人々は、その静中に一種名状し難き「動き」を感じた。
「ごらんなさい。我々は今、極く静かに下降しつつあるのです」
明智の指さす所を見ると、人々は愕然として目を見はった。
今打破ったドアの空隙が、時計の針程の、目に見えぬ速度で、ジリジリと上に昇って行くのだ。
部屋の四方は、窓とドアの部分丈けを残して、すっかり黒天鵞絨の垂れ幕で覆われている。そのドアの部分の長方形の隙間から、ドアそのものが、上へ上へと昇って行って、間もなく見えぬ様になってしまった。
ドアが消えたあとには、薄黒い漆喰壁が暫く続いたが、それが尽きると、下の方から再びドアが見えて来た。巨大なるエレベーターが二階から一階へと達したのだ。
「何と驚くべき着想ではありませんか。この部屋そのものが、一種のエレベーター仕掛けになっていたのです。さい前ルパンはその大時計の前に立はだかっていました。それにはわけがあるのです。彼は押釦を踏む必要があったばかりでなく、我々四人の目を、ドアからそらして、大時計の方に引きつけて置かねばならなかったのです。その結果、我々はドアに背を向けて立っていた為、この部屋の上昇を少しも気附かなかった。ドアを除いては、部屋中に何も動くものがないからです。動揺といっても、極く軽微なものだし、まさか部屋全体が天上するなんて思いもよらぬので、残念ながら、我々はまんまと敵の術中に陥った訳です」
云う内に、大エレベーターは、全く下降し切って、部屋の床と、ドアの外の廊下の床とがピッタリと、同じ高さになった。
ドアはさい前開いたままになっていたので、まだその辺に居残っていた仮面舞踏の客達は、室内の異様な変化にあっけにとられて、一かたまりになって、じっとこちらを見つめていた。
「だが変ですね。僕達がさっき調べた部屋も、この部屋と寸分違わなかった。赤い窓、黒い垂れ幕、黒檀の大時計、すっかり同じです」
刑事の一人が、けげんらしく呟く。
「それだ。それがこの
明智が説明をする。
調べて見るまでもなく、舞踏の客達がこの二重の部屋を目撃していて、口々に申立てた。
アア、何という大袈裟な機械仕掛であったろう。犯罪史上前例もないトリックだ。イヤ、たった一つ丈け前例がある。それはルパンの先輩に当る
ある部屋で人が殺されていた。池と流れた
抜目のないルパンは、この大先輩の考案を日頃研究していたに相違ない。そして、全権大使として赴任し、官邸に入るや、直ちにその考案を実行して、この巨大なる機械仕掛けを作り上げ、危急の場合の逃亡準備を整えて置いたものに違いない。
「ルパンの考えつき相な思い切ったトリックです」エベール氏は寧ろ感嘆の
「あいつはエレベーターの上に軽気球をつけて、屋根を打抜いて逃亡するという様な、突飛千万な幻想を抱く奴ですからね。昔ジェルボア氏事件では、同僚のガニマール老探偵が、この手でひどい目に会ったことがあります」
間もなく、ルパンが五人の部下と共に、ルージェール伯として、堂々と非常梯子から
怪盗ルパンと五名の部下の行衛は、それ切り分らなくなってしまった。F国全権大使の行衛不明! アア何という滑稽千万な出来事だ。当局者はこの重大事件を、極秘に附し、新聞記事をも差止めたので、大使失踪事件は公表されずに終ったけれど、奇怪なる噂話は、蔭から蔭と忍び歩いて、忽ち全都に拡がって行った。
「あの黄金仮面の怪賊は、F国大使ルージェール伯爵が化けていたんだってね。しかもその大使が又偽物で、ルージェール伯爵実はアルセーヌ・ルパンだってね。滑稽じゃないか。ルパンがF国の代表者になりすまして、国書まで捧呈したんだぜ。あとにも先にも、こんなべら棒な話は聞いたことがないね」
よると触ると、ヒソヒソ声で、奇怪千万な噂話だ。
警視庁では直ちに全市の建築業者を取調べ、例の大エレベーターの仕事を引受けた者を取押えた。電気技師一名、電気職工三名、工事監督一名、大工左官二十名、室内装飾業者三名、都合二十八名の技術者職人が、手間賃の外に、莫大な礼金を貰って、この大工事の秘密を保っていたことが判明した。
それから半月程の間、ルパン一味の行衛は
しかも一方東京市中の子供達の間には、皮肉にも、奇妙な遊戯が流行していた。
「黄金仮面して遊ばない?」
子供達は、そんな風に云って、剣劇ごっこの代りに、黄金仮面ごっこを始めた。
いつとも知れず、おもちゃ屋の店頭に、張り子の黄金仮面がぶら下る様になった。子供等はそれを一枚ずつ買って来て、てんでに怪盗黄金仮面に扮して、一種の鬼ごっこをやるのだ。
どこへ行っても、不気味な金色のお面があった。
この不思議な流行は、市民に名状し難き不安を与えた。夕暮の街頭で、一寸法師の黄金仮面に出合って、ハッと息を飲む様なことが屡々起った。
えたいの知れぬ恐怖が、尾に尾をつけて拡がって行った。
ある者は、一人も客のない深夜の赤電車の中に、黄金仮面が一人ぽっちで腰かけていたと云いふらした。その電車には、変なことに、黄金仮面の外には、乗客は勿論、運転手も車掌ものっていなかったという
ある者は、人通りのない町で、うしろから少しも足音のせぬ金色の怪物が、スタスタとついて来たと云い、又ある者は、丸之内の大ビルディングの、空部屋の窓から、黄金の顔が覗いていたと云いふらした。
人々は黄金仮面が、異国の兇盗アルセーヌ・ルパンであることを薄々知っていた。だが、ルパンだからとて、油断は出来ぬ。この国では、彼は血を見ることを恐れぬのだ。平気で人殺しをやっているのだ。
ルパンの性格が一変した。飼いならされた猛獣が、血の味を覚えたのだ。人々は、ルパンという紳士盗賊が、俄かにえたいの知れぬ恐ろしいものに思われて来た。三日月型の唇から、糸の様な血を流しているという、あの黄金仮面の印象が、ルパンを非常に不気味なものにしてしまった。
そして、間もなく、人々が恐れた通り、ルパンの性格が一変したことを証する様な、恐ろしい事件が起った。
その夜、麹町区M町にある、
雲山氏は、人も知る東京美術学校名誉教授、我国彫刻界の大元老だ。夫人は数年前に
雲山氏は二日ばかり前、所用あって関西に旅行し、明日は帰宅する予定になっていた。丁度その夜、妙なことが起ったのだ。
「絹枝、わしの不在中は、例の通り、必ずわしのベッドでやすむのだよ」
父の雲山氏は、出発に先だって、繰返し云い残して行った。
雲山氏は、和風建築の母屋の横に、西洋館のアトリエを建て、寝室もその中にあるのだが、寝室とドア一重の広いアトリエには、丹誠をこめて刻み上げた仏像などが、沢山置いてあるので、その見張番をさせる意味で、いつも留守中は、この洋館の方のベッドで、令嬢をやすませる習慣になっていた。
「このアトリエには、わしの命より大切なものがあるのだ。傭人達では信用が出来ません。是非お前に番をして貰わねば」
雲山氏はいつもそんな風に云っていた。
「その大切なものというのは、お父さまのお刻みになった仏像のことですか」
令嬢が尋ねると、
「それもそうだが、もっともっと、命に換え難いものがあるのだ。お前に云った所で分りはしない。兎も角、お客さんであろうが、召使であろうが、わしの留守中は決してアトリエへ入れてはならぬ。まして夜中に泥棒でも忍び込む様なことがあったら、必ず枕もとのベルを鳴らして傭人を呼び集め、泥棒を追払ってくれなくてはいかん」
雲山氏はくどくどと注意を与えた。
「マア、何て疑い深いお父さまだろう」
絹枝さんは口にこそ出さね、心では、我親ながら、余りの
その夜、絹枝さんは、何故か妙に眠れなかった。
「あすはお父さまがお帰りなさる。そうすれば、こんな淋しいベッドにやすまなくともよい」
と思うと夜の明けるのが待遠しかった。あたりは海の底の様に、異様に静まり返っていた。誰も彼も死んだ様に寝静まっていた。広い世界に起きているのは彼女たった一人だと感じると、ゾーッと寒気がした。
「何時かしら」
と寝返りをして、枕もとの置時計を見ると、もう一時を過ぎていた。
「オヤ、あれは何だろう、こんな所に手紙なぞ置いてなかった筈だが」
絹枝さんは不審に思って、置時計の前を見た。そこにまだ封を切らぬ一通の封書が投出してあったからだ。
寝ながら手を伸ばして、取って見ると、封書の表にはただ「お嬢さま」と書いてある。裏を返して見たが、差出人の名前がない。
「誰がこんなものを置いて行ったのかしら」
彼女は何気なく封を切って、中の手紙を読んだ。
「この手紙を見た瞬間から、あなたはどんなことがあっても、絶対に声を立ててはいけません。身動きしてはいけません。若しこの命令に背くと命がありませんよ」
手紙にはこんな奇妙な文句が記してあった。
絹枝さんは、それを読むと、心臓の皷動がパッタリ止った感じで、手紙を床に投げ捨てた切り、身動きが出来なくなった。叫ぼうにも、喉がつまって声が出なかった。
十分ばかり、生人形みたいに身体を強直させてじっとしていたが、少し気が静まったので、思い切って、枕元の呼鈴を押そうと、ソッと手を伸ばしかけると、部屋の隅に垂れている天鵞絨のカーテンが、まるで警告でもする様に、モクモクと動き始めた。
「アア、そうだ。やっぱりあの蔭に人が隠れているのだ」
と思うと、絹枝さんは恐怖の余り、手は伸ばしたまま云う事を利かなくなり、目はカーテンに釘づけになって、そらそうにもそらせないのだ。
カーテンはモクモクと動きながら、その合せ目が、少しずつ、少しずつ開いて行く。
一
黄金仮面!
絹枝さんは新聞や人の話で、世にも恐ろしい黄金仮面の噂を知っていた。その黄金仮面が、広い洋館に一人ぼっちの、彼女の寝室へ忍び込もうとは。余りのことに信じられぬ程だ。悪夢かしら、悪夢なら早く醒めよと祈ったが、決して決して夢ではない。
黄金仮面は、不気味に無表情な、糸の様な目でじっとこちらを睨んでいる。噂に聞いた三日月型の口がキューッと横に拡がって、今にもその隅から、タラタラと真赤な血が流れ出すのではないかと怪しまれた。
彼女は呼鈴を押すどころではなく、何が何だか無我夢中で、頭から毛布を
暫くすると、ドア一重向うのアトリエの中に、ただならぬ物音が起り始めた。恐らく数人の悪漢が忍び込んで、何かを盗み去ろうとしているのだ。ドタンバタンと、まるで引越しの荷造りでもしている様な騒ぎだ。
「アア分った。黄金仮面は美術品に不思議な執着を持っているということだから、あの物音はきっと、お父さまのお刻みになった仏像を盗み出そうとしているに違いない」
絹枝さんは、怖さに気も狂い相な中で、幽かにそんなことを考えていた。
毛布を引かぶった、汗ばんだ闇の中に、長い長い時がたった。夜が明けて、日が暮れて、又夜が明けて日が暮れて、絹枝さんには、数日が経過した程も、長い時間に感じられた。
実際は、恐らく三時間程もたったであろう。ふと耳をすますと、いつの間にか、隣室のやかましい物音がやんで、底知れぬ静寂の中から、殆んど信じ得られぬ様な、
閉じていた目を、毛布の中で開いて見ると、荒い網目を通して、早朝の薄白い光が感じられた。
アア、とうとう夜が明けたのだ。もう大丈夫だ。賊共はとっくにどこかへ立去ってしまったに違いない。
それでもまだ、とつおいつ躊躇したあとで、絹枝さんは毛布の中から、じりじりと、動くか動かぬか分らぬ速度で、右手を
間もなく、指先が、冷い押釦に触ったので、彼女は力をこめてそれを押えると、そのまま指を離さないで、じっとしていた。
聞えぬけれど、母屋の台所で、電鈴が危急を告げる様に、いつまでも鳴りつづけているに相違ない。
「アア、助かった。今に女中か爺やか、誰かが駈けつけて呉れるに違いない」
と思うと、絹枝さんは
夜明けの幽かな光が、ブラインドをおろした窓を通して、部屋の中へ忍び入り、電燈の光と混り合っていた。凡ての物体が、霧を隔てて眺める様な感じである。
先ずアトリエとの境のドアへ目をやると、ドアは何事もなかった様にとざしたままだ。やっぱり夢を見ていたのかしらと疑いながら、徐々に目を移して行ったが、ひょいと、例の天鵞絨のカーテンを眺めると、突如、地獄の底からの様な、何とも云えぬ恐ろしい悲鳴が、部屋中に響き渡った。
アア、何ということだ。あいつは、朝の光を恐れもせず、絹枝さんの挙動を監視する様に、同じカーテンの隙間から、ギラギラ光る顔で、じっとこちらを睨んでいたではないか。
黄金仮面は、その不気味な顔に、ニタニタと異様な笑いをたたえて、徐々にベッドの方へ近づいて来るかと見えた。
絹枝さんは、絞め殺される様な、恐ろしい悲鳴を上げて、毛布を引かぶり、身を縮めて、ガタガタと震えていた。
今にも、アア今にもあの怪物が、毛布の上からのしかかって来るのではあるまいか。と思うともう生きた心地もなかった。
毛布の上から、近々と頭を寄せた黄金仮面の呼吸の音さえ聞える様な気がした。
もう心臓は破れ相だ。
と案の定、巨人の様な手の平が、毛布ごと、グッと彼女の肩を掴んだ。
「ゲッ」という様な何ともかとも形容の出来ない、物凄い悲鳴が、再び絹枝の口をほとばしった。
「オイ、絹枝、どうしたのだ。しっかりなさい」
賊が彼女の肩を揺り動かしながら、太い声で云った。イヤ、賊ではない、聞覚えのある声だ。変だな。と考えるまでもなく、絹枝さんは嬉しさに、ガバと毛布をはねのけて、その人に――父雲山氏の身体に、すがりついた。
老美術家は、夜汽車で帰って、今
父の広い肩越しに、ソッと例のカーテンを見やると、……やっぱりいる、金ピカの怪物が、細い目でじっとこちらを睨んでいる。
「お父さま、あれ! あれ!」
彼女は脅え切って、父の身体にすがりついたまま、目でそれを指し示しながら、
云われて、その方を振返った雲山氏も、流石にギョッとしないではいられなかった。思わず身構えをして、怪物を睨みつけた。
だが、何という図々しさ! 黄金仮面はまるで人形の様に無感覚に、じっとこちらを見つめたままだ。例の三日月型の唇に、異様な微笑をたたえながら。
「ハハハ……」
突然、老美術家の口から、突拍子もない哄笑がほとばしった。
「ハハハ……、絹枝、何を怖がっているのだ。ごらん誰もいやしない。ホラ、金のお面とマントが、カーテンに引掛けてあるばかりだ」
雲山氏は、カーテンをまくって、怪物の正体をあばいて見せた。
何のことだ。では、絹枝さんはゆうべから、お面とマントに脅えて、まんまと賊のトリックに乗せられていたのであろうか。
雲山氏は、丁度そこへ這入って来た下男に命じて、金色の面とマントを取はずし、母屋の方へ持去らせた。
「サア、もういい、もう何にもいなくなったよ。お前、さぞ怖い思いをしただろうね。併し、飛んでもないいたずらをする奴がある。黄金仮面なんて、いやなものがはやるね」
「いいえ、お父さま、いたずらではありませんわ。本当の泥棒ですのよ。早くアトリエを検べて下さい。何か盗んで行ったに違いありませんわ」
絹枝さんは、黄金仮面がいなくなったので、やっと正気に返って、
「何だか、ゴトゴトゴトゴト、長い間やかましい物音がしていました。きっと色んなものを持って行ったのですわ」
それを聞くと、雲山氏は、顔色を変えて、ドアに駈けより、それを開いて、アトリエの中を覗き込んだ。
絹枝もベッドを降りて、父のうしろから、怖々部屋の中を見た。
「アラ、どうしたのでしょう」
思わず立てる驚きの声。
不思議、不思議、アトリエの中は、昨夜寝る前に見た時と、少しも違わぬ。テーブルも、椅子も、立並ぶ仏像も、何
テーブルの上の細々した品物も元のままだ。リノリュウムの床は、昨日掃除をしたまま、拭った様に綺麗で、予期していた泥の足跡など一つも見当らぬ。
庭に面した窓を検べて見たけれど、何の痕跡もない。窓は内側から閉ったままだし、その外の庭は乾いていて、足跡を見分けることも出来ぬ。
「お前、夢を見たのではあるまいね」
雲山氏は、異様に青ざめた顔で、令嬢を振返った。
「不思議ですわ。いいえ、決して夢なんかじゃありません。確かにひどい物音が続いていたのです。でも、何も盗まれたものがなければ、幸ですわ。何が何だか、まるで狐につままれた様ですけど」
「何も盗まれたものはない。だが……」
「アラ、どうなさいましたの? お父さまの顔真青ですわ。何か分りましたの?」
令嬢が驚いて尋ねたのも無理ではない。老美術家は、盗まれなかったと分ると、却って青くなった。物凄く見開いた目、ワナワナと震える唇、絹枝さんは、嘗つて父親のこんな恐ろしい表情を見たことがなかった。
「絹枝、お前は可哀相な子だ。ひょっとしたら、お前などが夢にも想像しなかった、恐ろしい事が起るかも知れぬ」
老彫刻家は、何かに
「お父さま、あたし怖い。そんなことおっしゃっちゃいやよ」
絹枝さんは、ダラリと力なく垂れた父の手を取って、甘える様にふり動かした。父の手は、まるで死人の様に冷たかった。
「絹枝、暫く母屋へ行ってくれぬか。わしを少しの間、一人で置いてくれぬか」
雲山氏は、力ない声で、妙なことを云い出した。
「マア、どうしてですの」
絹枝さんはびっくりして、父の青ざめた[#「青ざめた」は底本では「顔ざめた」]顔を見上げた。
「今に分る。何でもないのだ。心配することはないのだ。わしが呼鈴を押すまで、どうかあちらへ行っててくれ。少し考えごとがあるのだ」
父の声は、
「ほんとうに、どうかなすったのじゃありません? 大丈夫?」
「ウン、大丈夫だ。サア、早くあっちへ行ってくれ」
絹枝さんは、何となく心残りであったが、父の言葉にはさからわず、その場を立去った。
母屋へ来て、茶の間で、女中達に、ゆうべの恐ろしい出来事を話していると、突然アトリエの方角から、バーンという異様な物音が聞えて来た。
絹枝さんも女中達も、ハッと押し黙って顔を見合わせた。
「鉄砲の音じゃございませんか」
「エエ、アトリエの様だわね」
昨夜の今朝である。しかも、さっきの父親の妙なそぶり。「若しや」と思うと、じっとしてはいられなかった。絹枝さんは女中達と一緒に、胸おどらせてアトリエにかけつけた。
「マア、お父さま!」
案の定、そこには父雲山氏が、血を流して倒れていた。死体の側に転がっている一挺のピストル。
弾は右のこめかみから脳髄深く食い入って、毛糸の様な血が、トロトロと床を這っている。
絹枝さんは、たった一人の肉親であった父の死骸に取りすがって、その胸に顔を伏せた。押しつけられた唇から、やがて、悲しげなすすり泣きが洩れ始め、徐々に烈しく、はては身も世もあらぬ、無残の泣き声と高まって行った。
同じ日の午前、川村雲山氏変死の数時間後、事件の現場には、検事局の人々、警視庁、所管警察の人々などが、今一応の取調べを終って、不思議な事件について語り合っていた。その人数の中には、黄金仮面担当の波越警部の顔も見え、特に呼ばれた民間探偵明智小五郎も混っていた。
まるで狐につままれた様な、掴み所のない事件であった。何もかも
前夜絹枝さんを脅かした黄金仮面は、果して真の黄金仮面即ちアルセーヌ・ルパンであったか。それとも、最初から金ピカのお面と外套で拵えた
アトリエへ忍込んだのは何者であったか。又、彼等は
雲山氏は、なぜ娘を遠ざけて一人ぼっちになったか。彼の変死は自殺か他殺か。他殺とすれば犯人はどこから這入り、どこから逃げ去ったか。
凡て凡て、毛筋程の手掛りもなかった。
一座には様々の説が出た。
事件全体が、例によって奇想天外なアルセーヌ・ルパンの所業に違いないと云うものもあった。これはある大犯罪の序曲であって、賊の真の目的は全く別の方角にあるのかも知れないという見方だ。
イヤ、これは恐らく絹枝さんが、現実と悪夢とを混同しているので、雲山氏は、何か不明の理由で自殺したのだろう。それが偶然同時に起ったに過ぎないのだと説くものもあった。
明智小五郎は、さい前から黙って、それらの想像説を聞いていたが、会話がとぎれた時、ふと独言の様に、妙なことを云った。
「お嬢さん、お父さんはフランス語がお出来になりましたか」
隅っこの方に小さくなっていた絹枝さんが、びっくりして顔を上げた。
「いいえ、父は外国語は少しも出来ませんでした」
「あなたは?」
「あのフランス語でございますか」
「そうです」
「いいえ、ちっとも存じません」
「召使の方に出来る人はありませんか」
「そんな教育のある者は、一人もございません」
絹枝さんは、明智の質問の意味を悟りかねて、妙な顔をして答えた。
その意味を悟り得ないのは、絹枝さんばかりではなかった。
「明智君、フランス語が、この事件に何か関係でもあるのかね」
波越警部が
「ウン、関係があるらしいのだ。これを見給え」
明智は右手に握っていた、もみくちゃの紙片を、引のばして一同に示した。成程フランス語らしい綴りの文字が、三行程並んでいる。だが、あいにくなことに、明智の外には、誰もフランス語を完全に読み得る者がなかった。
フランス語の文句とは別に、紙片の一方の隅に、
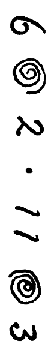
これ丈けは誰にも読めた。だが、その意味は少しも分らない。
「さっき、この部屋の隅に丸めて捨ててあるのを、見つけたのだ。若しここの家族にフランス語の出来るものがないとすると、そして、昨日この部屋を掃除したとすると、この紙切れは、昨夜忍込んだ奴が落して行ったと考えることが出来るのだ」
明智が説明した。いつもながらすばやい男だ。
「で、そのフランス語は、何が書いてあるのだね」
警部が尋ねる。検事、予審判事を初め、この不思議な問答に、きき耳を立てている。
「それが、ちっとも分らないのだ。気違いの文章か、おみくじの文句みたいに、不得要領なことが書いてある。こっちの隅の数字と渦巻も分らない。分らない丈けに興味がある。ひょっとしたら何かの暗号ではないかと思うのだよ」
「それが賊の落して行ったもので、本当に暗号文だとすると、非常な手掛りだが……」
「イヤ、確かに暗号だ。僕は殆ど確信している。あとはためして見る丈けだ」
明智が彼の癖の飛躍的な物の云い方をする。
「ためして見るって? 何をためすというのだね」
波越氏がけげん顔で聞返す。
「この数字と渦巻の意味をさ」
一同明智の
「僕の考えはこうなのです」そこで明智が説明を始めた。「川村雲山氏が、この部屋から何も盗まれなかったと知って顔色を変えたこと、それから令嬢に立去る様に命じたこと、この二つの一見不可解な事実が何を意味するか、先ずそれを考えて見なければなりません。部屋の中の品物が一つも盗まれなかったのは、川村さんにとっては、盗まれたよりも、もっと悪いことであったに違いない。川村さんは、賊の目的物が、このアトリエに並んでいる様な、ありふれたものでなく、もっと別のものであったことを知って、戦慄したのです。そして、その別のものが、果して無事であるかどうかを確める為に、令嬢に座をはずさせた。と考える外に解釈のしようがないではありませんか」
人々はここまで明智の説明を聞いて、何となく真相が分った様な気がし始めた。
「アトリエ内の品物が一つも紛失していないとすると、川村さんが顔色が変る程心配したものは、人目につかぬ極く秘密な場所に隠されていたと想像する外はありません。川村さんがこのアトリエの隣室に寝室を設け、そこに電鈴を仕掛け、旅行する時は必ず令嬢をここで休ませることにしていたというのは、アトリエによくよく大切な品物があったからでしょう。それを他人に発見されることを極度に恐れたからでしょう。こう考えて来ると、アトリエのどこかに、秘密の隠し場所があるという僕の想像が、一層本当らしくなって来ます。
川村氏は令嬢にさえ、それを打開けなかった。命にも拘る秘密なのです。現に令嬢を立去らせ、その隠し場所を改めた結果、命にかけて守っていた品物が、盗み去られたことを知って、川村氏は失望の余り、自殺したではありませんか。
明かに自殺です。若し他殺だとしたら、犯人は何を酔狂に、兇器を現場に残して立去りましょう。イヤ、そればかりではありません。僕は川村氏の旅行鞄の中から、ピストルのケースを発見したのです。このピストルはピッタリそのケースと一致します。
ところで、この川村氏が旅行中にさえピストルを所持していたことは一体何を意味するでしょうか。同氏が絶えずある種の不安にかられていたことを語るものではありますまいか。防がねばならぬ強敵があったか、それとも、いつでも自殺の出来る用意をしていたか、どちらにしても、命がけの秘密を持っていたことは確かです。
想像をたくましうするならば、その川村氏の大秘密をルパンの黄金仮面がかぎつけて、それを盗み去った。川村氏は絶望の極、遂に自殺したという順序です。賊がルパンであったことは、この紙片のフランス語や、令嬢を脅かした黄金仮面の扮装から想像することが出来ます。
川村氏は日本有数の彫刻家です。その人が命にかけて大切にしていた品物は、恐らく美術蒐集狂のルパンが、垂涎おく能わざるものであったのでしょう」
明智の組立てた筋書きは、全然空想の所産であった。併し、空想とは云え、理路整然、誠にさもあり相な筋書きだ。少くとも、一座の人々が持出した様々の想像説に比べて、数段立勝ったものであることは、
「で、あとはただ試してみるばかりです。僕の想像説が当っているかどうかを、実地について試して見ればよいのです。
そこで、この紙片の数字と渦巻に意味が生じて来ます。これは賊が川村氏の秘密をかぎつけて、その隠し場所のキイを、心覚えに書きつけて置いたものと仮定するのです。そして、この仮定が当っているかどうかを、試して見るのです」
試して見ると云いながら、明智は已に動かし難い確信を持っている様に見えた。
「僕はさい前から、この部屋のあらゆる部分を、入念に研究しました。そして、暗号の数字と一致するものは、あの
あの玉の彫刻は、全部で十六箇あります。ところで、暗号にある数字は、六、二、十一、三の四種で、どれも十六以下です。この数字は、
イヤ、必ずしも、そうではないかも知れません。渦巻が曲者です。六と二の間にある渦巻は右巻き、十一と三の間にあるのは左巻きです。これは若しかしたら、あの玉を、右に廻し、左に廻すことを暗示しているのではないでしょうか。
六番の玉を右へ、十一番の玉を左へ廻せということではありますまいか。
すると、二と三は、どちらへ廻すのかしら。アア、そうだ。これは玉の順位を示すのではなくて、廻す度数を記したものかも知れぬ。六番目を右へ二廻転、十一番目を左へ三廻転。そうだ、どうもそうらしい」
明智は語りつつ、彼の見事な推理を進めて行った。
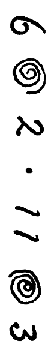
成程成程、六番目の玉を右へ二度、十一番目を左へ三度とは、うまい考えだ。
そこで明智は、
それを見ると、一座の人々は、すわとばかり立上って、ドヤドヤとその密室の前に群がり寄った。
中は三坪程の四角な小部屋になっている。
「やっぱりそうだ。何もない、空っぽだ」
波越警部が呟く。
明智の想像は次から次と当って行く。密室の中の品物は、恐らくルパン一味のものが盗み去ったのだ。
明智は暗室の中へ首を突込んで、暫く検べていたが、やがて、何か小さなものを指先でつまみ上げた。
「イヤ、空っぽじゃない。こんなものが落ちていた」
手の平にのせて差出すのを見ると、五分にも足らぬ長橢円形の、扁平なピカピカ光ったものだ。金属ではない。布でもない。紙でもない。えたいの知れぬ物質だ。だが、そんなものに何か意味があるのかしら。
明智は、窓際の明るい所へ行って、それを光にかざす様にして、入念に調べていたが、何を気づいたのか、愕然として、日頃の彼に
「本当かしら。信じられぬ。だが……アア恐ろしいことだ」
その様子が余り異様に見えたので、波越警部は思わず彼の側に立寄って、声をかけないではいられなかった。
「オイ、明智君、どうしたのだ。何か分ったのか」
「ウン、僕は今恐ろしいことを考えたのだ。非常に恐ろしいことだ」
日頃物に動ぜぬ明智が、声を震わせている。ただ事ではない。
「その小さなものは一体何だ。何か分ったのかね」
「ウン、分った様な気がするのだ。……アア、お嬢さん、電話室はどちらでしょうか」
明智は、そこに佇んでいた令嬢を振返って、惶しく云った。
明智が惶しく電話室の所在を尋ね、令嬢の案内でそこへ走り去ったあとに、人々は素人探偵の異様な振舞にあっけにとられて、ただ顔見合せるばかりであったが、そこへ令嬢が戻って来て、
「長距離を呼出していらっしゃいますの、少し手間取るけれど、どうかお待ち下さいます様にって」
と報告した。明智は至急報を依頼して、先方が出るまで、電話室を離れず、イライラとそこに立ちつくしていたのだ。明智程の男をかくも昂奮せしめたのは、
明智が電話室から帰って来たのは、それから三十分以上もたった頃であった。人々は手持無沙汰に待っている訳にも行かず、令嬢や召使達に質問を繰返したり、室内の捜査を続けたりしていた。
「皆さん、やっぱりそうでした。実に恐ろしい犯罪です」
帰って来た明智が、入口に突立って叫んだ。彼は電話室へ立去った時よりも、更に一層青ざめている。
「どうしたんだ。君は一体何を発見したんだ」
波越警部が真先に尋ねた。
明智はその場に居合せた令嬢や召使達に、暫くアトリエを立去ってくれる様に頼み、彼等の影が見えなくなるのを見定めて、やっと答えた。
「盗まれた品物が分ったのだ。皆さん、驚いてはいけません。ルパンはアトリエから、国宝を盗み去ったのです。それも並々の国宝ではありません。国宝中の国宝、小学生でも知っている程有名な宝物です」
「なんだって? 君は何を云っているのだ。こんな一私人のアトリエに国宝が置いてある筈がないじゃないか」
波越氏がたまげた様な声を出した。
一座の人々凡て波越氏と同じ気持であった。川村雲山のアトリエに国宝が安置してあったなんて、余りに突飛千万な、馬鹿馬鹿しい妄想ではないか。この素人探偵は頭がどうかしたのではあるまいか。
「それが、置いてあったのだ」明智は腹立たしげに叫んだ。「現に僕は今、奈良の
「エ、何ですって? 法隆寺? ではその国宝というのは……」
検事のE氏がびっくりして聞返した。
明智はなぜかあたりを見廻し、囁き声になって答えた。
「金堂に安置してある、
アア何ということだ。明智は気でも違ったのではないか。一同ギョッとした様に素人探偵を見つめたまま、云うべき言葉を知らぬ体に見えた。
「君、それは冗談ではないでしょうね。若し本当だとすると、実に容易ならん事件だが……それにしても、法隆寺では、この貴重な国宝がなくなっているのを、今まで気づかなかったのですか。小さなものではあるまいし、どうも少し変ですね」
検事は、信じ兼ねる様に云った。
「ところが、法隆寺の金堂には、別に異状はないのです。玉虫厨子はそこにちゃんとあるのです」
「ホホウ、すると君は……」
「そうです。
「偽物? ああ云う古代美術の偽物を拵えるなんて、不可能です。信じ難いことです」
検事を初め一同、容易にこの突飛な報告を信じようとはしなかった。
「法隆寺事務所の管理者もそう云いました。あれが偽物だなんて、そんな馬鹿なことがあるものか。つまらないいたずらは止し給えってね。僕が電話でいたずらをしていると思ったのです」
「そうでしょう。で、どうして偽物であることを確めたのです」
「僕は管理者に、厨子の底を調べてくれる様に頼みました。若しやそこに、ルパンの例の虚栄心たっぷりの署名がしてないかと思ったのですから」
「それで、その署名があったのですか」
「管理者は暫くすると電話口へ帰って来ましたが、まるで声が変っているのです。ブルブル震えて何を云っているのだか聞取れぬ程でした。『
信じ難い奇怪事だ。併し、まさか法隆寺の管理者が嘘を云う筈はない。厨子の底部にそんな署名があったとすれば、最早や疑う余地はない。日本随一の国宝は、憎むべき異国の怪盗によって盗み去られてしまったのだ。
「つまりこういうことになるのです」明智が説明した。「川村雲山氏は天才的な彫刻家であった丈けに、狂的な美術愛好癖を持っていた。愛好の余りその美術品を所有したくなるのは、無理もないことです。併し、雲山氏の場合は、不幸にして、それが金銭ずくでは所有出来ない国宝中の国宝だったのです。
普通の泥棒なら、国宝を盗むなんて馬鹿な真似はしません。盗んで見た所が、他人に見せびらかすことも、売払うことも、どうすることも、出来やしないのですからね。
ところが、雲山氏の場合は違います。彼は丁度恋人を愛する様に、この古美術品を我物として愛撫したかったのです。他人に見せる必要はない。無論金銭に替えようという訳でもない。ただ密室に安置して、朝に晩に観賞したり、愛撫したり、誰れも知らぬ秘密の喜びに浸っていたかったのでしょう。雲山氏がこの密室に命にも替え難い品を隠していたことは、旅行の度に、令嬢をアトリエへやすませ、それとなく見張り番をさせていたのでも分るではありませんか」
「成程、それをどうかしてルパンが探り出し、主人の留守を
検事が合槌を打った。
「そうです。恐らく
「で偽物の作者は、無論雲山氏自身ということになりますね」
「そうでしょう。あの精巧な美術品を作る為には、この密室で数ヶ月、或は数年の間、コツコツと仕事をしていたことでしょう。雲山氏の如き天才的美術家にしてはじめて企て得る悪事です」
「だが、偽物と本物と置き換えるのが大変です。監視人のついている中で、どうしてそんな手品が出来たのでしょう」
「大犯罪者は一見不可能な事柄を、何の苦もなくやって見せるものです。彼等は一種の手品師です。ところで、手品という奴は種を割って見ると実にあっけないものですが、今度の場合もその通りです。僕はあの国宝が時たま修理の為に外部へ持出されることを聞いていました。で、若しやと思って電話で、そのことを尋ねて見ますと、案の定、今から四ヶ月程前に、一度修理をした事があるというのです。それが手品の種です。川村氏は職業柄前以てその時期を知っていて、凡ての準備を整え、易々とすり替えをやったのでしょう。ご存じの通り十人や二十人の口止め料には事欠かぬ資産家ですからね」
アア何という大それた犯罪であろう。日本美術界の元老とうたわれる身を以て、その地位と、その手腕を悪用し、国家の至宝を
だが、彼は已に、罪の
「だが、それにしても、君はどうしてそれを推察したのだ。密室に隠してあった品物が玉虫の厨子であることを知ったのだ。僕には、その方が賊の手品よりも一層不思議に思われるのだが」
波越警部がふとそこへ気附いて、妙な顔をして尋ねた。
「ウン、それは何でもないのさ」
明智は事もなげに説明した。
「この紙切れに種があるのだよ。例の密室を開く記号の上に、三行ばかりフランス語の文句が書きつけてある。ホラ、これだ」
彼はその紙片をテーブルの上に拡げて見せた。
「訳すると、こんな風になる。『今夜、かの
アトリエの主人公は美術界の老大家だ。その人がこれ程の仕掛けをして隠して置いたもの、又それが盗まれたと知って自殺しなければならぬ程重大な品物――仏陀の聖堂――古い漆――古美術蒐集狂のルパンと考えて来ると、さしずめ思い当るのは玉虫の厨子だ。誇大妄想狂のルパンが狙うもので、しかも持ち運びの出来る仏陀の聖堂といえば、あの国宝の外には一寸考え当るものがない。そこで、僕は兎も角も電話をかけて、それを確めて見たという次第さ」
「なる程、そういう訳だったのか」波越氏は明智の鋭い想像力に感嘆した。「で、その文句のあとの方の、白い巨人に届けよというのは一体何の事だね。そいつが分れば、自然国宝のありかも賊の隠れ家も分って来るのだ」
「残念ながら、それは僕にもまだ分らない。白い巨人、つまり色の白い大男という意味だが、ひょっとしたら、ルパン一味の者の
明智は困惑の表情で呟いた。
国宝玉虫の厨子盗まる。しかもその盗賊は黄金仮面のルパンである。
このまるで悪夢の様な出来事は、忽ちにして日本全国に知れ渡った。当局者は、あらゆる手段を講じて、事を極秘に附していたが、新聞記者は彼等の鋭い第六感によって、早くも事件の内容を察知し、「ルージェール伯即ちルパン」の一条に触れぬ範囲で、この大椿事をこまごまと報道してしまったのだ。
アメリカなればリンチが叫ばれたかも知れない。温和なる日本人も、流石に激昂し、ルパンを捕えよ。国宝を取戻せの叫声が全国に湧上った。攻撃の的は警視庁だ。
「波越警部はどうした」
「明智小五郎は何をしている」とどこからともなく、非難の声が聞えて来た。
全警察力を上げて、ルパン逮捕の網の目が、蟻の
日本人なら知らぬこと、相手は目色毛色の変った異国人だ。まぎれ込もうとて、どこにまぎれ込む場所があろう。不思議だ。如何に妖術使いの黄金仮面とは云え、今は正体も曝露して、全日本を敵に廻しての逃亡だ。監視の目は町々村々に充ち満ちている。その中を、一人でもあることか、女連れの上に、普通の自動車には積み切れぬ程の大荷物を持って、(玉虫厨子は上下二つに分けても、極大トランク二箇程の容積は充分ある筈だ。しかも彼の
明智小五郎は、今日も開化アパートの書斎にとじこもり、例の謎の紙片を前にして、思案に暮れていた。大敵ルパンに飜弄され、その上世間からは非難の声をあびせられ、何とも云えぬいらだたしさに悩まされていた。
「白き巨人、白き巨人、白き巨人」
彼はこの不可解な謎の言葉を解く為に、丸四日を費して、未だに何らの
沈思する彼の前で、卓上電話がけたたましく鳴り響いた。
「アア又波越君に極っている。うるさいな」
波越警部は一日に二度も三度も電話をかけて、明智の出ぬ智恵を借りに来るのだ。
不承不承に受話器を取ると、案に
「アア明智君、吉報だ。すぐ外出の用意をしてくれ給え。例の謎の白い大男が見つかったのだ」
「エ、白い大男って?」
明智は余り
「ホラ、例の暗号紙片の文句さ。白き巨人という奴さ。あいつがやっと見つかったのだ」
「もっと詳しく話してくれ給え。よく分らないが」
波越氏が「白い大男」を文字そのままに解しているらしいのが何となく変に感じられた。
「部下の刑事が今電話をかけて来たのだ。戸山ヶ原の空屋ね、まさか忘れやしまい。君が黄金仮面と一騎打ちをした怪屋だ。僕は念の為にあの家のそばへ、刑事を一人張り込ませて置いた所が、その刑事から今電話なのだ。刑事が云うのには、三十分程前、あの空屋から一人の西洋人が出て来るのを見た。無論怪しいと思って跡をつけた所、その西洋人は自動車で銀座へ出て、今カフェ・ディックへ這入った所だ。表に見張りをしているからすぐ来てくれという電話だ。君もそちらから直接行ってくれないか」
「ウン、行ってもいいが、それがどうして白き巨人なんだね」
「そいつが頭から足の先まで真白なんだって。白いソフト、白い顔、白い服、白いステッキ、白い手袋、白い靴とね。僕はそれを聞いてギョッとしたよ。こいつこそ問題の白き巨人なのだ、背も非常に高く、馬鹿に太った奴だという話だ」
「よし、行って見よう。カフェ・ディックだね」
そして電話が切れた。
明智は寝室に飛込んだかと思うと、五分程の間に自動車の運転手といった風体に変装して出て来た。
十分の後、自動車はカフェ・ディックの十軒程手前で停車した。見ると、黒目鏡をかけ、つけ髭をつけ、古風なアルパカの背広を一着に及んで、黒の
明智は車を降りると、その老人に近づいて行って、ポンと肩を叩いた。
「波越君、
アルパカの男はびっくりして振向いたが、明智の変装は流石に手に入ったもので、暫らくは見分けがつかぬ程であった。
「アア、明智君か、静かに静かに、今白い奴が出て来るんだ」
波越氏は五六間向うの、カフェの入口を目で知らせた。その入口の向側の軒下には、商店の
間もなく問題の白き巨人がカフェの外へ姿を現わした。如何にも白い。頭から足の先まで
身体も巨人の名に恥じぬ偉大なものであった。六尺以上の身長で、しかも
彼はカフェを出ると、車も拾わず、ブラブラと銀座通りへ歩いて行く。
珍妙不可思議な尾行行列が始まった。先頭に立つのは白粉のお化け然たる肥大漢、それから十五六間あいだを置いて、アルパカ黒眼鏡の怪老人、赤い長靴の運転手、つづいて兵隊上りの番頭さんといった恰好の刑事君。
「あいつが果して暗号の白い巨人だとすると、根気よく尾行を続けて、家をつきとめさえすれば、ルパンの贓品の隠し場所が分る訳だ。イヤ、ルパンその人のありかも自然たぐり出せるというものだ。うっかり見失ったら大変だぜ」
波越氏が小声で囁く。
「ウン、そりゃそうだが、あいつイヤに白いね。どうも少し白過ぎる様な気がする」
明智はなぜか気のりがせぬ様子だ。
「白過ぎるって? それだから怪しいのだ。あの真白な出立ちに、何か僕等には分らない意味が隠されているのかも知れない」
ボソボソと囁きながら、奇妙な尾行行列は行手定めず続いて行った。
白き巨人は、白いステッキを打振り打振り銀座の電車道を横切ってそこの大百貨店に入って行く。
「変だぜ、あいつ尾行を悟ったのじゃないかしら。呑気らしく百貨店なんかへ入るのは」
「感づいたにしても、尾行をやめる訳には行かぬ。どこまでも執念深くつき纏って、あいつの隠れ家をつきとめなきゃ」
波越警部は異様に熱心だ。明智の方は、うんざりした体で、「オヤオヤ」と云わぬばかりである。
巨人はエレベーターで屋上庭園に昇った。尾行者達も同じエレベーターの片隅に小さくなって、獲物から目を離さなかった。屋上庭園には、おびただしい群衆が、空を見上げて、何かを待っていた。
「アア、
その日は丁度フランス飛行家シャプラン氏の世界一周機が、東京の上空に飛来する当日であった。
ラジオは、東海道の空を、刻々近づき来たるシャプラン機の位置を報道していた。
東京市民は、この前人未到の壮挙を迎えて、湧き立っていた。ビルディングというビルディングの屋根には、人間の鈴なりだ。
「フランス人は恐ろしい国民だね。シャプランを生み、ルパンを生み」
運転手姿の明智が感嘆する様に呟いた。だが流石の彼も、この世界一周機と、黄金仮面の犯罪事件との間に、あんな不思議な因縁が結ばれていようとは、夢にも知る由はなかったのである。
間もあらせず、湧き起る屋上の歓声が空の英雄の飛来を知らせた。一抹の雲なき青空、遙か西の方に三羽の
機体は見る見るその形を大きくして、仰ぎ見る群衆の頭上に迫って来た。
「オイ、見給え、あいつが変なことを始めたぜ」
波越氏が明智の腕を突いた。この忠実なる警察官に取っては、空の英雄よりも、地上の白き巨人が大切であった。
見ると、白き巨人は如何にも変てこな事をやっていた。彼は屋上の
「君、あいつは向側のビルディングの屋根にいる誰かに、合図をしているのだぜ。
波越氏はさてこそと目を光らせた。
「フフン、妙な真似をするね」明智は相変らず冷淡だ。
機影が空の彼方に没し、屋上の歓声も静まると、群衆は感激の言葉を交しながら、階下へと立去る。白き巨人もその人波に混って歩き出した。
エレベーターが一階に止って、はき出された尾行行列の四人は、巨人を先に立てて、百貨店の出口へと進んで行った。
「オイ君、どうしたんだ。愚図愚図していたら、見失ってしまうじゃないか」
波越氏がイライラして明智を引っぱった。だが明智は店内のツーリスト・ビュロー出張所の前に立止ったまま動こうともせぬ。
そこの壁に美しいポスターが下っていた。外国人向きの日本遊覧案内だ。画面には富士山がある。
「オイ、明智君、しっかりし給え。何をボンヤリ見ているんだ」
すると、明智はやっと警部を振返って、突然妙なことを云い出した。
「君、日本にはこんな大仏様がいくつあるか知っているかい」
「そんなことを知るもんか。サア、ポスターなんかあとにして、尾行だ。ここまで追跡して、今見失ったら、取返しがつかんじゃないか」
波越氏はプリプリして云った。
「何だか気分が悪いのだ」明智は額を押えて眉をしかめて見せた。「尾行は君達二人でやってくれ給え。僕はもう帰るよ」
「困るなあ。そんなことを云い出しちゃ。君、本当に気分が悪いのかい」
「ウン、本当だ。
問答をしている間に、白い大男はズンズン歩いて行く、大分隔たってしまった。
もうこれ以上愚図愚図してはいられない。
「じゃ、結果は電話で知らせるよ。大切にしたまえ」
波越警部は、あきらめて、刑事と共に大男のあとを追って行った。
警部を見送った明智は、柵の中にいる旅行案内係に近づいて何か忙しく尋ね始めた。その様子を見ると一向病気らしくもない。どうも変な鹽梅だ。
それはさて置き、波越警部達は、あくまで執念深く、テクテクと巨人のあとをつけて行った。西洋人はやっぱり車に乗りもしないで、健脚にどこまでも歩き続ける。
一時間も引っぱり廻されて、やっと日比谷公園と縁が切れた。今度こそ隠れ家かと意気込んでついて行くと、大男はつい公園の前の帝国ホテルへ姿を消してしまった。ではホテルの泊り客であったのか。併し、ホテルを贓品の隠し場所にしているとは思われぬが。
「君、一寸尋ねるが、今ここを這入った西洋人は泊り客かね」
波越警部は玄関のボーイを捕えて尋ねて見た。
「エエ、そうですが」
中年のボーイが、妙な顔をして、ジロジロと警部を眺める。無理もない、彼の服装はどう見ても集金人以上には踏めぬのだ。
波越氏もそれに気づいて、
「私は警視庁のものだが、一寸支配人に取次いでくれ給え」
と、ポケットから名刺を出した。
東京市民で波越鬼警部の名を知らぬものはない。ボーイは名刺を見ると、急に鄭重になって、早速支配人室へ案内してくれた。
尋ねて見ると、大男は今朝投宿したばかりで、一向馴染のない客であるが、別にこれといって変った所もないということであった。名前も分った。国籍は明智が想像した通りフランス人であった。若しや大きな荷物を持っていないかと聞くと、案の定大型トランクを三つも部屋へ持込んでいるとの答えだ。しめた、そのトランクこそ曲者だ。トランクの中味が国宝玉虫厨子だったらと思うと、波越氏は胸がワクワクした。
「少し尋ねたいことがあるのですが、その客の部屋へ案内して下さらんでしょうか。
警部が頼むと、支配人は快く承諾して、長い廊下を先に立った。その部屋に来て見ると、ドアが締っていて、ノックをしても開かぬので、部屋ボーイが呼ばれた。
「お客様は?」
「さっきご出立になりました」
「御出立になった? そんな馬鹿なことはない。今朝お着きなすったばかりじゃないか」
支配人がびっくりしてボーイの顔を見た。
「でもご出立になったのです。つい今し方です。外からお帰りになると、私を呼んで、これから出立するからと、そのまま手ぶらでお出ましになったのです」
では波越警部達が支配人室に入っている間の、極く僅かな時間に、まんまと逃げられてしまったのであろうか。
「手ぶらで? 車も呼ばないで? じゃ、荷物はどうしたんだ。大きなトランクがいくつもあった筈だが」
「それは部屋に残していらっしゃいました。アア、そうそうお云い置きがあるのです。エエと、間もなく波越さんとおっしゃる方がお出でなさるから、荷物はその方にお渡し申してくれって」
「エ、エ、何だって?」
当の波越氏は面喰って、思わず声を立てた。
「波越何んという方だ」支配人もせき込む。
「警視庁の方だっておっしゃいました」
「どうも変ですね。兎も角、そのトランクをお調べなすっては如何ですか」支配人が警部の顔を眺めた。
「見ましょう。ここをあけて下さい」
波越氏は、今にして明智の突然の病気の理由を悟ることが出来た。何というすばやい男だろう。こんな
「開けて見たまえ」警部の命令で、刑事とボーイとが、次々とトランクの蓋を開いた。
「畜生め、又一杯食わせやがった」
波越氏が乱暴な言葉で怒鳴った。
トランクの中には、赤ん坊程もある大きなキューピー人形が手を拡げて、両方の目玉を真中に寄せて、人を小馬鹿にして笑っていた。トランク三つとも、同じ人形だ。そして外には何一品入っていないのだ。警察を
白粉の化物みたいな大男、屋上庭園の仔細らしい旗信号、日比谷公園の追っ駈けっこ、そしてトランクの中には国宝どころか、畜生め、このキューピー人形だ。こんな甘手に乗ったかと思うと、波越警部は地だんだ踏んでも足らなかった。
スゴスゴホテルを引上げて、警視庁に帰って、それから退庁時間が来て、自宅に戻り、床につくまで、警部は殆ど口を利かなかった。警察官拝命以来、嘗てこれ程憂鬱を感じたことはなかった。
波越氏は翌日登庁すると早速明智に電話をかけた。昨日の恨みを云うつもりであった。ところが明智は
何とも云えぬ焦燥の内に、又一日がたって、その翌日の夕方、やっと明智のありかが分った。しかも今度は彼の方から、警視庁へ長距離電話をかけて来たのだ。電話は横浜の少し向うの神奈川県O町からであった。
「君はひどいよ。仮病を使って逃げ出すなんて。あれから僕は散々な目にあってしまった」
「やっぱりそうだったかい。あいつは偽物なんだね。僕は何だか虫が知らせたんだ。最初から気乗りがしなかった。でも、君がひどく真剣だものだから、ついよせとも云えなくなってね。僕だって、別に確信があったのではないし」
明智の声が気の毒そうに云った。
「まあそれはいいさ。だが君はどうしてO町なんかにいるの? 無論例の一件についてだろうね」
「ウン、吉報だよ。今度は僕の方から君を呼ぶことになったが、一昨日の様な偽物じゃない。正真正銘の白き巨人をつきとめたんだ。昨夜はその為に徹夜をしてしまった。だがとうとう確証を掴んだよ」
「その巨人というのは、O町にいるのかい」
「ウン、そうだよ。すぐ来てくれ給え。君が着く時分には、停車場へ行って待っているから。やっぱり変装して来た方がいいよ」
この吉報を聞いて打捨てて置く訳には行かぬ。警部は早速、
停車場に着くと、例の運転手姿の明智が待受けていた。
「電話で詳しい様子が分らなかったが、白き巨人て一体どんな奴だね。どんな家に隠れているのだね。そして、そこにまだ贓品が置いてあるのかい」
波越警部は明智の顔を見ると、せかせかと尋ねかけた。
「ウン、贓品は勿論、恐らくルパンも、大鳥不二子さんも、同じ隠れ家に潜伏しているのだ」
「エ、ルパンだって? そいつは大手柄だ。こんなに早く見つかろうとは思わなかった。それで一体どんな家にいるんだね。君はどうしてそれを探り出したんだね」
「マア、僕について来たまえ。今にすっかり分るよ」
明智は多くを云わず、警部を促して先に立った。
狭い町を出はずれると、ダラダラ昇りの丘になって、細道の両側に雑木林が茂っている。もう日が暮れ切って、空に星が美しく輝き出した。その外には燈火一つ見えぬ暗闇の林だ。
こんな淋しい丘に人家があるのかしら。人家があれば燈火が見える筈だがと怪しみながら、併し明智を信じ切っている波越警部は、苦情も云わず、テクテクと暗闇を歩いて行った。
だが、行っても行っても、闇は濃くなるばかりで、一向人家などあり相に見えぬ。少々心細くなって来た。
「オイ、明智君、一体どこまで行くんだね。こんな方角には町も村もない筈だが、その巨人というのはどこに住んでいるんだい」
「もう僕等はそいつを見ているんだよ。暗いから分らぬ丈けさ」
明智が変なことを云った。
「エ、見ているって。じゃこの辺にいるのかい」
「ウン、僕等は一歩一歩そいつに近づきつつあるのさ。もう少しだ」何だか薄気味の悪い話である。
やがて、道は雑木林を抜けて、ポッカリと丘の頂の広っぱへ出た。だが、暗さに少しも変りはない。無論人家も見えぬ。
「どうも分らないね。そいつは一体どこにいるんだね。僕の目には少しも見えぬが」警部は用心深く声を低めて再び尋ねた。
「見えないって? 見えぬことがあるものか。ホラ、君の目の前に立っているじゃないか」
それを聞くと警部はギョッとして、一歩あとにさがった。
「エ、どこに? どこに?」
「ホラ、星明りに透かして見たまえ。君の前にとてつもない巨人が立っているじゃないか」
云われて、ヒョイと見上げると、如何にも、如何にも、そこには美しい星空を背にして、小山の様な巨人が、二人の頭上にのしかかっていた。
「君はこの大仏のことを云っていたのかい」
波越氏はびっくりして尋ねた。丘の中央に奈良の大仏よりも大きいので有名な、O町名物のコンクリートの大仏様が安置してある。これなら明智に教えられずともよく知っている。
「変だな、君はこの大仏がルパンの仲間だって云うのかね」
警部は冗談だと思った。大仏とルパン。なんて突飛な組合せだろう。
「そうだよ」明智は大真面目で答えた。「これがルパンの所謂白い巨人さ。見給え、如何にも白い巨人じゃないか」
成程成程、云われて見れば、白き巨人に相違ない。
「ああ君は恐ろしい男だ、するとこの大仏様が……」
警部は声をひそめて、明智の黒い影を見つめた。
「ウン、これが『空ろの針』なんだ。君は聞いたことがあるだろう。奴が奴の本国で、『空ろの針』と呼ばれた奇岩の内部に、巧妙な隠れ家を作っていたことを」
明智が説明した。
「空ろの針! エトルタの有名な空ろ岩のことだね、ルパンの美術館と云われた」
「そうだ空ろの針!……白き巨人……一方は空洞の巨岩、一方は空洞のコンクリート仏、この奇怪な符合を見給え。何という驚くべき空想だろう。
二里四方から見えるという、この空に聳えた大仏様が、兇賊の最も安全な隠れ家、世にも不思議な美術館なのだ」
明智は大仏前面の密林の中を歩きながら、ひそひそと話しつづけた。
「だが、どうして君は……」
波越警部は、余りにも奇怪な事実を、容易に信じ得ぬ様子であった。
「もう大分以前からこの林の中に黄金仮面が出没するという噂があったのだ。近頃は関東地方一帯、そこにもここにも黄金仮面の怪談が転がっている。子供達がおもちゃの黄金仮面を被って飛び廻っている。誰も殊更らこの丘の怪談を注意するものはなかった。だが僕はその怪談を聞きのがさなかったのだ。なぜと云って、この丘にはコンクリートの大仏が聳えていることを知っていたからだ。僕は我ながら、余りに奇怪な着想に震え上った。だが、ルパンは世界一の魔術師だ。その着想が信じ難ければ、信じ難い程、却ってそれが事の真相に触れているのだ。僕はそこで、殆んど一昼夜、この丘の林の中をさまよった。そして、とうとう奴の尻尾を掴んだ」
「ルパンを見たのか」
波越氏がドキドキしながら尋ねた。
「ルパンではなかった。だが明かにルパンの部下と覚しき男が、這入るのを見た。賊等はみんなが黄金仮面の扮装しているのだ。その金ピカの奴が、向うの
アア何という簡単な、しかも奇想天外の思いつきであろう。コンクリートの大仏の内部が空洞になっていることは誰でも知っている。だが、それを極秘の倉庫として、又住宅として使用したのは、恐らくこのフランス盗賊が最初であろう。
O町のコンクリート仏が選ばれたのは、東京から近いばかりでなく、鎌倉の大仏などの様に礼拝所として胎内を開放したものでなく、隠れ家として最も適当であったからに相違ない。
「僕はルパンのズバ抜けた智慮が恐ろしくなった。あいつはひょっとしたら、この日本の大仏丈でなく、世界至る所に贓品美術館を持っているのではあるまいかと思うと、ゾッとしないではいられなかった。例えばね。有名な
「信じられん。まるでお伽噺だ」
驚歎した警部が、あきれ返って呟いた。
「大犯罪者はいつもお伽噺を実行するのだよ。まさか『自由の女神』などがルパンの倉庫になっているとは思わぬけれど、ふとそんなことを考えさせる程、奴の魔術は奇怪千万なのだ」
「で、その銀杏の空ろというのは、一体どこにあるのだね」
警部は半信半疑で尋ねる。
「ホラ、あれだ、あすこの森の中の大入道みたいな黒いのがその銀杏だ」
この丘で、大仏に続いて巨大なものは、その銀杏の老樹であった。それ等の二つが、まるで巨人の親子の様に梨地の星空に聳えていた。
「僕はね、君は容易に信じないだろうと思ったのだ。賊を捕えるよりも、先ず君にその大仏の秘密を信じさせる必要があった。それには実際を見て貰う外はないと思ったのだ。……サアここだ。見給え。あの大銀杏の根元を」
降る様な星明りに、老樹の陰が――その根元に開いた大きなうつろが、物の怪の如く浮上って見えた。大仏の胎内への出入口だ。
「サア、この茂みに隠れるのだ、そして、あのうつろを注意しているのだ」
二人はそこにしゃがんで、闇の老樹を見つめた。
どうせしばらくは待たなければなるまいと覚悟していたところが、まるで申合せでもした様に、彼等がそこへしゃがむかしゃがまぬに、早くも銀杏のうつろに蠢くものを見た。
「オヤ、変だぞ」
明智は何故ともなく、警戒の気持になった。
うつろの中から這い出したのは、果して黄金仮面であった。しかも一人ではない。次から次へ同じ衣裳の怪物が、あの世からの使いででもある様に、モクモクと湧き出して来た。
一人、二人、三人、四人だ。四人の全く同じ黄金仮面が、夜の大銀杏のうつろから這い出して来るなんて、波越警部ならずとも、恐ろしいお伽噺としか思えないではないか。
星の光に四つの黄金マントが、キラキラと怪しく輝いた。お揃いのソフト帽の下から、四つの無表情な金色の顔が、ボンヤリと見え、その三日月型の唇が耳まで裂けて、声のない笑いを笑っているのかと思うと、流石の名探偵、鬼警部も、ゾッとしないではいられなかった。
見ていると、四人の怪物は、無言のまま、足音もなくこちらへ近づいて来る。なぜだろう。偶然彼等の道が、明智達の隠れている茂みの
明智は訳の分らぬ不安を感じて思わず立上ろうとした。
と、その途端、恐ろしいことが起った。ノロノロと歩いていた怪物共が、突然矢の様に走り出したのだ。そして、アッと思う間に、一飛びで、明智と波越警部のまわりを取り囲んでしまった。四つの白く光るものが、夫々黄金マントの合せ目から、ヒョイと覗いた。ピストルだ。
「ハハハ……、とうとう罠にかかったな、明智小五郎」
一人の黄金仮面が低い声で言った。ルパンの部下の日本人だ。
「連れは誰れだね。恐らくは波越捜査係長だと思うが。アア、やっぱりそうだ。こりゃ迚も大猟だぞ」
三日月型の唇が嬉し相に言った。あとの三人の金色の顔から、ペロペロペロと低い喜びの声が漏れた。
「明智君、僕等がこんなに早くお迎いに来たのを、不思議がっている様だね。流石の名探偵も少し
黄金仮面は憎々しく
明智は一言もなかった。大仏様の白毫が物見の窓になっていようとは、不覚にもまるで気づかなかった。あの高い所から覗いていたとすれば、仮令夜とは云え、星明りに、明智達の
相手は四人、こちらは何の武器もない二人だ。絶体絶命である。
明智は波越氏の耳に口を寄せて、慌しく何事か囁いた。そうして賊に向き直ると、
「こちらは武器はないのだ。騒がなくてもいい。僕達をどうしようというのだね」
と声をかけた。
「暫く僕達の隠れ家の客になってほしいのだ。君達が自由に歩き廻っていることは、少々邪魔っけなのでね」
賊がおだやかに答えた。
「それでは、案内して呉れ給え。君達の隠れ家を拝見しよう。僕等はルパン君にも逢い度いのだから」
明智は事もなげに云って、もう歩き出していた。四人の賊は、案外らしく、でもピストルを構えたままあとに従った。
二三歩あるくと、明智の身体が
「サア、君達の
明智の左手は一人の黄金仮面の片腕をねじ上げていた。ピストルを取られた男だ。
残る三人は同類の命を思って、立ちすくんでしまった。
ジリジリと汗のにじむ睨み合いが続いた。明智のピストルは一人の賊の脇腹に、三人の賊のピストルは、隙もあらばと明智の胸板に狙いを定めて、闇の中に五人の影が化石していた。
「ハハ……、イヤ御苦労御苦労もういいんだよ、波越君さえ着弾距離の外へ逃げてしまえば、僕はおとなしくするよ」
突然明智がピストルを下げて笑い出した。仮令武器を奪ったとて、残る三挺のピストルに敵対出来る筈はない。明智の巧みなトリックに過ぎなかったのだ。死にもの狂いの睨み合いで、賊の注意を一身に集め、その隙に波越警部を逃がす咄嗟の思いつきなのだ。
「畜生め」
明智が力を抜いたので、今まで腕をねじ上げられていた奴が、いきなり飛びかかってピストルを奪い返し、反対に明智の背中へ
「こいつは俺が引受けた。早く波越の奴を追駈けてくれ。逃がしては取返しがつかんぞ」乱暴な仏蘭西語が怒鳴った。
云われるまでもなく、残る三人の黄金仮面は、星明りに金色のマントを飜して、滅茶滅茶にピストルを発射しながら、遙かの人影を追って走り出した。
大仏の胎内には天井からぶら下った、アセチリン燈がただ一つ、広い空洞をおぼろげに照らしていた。
縦横に交錯する鉄骨、鍾乳洞へでも入った様な、コンクリートの内面の不気味なでこぼこ、その辺に転がっている茶箱の様な荷物(その中にルパンの数々の贓品が入っているのだ)。それ等が
床に横わる太い鉄骨の上に、こればかりは非常に贅沢な羽根蒲団を敷いて、そこに二人の黄金仮面が腰かけていた。
ひそひそと囁き交わす言葉の調子が、決して男同志の話振りではなかった。それに小柄な方の声が透き通る様に細いのは、女性である事を語っている。ルパン一味の女性と云えば不二子さんの外にはない。そうして不二子さんとこの様な
そこへ、地下道から、次々と、さい前の四人の黄金仮面が帰って来た。
四人のものは口々に、首領の前に事の仔細を報告した。
波越警部は逃げおおせたのだ。
いかに足長の西洋人でも、余りにハンディキャップが多過ぎたものと見える。それに長追いをして、O町の人家に近づいては却って危険なので、残念ながら引返す外はなかった。追手の三人はまだゼイゼイと息をはずませていた。
折角明智小五郎を
日頃のルパンであったら、ドジを踏んだ四人の部下を、こっぴどく叱り飛ばしていたに違いない。又仇敵明智小五郎を面前に引きずり出して、得意の毒舌をふるったことでもあろう。だが今は流石のルパンもそれどころではなかった。一刻を争う危急の場合だ、一秒を惜しんで、前後の所置を考えなければならぬ。
「自動車を二台、いつもの所へ用意して置け。それからこの荷物を運び出すのだ」
ルパンは立上って、早口に異国の言葉を怒鳴った。
命令一下、二人の部下が地下道へと飛び込んで行った。附近に隠してある自動車を引き出す為だ。
「明智の奴はどうしましょう」
「その辺の鉄骨へ縛りつけて置け。俺は血を見るのは嫌いだ。併しこの黄色い悪魔丈は我慢がならん。荷物を運び出したら爆発薬の口火に点火して置くのだ」
鉄骨に縛りつけられた明智は、奇妙な唸り声を立てて、未練らしく、もがき廻った。
まぶかに冠った運転手帽、猿轡の上から鼻と口とを覆った広いハンカチ、暗いカンテラの光では、殆んど顔も見分けられぬ、みじめな姿だ。若しルパンの心に少しでも余裕があって、明智の帽をとり、猿轡をはずして見たならば、この物語の結末は、もう少し違ったものになっていたかも知れないのだが、逃亡に気をとられた彼は、明智の所置を考える丈がやっとだった。
「サア荷物を運び出すのだ」
ルパンと二名の部下と不二子さんまでが手伝って、五つばかりの荷物を、窮屈な地下道へと運び始めた。
× ×
波越警部が十数名のO警察署員を引連れて大仏の丘を上って来たのは、それから二十分程後、丁度ルパンの一味が自動車へ荷物を積み終って、出発しようとしている時であった。
「ア、エンジンの音じゃないか。こんな所に自動車なんて変だね」
一人の巡査が林の彼方の物音を聞きつけて呟いた。
「賊が逃亡しようとしているのかも知れない。君、確めて呉れ給え」
波越氏が命令を下した。
と、その言葉が終るか終らぬに、人々は突如として、大地のくずれる様なはげしいショックを感じた。同時に、地上の小石まで見分けられる白昼の火光、何とも云えぬ恐ろしい音響。
「ワアッ」というときの声が上った。
人々はその一刹那の恐ろしくも美しい光景を、長く忘れる事が出来なかった。
奈良の大仏よりも大きいというコンクリート仏が、
人々は思わず腹這いになった。大仏からは一町も隔っていたけれど、背中一面時ならぬ雹の御見舞を受けた。
だが、出来事は一瞬にして終った。目もくらむ火光が消え去ると、闇が二倍の暗さでおしかぶさった。耳も
人々は、意識をとりもどすと、先ず考えたのは、賊が巣窟を爆破して、自から亡びたのではないかということであった。兎も角、現場を調べて見るのが急務であった。
さい前賊の自動車を確めることを命じられた一巡査は、単身林の
近づくに従って、大きなコンクリートの塊りが足の踏み場もなく、ゴロゴロと転がっていた。
「オヤ、こんなものが落ちていますぜ」
一人の巡査が長靴の片足を振って、波越氏の懐中電燈の光にかざして見せた。余り上等でない赤皮の長靴だ。
警部は一目それを見ると、ギョッとして立ちすくんだ。確かに見覚えがある。運転手に変装した明智がはいていた長靴に相違ない。
明智が警部を逃がす為に態と賊の虜となったことは明らかだ。賊が虜を大仏の胎内に運んだことも容易に想像される。とすると、明智は今の大爆発に、万に一つも命を
イヤ、何よりもこの長靴が証拠ではないか。彼のはいていた長靴が、爆発の為に吹き飛ばされているからには、当の明智の身体は恐らく粉微塵になってしまったことであろう。
波越氏にとって、ルパンの逮捕などより、明智の死の方が、どんなに重大問題であったか知れない。彼は何とも云えぬ激情の為に、ブルブルと震えながら、物を云う力もなく、いつまでもそこに立ちつくしていた。
× × ×
三台の自動車が夜の京浜国道を、風の様に
波越警部が賊の逃亡を知って、行手に当る警察署へ、電話で急を報じたものに相違ない。先頭の車はルパンがハンドルを握り、大鳥不二子さんと、今一人賊の部下が同乗していた。三人とも黄金仮面の扮装のままだ。
次のオープンカーは茶箱の様な贓品の荷物を満載して、二名の部下が乗っていた。残る二名は日本人であったから、首領と別れて別の方向に身を隠したのであろう。
速力はルパンの車が最も優れている様に見えた。第一の車と第二の車の間は約半町、第二の車と警察自動車の間は、一町程隔っていた。
「あなた行先の心当りがおありになって?」
不二子さんが運転席のルパンの肩に手をかけて、
「当てなんかありゃしない。だから一分でも一秒でも、逃げられる丈逃げるのだ。最後の一秒にどんな奇蹟が現われぬとも限らぬ。失望してはいけません。ごらんなさい。僕はこんなに元気ですよ」
ルパンの怒鳴り声が、矢の様に不二子さんの耳たぶをかすめて、うしろへ飛び去る。如何にもルパンは元気であった。五十
もう行手に品川の町が見えていた、東京市中へ入りさえすれば、何とか警察自動車をまくことが出来るだろう。それが唯一の頼みであった。
突然、うしろに銃声の様なものが聞えた。さては警察自動車が発砲を始めたのかと、驚いて振向くと、アア万事休す、第二の自動車がパンクしたらしく、酔っぱらいの様によろめいている。とうとう、命がけで蒐集した美術品を放棄しなければならぬ時が来たのだ。イヤ美術品はあきらめるとしても、二人の
「エエクソ、泣くなルパン。あきらめろ、あきらめろ、美術品は何度でも蒐集出来るんだ、部下の奴等はあとから貴様の腕で救い出せばいいじゃないか」
ルパンは我心に云い聞かせながら、目をつむってあとの車を見捨てた。無論警察自動車は瞬く内に破損自動車に追いついて、贓品を取戻し、二人の黄金仮面を逮捕した。
だがそれに手間どっている間に、彼等は忽ちルパンの車を見失い、その追跡を断念しなければならなかった。ルパンと分っていたら、第二の車を見捨てても、それを追ったであろうが、警官達には黄金仮面の真偽を見分ける力がなかった。
それから何分かの後、ルパンの自動車はやや速力をゆるめて、東京市内の淋しい町を縫って走っていた。
「ねえ、あなた、あたしもう力が尽きてしまいましたわ。こんなことをして、いつまでさまよっていたところで、ガソリンがなくなると一緒に、あたし達の運命も尽きてしまうのじゃありませんか。ねえ、もうあきらめましょうよ。二人手を引合って天国へ行きましょうよ」
不二子さんは頬を伝う涙を拭おうともせず、ルパンの肩をゆすぶって、かきくどいた。
「いけない。断じていけない。僕がいいというまでは、口の中の袋を
ルパンが妙なことを云った。口の中の袋とは一体何を意味するのであろう。
それは一瞬にして人命を断つ恐ろしい毒薬を包んだ厚いゴム製の豆粒程の袋であった。その
日本娘の不二子さんは、捕われて
だが、運命というものは面白い。いやいやながら口にした、この毒嚢のお蔭で、ルパンは逮捕を免れることが出来たのだ。ルパンの逃亡と口中の毒嚢との間に、どんな因果関係があったのか、間もなく分る時が来るだろう。
「不二子さん、僕は今非常なことを考えている。明日は十八日でしょう。それをやっと今思い出したのです。分りますか。アア、考えても胸がドキドキする。恐らく僕の生涯での大冒険だ。僕は逃亡の手段を発見したのですよ。実に危険だけれど、うまく行けば僕等は一飛びに追手のかからぬ場所へ逃げられるのです。失敗すれば可愛い不二子さんと心中だ。いずれにしてもその外に、採るべき手段は絶対にないのです」
ルパンが俄かに元気づいて、生々した顔を振り向けた。
「僕の力を信じて下さい、やっつける。必ずやっつけて見せる。僕等は丁度三人だ。これも非常に都合がいいのです」
三人というのはルパンと不二子の外に、その車にはもう一人の部下の黄金仮面が乗っていたからだ。
翌十八日は、フランス飛行家シャプラン氏の世界一周機が、郊外S飛行場を出発して、所謂
離陸予定は早朝五時、夜の明ける前から、S飛行場は見送りの群衆で埋まっていた。
定刻が近づくと、航空局長官のG氏を始め朝野の関係者が、
ゴッタ返す
まだ薄暗い早朝ではあったし、渦巻き返す騒擾の為に、不思議に注意力を失った人々は、誰一人それを疑う者はなかったけれど、シャプラン氏を始め、送別の辞を受ける時も、乾盃の折にも、天空の勇士の無造作と云えばそれまでだが、飛行帽を冠ったまま、飛行眼鏡をかけたままで押し通したのは、考えて見れば、何となく異様なことであった。
殊に一行中一番小柄な飛行士は、よほど人嫌いと見えて、殆んど最初から機体の蔭に隠れて顔を出さず、点検もすまぬ内に操縦席へ飛込んで、出発まで一度も顔を出さなかったのは、何ともいぶかしい次第であった。
だが、熱狂する群衆は、そんなことには少しも気附かず、うなり出したプロペラの響に、声をからして万歳万歳を叫んでいる。
やがて一際高まる歓呼の声と共に、飛行機は、平坦な滑走路を、ユラユラと左右に揺れながら少しばかり走ったかと思うと、夢の様に、もう空中に浮んでいた。鳴りもやまぬ万歳の声、飛行機を追って「ワアッ」とばかり津波の様に押しよせる群衆。
と、不思議なことが起った。一路北方に向うものとばかり思っていた群衆の頭上を、シャプラン氏の飛行機は、低く旋回し始めたではないか。
名残りを惜しむ意味かしら、それとも機関に故障でも起ったのではあるまいかと、群衆は鳴りをひそめて、空を仰いだ。
少し高い樹木には、ぶっつかりはしないかと危まれる程、低く飛んでいるので、操縦席のシャプラン氏の姿なども、手にとる様に眺められる。
とみると、これはどうしたことだ。シャプラン氏の顔が金色に光っている。いや顔ばかりではない、全身がまばゆい金色に包まれているではないか。折から雲を離れた朝日が、それに映えて、飛行家の全身が黄金仏の様に、キラキラと輝き渡った。
「黄金仮面――、黄金仮面」
群衆の間に奇怪なる呟きが起り、瞬く内に空中の悪魔を罵る怒号と変って行った。シャプラン氏はいつの間にか、あの恐ろしい黄金仮面と形相を変えていたのだ。群衆の頭上を
狼狽した警官達は、あてもなく右往左往した。群衆は
臆病な人々は、空の兇賊が今にも爆弾を投下するが如くに逃げまどった。
機上では金色の飛行士が、片手を上げて、「おさらば」をしながら何かわめいていた。本物のシャプラン氏がこんな馬鹿馬鹿しい真似をする筈はない。いつの間にか人間のすり換えが行われていたのだ。太平洋横断の勇士は、兇賊アルセーヌ・ルパンと早変りをしたのだ。
× × ×
機上では、シャプラン氏に化けおおせたルパンの黄金仮面が、手を振りながら、叫んでいた。
「日本の淑女紳士諸君、長々お邪魔をしました。ではおさらばです。明智小五郎という日本の名探偵の為に、僕の計画はすっかり
僕は失敗した。だが、少しも後悔などしていない。復讐はとげたのだ。それから……諸君、これを聞いて呉れ給え。僕はね、千の美術品よりも尊い宝を手に入れたよ。外でもない、大鳥不二子さんだ。僕は今この可愛い恋人と一緒に、死なば諸共の空の旅に出発せんとしているのだ。愉快、愉快、……では諸君、おさらば」
ルパンは下界の群衆に向って、
演説が終ると、今度はうしろの席の不二子さんに、通話管で話しかけた。
「不二子さん。もう大丈夫だ。口の中のものを吐き出してしまいなさい。僕はとっくにあのゴム玉を靴の底で踏みつぶしてしまったよ。空ではあんなもの必要がないのだ。命が
飛行士F氏に化けた不二子さんは、それを聞くと、思い出した様に口の中の小さなものを吐き出した。
飛行機は旋回を終って、徐々に高度を高めながら、北方をさして速力を加えていた。
突然、最後方のシートから、爆発する様な笑い声が起った。それが余り高い声だったので、プロペラの音に消されながらも、前方のルパンを振向かせた。見ると、機関士に化けた部下のKが、飛行眼鏡の下を口ばかりにして、ゲラゲラと笑っているではないか。
一体全体何事が起ったのだ。Kの奴気でも違ったのか。
ルパンは気がかりなままに、通話管を取って耳に当てた。訳を話せという合図だ。
Kはまだ笑い続けながら、同じ通話管を取って口に当てた。すると、ルパンの耳に突如として雷の様な笑い声が響いて来た。
「ワハハハ……、あなた方はとうとう毒薬のゴム袋を吐き出しましたね。僕はどんなにそれを待ち兼ねていたでしょう。僕は今こそ云い度いことが云えるのだ。ところでルパン君、僕は君のうしろから、ピストルの狙いを定めているのだぜ。この意味が分るかね」
部下の口調がひどくぞんざいに変って行った。そればかりではない。いやに下手なフランス語だ。
「貴様Kじゃなかったのか。一体誰だ」
ルパンが変って送話者になった。
「誰でもない、たった今君が
飛行機がグラッと傾いた。ルパンが如何に驚愕したかがよく分る。
「君は僕を爆発薬で殺した積りだろうが、それは飛んでもない間違いだぜ。あれはね。僕の着物を着せられた、君自身の部下だったのだよ。つまりK君だったのさ。気の毒なことをしてしまったね。僕はまさか君があんな
あの時三人の賊が波越警部を追駈けている間、明智は賊のKと二人切りになった。彼はその機会をとらえて、驚くべき芝居を仕組んだのだ。ピストルは敵の手にあったけれど、一人と一人なら武器はなくとも、腕に覚えの柔術で、相手を叩き伏せ、黄金衣裳をはぎ取って、自分の運転手服と着換えさせ、猿轡をはめて、賊を明智小五郎に仕立て上げる位のことは、何の造作もなかった。
そうして、明智自身は賊から奪った黄金仮面、黄金マントでルパンの部下になりすまし、逃亡の自動車に同乗して、隙もあらば引捕えんと、
だが残念なことには、ルパンも不二子さんも例の毒嚢を口に含んでいる。迂闊に手出しをしようものなら、忽ちゴム袋を噛み破って、自殺されてしまう。ルパンは兎も角として、不二子さんを殺してしまっては取返しがつかぬのだ。
そこで、あくまでルパンの部下のKになりすまし、首領の命を奉じてシャプラン氏その他を手ごめにし、飛行服を
いかに明智の腕前とは云え、その困難極まるお芝居を、どうしてこんなに易々と行い得たか。それには偶然にも凡ての条件が実によく揃っていたからだ。時が夜更けから早朝にかけての暗い間であったこと、賊の一味が黄金仮面をつけ、絶えず顔を隠していたこと、飛行場では、ルパンを初め飛行眼鏡をかけ通していたので、明智の不自然な顔面
それはさて置き、殺したと信じた明智が生きていたばかりか、部下のKになりすまして、逃亡の飛行機に同乗していようとは、流石のルパンも余りのことに、一刹那全く思考力を失ってしまった程、ひどい驚きにうたれた。
飛行機は、迷い鳥の様に、止めどもなくフラフラと揺れ傾いた。不二子さんが思わず悲鳴を上げた程である。
だが、如何なる困難に遭遇しても、血迷う様なルパンではなかった。彼は忽ち気を取直して、送話管を取ると、
「負けた。明智君、俺の負けだ。世界の大賊アルセーヌ・ルパン、謹んで日本の名探偵に敬意を表するぜ。だが、そこで君は、一体俺をどうしようというのだね」
「飛行機を元の飛行場へ着陸させるのだ。そして、不二子さんを大鳥家に返し、君はエベール君の
「アハハハ……、オイオイ、明智君、そんなごたくは陸上で並べるがよかろう。ここは君、一つ間違えば敵も味方も命はない、何百メートルの雲の上だぜ。ピストルなんてけちな武器は何の力もありゃしない。若し君がそれを発砲すれば、飛行機は操縦者を失って、忽ち墜落するばかりさ。ハハハ……、雲の上では、どうも俺の方に
アア何たる不敵、怪賊はこの難境にひるむどころか、却って
「では、君の方では、一体僕をどうする積りなのだ」
「知れたこと、北の海の無人島へでも連れて行って、俺の腹がいえる様にするのだ」
氷山の上かなんかへ、置去りにする積りかも知れない。
「ハハハハハハ、オイ明智君、君はひどく困っている様だね。何とか云わないかね。君の智恵はもうそれ切りなのかい」
暫く沈黙が続いた。明智は最後の非常手段をとるべく、ひそかに準備をしていたのだ。
「ではルパン君、君の逮捕はあきらめよう。その代り、君の計画は最後の一つまで、すっかり放棄しなければならぬ。君は我々の国から、一物をも奪い去ることは出来ないのだ」
「エ、何だって?」
「僕はね、君の唯一の収獲であった不二子さんを、君の魔の手から取戻そうというのさ」
その言葉が終るか終らぬに、飛行機がグラグラと揺れて、甲高い悲鳴が下界へと下って行った。二つの黒い塊りが、大空にもんどり打って、砲弾の様に落下した。嫌がる不二子さんを小脇に抱えた明智小五郎が、身を躍らせて飛行機を飛び降りたのだ。
だが、決して自殺を計った訳ではない。明智の背中にも、不二子さんの背中にも、パラシウトの綱がしっかりと結びついていた。
噂の
家々の屋根には、町中の人が鈴なりになって、大きな口を揃えて空を見上げていた。白い国道には、十何台の自動車が、飛行機のあとを追って疾駆していた。その大部分は、新聞記者とカメラとを積んでいるのだ。
二つの落下傘が、あとになり先になり、巨大な
二つのパラシウトが着陸したのは
我が明智小五郎が、一同の人々から、如何に
彼は大鳥家の人に不二子さんを渡してしまうと、波越警部とエベール氏を
「ルパンは逸したけれど、同類は悉く就縛したし、国宝を初め美術品も取戻したし、最後に不二子さんさえルパンの魔手を逃がれたのだから、先ず先ず、今度の戦いは僕の勝利といってもいいだろうね。だがルパンは慣れぬ異郷の戦いなのだから、そこにいくらかハンディキャップをつけてやらなければ可哀相だね」
× × ×
ルパンの飛行機は、そのまま数日の間消息を断っていたが、ある日太平洋航行中の汽船が、海面に漂うシャプラン氏の飛行機を発見したという新聞電報が人々を驚かせた。
ルパンは太平洋の