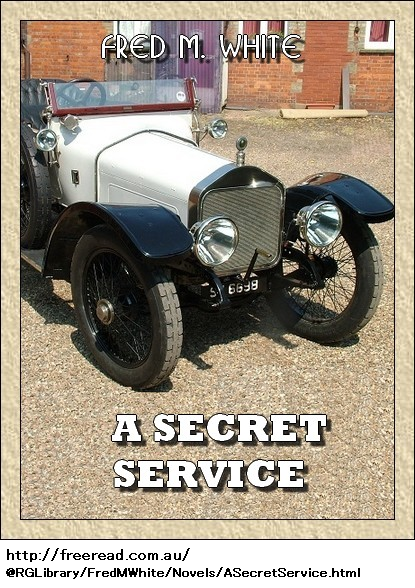主な登場人物 備考
アイダ 娘
バンストン 父
エイビス 結婚相手
エルシ 服飾仕立師
バレリイ 上流社会の令嬢
ウォルタ卿 英国ベルリン大使
グレイ 大使の個人秘書
グラスゴウ 殿下、諜報部長
トラフォード警部補 警部補
ヘプバン編集長 編集長
アーノット 新聞記者
ハースコート 裏切りスパイ
トラスコット先生 医者
スコット次官 外務省・事務次官
ゼナ王女 ボーン国王の妹
ルペラ男爵 石油採掘権を持つ
ジェフリ ウォルタ卿の息子
ボーン国王 ゼナ王女の兄
デントン 現場監督
グラハム警部補 警部補
バロフ所長 刑務所の所長
イズリアルス ユダヤ宝石商
第一章 ロンドン砂漠
アイダが見上げたうっとうしい煙突群からは黒煙がたなびき、あたかも我が身の希望と怖れを暗示しているかのようで、生まれて初めて怖くなった。でも嫌なら終止符を打つことも出来た。便せん一枚と一ペニ切手があれば生活苦を終わらせることが出来る。ああ、それだけはまっぴらだ。そう思いながら眺めた煙は鉛色の三月の空に絶えず渦巻いている。
アイダは生まれも育ちも上流階級だが、妙な立場だった。現実は、最後の有り金と別れ、稼ぐ見込みもない。さらにいろんなもめ事に加え、数週間も家賃未払いで、あす払わなければ路上に追い出される。
状況は最初から絶望的だった。それを承知で家出した。眼の前の
父に
「絶対に結婚しません。この家から出て自活します」
父のバンストンが悠々とポートワインを飲んだ。冷徹な美男子が妙な笑顔をたたえ、こう答えた。
「ようく分った、アイダ。邪魔はしない。状況はよく説明した。お前がエイビスと結婚しなければわしは破産する。贅沢品をすべて手放し、この由緒ある豪邸を売り払い、どこか外国のみすぼらしい川辺で余生を終わる羽目になる。もちろんお前には関係のないことだ。お前にはこの二十年間、欲しいものを何でも与えたが、ちょっと見返りが欲しいと言っただけで拒絶だ。エイビスが昨夜言ったが、お前が婚約に同意した時点でわしを助けてくれるそうだ。この程度のことに同意しないのだから全く分らん」
「前言を撤回しろですか、お父様」
「当然だろ。アイダ、それがどうした。心変わりは女の特権じゃないか。エイビスは厳しいから、わしを追い詰めたが、わしは少しも泣き言はいわない。ちょっとわしにツキがあったら、逆に追い込めた。それもこれも勝負ごとだし、わしと同じぐらいシティにおればお前にも分ろう。エイビスの何が気にいらんのか。奴は美男だし大金持ちだから、大半の女達がお前の幸せをとても喜ぶ。それに、これも言っておこう。エイビスは欲しい時にいつでも爵位がもらえる。奴より諜報部の動きに詳しい男はほかにいない。ちょっとしゃべりすぎた。さあ、分かったか、アイダ」
「エイビスは愛せません。もっと言えば嫌いです。そのうちお父様のように世間ずれしてお金がすべて、名誉や誠実は重要でないと思うかも知れません。いいですか。お父様は挑戦を捨てたのですよ。私は自活して、写生画で稼ぎます」
「その場合、何も援助しないぞ」
「わかっています。成功するかもしれないし失敗するかもしれませんが、完敗してお父様の助けが必要になったら実家に戻り、エイビスがまだ求婚していれば、妻になります」
父がポートワインを手酌でつぎ、にやり。悦に入って眺めた食堂には年代物の
切れ者ではあったが何かものぐさの気質があり、そのためにいつも勝ち損ねた。誰もバンストンほどの大計画を立て得る人物はなく、いままでどんな投機家も実行した人はいない。
だがたった一日、歓楽の誘惑に負け、ここぞと言うときに地位から引きずり下ろされてしまった。また他人の能力を軽蔑したのも致命傷になった。だが世俗の知恵と皮肉癖は相変わらずだ。
「お前に大いに感謝する。残酷に言えばそうなると思う。エイビスにはちょっと辛抱してもらうが、お前がエイビスと結婚すればたいそう快適……、まあ意に反するだろうが。お前の死んだ母さんも昔は同じだったが、充分幸せだったよ」
「そうでしたね」
とアイダがあいまいに答えた。
「当然だ。さてと、これ以上不快な話はよそう。それから大騒ぎするなよ。自活のために家出を許すけど、助けが必要になったら手紙を送れば喜んで迎えに行って、あのう、そのう、質草を取り戻してやろう」
「もし成功したら、お父様」
「アイダよ、そんなことは万に一つだ。すまんが煙草を取ってくれ」
こんな場面が痛々しくくっきり眼前に浮かんだのは、忍び寄る暗闇に座り、絶望的にロンドンを眺めていたときだった。この六ヶ月、万一の望みにかけて奮闘し、日ごとますます絶望の泥沼にはまっていった。大して長くかからずに分ったことは、素人の手慰み作品と、たとえ二流だろうがプロ画家の作品とが、天地ほど違うということだ。
あらゆる方面に腕を試したが、結果はいつも同じだった。最初、編集長は親切だが、そのうち事務員に阻止される。六ヶ月でいくらも稼げず、どうしようもないほど金に窮してしまった。仮に質屋の扉をくぐっても赤面する場合じゃない。
終局がやってきた。文字通り着ている衣服以外に何もなく、ただ若さと美貌と勇気があるのみ、これらはまだ失っていなかった。決心した。
「実家には戻らない。ほかを当たってみよう。六ヶ月かかって画才が無いのを知るとは。女中奉公しよう。負け犬にならないうちに床磨きしよう。職業紹介所へ行けば……」
*
アイダが帽子をかぶり上着を引っかけ、汚い階段を降りて部屋の外で立ち止まり、聞き耳を立てた。中で誰か作業しており、ミシンの音が聞こえる。一瞬躊躇したが扉を開け、のぞいて、尋ねた。
「お忙しいですか」
茶色の瞳を哀れげにミシンから上げて、美貌だがやつれて青白い顔の縫い子が微笑んで、言った。
「ええ。少し手伝って下さらない? 先週何も出来なくて、いまが山場なのです。三日間ひどいリューマチで寝込んでおり、指がとても不自由なのです」
「まあお気の毒に。もっと早く来て会うべきでしたね。知らなくて」
痩せた青白い女がまた微笑んだ。縫い子のエルシの歳はアイダと同じくらいだが、貧困と苦労を散々なめてきた。どこか悲劇がありそうだが、過去は何も言わなかった。
女二人、
「ずけずけ言って怒っていない?」
とエルシが尋ねた。
「いいえ、ふふふ、逆ですよ、自分にかかりっきりで。どうして欲しい?」
とアイダが微笑んだ。
「じゃあ、ここへ来なかったのは誇りのためですか。ええ誇りは大切です。私もそれしか残っていません。でも噂は消せません、特にがさつで冷酷な女家主は下宿人のことを秘密にしません。全部知っています。あすまでに払わないと、プリース夫人が追い出すとか。赤面することはありません。私も何回もそんな瀬戸際に会いましたから。いまお助けしましょう。だってあなたがやってくれたら私も助かりますから。あの怖い女家主に未払い家賃を立て替えましょう。その代わり働いて下さい、あなたがいなければ、ほかの誰かに頼まなければなりません。あなたのようなレディが工女よりもむしろいいのです。実は私もレディですから」
「それは最初から分っていましたよ。でも、あなたが一生懸命稼いだお金をどうして借りられましょう」
「ばか言わないで。助手が必要と言ったでしょう。医者が言うにはこんな東風に出歩くと危ないそうですが、生地を握れないと仕事を失います。もし手助けして戴ければ簡単に三倍稼げます。お分かりのように私は仕立師なのです。西部の大邸宅から美しい生地を大量に預かりそれを仕立てるのです。衣装を見る目があるのです。大化けします、たとえば
アイダは台に突っ伏して顔を両手で覆った。幸運な助け船に涙した。あたかも肩から重荷が取れたかのよう、鉄の爪を取り除いてくれたかのよう、何週間も心臓を捕まれていた。エンバンクメントでの夜霧や恐怖に、もう悩まされない。だってエルシの申し出を受け入れるつもりだし、この機会に感謝しているもの。少し前なら見下していたかもしれない。こう、ささやいた。
「ご親切にありがとうございます。感謝しきれません。して欲しいことを言って下されば、全身全霊で働きます。今夜は後悔させません」
第二章 バレリイ
エルシが応じた。
「責任はすべて私にあります。これを見て下さい。ここにある衣装はあるレディのために仕上げるもので、今晩の慈善舞踏会用です。ある豪邸にお住まいのレディ向けですが、舞踏会終了後は衣装に無頓着です。特殊な要望はおっしゃらなかったのですが、馬鹿な男性服飾商には意味が分りません。今まで仕立てた中で一番美しい夜会服だそうで、全くその通りです。上流階級の女性は十中八九ただ夜会服を見せて楽しむだけです。これはギリシャ風のすばらしい黒生地ですが、私の意見ではちょっと暗すぎます。赤毛の女性向きで、バレリイ嬢は黒髪だと思います。私が着てみますから、あなたは見て下さい。意見を聞きたいのです」
エルシが自分の体に巻き付け、柔らかくひだをつくって、明かりを全身に浴びた。細身のしなやかな体がぐっと引き立った。すっかり別人に変身したかのよう。
「わあ、きれい。エルシはなんて美しいのでしょう、いままで……」
「ほかの生地が良かったかしら。でもそれはよしましょう。私は金髪ですからこのドレスが似合うのです。あなたが着て向こうの姿見で確認して、感想を言って下さい。あなたは黒髪美人、どこか南方系ですね」
「母がイタリア人でした」
「ああ、だから澄んだ瞳、オリーブ色の顔なのですね。いま、生地を足しますから。そう、安全ピンで留めて下さい。この衣装の利点はきちんと調整すれば誰にでも合うことです。姿見に向かって確認して下さい。アイダはかわいくて色彩も完璧ですが、滑らかで真っ黒な生地は顔色を暗くしてしまいます。白い水玉模様をちらし、この素敵な
対面の姿見に映る我が身を眺めた。口が半開き、ほほにほんのり朱が差している。
「これが私ですか。エルシ、あなたはまさしく魔女だ。ちょっと刺繍を加えただけで、こんなに変わるなんて信じられません」
「ふふふ、それが刺繍なのです。まだ脱いではいけません。少し私のモデルになって下さい。別な霊感が湧きました。心に浮かんだことをすべて仮縫いしてみて、それからあなたにミシンを使ってもらいます。ところで、今までミシンがけしたことは?」
嬉しいことにアイダがミシンがけを保証した。次の一時間か二時間、無言で、急ぎ仕事を行い、ついにエルシが満足そうにため息をついて、仕事を終えた。
「どんなに安心したか、あなたには分らないでしょう。手伝ってもらわなければ絶対終わらなかったでしょう。契約では今晩十一時グロブナー広場四五A番地にドレスを引き渡すことになっています。あなたに行ってもらい、バレリイ嬢にこれを渡してもらいたいのです。レディ付き侍女のように振る舞わねばなりませんが、あなたにその心配は要らないと思います。不安ですか」
「何でも致します。ああ、きょうは何という幸運に救われたことか。バレリイ嬢に気づかれなければ大丈夫です」
「何ですって。バレリイ嬢を知っているのですか」
「いいえ。名前すら聞いたことはありませんが、ちょっと妙なことがありまして。グロブナー広場四五A番地は父の友人が住んでいます。六ヶ月間、家を貸したと聞いています。ひょんな事で服飾助手として行くことになりましたが、むかし客として招待されたことがあります」
*
やはりアイダはちょっと不安だったが、グロブナー広場の豪邸正面玄関ベルを鳴らした。万が一、友人の召使いに当たれば正体がばれるかもしれない。だが扉を開けた従僕は見知らぬ男で、しかも外人だ。痩せた背の高い男で、射すくめるような目つきで能面のよう。何かぎこちなく、本職が従僕でないかのようだ。言葉は本場の英語、アクセントも洗練されている。印象としてはぎこちなく、舞台俳優の召使いといったところ。
照明がきらめく大広間には絵画や彫像、大量の花々が備わり、ほかの召使い達も静粛、従順、上品に立ち回っている。もしかしたらアイダも招待客として丁重におもてなしされ、応接室へ招かれた気がしないでもない。
バレリイ嬢はその時忙しいとかで、長くは待たせないよし。応接室は電気が煌々と輝き、観音扉越しに豪華な別室が見えた。別室も明かり全開で、アイダの見たところ無人だ。美しくて懐かしいが、妙に豪華で印象的に見えるのは、みすぼらしい屋根裏部屋に長いこと住んでいたせいだ。
ついたてを陰にして座っていると、向かいの別室に誰かが入っていくのが見えた。スカートの擦れる音が聞こえ、優しい澄んだ声がして、何か命令している風で、その話しぶりからスペイン人かイタリア人とみた。やがて内扉がそっと閉まったが、アイダが首をひねって観音扉越しに中を覗くと、一人の女性が突っ立ち、手に手紙を持っている。
何かこの女性には関心を釘付けにするものがあった。それほど背が高くなく威圧的でもないが、顔は青ざめ、黒い瞳が憂鬱そうだ。手紙を何回も読んでから、ずたずたに破り、火にくべた。
そのとき別な扉が開いて、男が入ってきた。女性のそばに寄った男は立派な体格で、シミ一つない夜会服を着て、きちんと身なりを整え、紛れもなく英国人だ。男の横顔を見たアイダの印象は、堅物のタカ派、きれいに剃った口元を固く結んでいる。
男の言葉は挑発気味だった。
「わかった、わかった。俺はここに居る。きみは俺がいないと何も出来ない。きみはいい女だが、バレリイ、時々賢すぎる」
バレリイが憂鬱に笑った。
「フフフ。時々あなたも、しゃくに障りますよ。たびたび嫌いになって頭に血が上り、堪忍袋が切れたら、友人のあなたでも数日中に刺し殺しかねません。私をこき使えば当然でしょう。独自の理由とやり方でそうなさるのでしょうが、もうできないと知るべきです。今晩の慈善舞踏会に出席すべきじゃないと思って、私を引き留めたいのでしょう。ふん。このバレリイが女と生まれてこうと決めたことを、どんな男がひっくり返すというの。間違いなくあなたにも止められない。どうあろうと、私は行きます。いつか世間はその訳を知るでしょう。どうかほっといて、時間がありません。出て行きなさい、さもないと召使いを呼びますよ」
「おっと、その必要は無い。きみが愚かで馬鹿なことをしようとしているから必死に止めた。お休み、バレリイ」
男が静かに部屋から出て行くと、バレリイが観音扉からこちらへ来た。アイダを見てちょっと驚き、いぶかしげにギロリと見て、尋ねた。
「ドレスを持ってきたのですか。ちょっと忘れていました。あの部屋での会話を聞きましたか。たいしたことではありません。若いあなたには分らないでしょう。さあ、明かりの所に立って顔を見せて下さい。まあ」
バレリイが穴の開くほどアイダを見て、妙な目つきになって、叫んだ。
「まあ、そっくりです。うりふたつですね、こんな似た人がいたなんて、奇妙でびっくりです。ボンド通りの店員が私の生き写しだなんて。国籍も同じですか」
「母がイタリア人でした。でもお嬢様、そのお話はしたくありません。お分かりのように、私は単なる店員で、ドレスの着付けに伺っただけでございます」
バレリイが滅入って答えた。
「そうでしたね。なんでも好機は来るし、つねにあしたは来ます。そのドレスを取ってあなたが着てください。姿も顔も似ていますから。邪魔されないように鍵を閉めて。ふとあなたのドレス姿を見たくなりました。着付けを手伝います。ああ、すごい。腕の立つ服飾師を紹介され、水晶をダイヤに変えるとか、見なさい、やってくれました。あなた、すてきですよ、うらやましい」
「私の仕事ではございません」
「とにかく今夜はそうですね。ところでざっくばらんに言いますが、気を悪くしたらごめんなさい。ふとある考えが浮かんで、ぜひ実行したいのです、分りますね。あなたは店員で貧しい。真っ当に稼ぐ限り、お金の為なら何でもやるでしょう。あなたは私の双子同然、勇気もある。これからやろうとすることは危険もありますが、いいですか、一生見たこともないような大金をさしあげます。さあ、わたくしにすべてをゆだね、言うとおりにしてくれますか」
第三章 駐独英国大使館
コーヒー、お酒、煙草が回されて、ウォルタ卿の招待客達は完璧な食卓で悠々と過ごしていた。公式な晩餐会じゃなかったが、食事が提供されたのは、ベルリンにある英国大使館の居間だった。
大衆小説の見立てなら、ウォルタ卿は大物大使じゃない。皆が読みたがるような狡猾な性癖も持ち合わせていない。同大使の仕事は歴史を作ることじゃなく、功績となる劇的な勝利もない。
また秘密とか卑劣とかいったことも全くない。平凡で快活、良識ある英国人で、手札はいつも堂々と公開するが、それでも駆け引きのすべてを知っている。裏仕掛けや権謀術策網がなければ外交を制することは不可能だが、部下にすべてを任せた。
かつては有名な野外活動家であり、いまでも腕の立つ釣り師や射撃名人であり、当時の批評家がよく言ったものだが、もし面会することが大使の仕事なら、ウォルタ卿が適任者じゃないと言う人はいないだろう。
まずもって王室をもてなしたのも、同大使が資産家であり、大使夫人も欧州上流社会で一番の人気者だったからだ。
とはいえ、大使が不安の陰を顔に浮かべ、友人と語らっているのを、グレイが気づかないはずがなかった。事実グレイの仕事は大使の気分と変化を掴むこと。それがここに居る理由だ。三年間ウォルタ卿の私設秘書を務め、大いに信用されている。
大使はグレイに何も隠さず、すべてをゆだねた。二人はお互い完全に理解し合っていたので、他人に知られずに会話でき、多言は必要なかった。科学者ならこの現象を説明できるかもしれない。似たもの同士はそんな意思疎通が確かにできるからだ。
どう見てもグレイが熱中しているのは煙草とシャトーラフィット・ワインであり、この二つを無造作に指でいじっていた。柳腰のオーストリア大使館員と狩りに行こうか熱心に話をしていたとき、グレイが頭の向きを変えた。
何かあるんじゃないかとずっと辛抱して監視しており、理由は大使の関心事を見逃さないためだ。自分の名前が聞こえたので、聞き耳を立てつつ、表向きの関心はオーストリア大使館員との会話だ。
ウォルタ卿が話しているのは隣の真っ黒なあごひげのロシア人だ。
「ロシア大公閣下、そのうちそうなると申し上げたでしょう。何年も前に言いましたが、英国が生き延びる唯一のチャンスは欧州にスポーツ害毒を植え付けることです。これを仕込めば対ドイツにも安全ですな、何百
ロシア大公が杯を上げた。
「スポーツ万歳。とりわけゴルフ万歳。ゴルフがなければ今頃こうして素晴らしい赤ワインの香りを楽しんではおりません。おおゴルフよ、汝なかりせば」
英国大使が笑った。グレイが聞いているのを流し目で確認した。
「ええ、諸刃の剣ですな。確かに善し悪しです。たとえば秘書のグレイです。信じられますかな、図々しくも一週間休暇をくれと言って、セントアンドルーズへ長旅して、保持しているチャレンジカップを防衛するんだとか。いいですか、さも当然という態度です。かのパーマストン首相なら何と言いますやら」
グレイがにやり、早速仕事だ。校長から頼み事を言われた上級生よろしく、見事に意味を掴んだ。実際そんな要求はしていなし、事実初耳だった。
ただ分ったことは緊急用件で英国へ帰れということを、客人に知られないように伝えたことだ。コーヒーと一緒に手紙が数通ウォルタ卿に届き、開けて慎重に眺めていた。手紙をテーブルに置き、あたかも重要でないかのようにした。
ロシア大公が尋ねた。
「グレイ君、いつ行くんだね。大使は拒否しないと思うけど」
大使が言った。
「今晩にも行きたいようだな。スポーツのことになるとみな餓鬼だ。だろグレイ君、違うか。今晩発つのか」
「そうしたいです」
「そうか、そうか。嫌な話はよそう。この手紙を持って、出発前に返事を出してくれ。裏面に指示を二、三メモした。ついでに書斎へ行ってテーブルの葉巻を持ってきてくれ。ハバナ産の絶品だよ」
グレイが無言で退出した。
英国へすぐ旅立たねばならないし、誰にも言う必要も無いが、事案はこの手紙に関わっている。書斎で手紙をざっと読んだが、グレイにはちんぷんかんぷんだ。その時慎重に解読したのが数行の速記、ウォルタ卿が客人と話しているとき走り書きしたものだ。
指示は明白だ。
『すぐロンドンへ発ってくれ。今晩何か掴んだけど君に説明する暇が無い。金庫の左引き出しにある桃色の書類束を取り出し速やかにロンドンへ運べ。直近 路線は行くな、尾行される怖れが大きい。うがった見方では、君も知っているある国王が、急送文書をとても見たがっている。従ってパリへしゃれ込み、追っ手をまいた方がいい。昼間ドーバー海峡を渡り、夜行でチャリングクロスへ行け。少なくともいまロシア大公は騙さねばならん。駅へ行く途中でロイターストラーセに寄って某氏に会え。きっと王女宛の小包みをロンドンまで運ばせると思う。分らないから想像で言うけど、小包みは宝石としてかなり高価なものだと思う』
グレイはこのメモを火にくべて、葉巻を持ち、路線を慎重に選び、疲れる遠回り路線に乗り、パリに着いたのは二日後、疲れ果てぐったり。時間的には快適な睡眠やら、お風呂やら豪華な食事にありつけて、翌日の夕暮れ、ドーバー桟橋を離れ、駅の方向へ歩いて行った。ここまで旅は平穏で退屈、単調の極みだ。
一等車の通路側座席を選び、葉巻に火をつけた。まるで貸し切ったかのようで、列車は混んでいなかった。そのとき、髭無し男が用心深く一等車を覗いた。グレイがそれを見て、うなずいて笑った。
「君もここへ乗るのか、エバンス」
「そうではありません。周りに敵がいないか警戒しております。パリであなたを見つけてずっとつけてきました。予防手段です。諜報部長の指示で動いています。いま敵が一人も汽車に乗っていないとは言い切れません。知らせておこうと思いまして」
エバンスが席を探すかのようにして通り過ぎると、やがて列車は闇夜へ滑り込んだ。建前は急行だが、ちっとも速くなく、通常ならチャリングクロス駅には止まらないけど、グレイの横に体育系の男が乗ってきた。
しばらくは気が張っていたが、次第にうとうとしてきて目を閉じた。意識が遠のく直前、はっと目が覚めた。寝ちゃいかんと独り言。前夜ぐっすり寝たので、疲れているはずはない。怪しいものは何もないし、一人じゃないし、信頼できるエバンスが数メートル先にいるじゃないか。またもまぶたが降りて、今度はすっかり寝てしまった。
列車は夜の激しい東風に向かって走り、速度が落ち始め、トンネルの手前で完全に止まってしまった。暗闇に小さい炎が見え、下り線路でカンテラが前後に振られている。物見高い乗客達が寝間着のまま身を乗り出し、外を覗き、状況を知りたがった。
車掌が説明した。
「みなさん、何も心配は要りません。保線係が線路上に障害物を発見しました。列車通過後に石が落ちたようです。間に合わなかったら重大事故になったかも知れません。ジョージ、前方は大丈夫か」
しわがれ声が暗闇から大丈夫と応じると、車掌が車掌車に乗り込んでランプを振った。列車は速度を増し轟音を立ててトンネルを通過し、乗客も再び落ち着くと、次第にロンドンの明かりが見え始めた。
グレイが快適に過ごす一等車、その尻に連結された二等車にエバンスは座り、本を読んでいた。エバンスの見るところ誰も列車の最後尾に乗り込んでいない。でもグレイの無事を確認したほうがいい。エバンスが通路をよろよろ進み、一等車をのぞき込んだ。
個室が空っぽだ。
警備の警察犬すら一声も吠えなかった。真向かいの扉へ行って鍵を確かめた。取っ手を回したが完全に閉まっている。グレイは向かい側へ行っていない。姿はないけど、あったのが開封済み封筒、裏面に組み文字が書いてある。
第四章 報道規制
ピカデリ九九九番地には世界的に有名なスポーツ用品店があり、経営者はグラスゴウ殿下。殿下は仲間うちで「ちゃんこ」と言われ、その由来はだじゃれ、クライド伯爵の三男であり、全盛時スポーツ界では「あっぱれクライトン」のあだ名だった。
言うまでもないが、グラスゴウは三冠王であり、国際試合出場選手でもあった。世間的には健全な英国人の典型であり、ただ一つの目的に突き進む人物に見えた。
とても賢い考えだと思われたのは自営業を始めた時であり、これが驚くほどうまくいった。上流階級の女性が簡単に稼げるなら、上流階級の男性も簡単に稼げない理由はないはずで、目利きならなおさらだ。この数年間グラスゴウはピカデリ九九九番地で年に数千ポンド稼いでいる。
店舗の上階に住み、快適な部屋をいくつも持ち、豪華な事務所はスポーツ代理店の商談場だ。最適なシカ
容姿は丸顔のぽっちゃり、気さくな男だがそれ以上の秘密があった。表向きはスポーツマン以外の何者でもないと自称していた。
というのも友人の誰にも知られていないことであるが事実上、諜報部の部長だったからだ。部長以下、敏腕部下が十数名おり、絶えず欧州を旅しており、もちろんスポーツ関連だとみな思っている。だがこれらの部下達は決まって私立中高一貫校や大学の代表選手であり、容易に欧州の最高クラブに入会できた。
グラスゴウが私室の机を前に、警視庁のトラフォード警部補と話し込んでいた。
「警部補、いいですか。これは警察の所管で私のじゃない。既に申し上げたようにグレイ氏が三日前にベルリンを発ち、重要な公文書を
「グラスゴウさん、そもそも列車が止まったのですか」
「ええ、実際止まったが、通常は止まりません。障害物が線路上に見つかって、数分間停止しました。おそらく同意見でしょうが、故意に置かれたのです。ですから警察の所管です。誰もまだグレイが消えたことを知りませんし、今は公表しません。
「何か手がかりはありませんか」
「何も。エバンスの話では列車が止まったのでおやと思い、グレイ氏が消えているのを発見しました。以上がすべてです。警察の自由にやって下さい」
トラフォード警部補があたふた帰ると、グラスゴウはまた机に向かった。ペンを取る間もなく、私用電話が鳴った。
「ご用件は?」
「グラスゴウさんですか。日刊センティナル紙のヘプバンです。用件ですか。はい、今事務所に私一人です。あなたもそうだと思いますので、ざっくばらんに言います。特約記者の一人がいま編集室へ来て特ダネらしきものを出しました。この記者は敏腕で信頼でき、ガセで
グラスゴウが小声でののしった。最初から怖れたことであり、不測の突発事態だ。もし自分の思い通りに出来るなら、新聞を厳しく検閲し、国家に害を及ぼすようなことは一切載せない。
「いやあ、御社の記者は鋭いですね。その調子では貴社の新聞が欧州戦争を引き起こしますよ。発表して何の得がありますか」
「グラスゴウさん、我々は商売をしているのであり、帝国防衛連盟じゃありません。あなたをだしに、もの笑いするために電話したのではなく、本件を相談したいのです。もし差し障りがあるとおっしゃれば、記事は差し止めます。当該記者の口止めなら約束します。我々は儲け主義ですが、非国民とは誰にも言わせません」
「本当にありがとうございます。すっ飛んで行きますから、ちょっとお話しましょう。夜十時以降あなたの仕事は忙しいと知っていますが、数分ならいいでしょう。御社の記者は事情通なので手がかりを掴んだのでしょう。もちろん、書いて欲しくありません。あなたには何回も助けられたので、全力で便宜を図ります。しかもあなたは私が諜報関係者だと知っている数少ない部外者です。一〇分後に寄ります」
十五分以内にグラスゴウは日刊センティナル紙の編集長と直談判した。編集長の机には記事の試し刷りがあった。大量の情報が載せられ、グラスゴウも初めて見た。
「大変腕の立つ記者のようですね。ぜひ会いたいものです。このように鼻の利く猟犬は我が部隊でも使えます。しかも多くの情報を掴み、我々を傷つけずに記事に使っています。記者を紹介してくれませんか」
「ハハハ、駄目です。我が社の有能な記者を売り渡すなんて。しかもあなたとは気が合いませんよ。無口な変人記者で、懲役刑に服したそうです。無実の罪に落とされたといつも言っており、他人も同様なことを言っていましたね。それやこれやで気難しくなり失望しているから、質問には怒るかも知れませんよ。怒らなければいいが」
「じゃあ情報源は知らないのですか」
「グラスゴウさん、全然知りませんよ。そんな出過ぎたことを訊けばもう我が社には近寄らず、競合他紙で有り難く、かの記者の記事を拝読する羽目になります。私が直接会って外交上の理由で記事は載せないと伝えますが、当該記者はちっとも損をせず、既に小切手を受領済みです。この記者が夕暮れ時に来て言うことに、入手した開封済み封筒から話を組み立てたとか。素晴らしい推理に違いないし、精密に組み立てられていますし、グレイの失踪を否定する事実もありません。もちろん記者は情報源を知っているでしょうから封筒にもう用はないでしょう」
「その封筒はどうしましたか」
「さあ、知りません。もう捨てたかも。そういえばあの記者が手に持っていました。手柄を自慢するように一〇分以上しゃべり続け、去年一年間の総おしゃべり時間より長かったくらいでした。さあ、あの封筒はどうしたか。私は開封済み封筒なんかに興味はないし、最新記事が机にありましたから。あの記者が投げ捨てたかもしれません、出て行きながら紙煙草を巻いていました。くずかごに捨てたかもしれませんよ。ちょっと待って下さい、見てきます。結局そこかもしれません」
直後、ヘプバン編集長が例の封筒を意気揚々と掲げてきた。薄い灰色がかった手作り封筒で、垂れ蓋の所に小さな朱色の組文字がある。グラスゴウの目が少し光ったようで、封筒をポケットに収めた。あとは冷静にこう言い残した。
「これは役に立つかもしれない。口外しないように。大変お世話になりました。早々に退散します」
タクシーをすっ飛ばし自宅へ戻った。封筒をテーブルに置き、強力な虫眼鏡で調べた。結果に満足した様子で、にやり笑って電話機を取り、部下を呼び出した。
「ナンバー三か。グラスゴウだ。すぐグロブナー広場四五A番地へ行ってバレリイ嬢が在宅か確認しろ。在宅ならよろしい。外出なら行き先と帰宅時間を調べろ。結果を近くの電話から伝えろ」
一〇分後に返事が来た。バレリイ嬢はコベントガーデンの慈善舞踏会に外出して、帰り時間は不明とのこと。
グラスゴウが帽子をひっつかみ、階段を駆け下りて、流しのタクシーを拾った。
「行く先はコベントガーデンだ。いや、オペラハウスじゃない。ベーカー通りの衣装店だ。一〇分以内に着けたら半ソブリン金貨をやるぞ」
第五章 舞踏会にて
アイダはまごつき混乱し、どう答えていいものか、哀れげに懇願するバレリイ嬢の目をじっと見つめた。数時間前アイダは単なる浮浪児、人間の落伍者、人生の流れに浮き沈み、忘却と暗黒の海へと消え去る運命だった。それがいまやゴミ箱からつかみ出され、冒険の渦へと巻き込まれた。
喜ぶべきか悲しむべきか、興奮すべきか恥ずべきか、分らない。だが、どうあれ強烈な抗しがたい誘惑があった。それに若くて強いし、まだひどい飢餓状態を脱していないし、これから恐ろしい予感があるものの、勇気はまだ失っていない。
六ヶ月前こんな冒険を夢見ていたものだが、昨今の浮き世を体験した結果、危険を感じて尻込みした。
バレリイ嬢がいらついてねめつけた。
「話は聞いたでしょう。もちろん危険はありますが、あなたの性格からして気にしないでしょう。さあ、あなたの立場ならためらわないはずです。私が口出する事じゃないですが、なぜそんな境遇になったか尋ねません。きっと生まれつきではないでしょう」
「それが何か?」
とアイダが冷たく言い返した。
「ごめんなさい。言うべきではありませんでした。でもきっとあなたは野心家、一生、店員ではいられません。私に任せればお金を稼げます。実家に帰り、慣れ親しんだ人達と暮らせます。あなたのためなら私に出来ないことは一切ありません。お金はあります。貧乏であれば、こんな豪邸に住めますか。それに私の全責任において、私がけちだとか、私に使えてくれる人々に良くしないとか、敵に言わせません」
「信じてよろしいのでございますね。私は恐いものなしでございます。餓死寸前状態が余りにも長かったものですから何も怖れませんが、例外は文無しでございます。恐いのは悪事を強要されることでございます」
「犯罪ということですか」
「はい。それが納得できれば……」
「私の言葉を信じなさい。法律の網にかかるようなことをしろというわけではありません。万が一そうなったら私が責任を取ります。さあいいですか、ときにあなたのお名前は?」
「アイダ・バンストンと申します」
「まあ、偽名を言うかと思いましたよ。どうか分って下さいね。私をうらやましいでしょう。若くて独身、金持ち、美人、充実した人生、勇気もある。でも切羽詰まり、監視され
「でもお思いになられているほど似ておりません。妄想で判断が曇っておられます。少し離れればごまかせるかも知れませんが、弱点がございます。バレリイお嬢様には大勢のお友達がおられて、その方々も舞踏会においででございましょう」
「おそらくそうでしょうが、どうって事はありません。私は気むずかし屋で通っています。お金持ちで若くて美人の娘にはそんな特権が許されます。私は踊りません。みんなから離れて不機嫌にしています。誰にも話しかけないし、午前二時には勝手に帰ります。タクシーで戻ります、つまりあなたが戻ると言うことですよ。これは私の指示です。いま言っていることはあなたのするべき今晩の行動です。コベントガーデンを退去して、ここへは午前二時半ぴたり到着して下さい。その時間には私も帰っていますので、タクシーが扉の前に止まったら、中にいれます」
驚いたことにアイダはこの妙な冒険に乗り気になってしまった。この女性の魅力で自制心を失ってしまった。結局そんなに大きな危険があるわけじゃないし、たとえ変装がばれたとしても厳しい結果にはなるまい。
「わかりました。仰せの通りに致します。ですが、まず友人にメモを書かせて下さい、エルシが私の身を案じます。メモを送ってから、身代わりになります。もう言うことはございません」
「それでいくらほしいの?」
「お任せいたします。私は文無しでございます。一、二時間前エンバンクメントでは寝食の危機に直面しました。こんな窮乏になったことはありません。私が家出したのは必死に自活するためで、父の強制する男性と結婚したくなかったからでございます。情勢が変わって、わずかなお礼がもらえる見込みに少なくとも……」
「やめて。そんなに私を苦しめないで。だってかつての自分にほかなりませんから。むかし私はローマ通りを裸足で歩き回り、どさ回り欧州芸人一座にいました。あなたには最初百ポンド、あとでもっと差し上げます。さあ、私の部屋へいらっしゃい、時間がありません。必要なものはそろっています。衣装もぴったりだと思います。準備が出来たら私の寝室に案内します。私は勝手口から出ますから、あなたが当分の間バレリイですよ。上手に身を包めば誰にも違いは分りません。それからベルを鳴らして車を用意させなさい。嬉しいほど簡単でしょう。コベントガーデンについたら車を行かせて、帰りは召使い不要と言いなさい。あとはあなたにまかせます。なによりみんなから離れることです、あなたがバレリイ、うんざり不機嫌の振りをするのですよ。保証しますアイダ、時々そんな不機嫌で間が悪くなります。どの友人も皆そう言います。さあ、行きましょう」
アイダは妙に興奮し、来たるべき荒々しい冒険にぞくぞくだ。若くて柔軟、心意気も上々。六ヶ月恐怖を味わった後、最高の人生がまた見られるとあっては元気も出よう。よどんで窒息しそうな環境から出られ、なんて素敵なのだろう。
芯から元気が出たのは、豪華な作りの寝室に我が身を置いたとき、電灯が煌々と輝き、化粧室の銀製品に暖炉の炎が反射して踊っている。絹織物の肌触りに心がなごみ、上品な手袋や靴は、新顔アイダのためにバレリイが用意したものだ。アイダが息を呑んだ、姿見に我が身を見て、まさしく口あんぐり。
「素敵でございます。もったいなく存じます。今ならどこでも通用します。それに引き替え、あのみすぼらしい衣装で、よく恥ずかしくも自分の絵を半ペニで売ったものでございます」
「でも、いい心がけですよ。さて、あなたを置いて私は行きます。この黒い上着とフードを付けて家を出れば誰にも分りません。あなたもあの上着を着て、鼻だけ見えるようにしてベルを鳴らしなさい。言葉は少ないほうがいいですよ」
たまたま何も言う必要はなかった。アイダがベルを押すと扉が開いて、制服姿の侍女が入ってきた。アイダがだるそうに立ち上がると、すぐさま侍女が舞踏会の入場券を差し出して言った。
「お嬢様、お車が下で待っております」
指差して侍女を先導させると、数分後にアイダはもうコベントガーデンへすっ飛ばしていた。くよくよしないし、あるのはとことん見てやれという熱望だけだ。
どうも前に行ったことがあるような気がして、式次第のすべてを知っている。やるべき事を正確に知っており、自分の役割も心得ていた。ひょっとして友人に身元を知られるかもしれないが、それすらちょっとした快感であった。
アイダの予想通り、ごった返していた。数千人以上の招待客が慈善という尊い名前の元に集まり、高貴な男女が中流階級とつきあい、着飾った女性もあちこちにちらほら。実際コベントガーデンの連中はいつもこんな催しに集まる。
アイダが部屋をぶらついても格別注目を引かず、どんな邪魔もない。大いに楽しみ、ちょっとした知り合いにも警戒し、避けるようにした。たぶんそのうち退屈になるだろうけれども一方、華やかな衣装、きらめく照明、楽団の調べ、さんざめく笑い声につられて抗しがたく前に出てしまい、少し不注意もあったのだろう。またこの
アイダがはっとして立ち上がった。数メートル先に見えた男は薄い唇のとがり顔で、グロブナー広場の客間で見た男だ。とがり顔が話し込んでいるもう一人の男は背の低い小者のようで、黒目をきょろきょろ動かし、不機嫌で神経質そうな口元だ。
とがり顔の男があたかもアイダの磁力に引かれたかのように振り向き、意味ありげに微笑んだ。からかっているように手を振ったので、アイダは気持ちが少し落ち込み、独り言。
「予想外だ。注意しなければ。あのとがり顔は今晩バレリイにとって一番危険な男だ」
アイダは席を移動し、見えないところに腰掛けた。直後、とがり顔と話していた小男がやってきて、耳元でこうささやいた。
「お話があります。温室まで来て下さい。グレイのことです」
第六章 ダイヤモンド
アイダが歯で唇をぎゅっと噛み、かろうじて叫び声を押さえた。運良く男に背を向けていたので、真っ青な驚き顔を見られなかった。明らかにこの小男はバレリイ嬢のことを知っており、何か重要なことを言おうとしている。この小男がバレリイ嬢の敵か味方か、替え玉のアイダには分らない。とにかくこの男に替え玉だと悟られてはならない。
アイダがもどかしげに
「どうしましたか。こんな時に心配させて」
「あなたのためにと思いまして。この私アーノットのことを知らないと言わないで下さい」
アイダが警戒した。素早く糸口を捕まえなくては。明らかなのは、この小男が誰であれ、生身のバレリイ嬢に会ってない。
「無視するつもりはありません。どうぞお続けになって」
「あなたのお役に立ってきたのは否定しないでしょうし、こんな会話が危険でないと分っていたら、もっと前に来るべきでした。なんとかハースコートは振り払いました。無駄足を運ばせたので、まだ戻って来ないでしょう」
そうか、ハースコートというのはあのとがり顔、薄い唇の男か。とにかく重要な情報だ。今の無気力態度を保ち、しつこく
「話を進める前に確認しておきますが、ハースコート氏に会話を知られたくなかったのですね。アーノットさん」
アーノットと呼ばれた男が答えた。
「もちろんです。あなたはハースコートを信用していますか」
「全然信用しておりません。むしずが走るくらい嫌いです」
「ええ、口論されたことを知っております。バレリイ嬢、あの男は裏切り者です。英国のために貢献していると公言していますが、常に我が身のためです。奴にとってはすべてが金です。あんな男は見るのも嫌ですが、英国愛国者の振りをして英国陸海軍の秘密を売っています」
「ではあなたが止めればいいでしょう、アーノットさん」
「できる、いやできないです。私は奴の汚れ役なのです。私の名誉を晴らし、世間に再び顔向けが出来る証拠を奴が握っています。本当のところ私はハースコートの雑用係で、奴の言いなりで、雇われスパイになり、外国政府に潜り込み、いつかきっとこの地獄から抜け出す鍵を探っています」
「最悪ですね」
「ヘヘヘ、よくもそんなことをバレリイ嬢が言えますね。バレリイさん、私の前で格好付けても駄目です。私もベルリンに住んでいたのですよ」
アイダが作り笑いした。妙なことが分ってきた。間違いなくバレリイ嬢はスパイ組織の一員だ。バレリイは何らかの陰謀の中心におり、遠くから危険が迫っている。
アーノットが続けた。
「我々は評判ほど悪くないです。もし運命がこれほど厳しくなかったなら、誰もこんなにならなかったでしょう。有り難いお心遣いで、私を励まされようとされた。私の立場に身を置いて下さい。五年前、私は幸せの絶頂でした。意のままに記者舞踏会を開催し、デボン地区一番の美人と婚約を発表しました。この時、有罪判決を受けて、皆の軽蔑する男になり下がりましたが、たった一人我が社の編集長だけは違いました。私は無実です。婚約者は私をまだ待っていると思いますし、事実そうだと知っています。だが無実の証拠を掴むまで婚約者に近寄らないと誓いました。証拠を掴む為に、汚いスパイ組織に入り込んだのです。あなたに告白する理由はあなたの評判をいろいろ聞いたからで、あなたは運命のいたずらでこの嫌な世界へはいられたとか。もし私がハースコートから買ってでも、いや盗んででも証拠書類を手に入れれば、再び清廉潔白な生活に戻れます。ハースコートのような英国紳士が外国勢力と共謀して自国を攻撃するのは良くありません」
この男は本当のことを言っているとアイダがはっきり信じ始め、一瞬も疑わなかった。この男には誠実さがあり、説得力がある。だが気を許し自制心を失ってはならない。心にたたき込むべきは、自分はバレリイ、華麗な国際スパイの成功者、そしてこの横にいる男は同じ穴の
「ええ、私達は二人とも運命の犠牲者です。個人的には疲れましたけど。でも私をここへ連れてきたのはこんな愚痴を言うためじゃないでしょう。誰かのニュースが……」
「グレイのことです。要点に引き戻して下さって感謝します。いま数人を除きグレイの居場所を知っているのは私だけです。奇妙な列車事故のことは聞かれましたか」
「だいたいです。その時ほかに事情がありましたから。詳しく教えて下さい。私も知っておかなくては」
「グレイは重要な公文書を持ってベルリンを発ちました。でもこれはあなたに言う必要もないし、あなたには第一報が行ったはずです。この公文書を手に入れれば数千ポンドの大金がせしめます。ドーバー駅からチャリングクロス駅の間でグレイは消えました。現在、事件は警視庁が担当しています。大衆がこのことを何も知らないのは私の責任じゃありません。私はこの情報を自分の新聞社へ持っていきました。グレイが消えたとき一石二鳥だと直観しましたが、どういう理由か知らないし、どうでもいいことだが、編集長が記事を差し止めました。とにかく警視庁は途方に暮れています。グレイが列車から消えたのは知っています。扉も開いておらす、窓も閉まっていたので、刑事達は筋立てに面食らっています。いいですか、列車から身を投げたあとでは鍵を閉められないし、今はこれが精一杯の情報だと思います。もし良ければ警視庁にもっと情報を与えられるし、たぶん一日か二日したら与えるべきでしょうが、公文書を見つけるまでは与えません」
「じゃあ、まだ見つけていないのですか」
「そう単純じゃありません。公文書はグレイが持っていました。誰にも渡していません。でも奇妙なことに消えました。ここが重要なところです。もし我々が公文書を見つけなければ、ハースコートが手に入れます。だからあなたがグレイに会いに行ってほしいのです」
「グレイに会いに行きます」
「そうしてください、グレイは列車を降りる際に事故に遭っています。事実あからさまに言えば、具合がとても悪く、骨折の症状のようです。何とか医者に見せました。金目当てじゃないから医者に診せたのです。ぜひグレイに会って下さい」
「あすの何時がよろしいですか」
アイダが出来るだけ平静に尋ねた。少しうろたえてまごついてはいたが、次にアーノットが言った驚くべき返事に、もはや心穏やかじゃなかった。
「あすでは遅すぎます。いま行って欲しいのです。こういうことに関してあなたの行動は素早いし、あなたの直観は天才的です。あなたが公文書を発見できなければどんな女性が出来ますか。しかもあなたが今晩ここへおいでになると聞いてすべてを手配しました。会場を出て部下に合図すれば、車が自由に使えます。外套も用意しましたし、この名刺に住所も書いてあります」
一瞬もアイダは
これまでアイダは約束を守ってきた。もし出かけてもバレリイ嬢を裏切ることにはならないだろう。また若い英国外交官が傷ついて囚われの身になっていることを考えると、アイダの母性本能と感性に訴える何かがあった。頭にスカーフを巻いた。
「すぐ行きます。速いほどいいでしょう。最重要事項はグロブナー広場に午前二時十五分までに戻ってくることです。どうぞ先に行って下さい。一緒しない方がいいでしょう」
強い東風がアイダの顔に心地よく感じられるのは東部生まれのせい、次第に道がでこぼこして狭くなり、遂に車が止まったのは川べりのぼろ家の前だった。
*
運転手に待機を命じて、扉をノックすると、長い間を置いて返事があり、人相の悪い老婆が暗闇をのぞきながら、喫煙灯をさえぎる手が黄色い骨皮で、
「おや、べっぴんさんだ、おはいり。珍しいねえ、高貴なお方が、こんなぼろ家へ来るなんて」
「患者の具合はどうですか」
「べっぴんさん、否定はしないよ。悪いよ。いま先生が診てる。医者に話があるんだろう?」
「ちがいます。居間に案内して下さい。医師が退去するまで待ちます」
二階からうめき声が聞こえると、老婆がにやり。目が悪魔のようにぎらり。
「あれが患者だ、ヒッヒッヒッ。うわごとだよ。そのうちおとなしくなる」
第七章 鹿毛の外套
アイダが激しく身震いした。もし衝動的に動けたら、この家から飛び出して、車に飛び乗り、邸宅へ全速で帰り、こんなぞっとすることには関わらないだろう。
結局アイダはバレリイに義理はない。首を突っ込んだのは全くの親切心からであり、たぶんエルシを助けられるからだ。とにかくこんなことに巻き込まれるなんて予想していない。すぐ警察に連絡するのが義務だ。だがそんなことをすればバレリイに不都合だろうし、厳しい事態を招く。もう少し待った方がいい。
辺りを見回すと、部屋は黒ずみ薄汚れ、壁には蜘蛛の巣がかかり、天井は変色し、こんな不快なむっとする環境では息も吸えない。深夜にもかかわらず、地階では子供らが泣きわめき喧嘩している声が聞こえ、二階では病人がうめいている。神経がぴりぴり、次に何が起こるやら。老婆が言った。
「お嬢さん、どうぞ座って。医者はそのうち降りてくる。あんたお金を持ってないかい? あたしゃ金欠でね。それに二階の紳士には金がかかる。どう五ポンド紙幣で?」
「お金は持っておりません。大急ぎで来たものですから」
「ここは危なくないよ、お嬢さん」
「危険はありませんがリスクは常にあります。後でお金は渡します。二階へ行って、お医者様にどれくらいかかるか
どうやら分ったようで、片目が光り、残念そうに首を振ってこう言った。
「どこにもなかったよ、お嬢さん。探しまくったがどこにも見つからん。あの紳士だが、あんた名前を知ってるだろ、あたしの手落ちだとさ。あたしが取ったと信じとる。無学なあたしに何の得があるってんだ。文盲さ。お金をくれれば誰にも喋らないよ。でも書類なんか持っちゃいないね、おあいにくさまだ。警察がしつこかった。サツは何回も来たよ。密輸してないかだと。まったく、何も見つけられやしない。でもサツはここを監視してないから、商売になるような物が手にはいれば、すぐに売り払うさ。あたしの見立じゃ二階の紳士は書類なんて一切持ってやしないよ」
「気の揉む話ですこと。はっきりさせましょう。まずグレイ氏はなぜここへ来たのですか。誰が運んできたのですか」
老婆が狡猾に首をかしげ、独眼をウィンクした。悪魔の
「知らないねえ、お嬢さん。何も知らねえよ。あたしのような貧乏やもめに訊いたって。でも少しは聞いたよ。あの紳士は事故に遭って、列車から落ちたとか何とか。たぶん友達に知られたくないんだ、英国にいることや事故ったことを。とにかく線路わきで見つけて、ここへ連れてきた。あたしゃおもり役だよ」
アイダは嫌になって腰が引けた。この老婆の話しぶりにはむかつく。ランプが黒煙を吐き始め、油面が下がり、部屋中が油臭くなった。アイダは抗しがたい衝動に駆られ、いまにも逃げ出したかったが、二階の病人を助けたい母性本能と興味とで思い留まった。退去できなくなった。
おそらく二階の患者は紳士であり、悪党一味の手に落ちて、悪党連中に
アイダは医者に会うまで留まろうと決めた。医者から情報を聞けるとは思っていないし、どんなまともな開業医がこんな所へ往診するか。
数分後に医者が降りてきた。アイダをじっと見て驚き、ぼろ帽子を取った。アイダが言った。
「少しお話をしたいので、おばあさん、お医者さまと二人だけにしてもらえませんか」
老婆が汚れた階段を上がっていなくなると、アイダが藪医者にきっと向き直った。予想通りだ。
くたびれた衣服の折り目と縫い目のはしはしに、この医者の困窮ぶりが見て取れ、くぼんだあごには数日間剃っていないひげがごわごわだ。両目がどんより赤く、太い手が絶えず震えていることから想像がつこう。あとは上品さを欠いておらず、あきらかにかつては上流社会と関わっている。事実、アイダは世間をそれほど知らないが、この医者の人生は説明しなくても分る。
「ここの患者さんに興味があります。詳しく言えませんが、その患者に会いに来ました。ところで、あのおばあさんはあなたのお名前を言いませんでしたが」
「トラスコット医師、マ、マシュー・トラスコットと申します」
「正式な医師免許がおありなのでしょうね」
アイダが痛いところを突くと、血色の悪い顔が怒りで紅潮した。
「ロンドン大学の医学博士だ。これは事実だ。こんなところで何をしているかと思ったのだろう?」
「当然でしょう、トラスコット先生」
トラスコット医師が一瞬言い淀んだ。
「率直に言う。長いこと淑女と話す有り難い機会がなかったものだから、話しかけられたとき、いらぬ詮索したことを許してくれ。妙な場所でロンドン大学医学博士が患者を往診するものだが、同様に妙な場所で、あなたのような上流社会の淑女に会うとは。あなたが率直に話してくれれば、私もそうする。淑女の名前など
「ふふふ、お心遣いに感謝します。要するに私の関心は患者です。数時間前までは全く関心はなかったのですが、時間がありませんのでそこには触れません。珍しくありませんか、グレイ氏のような紳士がこんな貧民窟に隠れているなんて。とても具合が悪いそうで、友人の所へ運んだ方がいいのでは。そう思いませんか」
「それほどでも。医者は妙な場面に出くわすもので、しばらくすれば慣れるものだ。私はここで開業しているからグレイ氏の往診に呼ばれた。あなたがおっしゃるまで名前すら知らなかった。聞いた話では事故があって、患者の友人に連絡できない訳があるとか。一日に二回往診し、往診毎に前金でギニー金貨を一枚もらっている。私も妻子を養っていかねばならないし、家族の食い物に困る始末だ。数年前、西部で開業していたときは……」
トラスコット先生が急に詰まって、小声にかき消えた。アイダが先生の肩に片手を置いて優しく言った。
「お気の毒に。詮索しすぎてごめんなさい」
「私の事例は決して珍しくない。昔は稼ぎまくった。働きまくって、成功するまで休みも取らなかった。そのとき酒におぼれるのを怖れて薬に頼った。最初は少量で効いたがあとはずぶずぶ。身の上話でうんざりさせる気はない。私は落ちぶれ破産者になった。最近やっとやめられたのは体が壊れる寸前だったから。だんだん良くなっておる。泥沼から這い上がり始め、たぶん間に合う……。何でこんな話をしなきゃならん。たぶんあなたが優しくて同情的だし、元来の上流階級と話が出来たせいだろう。患者に対するあなたの見解には同意する。この事件には不審なところが多いが私は無力だし、せめてレディが救助に来てくれただけでも嬉しい。これで気持ちが大いに楽になった」
「患者は重症なのですか」
「そうとも言えるし、そうとも言えない。頭蓋骨に少しひびが入っており、脳に影響している。意識が半分混濁するときがあるが、頻繁じゃない。数日経てばグレイ氏を運び出せるだろう。この家の人々なら何も危害を加えない。患者はあの状態にありながら家人達を怖れており、疑っている。一方、私に対しては全く警戒していない。一回か、二回正気に戻ったとき、私に投げかけた質問で、何か気にしていることが分った。明らかに何か重要なものを紛失している。あんな脳状態の患者のうわごとはまともに取り合わないのだが、あの患者はいつも同じ事を言っている。うわごとはいつも
「よく分りました。グレイ氏との面会に何か支障がありますか」
「何もない。上がってもいいでしょう。階段上の最初の扉だ。ばあさんに話しておく、邪魔しないように。たぶん収穫がある」
「それではすぐに参ります」
第八章 お宝
がたついた階段をアイダが駆け上がった。目の前の扉が少し開いており、中で黄色い電灯が明るく光っている。部屋に押し入ると、床置きランプが見え、緑色の傘をかぶせてある。
著しく場違いに感じたのは、豪華とは言えないまでも部屋が快適にしつらえてあることだ。床には厚い絨毯が敷かれ、壁には趣味のいい版画がいくつか掛かり、最新式暖炉には火が赤々と燃えている。ベッドは真鍮製、シーツは清潔で真っ白、洗い立てのよう。
仰向けに患者が横たわり、天井を見ている。両目は開けているが、とろんとして明らかに何も見えていない。時々何かつぶやいており、不明瞭なのでアイダには意味が分らない。同情と母性本能で胸が詰まり、ベッドに近づき、細くて冷たい手を、患者の熱い額に当てた。
「かわいそうに」
一瞬患者の目に意識が戻り、視線を向けて、つぶやいた。
「アイダ、
ほんの一瞬だったが、その後また目をつぶる有様は睡眠をむさぼるかのよう。アイダはベッドに突っ伏して、両手で顔を覆った。くらくらめまいがした。だってグレイは古い知り合い、いやたぶんそれ以上だったからだ。
失態だ、名前の類似性を見落とすなんて。古い友人の名前はグレイ・フレイザーだったが、この危ない劇場型冒険者のグレイだとは連想しなかった。
いま
ピクニックでボート遊びに興じ、月明かりの桟橋、最高の夜、星の瞬く下でグレイがキスをした。なんとアイダもキスを返した。グレイの言うことに、自由になったら迎えに来るからその間、二人だけの甘い秘密にしよう。
その時の話では、グレイは外交関係の仕事に就いており、今は貧乏だが野望があり、上司に信頼されており、やがて家庭を持てる地位に就き、妻にするまでたぶん待たせるという。
また金持ちの風変わりな叔母さんがいて、いつか遺産が転がり込むとか。果たしてその日が来て、叔母の財産を手にして、フレイザーの名字を捨て、単純にグレイにしたのか。
たとえそうであれ、ここにいる男はアイダが心を許し、長いこと待ち望み、絶対の信頼を置く男だった。じっとしていたら、ずっと淡い空想だったろうが、二人の間に約束も署名もなかったので、はたしてグレイがアイダの元へ帰り、一緒に計画した理想の家に迎えたかどうか。
その時が来たかもしれない、今までのつらい期間でますますその気になった。遂に見つけた愛する男は、瀕死状態で危険にさらされている。それを思えば気が滅入る。
どうやってここから運び出すか、全くの一人で、しかも文無しの身で。バレリイ嬢に助けは求められない、というのも何となくグレイの事故に何か絡んでいるからだ。でも前途はいい。確かに見えざる力が土壇場で働き、きっとこの不思議な力が助けてくれる。
ふさぎ込んで嘆き悲しむ時じゃない。決然と過去を断ち切り、将来を見据えねば。何かしなければ、すぐに。
再びグレイの額に手を置くと、冷たい感触で、またしても目を開けた。
「しっ、私が分りますか。アイダです。神に使わされ、助けに参りました」
「アイダ、アイダ。どこかで聞いたなあ、フォークストン……ある晩……そうだ、そうだ。帰ってきたのか、アイダ。頭が回ればなあ。でも上着がない。自分で隠したんだ」
「私が探しましょうか」
「やってくれ。見つけても僕は何も出来ない。きみが慎重に隠してくれ、僕が最善策を考えつくまで。上着に何を入れたか思い出せないが、重要なものだし、きみが保管してくれれば安心だ」
「ここにいては危険です、グレイ」
「安全だ、と思う。ともかくだが。ああ、またぼんやりして気が遠くなっていく。上着を見つけろ、見つけてくれ。僕は動けない。体が痛いんだ。何でいつもそんなに引っ張り回す」
またぶつぶつ言うのをアイダがはっきり聞いた。紛失上着に何か入っているのか、単なるうわごとなのか。手がかりを求めて頭を絞れば、ぱっと霊感が湧いた。なぜグレイは動きたくないのか。
痛みは仮病じゃないか。
手足は引きつっていないし、ため息やうめき声や切迫呼吸に身体の苦痛は伴なわない。もしかして自分の体をベッドに貼り付けて、マットレスの間に上着を隠していないか。おそらく意識は半分あるのだろう。
アイダが力まかせに、上のマットレスを持ち上げると、その下から長い外套が現れた。
ぞくぞくしながら、戦利品を床に広げた。大発見だ。たぶんポケットに貴重な文書、国際的に重要な究極の書類がある。もどかしくポケットに手を突っ込んだ。探しまくったが、紙くずすらなく無駄骨だった。
上着をベッドの上に置いて、存分に甘言を弄して、グレイの意識を取り戻そうとした。しばらくして意識が戻り、上着を差し出して、グレイに検分させた。
「それだ、なんてきみは賢いんだ」
「でもポケットは空っぽでした」
「問題ない。今は説明できない、もうろうとしているから。でも安心だ、きみが保管している限り。僕はじきに良くなるからその時説明する。絶対離すなよ、何があっても、上着を手放すな。なぜ注意しろかは分らないが……」
グレイが目を閉じたので、アイダが覆い被さったが、ついに幼な子のように爆睡した。また揺り起こすのは残酷だし、痛んだ脳を休める必要がある。グレイはすっかり心の重荷を下ろし、眠りをむさぼれば元気になる。
アイダがグレイの額を唇でそっと触れ、きびすを返し部屋を出た。グレイは今に良くなるだろうし、悪化しないだろうし、すぐに元気になって動けるようになるだろう。
嬉しかったのは医者と知り合いになり、信用を勝ち得たことだ。階下の悪魔みたいな老婆からトラスコット先生の住所を聞き出せるだろう。
アイダが踊り場に立ち止まった。というのも一階で口喧嘩が聞こえ、甲高い老婆の声がしたからだ。老婆が興奮している。
「なんとでも言え。この家にはあたしと子供らしかいない。餓鬼共はまだ寝ていない、畜生め。医者は帰った。レディが一人来たけどどうなったか知らん。あんたらが家中探し回っても見つからなきゃ、ここにないね。ダイヤだって、実際はガラス玉だ。餓鬼のおもちゃに最適だ」
「この老いぼれ。言ってることが分ってるのか。さあ、エイビス、一晩中ここにいて家捜ししてやる」
アイダが手すりによろめいた。
誰に言う必要もないが、一階の話し手は父。エイビスも一緒だ。暗褐色の肌色、脂ぎった謎の男、アイダを不当に欲しがり、妻にしようとしている男だ。エイビスがいるだけで恐ろしくなり、むかむかして気が遠くなりそうだ。
二人の男が二階へ上がって来て、グレイの部屋に入ってくるので、アイダは急いで窓のカーテンの後ろに身を隠した。カーテンの後ろは小部屋になっており、そこから一階の中庭が見渡せ、更に下の地階も見えて、四人の子供が遊んでいる。
あのばあさんが言った子供だろうが、不安な気持ちはともかく、当然疑わざるを得ないのは、どんな家の子供が夜中に遊びを許されるものか。
少し安心したのは階段が見つかり、この小部屋から下へ通じているのが分ったからだ。立ち直ったのは、自分の勇気と、この階段を信じて、危機から脱出しようと決めた時だ。
既に二人の男が部屋に来て、低い声で話す内容はアイダには分りかねたが、グレイという名前が数回聞こえ、王女という言葉にも触れたが、さっぱり訳が分らない。そればかりか、男どもは一体何が欲しいのか。あちこち探して動き回り、ののしり声が二、三回聞こえた。その後しばらく静かだった。
でもアイダは手がかりを掴むまで動くつもりはなく、何か重要なことが聞けないか待った。何気なく明かりのついた地下を覗くと、何かぴかっと光るものがあり、それで子供達が遊んでいるじゃないか。
第九章 監視
アイダがコベントガーデンへ着くほぼ同時刻、グラスゴウ部長のタクシーが有名な貸衣装屋の前に止まると、そこは舞踏会場と目と鼻の先だった。
グラスゴウは急いでいても表に出さず、店に入ると、計画を進めるかどうか決めかめている風だ。店員が進み出て用件を
「隣の舞踏会へ行こうと思うのだが、遅いから簡単な衣装でいい、教会の高僧とかそんなものだ。いや、待て、それには変装する必要がある。顔中
店員が一瞬考えて、提案した。
「テムズ川の水先案内人はどうでございましょうか。あご髭と口髭、船員服でどうでしょうか、ダブル外套で簡単に隠せます。お客様は上着を着て、長いあごひげを切るだけでございます」
「すばらしい。大至急それでやってくれ。遅く戻って来ても、衣装替えしてくれるか」
衣装替えはそれほど難しくないだろうと思った理由は、グラスゴウが上得意だったからだ。実際、貸衣装屋で変装する方がずっと簡単で、自分でやって自室を取り散らかすよりましだ。
この格好なら招待客は自分をお人好しの風変わりな人物、仮装服愛好家と見なすだろう。満足げにうなずいたのは姿見に映った巧みな変装を見たときだ。
数分後にはもう踊り手達に混じって、不測事態に備えて、目を光らせていた。複数の人物を探し、すぐに全員を見つけ出した。
やがてにんまりしたのは、豪華な刺繍を付けた素敵な黒いドレスを召したご婦人を見つけたときだった。もちろん知らないことだが、バレリイ嬢と思った人物は、実際はアイダ。
今までの所、グラスゴウは事態の進展に満足だ。やがて軍服姿の客のそばに行き、さりげなく話かけた。だが話しぶりでたちまちばれてしまった。
「グラスゴウ部長じゃございませんか、見事な変装で……」
「ちょっとした変装だろ。エバラード君も元気そうだな。ウォルターズ等もここへ来ているか。了解。いや、今晩特に仕事はない。向こうにレディがいるだろ、刺繍入り黒ドレスの」
「バレリイ嬢でございますか」
「エバラード君、知りすぎだ。忠告しとく、この業界で知りすぎは禁物だぞ。向こうへ行って部員に私の指示を伝えろ。黒服のレディが会場を退去したら私にすぐ知らせろとな。同じことを手配の二人組の男にも適用しろ。やつら監視下にある限り、悪事は出来まい。写真を送ったのは確実にここへ来るからだ。わざわざ変装はしてこないだろう。変装する理由がないからだ」
「二人組はもう来ております。会場には部員が六名おりますから、とんずらさせません。ほかに指示はありませんか」
「ある。スコット氏を見つけてくれ。どこにいるか教えてくれ、すぐにだ」
一、二分後、スコット外務次官に声をかけたのが例の船乗り、少し話がしたいとか。二人は食堂へ行ってテーブルに腰掛けた。グラスゴウの正体を見破って、外務次官が言った。
「グラスゴウ部長、うまい変装ですな。どこにでも出没しますな。何かニュースは?」
「グレイのことですか。いいえありません。極めて不可解な謎に当たったものです。まあ、私の見立てはあります。でも有名国際スパイの手に落ちたとは思いません。まだ調べておりませんが、公文書はまだ使われていません。つまり、ちっとも驚きませんよ、公文書がまだ紛失中でも」
「グラスゴウ部長、ある意味では全く公文書じゃないですな。小説だけの話ですな、帝国の運命を握る秘宝が色仕掛けスパイに盗まれるというのは。だって帝国の運命はメモ用紙などにびくともしません。グレイに預けた書類は純粋に国内的なものです。回想する必要もないが、王族も一般人と同じように口げんかをするし、欧州の王族は全員近縁ですから、時々えげつない口論をします。ゆゆしい事態を避け、丸く収めるために必要なことは、直ちにベルリンからロンドンへ親書を送る必要があったのですな。そんな文書を不謹慎な輩が手に入れたら遅かれ速かれ、おおやけになりますな。新聞社が英国にも米国にもあるし、特に米国系ならそんな文書に二万ポンドの二倍でも支払いかねません。グレイが運んでいたものはいずれ誰かが見つけて、大騒ぎになりますな。そう思いませんか」
「ハハハ、全然。それどころか、次官のお話を承って嬉しいです。お話から確信したのは、運命神のご機嫌が一番悪い時、グレイが犠牲になったことですね。さて、次官は次官のやり方、私は私のやり方がありますし、我々は賢い故、お互い手の内を見せません。でも私の予想では当該文書は人目にさらされないでしょう。さらにグレイを捕らえた連中には見つけられないでしょうし、存在すら知らないと思いますよ。三、四日前、私に知らされた暗号電文では、グレイが貴重品を持ってベルリンを発ったので監視を付けるはずでした。私が暗号電文で手配して、ベルリンに三名の部下を派遣し、英国到着までグレイを監視する計画でした。いいですか、ベルリンに三名の部下ですよ。一人の部下はコーヒーに毒を盛られ、二人目の男はタクシーで駅に行く途中事故に遭い、三人目の男は邪魔が入って列車に乗り遅れ、グレイはいずれにしろドーバー駅まで護衛なしでした。大失敗と認めざるを得ません。でもいいですか、たまたま名前と写真で私はスパイ一味と公文書強盗犯を知っており、連中が事故を仕組んだのです。これもたまたま知ったのですが、おそらく連中の中でもやり手がベルリンに行き、グレイが出発するとき、つまり同じ列車に乗ったのだと思います。この連中はでかい山じゃないと手を出しません。実際、連中は公文書なんか軽蔑するし、国債とか国際情報とかが本命であり、それを株式市場に利用します。もし何か通常以外の事態、たとえばトルコに新事態が生じ、これを連中が知ったら、次官もお分りでしょう、連中は莫大な利益を得られます。大規模列車強盗を一、二件やったことも知っています。連中を見たいですか」
「まさか、ここにいるとでも?」
「確実にここに、普通の英国紳士の服装で居ますよ。生まれも育ちもいい連中で、うちの一人はよくご存じです。おっと、大間違いしない限り、連中が来ましたよ」
グラスゴウの言うとおり、目立つ格好の男が二人、ぶらりと食堂に入ってきて、隣のテーブルに座った。コーヒーとリキュール酒と煙草を注文し、うんざりした様子だ。何ら怪しいところはなく、普通の上流階級の男達が普通に一、二時間、時間をつぶす何物でもない。まごうことなく、グラスゴウの言う階級の男達だ。グラスゴウが連中に背を向けたまま、次官に言った。
「ご自分で確認して下さい。私はもう顔を確認済みです。金髪口ひげで、垢抜けた感じの背の高い男がバンストンです。通常の住所は田舎の世襲の領地です。遺産のほとんどを賭け事で無くし、もしエイビスという男と交際しなかったら、そんなことにはならなかったでしょう。エイビスは米国人で、元は大学教授でした。エイビスほど犯罪や犯罪方法に詳しい男はいません。大学に勤めている頃は警察に協力して犯罪を大いに防ぎました。具体的には忘れましたが、何らかの醜聞を起こし、エイビスは姿を消しました。それ以降、犯罪と陰謀に手を染めたのです。以前は犯罪抑止に使っていたのに。今あの二人の所に行って、お仕事は何ですかとあからさまに
「じゃあ、書類を持っているかな?」
グラスゴウが、力んで言った。
「いいえ、持っていません、ひどく見つけたがっていますが」
第十章 にせダイヤ
スコット次官が笑った。
「グラスゴウ部長は実に不思議な
「次官、仕事柄そうなりますよ。今まで確実に事件を解決してきましたが、余り訊かないで下さい。逆にですね、次官を引き留めたのは次官に尋ねる為です。私一人でも真相解明するつもりです。一番怖れたのはグレイの失踪が公表されることでした。一人の有能な記者がかぎつけて、もし私が日刊センティナル新聞の編集長と親しくなかったら、とっくに英国中に広がっています。私はグレイが死んだと思っていません。グレイはさらわれて、隠れ家に留置されていると
次官がびっくりして片眼鏡を落とした。
「これはこれは。グラスゴウ部長はすごいお方ですな。そんなに知っているとは」
「次官、だから我々がここにいるのです。自慢じゃありませんが、我々の仕事はあなた方よりも役に立ちます。でも強調したいのは内密情報を戴かないと何も出来ません。言っても構いませんが、ゼナ王女の件は当てずっぽです。いいですか、事実上我が諜報部にすべて集まります。仕事柄、厨房の醜聞も、特に王室からであればもちろん注目するし、実際は敵対関係ではありませんが、外事情報部の部員や資料からも情報を取ります。ところでゼナ王女は過去しばらく幸せからほど遠いですね。恋愛の噂があり、相手はさる伯爵で階級が遙かに低いとか。ゼナ王女は美人で非常に頑固で、日頃おっしゃるに女性は宇宙の中心だとか。少しの疑いもないのは、ゼナ王女がこの伯爵と結婚を決意され、兄である国王が反対したことです。しばらく王女は事実上軟禁されましたが、やがて英国へ脱出しました。各紙は脱出と書かなかったがそういうことです。どうですか、厄介なことになっていませんか」
スコット次官が悲しげに言った。
「今そうなっておるな。国王がどんな人か、知っているかな、欧州一の専制君主だ。ゼナ王女を強制送還しろといっておる。それは出来ないけれど、英国もまずいし、バルカン半島も混乱する。さて、もうざっくばらんに話そう。その国王が掴んだのがゼナ王女と伯爵の手紙だ。ゼナ王女も争いに負けるわけにいかず、国王の金庫をなんとか開けて、兄の古傷、色事証拠を探り出した。何も恥じることではないが、兄を笑いものにするには充分で、国王は世間で軽蔑されることを一番怖れておられる。今日まで国王、王女ともに尊敬されてきた。ところで、なぜ知りたいのかな」
「グレイの失踪に関係しているからです。ゼナ王女に関係なければ、グレイは連れ去られなかったと思います。ここが重要なところです。王女に会わせて戴けませんか」
スコット次官が困ってため息をついた。グラスゴウ部長は裏事情に通じており、楽しんでいる風だ。
「ゆっくりでいいですよ。どうか、かたくなになりませんように。それに次官のお話もまだ終わっていませんし」
「君はまさに悪魔だな。でも君だけが協力者だ。きっと全部しっとるだろ。ゼナ王女と会見できない単純なわけは我々の友人グレイ同様に、王女が跡形もなく消えたからだよ」
「本当ですか。非常に複雑になりましたね。同じ一味に神隠しされたのですか。同じ
「グラスゴウ部長、私も説明に困っておる。言えることは王女が消えて跡形もないということだ。英国に同行したのはメイドと老侍女の二人、リマーズホテルに偽名で密かに泊まっていた。昨日の何時か、王女は買い物に外出された。一人で出かけて、夕食前に帰れそうにないと言い残された。夜十時まだ帰宅されず、十一時直前に電話があり、数日留守にするから、心配するな、なにより警察には連絡するなとのこと。老侍女が今朝外務省に来て私と面会した。君も分るだろうが、大衆には絶対隠さなければならないし、とても心配で不安なことは君も想像できよう」
「私なら心配しませんよ。信じられないでしょうが、あり得ることです。情報を色々ありがとうございました。失礼します」
その時、軍服姿の男が食堂に入ってきて、グラスゴウに素早く、そっと合図した。グラスゴウが立ち上がり、舞踏会場へ歩いて行くと、忠実な部下が後を追った。
グラスゴウ部長が詰問した。
「何か起こったのか」
「はい、そう思います。黒ドレスのレディが内緒話をして、その相手はみすぼらしい服装の、見慣れない男でした。レディは退去するようで、その男が外へ出てタクシーを拾いました。重大事項が起こらない限り、レディは退去しません。私が後をつけてよろしいですか」
「いや、私が行く。これが番号札で、服の預け場所へ行って私の上着を取ってきてくれ。それからタクシーを呼んで正面玄関に回せ。ぐずぐずするな。早く呼べば助かる。私が戻るまでここで待て」
一分後にグラスゴウの乗ったタクシーは東方向へ走り、先行車を慎重に視界に収めた。グラスゴウは自分の仮装に感謝したい気分だ。この仮装服は現場に合うばかりでなく人目を引かないし、分厚い上着のボタンを掛け、襟を立てればいい。東部へ冒険に出かけるなら、そうなると確信していたけれども、この外套があればいささかの興味も引かず、通れるだろう。
にやりと外を見れば、だんだん道が狭くなっていく。表情がこわばり、前の車が止まった時、慎重にメモしたのは黒服の女が入っていった家の番地だ。自分のタクシーは止めず、やがて二百メートルほど前進させてから飛び降りて、運転手に半ソブリン金貨を渡し、こう言った。
「ここで待っていてくれ。一時間だ。一時間で戻ったら更に半ソブリン金貨をやる。一時間以内に戻らなかったらそれ以上待つ必要は無い」
黒服の女が入った家に戻ってみれば、道路は無人。明かりはほとんど無く、飛び飛びあるだけで、倉庫への通路隅に簡単に身を潜め、誰にも見られず家を監視できる。
じっと待っていたが、問題の家からは何の兆候もなく、ただみすぼらしい格好の人影が、すたすた通り過ぎただけだった。それが暗闇に消えると、別な人影が路上を横切り、グラスゴウがほくそ笑んで、独り言。
「誰だか分るぞ。面白くなってきた。奴らが来た」
二人組が道路の真ん中を歩いてくる。長い外套で首まで覆い、帽子を目深にかぶっているが、グラスゴウは一目でエナメル靴と黒ズボンを、夜会服用と見抜いた。自分の数メートル先で二人組が止まったので、会話が筒抜けだ。
エイビスがこう言っている。
「ここです。この時間は老婆一人だから、話が出来ます。まさか来ると思っていないでしょう」
バンストンが心配げに訊いた。
「銃を持っているか。俺は大嫌いだが」
エイビスが鼻白んだ。
「拳銃なんて。そんなものは持ったこともありません。拳銃を持つようでは犯罪者の誉れに値しません。殺人道具であり、流血など達人のすることではありません。さあ、行きましょう」
二人組がやがて家の中に消えると、グラスゴウが隠れ場から現れた。現場の配置を一瞬で判断し、家の裏側へ回り込んだ。正面より裏側が明るいことを見抜いたばかりか、地階の微光も見逃さなかった。大体の計画はあったが、進展を待った。
五分、一〇分、一五分過ぎても家から何の兆候もなかったが、突然くぐもった叫び声が一、二回聞こえ、つんざくような女の金切り声が上がった。
本能的にグラスゴウが裏扉に突進し、立ちすくんで警戒して震える様子は、さながら猟犬が獲物に襲いかかるが如し。
第十一章 金づる
バレリイ嬢の住むグロブナー広場の向かいに一軒の家があり、壁が白く塗られ、花々が咲き誇り、いつも通行人の注目を引いた。ここがルペラ男爵の邸宅であり、ここで限定夕食会が開催され、友人や知人の羨望の的であった。
男爵はフランス人シェフを雇い、このお抱えシェフの年俸は少なくとも千ポンドだとか。そうだろうというのも、男爵は有名な金融業者であり、ほかの外国人資本家と違い、爵位は世襲の本物であった。
歴史を学んだものなら皆知っているが、欧州勢力図にルペラ家の役割は小さくない。この百年ないし二百年、ルペラ家はどの反乱や暴動にも大活躍し、たいてい同家の利益にならず、その理由はルペラ家がいつも敗北側であったからだが、長い目で見れば敗北側もたまには潤う。
現在の爵位保持者は十年前まで母国の政界で派手に活躍していた。実際絶頂期には東欧最強の首相同然と見られていた。だが誰も、いや英国外務省さえルペラ男爵が没落した内幕を知らない。ルペラ男爵は名誉と財産を奪われ、英国へ来たときは片言英語と、所持金一〇ポンドと、不屈の勇気だけだった。
もし男爵があの程度で戦争を止めなかったら、少なくとも世界経済は破壊し尽くされ、実際そうなっていただろう。英国でのルペラ男爵はシティの事務員から出発し、十年経つと十件の国際融資を募集するまでになった。四十五歳の時、経済界の実力者にのし上がった。実際、上流階級側として、妻と共にメダルの表側に数えられた。
あとは黒髪、やせ形の小男で、精力的に物事を的確に素早く理解する能力があり、仕事を苦役というより楽しんでいる。そのため劇場とかライチョウ狩場にも時間を
一緒に英国に連れてきた妻は上品、妖精似、小柄な金髪で、無邪気さを知性で覆い、小魚のようにすばしこくて目先が利いた。おしどり夫婦で、お互いに助け合い、人気があるのも当然だ。
ルペラ男爵がシティから昼食に帰宅するのはいつもの習慣。大型車を走らせ一時間ばかり在宅し、気分を変えることが最高の強制剤だといつも言っていた。
どうやら今回は昼食に客がおらず、夫婦水入らずのようだ。軽い昼食が恒例で、温室栽培の桃を二個食べ終わり、テーブルでのんびり煙草をふかし、小さなカップでブラックコーヒーを飲んでいた。
「あなた、悩んでいますね。良いことではありません。憂鬱になってはいけません。ここシティでは美しいランや桃は育ちません。ぜんぶ私が取り寄せたものです。もしかして私に隠し事をしていませんか」
「おまえにいままで無断で何かしたことがあるかい? 隠す必要があるかい?」
男爵夫人が叱るようにかぶりを振った。
「いいえ、一度も。あなた、お話する機会をありがとう。私をだませないですね。ここ何か月も憂鬱そうでした、お仕事に悩んで家庭を暗くしてはいけません。一〇分間も一言もおっしゃらないもの」
男爵が新しい煙草を自分で取って言った。
「今日は客がいなくて幸いだ。おまえに言いたいことがあるからだ。このところ株が思わしくないんだ。知っての通り、私は大胆な投機家で、何年も思いのままだった。いや、破産はしてないし、させない。おまえにダイヤや車や邸宅を買っては友人をもてなしてきた。でも、私は負けないよ。まるで誰かが私の心を読んでいるかのよう、あたかも忠実な召使を買収しているかのようだ。だがそうじゃない。私が見向きもしなかった株が高騰し、私がぶち込んだ株が暴落だ。私の判断ミスで誰が儲けているか自問した。いい気持ちはしないよ。いつもミスしていたのだから。欧州で人気の株を三、四銘柄売った所、妙な筋から売り浴びされた。株価が下がり、弱含みになったので金をつぎ込み、支えるしかなかった。誰にも私の名声をあざ笑わせない。またしてもぼろ株と思っていたものが大化けしたが、実は私に勧められた銘柄で、私が拒絶した株だった」
「じゃあ、あなた、敵対
「いや、逆張りしているとは言えない。どっちかといえば陰で笑っている。誰が市場で私の持ち株を馬鹿にしているか調べねばならないし、
「あなた、怖くないですか」
「私は誰も恐れない。誰にも邪魔させないし、惑わされない。でも奴らが邪魔している。誰だかわかれば交渉できる。だが前に言ったとおり作業が膨大だ。でも謎を解いたので、気分が楽になった。最近の組み合わせ、すべてに二人の男が突出していた。解決に多くの手法を適用した。大数学者にまでも協力を求めた。いいかい、株主の名前でなく数値を渡してみたところ、結論は私と同じだった。そうだよ、ついに名前を突き止めた。全部で三人だった」
「あなた、私の知っている人ですか」
「一人は知人だが残りの二人は全く知らない。知人は後回しにしよう。後の二人はシティの株式仲買人で、名前はエイビスとバンストンだ」
「えっ、あの有名な会社じゃない?」
「いや、全然ちがう。どうやら小さな会社が大きな評価をされ、合法商売をして、利益を少し上げているようだ。おそらく損益計算書を見れば、年間利益は二、三千ポンドだろう。大きく賭けてうまくやっている。独自情報なしでは大損しているだろう。時々連中は内閣の秘密を知っている。欧州で問題が発生するとそれを知っている。もし政治的な古傷に手術が必要となれば外科医、つまり外交官の名前を知っている。だから、ちっとも不思議じゃないよ、この平凡な株式仲買人はおそらく郊外で楽しく暮らしているのだろうが、連中が鉱山情報を思いのままにしていている件だ。例えば最近の事件を考えてみなさい。ある秘密筋から私の耳に届いたのだが、ボーン国のゼナ王女が広大な領地を有しており、原油埋蔵が分った。私はすかさず投資した。
「まあ、あなた、大変。私が王女に会って……」
「王女に心配させてはいけない。少なくともまだだ。さあ連中はどうやってこの優良物件を見つけ出したのか。私は欧州政治に長く携わってきたが、連中に比べたらまるで子供だよ。連中の手口がわかればなあ、手掛かりはここへ来るもう一人の男……」
「あなた、面白くなってきましたね」
「これ以上きみを不安にさせない。もう一人の男というのはここへ来るハースコートだ。エイビスとバンストンとグルになって、連中の上前をはねている。おっと反論する所じゃない。私の数式は正確だから間違い無い」
「信じられないわ。ハースコート氏はいつも嘆いていらしたのよ、事業では常にドジして惨めだって。芸術肌の人だから絵画や磁器などの美術品を売買して生計を立てています。運のいいことに芸術品を見る目があります。しかもゼナ王女の知り合いです。同氏の妹さんが親友じゃなかったですか。ゼナ王女がそう言われたもの。いま王女を探していないですか。だから、あなたは間違っていますよ」
男爵がかぶりをきっぱり振って言った。
「間違ってない。確認するが、ハースコートはゼナ王女の居場所を知らないだろう?」
「ええ知りません。きっと情報が欲しいでしょうね」
「全くその通りだ。これこそ英国人の言う仕返しをする場面だよ。ゼナ王女に忠誠を尽くす人は他にもいる。そういえばきみも同窓生じゃないか。もしゼナ王女に会いたければいつでも……」
「あなた、ぜひ会いたいわ」
「じゃあ今晩就寝前にでも。いいかい、良くお聞き――」
第十二章 特別観劇室
ルペラ男爵夫人が言ったのはハースコートの表向きの生計が合法の芸術品売買であるということ。同氏は貴族生まれだが、貧しさを自慢するぐらいだから何も出来ず、せいぜい出来ることは小商いぐらいで、たとえあるにしてもほとんど儲けがなかった。
だが、町に高額な部屋を借りて、身なりも良くて、一流の人々とつきあっている。独身であり、射撃がうまく、踊りも上手だからどこでも歓迎され、特に田舎の邸宅や、町の会員制夕食会ならなおさらだ。
朝食は別として、夕食費用は滅多に払わないから懐を痛めないが、家賃やタクシー代、鉄道運賃、衣服や煙草などは自腹を切らざるを得ず、現金が必要な場合もしばしばある。
不正な金儲けの裏道も知り尽くしている。長年、外交官勤務をして、ある規律違反がなければ順風満帆だったかもしれないが、結局解雇されてしまった。
同氏は有力な身内がいるハースコート一族だったので、その筋がなければ起訴とはいわないまでも、大醜聞になっていたかもしれない。職務秘密を売買したり
英国へ帰国したとき三カ国語を操り、うさん臭い知識が豊富だったので、経済界でのし上がった。もっと早くから手を染めて、職業にしていたら今頃親分だろう。そういうことで、感謝すべきは鑑定眼、古代や現代の美術品に目が利き、生活の糧になった。
最近知人が気づいたのは同氏の懐具合が良くなり、もう悪い噂が聞こえず、カードの未払いがあるとか、当座預金が底をついたとか、競馬場で聞かなくなった。去年は狩猟を楽しみ、モンテカルロも満喫した。
コベントガーデンの舞踏会では自室で朝食を悠々と食べ、煙草をくゆらす姿が世界屈指の関係者かと思えるほど。やがて従僕がやってきて、エイビス氏が下でお待ちですと告げた。
ハースコートがぶっきらぼうに言った。
「上げろ」
エイビスが入室し、そっと扉を閉めた。こそこそする態度は疑い深く、誰からも信用されない
ハースコートが軽蔑笑いした。
「ヘヘヘ、怖がらんでいい。誰も聞いちゃいない。よくもめちゃめちゃにしてくれたなあ。俺がずいぶん苦労して情報を掴んだのに、お前はグレイをウナギのようにするりと逃がした。一体全体、お前の部下は何やってんだ」
「本当にグレイが指から逃げますか。石は見つかりませんが。失礼、わたし何を言ってるのか。もちろん書類の事です。例の手紙のことですよ」
一瞬、冷酷、無表情のエイビスがちょっと狼狽した。
ハースコートが目を細め、額にしわを寄せて詰問した。
「お前は今までどんな汚い不正をやってきた? 石って何のことだ? 石とは恐れ入ったな。石と書類は全く別物だ。お前とバンストンの一番悪いところはな、手の内をすべてさらすふりをして、俺の背中に回り、結託して俺の分け前を奪うことだ。これが初めてのことじゃないぞ。さあ、白状しろ」
「何もありませんよ。あらぬ事を考えていました。失言でした。口論して何になりますか。手紙の追跡を頼まれ、奪取方法を教わりました。手紙が手に入れば、数千ポンドで売り飛ばし、ルペラの取引をぶちこわし、もっと儲ける予定でした」
「結構なことだ。で、どこに手紙があるんだ?」
「さあ。ベルリンを発つときは確実にグレイが持っていました。私とバンストンで猫がネズミを見張るように監視していました。我々の知る限り、ドーバー駅に着くまでグレイは誰にも会っていません。投函もしていません」
「グレイも馬鹿じゃないからそんなことはしない。ずいぶん要点まで長かったな。グレイが消えたことは外務省が外交上の理由で当分内密にした。だがお前はドーバー駅とチャングクロス駅の間で奴がどうなったか、何が起こったか知っている。奴の居場所など知りたくもない、奴の身体検査をしたか。重要なことは手紙が手に入ったかどうかだ。後のことはどうでもいい」
「駄目でした。我々は面が割れているので手下を使わざるを得ません。手下は信用できます、手紙に利用価値がないからです。グレイの持ち物を調べても、封筒一枚すらありません。いいですか、もし手紙を持ってきたら五百ポンドやると約束していたのにですよ。ハースコートさん、間違いありません。グレイがどこかに隠しています。でも誰が持っているのか、どこに隠したのか誰にも分りません。もし外務省が入手したら……」
「外務省は持ってない。これは事実だ。お前を信用できればなあ」
「我々が
「エイビス、もっともらしいことを言っても駄目だ。都合次第で、この私を明日でも売り渡しかねないし、塀から撃ちかねない。でもお前の言葉を信じよう、手紙はなくなった。次はどうする?」
「はい、一緒に行動します。判じ絵で言うように、王女を探せです。手紙を見つけられない場合、手紙を盗んだ女を捕まえます」
「なるほど。でもその手はちょっと無理があるぞ。妙な一致じゃないか、手紙と王女が同時に消えるとは」
「嘘だ、ハースコートさん」
「なんだと? 前言を取り消さないと、首をへし折るぞ」
エイビスが、謝るようなことをもごもご言うと、ハースコートがまた冷静に続けた。
「文字通りの真実を言おう。完璧に分っていることは王女がリマーズホテルに
「さあ。
「俺も同じ考えだ。最善策は調べることだ。今晩コベントガーデンで行われる観劇会へ行く予定だ、ルペラの専用個室で夕食に招待されている。いい機会だから二、
エイビスが退出すると、ハースコートは色々考えた。この奇妙な事件の裏には誰かがおり、自分を追い詰めている。
*
依然としてわだかまりが心に引っかかっていたが真夜中ちょうど、劇場の廊下を歩いてルペラ男爵の専用個室に行った。
男爵が手を差し伸べて歓迎してくれたので不服はない。男爵夫人も最高に魅惑的な笑顔で迎えてくれた。男爵夫人が手招きして自分の隣の空席を指した。専用個室には桃色傘付き電球が一個テーブルの真上にあるだけで、テーブルには最高のごちそうが乗っている。
光の届かない陰に、古風な女がドレスデン陶器風の女羊飼い服装で座っていた。ハースコートの見るところ老女のようだ、というのも髪は白、顔には無数のほうれい線やしわが刻まれていた。
男爵夫人が言った。
「カウフマンさんには会われたことがないと思います。母の古いお知り合いですの。さあ、奥様今回だけはしきたりを破って一緒にお食事なさいませんか。差し障りないと思いますが」
だが老女は何かぶつぶつ言って、医者に止められており、踊りを見るだけで嬉しいとか。男爵夫人が自分の額に意味深に手を当てて、こっそり伝えたことはこの老女が精神的な病に苦しんでいると言うこと。それから夕食が華やかに始まり、会話が弾み、下の舞踏会場からは楽団が音楽を奏でた。
男爵夫人が言った。
「じゃあ、ゼナ王女のことは何も聞いていらっしゃらないのですの。とても奇妙な事件ですね」
ハースコートが立ち上がって言った。
「何にも。さて、長居はできません。約束の時間がありますので。王女はまた現れるでしょう。何という愚かで夢見るお馬鹿なんだ、私の知る最大のアホですね。私なら閉じ込めますよ。さらって母国へ送り返すのが親切ってものでしょう。今にいいことをやろうと思いますが、おっとゼナ王女にとっていいこと、という意味ですが、このような異常な方法で姿を消し、私をまごつかせて困らせるのですから。さて、行かなくてはなりません。素敵な時間をありがとうございました。もし王女の隠れ場所を見つけたら、お知らせしますよ。王女の気まぐれな行動は高くつくでしょうな、男爵、噂はほとんど当てになりませんね」
男爵が冷静に言った。
「
個室の扉が閉まると、男爵夫人がドレスデン女羊飼い服装の老女に話しかけた。
「ゼナ王女さま、あの最高顧問をどうお思いになられますか」
第十三章 地下室
一方、アイダは川べりの家でどうすべきか、この先どうなるかと不安に待った。グロブナー広場で用事を言いつけられてから何年も経ったような気がした。
ほんの数時間前は、この世に一人ほっちで、食事や寝る場所さえなく、さまよっていた。これまでの所、運命はそれほど過酷じゃない。恐ろしい破局から這い上がり、強力な友人にも恵まれた。
バレリイ嬢がわざと危ないことに引き込んだのかどうかは分らないが、危害を加えるつもりはないだろう。
もうこの頃になると、驚きという感情は通り過ぎて、恐怖もすっかり遠のいた。何があろうと、父とエイビスに姿を見られてはならない。二人が何か不名誉で卑劣なことをしていることは言わずもがなだ。
過去何度も疑っていたのは、二人が結託してなにやら不法なことをもくろんでいる。嬉しかったのは家出して世間に大胆に挑戦したことだ。
いずれにせよ正義を行うのが義務だ。その義務が二倍になったのは愛する男グレイが命の危険にさらされているからだ。しばらくこの薄暗い階段に留まろう。暗闇の覆いに紛れて何か聞けるかしれないし、後で有利になるかもしれない。全身が身震いしたのは恐怖のせいじゃなく、寝室で何が起こるか全神経を集中したからだ。
エイビスがぶつぶつ言っている。
「大変なドジです。とても危険です、獲物がない」
バンストンが応じた。
「あの婆さんが盗ったのだろ」
エイビスが続けた。
「そうは思いません。ダイヤを盗っても何が出来ますか。ダイヤを売っても五十ポンドも稼げないし、警察に聞かれることは言うまでもありません。その考えは捨てて下さい。手下に五百ポンドを渡し、計画を実行し、事が終わるまでグレイを監禁します。グレイは我々を騙し、何かやっています。ベルリンを発つとき、芝居用の安物ダイヤを大量に持参し、本物は別な方法でロンドンへ運んだのです」
バンストンが言った。
「とにかく王女は持っていない」
「なぜ分りますか。誰かそう言ったのですか、それとも推量ですか。知らないのですか、王女が消えてハースコートも居場所を知らないのですよ。大混乱です」
バンストンがくってかかった。
「無駄話をするな。やり直しだ」
エイビスが声をひそめた。やっとのことでアイダがついていけた。
エイビスが続けた。
「無駄話じゃありません。私は今朝ハースコートを尋ねてダイヤを見つけたか訊いて、あやうくばれるところでした。ダイヤのことは全く言うつもりはなかったのですが、副産物だということをうっかり忘れていました。ハースコートは存在すら知りませんでした。何とか疑惑をそらしましたが、勘が鋭いので何とも言えません。奴はダイヤに関心が無く、追っているのはある書類、この書類のためにグレイが英国へ帰国したのです。我々にはどうでもいいですが」
「知らんもんはどうでも良い」
「でも今知ったし、ハースコートもそう思っているから同じ事ですよ。グレイは死人同然で寝ているから、書類はどこかにあります。私の考えは見つけるまで家捜しすることです。時間はたっぷりあるし、邪魔も入りません」
「かまわん」
とバンストンがぶつぶつ言うと、
「やりましょう。もしグレイが起きてきて止めたら……」
「起きるだと。それはない。これぽっちもない。数日間は意識不明だろう。喋りすぎだぞ」
声が止んで、アイダに聞こえたのは寝室へそっと進む足音だ。地下室では垢まみれの子供達が依然として遊んでいる。まだ寝ないのか。不思議だ。誰も世話する人がいないのか。
見ればオイルランプの明かりが、子供らの遊んでいる石ころに当たって光っている。思わずにやり、部屋の男達が見たらなんというか、一瞬でもここに立ったらどうだ。大間違いしない限り、謎の一端を解いた。一方、父とエイビスの言っていることが正しくて、グレイが騙している可能性もある。
とはいえ、子供らの遊びに加わって、この目で確かめねば。
慎重に階段を降りて、手探りで真っ暗闇に進んで行った。腰板のところで何かこすれる音がして、足元でこそこそ動く気配がする。ぞっとした、このおぞましい場所にはネズミがうようよおり、喉から出かかる叫び声を必死に押さえねばならなかった。
行動開始以来、最大の恐怖に襲われ、神経がまいった。だが決して頭が壊れて、狂ってはならない。というのもグレイが危機に陥り、自分の手に未来がかかっているからだ。
やっと階段下にたどり着いたとき、深く息を吸って感謝した。手探りで扉を押すとすぐ開いた。脂ぎった汚い部屋だが、新鮮な空気が強壮ワインのよう。別な扉が地下室へ通じており、躊躇せず開けた。はっと息を止めたのは、むっとする汚染空気がわっと襲ってきたからだ。
アイダが部屋に入ると、ぼろ服を着た鋭い目の子供四人が遊びを中断してこっちをじっと見た。全然驚かないし、狼のような黒目には恐怖すらない。
女二人、男二人、最年長でもせいぜい十二歳、やせこけた姿や狭い眉や射るような目つきのため、ずいぶんませて見える。アイダは強烈な衝撃を受けてうろたえたが、この人間性を失った浮浪児らに哀れみの感情を抑えることが出来なかった。
「ゲームを続けなさい。何をしているか見に来たのよ。怖がらないのね」
年長の女の子が突っかかった。
「なんもこわくねえ。ねえちゃんが誰だかわかるよ」
「ほんと? ふふふ。じゃあ誰?」
「巡回人だろ? シャドウェル救護院からきたんだろ? おばさんはどうした? ちょいちょいスープをもってきてくれた」
「こんやは来れないのよ。だからかわりにきたの。手伝うことない?」
「一ペニ、くれ」
ともう一人の小さい女の子が甲高い声で言った。
「こんやは一銭ももってこなかったの。でもいうことをきいたら、ひとりひとりに六ペンスあげましょう。さあ、あすどこで会いましょうかね、みんなで二シリングになるわよ」
年少の女の子はもっと話したかったようだが、年長の女の子が頭をばしっと叩いたので黙った。当たり前のように受け止めて、痛いとも、文句も言わなかった。動物のような振る舞いに、アイダは驚いて後ずさりした。
年長の女の子がてきぱき言った。
「グリーンマン・パブの外で朝十一時だ。でも見て、ねえちゃん、何もあげる物はねえよ。ここには何もねえ、半分も」
「そうね、今なにをして遊んでいたの。お遊びのすてきな石を見せてほしいわ。まあ、なんてすてきな光る石ですこと。どこから?」
「二階のいい寝室にいるやろうからだ。事故にあったんだと。船のはしごからおちて、頭をうったんだ。よくなるまで誰かが監視している。ったく、おおぜいのやろうが事故にあうんだから。でもばあちゃんは気にしねえ。二階の男が、ばあちゃんにこのガラスをくれた。女優が舞台でつけるダイヤだってさ。中をあけると紙がいっぱいでてきたよ。これを買うか」
「いくらほしいの? 五シリング?」
「ばか言え。七シリングだ、いいか。あすの朝、グリーンマンの外で会おう、それでおわりだ。わすれるな」
「おばあちゃんは何というかな?」
子供の目に狡猾な光が走った。
「ばあちゃんには何も知らせねえ。向かいの波止場のガキがガラスを盗んだというさ。ばあちゃんは頭をぶって、これから気をつけろというよ。ったく、もし金をもらったと知られたひにゃあ、ナイフをちらつかせてやる。アギー、ビル、ジェス、石をあつめて、箱にいれて、ねえちゃんに渡しな。紙はなかだ」
年少の女の子が言った。
「はこのそとがわには金のおうかんがある。あたいのベッドの下だ」
ベッドとは名ばかりの汚いぼろ下から、子供が赤くて四角いモロッコ小箱を取り出すと、まさに本物の金の王冠スタンプが押され、組文字があった。
手に取ったアイダは心臓をばくばくさせて、バネを押した。中には小さなビロードが幾層にも重なり、どうやら宝石箱だ。そこに紙が入っており、まさしくグレイの手書きだった。
第十四章 地獄で仏
アイダがランプの下に紙をかざした。次のような内容だ。
『親愛なるきみへ。もしこの小箱の中身をきみに渡し、演劇に間に合ったら、素敵な宝石をまとい、逃亡王女の役割を見事に演じきれると思う。この舞台宝石はよくできているから、今まで見た中で一番本物に近い。きっときみが舞台に立てば、大勢の人々は家宝の宝石をつけていると思う。今度会ったときに入手先を教える。有名な女優に関係があり、この女優に本物の王子が恋に落ちた。劇中の王女は舞台で宝石箱を見せなければならない。そんなことを思い出した。とにかくこの小箱をしつらえて、外側に王冠と組文字を押した。次に会ったら、私がむかし扱った本物のダイヤの話をしよう。きみは大変いい人だから、おじさんのグレイを忘れないでおくれ』
アイダは二回も読み直し真意を掴もうとした。こんなに危ない目に遭って無駄足か。おそらくこの宝石なるものは一ポンドぐらいの価値しかないだろうが、手紙には謎の意味があるかもしれない。何も無いかもしれないし、逆に重要な意味を伝えており、外交官なら行間が読めるかもしれない。ことによると巧妙な暗号が隠れているかも。そうかもしれないが、これらの装飾品はここに用はない。狙っている男らに渡してはならず、アイダは自らの役割を果たすために、石を持っていくことにした。
机に山と積まれたきらきら輝く中には、髪飾り、四列首飾り、数々のブローチ、二、三組のイヤリング、それに一握りの石は組み物からもぎ取った物だ。どうやら何もなくなっていない、というのも組み物が完成したからだ。オイルランプの煙光でも、様々な色に輝いている。
アイダは宝石鑑定など出来ないが、かつては自分も宝石を持っており、これが舞台用に作られた単なる装身具だとはとうてい信じられない。優しく丁寧にこれらの品物を専用容器に戻し、パチンと鍵をした。
「これで全部ですね。あした会う場所は覚えました。もし私が行けなかったら代わりの者にお金を持たせます。いいですね、これは私達だけの秘密で誰にも言っちゃいけませんよ」
年長の女の子が小馬鹿に言った。
「なに言ってんだ。もらったかのようだ。なんで五分後に四分の一ペニもらえない? つごうできねえか。ねえちゃん」
アイダの結論として、この子供らは怖れるに足らない。自分は急いでグロブナー広場へ車で戻らねばならない。でも位置がさっぱりつかめず、暗闇では車を見つけられそうにない。
そうするには来た道を戻らねばならないが、がたがた階段にネズミがうようよいるのを考えると、身震いした。しかもグレイが寝ている部屋に父とエイビスがまだいるかもしれない。いい考えがある、子供に案内を頼もう。
「ところで、道案内してくれない? 誰にも見られないように外へ出してちょうだい。正面通りに出たいの、お友達が車を借りて、ずっと待っているから」
年長の女の子がにたにた笑って言った。
「そんなこったと思った。ついてきな。車まであんないする」
アイダが扉の方へ向かった。逃げたいどころの騒ぎじゃない、不潔な場所や空気に息苦しくなり、時々吐き気がして、くらくらする。
出口扉に手をかけた途端、グレイの寝ている部屋から悲鳴が上がったので立ち止まった。二階を見れば窓に人影が横切り、何か抗議している。
なにが起こったか知らないうちに、煙臭いランプが消えて、四人組に後ろに引っ張られた。信じられない、ろくに食べていないがりがりの小さい子供らに、こんな力があるとは。
年長の女の子がささやいた。
「しっ、まだいくな。一、二分まちな。やつらがおりてくる」
「どういうこと?」
「さあ。わかんねえ。でも病人が来たときゃいつも大さわぎだ。突っ立っちゃだめ。奴らがおりてくる。あたいのベッドにもぐりこめ。そこなら安全だ。うまいこと切り抜けてやる」
「でも服を着ています」
とアイダが小声で訴えると、
「ったく、あたいらは夏以外、服はぬがない。さあもぐれ」
仕方がない、逃げ道はない、この場は危険だ。ぼう然としてアイダはベッドと称するぼろきれと布きれに体を突っ込んだ。
子供らは隅っこにこそこそ移動した。その時、扉がバンと開いて二、三人が入ってきた。誰かがマッチを擦ると、オイルランプがまた煙り、火をともした。
老婆が金切り声で抗議している。
「全部本当だ。一ヶ月でも居座ってろ。臨終でも言うさ。がらくたは子供らの遊び道具にくれてやった」
エイビスが割って言った。
「婆さんは嘘つきだね。二階の寝室で見つけたあの石は一ペニになる」
「あたしゃ知らないね」
バンストンがさえぎった。
「もちろん知らないさ。それは分ってる。エイビス、冷静になれ。もし婆さんが本物だと知っていたら、放っとくと思うか。理屈にあわんだろ?」
老婆が叫んだ。
「あ、あんたは紳士だよ。五百ポンドくれないかい? そうすりゃあんたらのことは何も
エイビスが言った。
「餓鬼を起こせ。とにかく物を見せろ。こら、がきども、起きろ」
寝ぼけ声やあくびが聞こえた。余りに演技が巧妙、狡猾なので、不潔なベッドに潜り込んだアイダは震えながら驚きを抑えきれなかった。
やおら年長の子供が二人起き上がって、ぶつぶつ文句を言うと、年少の二人がめそめそ泣き始めた。
エイビスが言っている。
「おい、お前らに言うことがある。おばあちゃんがおもちゃにあげたガラス玉を見せろ。どこにある?」
女の子がぶすっと言った。
「もってねえ。ずっとねえ。ガラス玉をもって波止場であそんでいたときオカリー通りの悪ガキにとられた。全部もっていきやがった」
「箱ごとだ」
と年長の男の子が付け加えた。
エイビスがかっとなった。
「ったく。この餓鬼共は婆さんと同じ嘘つきだなあ」
年長の女の子が戸口を咄嗟に掴んで叫んだ。
「あんたも嘘つきだ。うそつきめ、このガリガリけだもの。誰だい? あたいらが寝ているのに起こしやがって。のら犬、見な。あたいのこの額の傷だ。背中にもあるぞ、どうしたかって? 知らねえし、気にもせんだろ。あのガラス玉を取りもどそうとしたら、オカリー通りのジンジャーにやられたんだ。こんど会ったら殺してやる」
すごい演技だ、すさまじい迫力と復讐心にびっくり仰天して、アイダは、ぼろ布の下で震えていた。
だんだん分ってきた、寄る
ちょっと後ろめたい気もする、だって自分がこのペテン劇場を引き起こしたのだから。疑い深く狡猾なエイビスさえ、この剣幕にびびってこう言った。
「殺しちゃいかん。さあ、箱を渡しなさい、代わりにソブリン金貨を一枚やるから」
アイダの心臓がドキッ。この子らは貧民
その時、壁にカチンと当たる金貨の音がした。女の子が激しく投げ返しているじゃないか。
「あたいが嘘つきかい? 上等だ、だんな。これが嘘つきのするこった」
エイビスが捨て
「ねえちゃん、うまくいったよ。でもいいかい、あした七シリングに一ポンド金貨をついかだ」
「ええ、分りました。差し上げます」
これ以上用はない。荷物をまとめて部屋から外へ飛び出した。どっこい、ぱっと捕まえられて、優しくささやかれた。
第十五章 部長の深謀
でもこっちの方がずっといい、あのきたない空気の恐怖宿よりましだ、ぼろ布や不潔や不道徳にまみれ、
男が言った。
「私が恐くないですか」
「いいえ。友人とおっしゃったし、一番欲しい人ですから」
「私は敵ではありません。あなたは安全です。ここにいて下さい、危険が無いか確かめますから」
アイダがはっと我に返り、声を上げた。にわかに思い出したのは、あの家から急いで逃げ出したとき、散々危険を冒して獲得した物を置いてきてしまった。
金文字入りの赤いモロッコ小箱は、ぼろベッドの下だし、グレイの上着も忘れてしまった。これらがなければ無駄骨だ。手ぶらじゃ今晩の働きはむなしい。たぶん宝石箱はたいしたことがない、中身の価値がないもの。
だが
男はアイダの動揺を見逃さなかった。
「何か困っていますね。お助けしましょう。お名前は知っております。そのほかも知っております。大迷惑も受けましたが、あなたに同情するのは事実です。我々は同じ目的に向かっていますが方法は異なります。ご用を申しつけて下さい」
「ごめんなさい、何もありません。急いで出たものですから忘れ物をしました。二つ取り戻さなければなりませんが、地下にあります。あなたでは取り戻せません」
「そうは思いませんよ。物の名前は?」
「しっ、ちょっと待って下さい。誰か私の名前を呼んでいます。確かです。どうかここで待っていて下さい」
グラスゴウ部長は反対しなかった。アイダが慎重に暗闇に進んでいった。数メートル先に小さな陰がぼんやり見えた。
「ねえちゃんかい?」
「ここです」
陰がぬっと現れた。年長の女の子だった。
「ねえちゃんは賢くねえな。ここへ来て大騒ぎして、ガラス玉にカネをやると言って出たら、置いて行きよった。この上着もそうじゃねえか」
アイダが感謝のため息をついて言った。
「上着もそうです。ありがとう、お手間を取らせて。よく私が分ったわね。行き先が見えたの?」
「運がよかった。遠くへ行けねえとふんだ。でも礼をいうな。そんなこたあ、してない。知らないでか。あたいは抜け目がないから気づくさ。手ぶらで帰ったら、あした金をもってくるかい? もって来ねえだろ」
「あなた損したかもよ。いい子だから約束を守ったのでしょ? あの紳士がソブリン金貨をあげたのに」
「くっくっ、ねえちゃんは甘いな、もし受け取ったら、一ポンド七シリングはどうなる? あたいは七シリング損する。ばあちゃんがソブリン金貨を取り上げるからな。もしねえちゃんぐらい甘ちゃんだったら引っかかって大損さ。さあ、ここに宝石箱と上着があるから、あしたパブの外で金を持ってくるのを忘れるな。じゃあな」
それ以上言わず子供が消えると、宝石箱と上着がアイダの手元に残った。今までのところ順調、あとはグロブナー広場へ帰るだけだ。
子供が去ってすぐ、グラスゴウ部長があばら屋から現れて、アイダの横に来た。道案内する様子は家回りを熟知し道路への道を知っているようだ。遠くに車の明かりが見えた。
部長が言った。
「グロブナー広場へ帰られると思いますが。ご一緒してよろしいですか」
またもや今晩の驚きだ。この見知らぬ人はヨット船員と関係がありそうだし、アイダの行く先を知っているけれども、実のところ見たこともない。あごひげとふさふさの口ひげがあるものの、紳士の態度だ。
実際、
「どうぞ、ご一緒したいなら。ご希望の所で下ろします。グロブナー広場へ戻ります。あの教会の時計が正しければ時間がありません」
車が出発すると車内灯がつき、グラスゴウ部長が相手に向き直り、びっくりまなこで言った。
「お互いにもっと知り合った方がよくないですか。我々は同じ目的に進んでおり、競争しているが、協力した方がいいでしょう。どんな偉い男でもあなたの支援があれば自慢しますよ、バレリイ嬢」
アイダがはっとした。一瞬忘れていたのが自分とその役割だ。
「私はバレリイではありません」
今度はグラスゴウ部長が驚く番だ。穴の開くほど見つめた。
「これは、これは。その通りだ。お嬢さん、あなたが誰だろうが、どっきりに成功だし、簡単な事じゃありませんね。近いから違いが分りますが、少し離れればどこでもバレリイ嬢で通りますよ。お名前は? 失礼ですが」
「どういうご関係か分りませんが、何も隠すことはありませんので言いましょう、アイダ・バンストンと申します」
またしてもグラスゴウ部長が驚いた。部長にとっても驚きの夜だが、隣のアイダにとっても同じだ。
「バンストンという男性は知っていますよ。ロバート・バンストン氏という人で、ハインドヘッド近郊に住んでいます」
「私の父です」
部長が無言でうなずいた。この新情報を頭の中でくるくる考えた。ロバート・バンストンを知っていると言ったのはちゃんと根拠があるからだ。もし父親の過去の経歴を部長がどれだけ完璧に知っているとしたら、アイダは驚き、心痛、恥辱どころの騒ぎじゃないだろう。
部長が疑ったのは、果たしてこの女は父親の陰謀をどれだけ知っているのか。この女の情報量は? もしや仲間じゃないのか、無邪気な表情と純真な目をしているけれど。
あらゆる人間性を知り尽くした者として、簡単には騙されないし、経験上こんな無邪気な表情の人物に遭遇し、えてしてその手に苦しめられた。でもどうやらアイダはそれらと違うようだし、ある種の超然とした誠実さがあるので、かなり気に入った。
「もちろん、あなたの今夜の行動は知りませんが、不作法を承知で一つ
「そうですね。率直に言いましょう。おっしゃる貧民窟に行ったのは仕方なかったからです。数時間前までは微笑んでいさえすればよかったのですが、こんな驚きの経験が今晩あろうとは。でも、どうでもいいことでしょう、少なくともあなたには関係無いし、あの恐ろしい家で私が何をしようと、あなたに見つかりましたけど。しかもあなたは名前すらおっしゃらない」
「言えないのですよ。母国のために今は名前を申し上げられません。でも紳士であることを信じて下さい。ここまでは言っていいでしょうが、私の父は上院議員ですし、私も政府の高官に信用されています。約束します、アイダさん、あなたを助けたいのです。そのためにも赤いモロッコ小箱の入手方法を尋ねたのです」
「私があの家を監視していると、子供達が石ころで遊んでいました。一シリングで交換を申し込むと受け入れてくれました。石にはまったく興味も無く、何の知識もありませんが、見かけ以上に価値があるような気がしましたので、疑いが晴れるなら警視庁へ届けます。話せばずいぶん簡単なことですね。あなただったらどうしますか。扱いをご存じのようですから」
部長が返事に窮した。
「融通を利かせましょう。私なら保管して、当分警視庁には言わないでおきます。ここまで来たら、小箱の中を覗かせて戴けませんか」
第十六章 はぐらかし
アイダが微笑んで小箱を膝に乗せてバネを押した。宝飾品が所定の位置に納まり、ビロード張りの布からきらきらと光りが溢れた。
グラスゴウ部長が片手で顔を覆う仕草は、ぎらつく目をアイダに見られたくないかのようだ。かがみ込んで一個ずつ手に取り、回したりひっくり返したりすると、電球の明かりがカット面に当たり、
部長はこれが本物だといささかの疑いもなく知っていた。そればかりか少しも疑わなかったのは、石の入手先をこの女は知っているな。
口まで出かかってアイダに本当のことを言おうとした。でも長年の経験と慎重さでやっと止めた。結局この女は赤の他人だし、見かけの率直さは騙すためかもしれない。そのとき面白い計画が心に浮かんだ。
「いい品物ですね。実際本物かも知れませんよ。でも私は宝石の目利きじゃない。最善策は鑑定してもらうことですね。価値がないと分ればそれまでです。逆に本物であれば、バレリイ嬢が指示するでしょう。今晩帰宅されたらバレリイ嬢に見せなさい。でも何か手がかりを掴んでおられるようですね」
「紛失宝石を見つけた気は一切ありません。ところであなたは顔が広いようですからグレイ氏の名前をご存じでは?」
部長がうなずいた。女の言葉が信じられなかった。さらなる驚きだ。散々グレイを探しているのに、この無邪気な女があっさり言うとは。
グラスゴウ部長が尋ねた。
「グレイ氏を知っているのですか」
「数回会いました。いいお友達でした。あなたもお知り合いですか」
こう言いながらアイダが自分に立腹したのは赤面したからであり、更に許せないのは相手に感づかれたからだ。
グラスゴウ部長が答えた。
「一番尊敬する大好きな男ですよ。人生も一緒、学校も一緒でした。居場所が分れば、たっぷりお礼しますよ」
この男はもっと知っているなと思ったが、実際すべてを知っているわけじゃない。これまでこの男を信用したが、グレイの命が大事なのでこれ以上は打ち明けない。この男には小箱の手紙を見せるけど、それ以上は黙っていよう。
「この小箱は最近までグレイ氏が持っていました。どうやら女友達にプレゼントするつもりで、相手は素人芝居の女優さんのようです。手紙は小箱の底にあります。ご自分で見て下さい。取りましょうか」
グラスゴウ自ら手紙を抜き取る指が震えている、しかもぶるぶるだ。最重要手がかりを偶然掴みつつあった。間違いなくこの女は素のままに違いない。もし不正直、狡猾であればここまでグラスゴウを信用しないだろう。
車内灯の光でグラスゴウが何回も手紙を読み、書き手のしたたかさに感嘆したが、アイダにはそぶりも見せなかった。手紙を小箱に戻し、留め金をパチンと掛けた。
「そういうことでしたか。グレイ氏は、ほかの誰よりも小箱の価値を知っていますね。ここで車を止めて下ろしてもらえませんか。お休みなさい。アイダ嬢、ありがとうございました。率直に話して戴いて、何も損はありませんよ。またほどなく会うでしょうが、その時はご協力にきっと感謝します」
グラスゴウがひさしのあるヨット帽を触って、ピカデリの方へ歩いて行った。時計が午前二時半を指したとき、車がグロブナー広場に滑り込み、アイダがへとへとになって戸口階段に立ち、応答を待った。
直後、大扉が開くと、バレリイ嬢が満面の笑みで出迎えた。片手をアイダに回し、二階に案内し、最高にしつらえた寝室に行くと、そこには二人分のおいしそうな小料理が並べてあった。バレリイ嬢が椅子を勧め、上掛けを脱がしてくれた。
バレリイ嬢が言った。
「本当に心配しましたよ。なぜ帰ってこなかったのですか。いえ、これ以上言いません、夕食を終えるまで。へとへとのようですね。手に持っているモロッコ小箱と上着は何ですか。どこで手に入れたのですか」
「ごめんなさい、あとで。この食事を見るまで空腹すら忘れていました。夕方のお茶時間以来何も食べていません。あのときはバター付きパンのみでした。実はこの六ヶ月間、こんな食事にありついたことがありません。決心して実家を出たとき、いや、あなたには分りますまい……」
バレリイ嬢はおもんばかって何も
バレリイ嬢が煙草に火をつけながら言った。
「さあ話してちょうだい。よかったら今晩はここで寝て下さい。さあ、手柄を話して。きっと大冒険ですね。そうでなきゃ、ほほが染まり輝いてないもの。でも冒険は契約に入っていませんでしたよ。自分にとっておいたのですから。実は私の人生は長い冒険なのよ。うすうす感づいているかも知れませんが大きな理由があって、今晩一、二時間自由になり、誰にも見られず消えて、その間、監視役が昼夜警戒を緩めないから、私がコベントガーデンで楽しんでいると思わせたかったのです。ええ、この貴重な一、二時間をもらい、有効に使いました。まもなくある人々は損に気づくでしょう。あなたへの指示は単純でした、つまり私の真似をして偽物と気づかれないことです。皆から距離を保ち、口実として頭痛とか不調とかもっともらしいことをでっち上げて、ここに午前二時十五分に帰るはずでした。それをしないであなたは冒険をしてしまった。全部おっしゃい」
「私が過ごした今夜はなんだか冒険小説のようでした。しばらく言われたとおりにしていると、だんだん寂しくなってきて、ある紳士がここへ来ているのが見えました。尖り顔の薄い唇の男です」
「ハースコートです。まさか話をしたとか? もし話したらすぐに偽物と見破ります。そうすると私の努力がすべて無駄になります」
「いいえ、話しませんでした。ハースコートは見ましたが、見破られたとは思いません。慎重に監視して近づかないようにしました。しばらくすると別な男が来て、男同士で話していました。後から来た男は陰気な目つきの不機嫌な表情でした」
「アーノット記者のようですね」
「ずばり当てました」
「どんなお話をしましたか」
「しばらくあとです。最初ハースコートという紳士を追い払いました。それから自己紹介をしました。あなたのことはよく知らないようで、私を確実にバレリイと思っていました。率直に自分の経歴を話してくれました。どうやらこの男は刑務所に入っていたようですが、誤審で有罪になったと言っていました。また自分の恋愛話もしてくれました。ハースコートについては憎んで軽蔑しているとか。察するに、ハースコートがある書類を持っており、それがあればアーノット氏は再び世間に顔向けが出来るようでした。でもハースコートは書類を渡すつもりはないようで、その理由はアーノット氏を手下としてうまく使えるからです。でもこの件は私と同じくらいご存じでしょう」
「それほどでも。実際あなたは貴重な情報を教えてくれました。アーノット氏はロンドン一切れる敏腕記者であり、国際陰謀の知識は計り知れません。会ったことはありませんが、きっと私より私のことを知っているでしょう。さあ、続けて。どうなったか教えて。もうさえぎらないから」
そこから話したが、もうバレリイは何も言わなかった。バレリイは熱心に聞き入り、口をぽかん、目を輝かせ、最後まで辛抱した。そのあと、にやりとしてこう言った。
「何か隠していますね。以前グレイに会ったことがあると言うのはいいですが、恋仲だったと白状すべきでしょう」
「そ、それは知りえないはず」
「いいえ知っています、ふふふ。名前を言ったときの表情と、ほほが赤くなったことから推測しましたよ。全部喋るはずはないし、あの恐ろしい場所から救う助太刀が欲しいでしょう。私を冷たいとか冷酷だとか思わないで下さいね、私の見るところ、グレイ氏は当分絶対に安全です。今いるところがずっといいと言っても、私がおかしくなったと思わないでください。いま理由は言えませんが、あとで正しいことが分ります。ところで例のにせダイヤを見せて下さい、大変な危険を冒して舞台宝石を手に入れたようですけど」
アイダがモロッコ小箱をテーブルに置いて、開けた。バレリイがきらめく石を見て声を上げた。
「まあ、あなたってすごいお人ですね。とびきり賢くて運のいい女性です。人生最高の夜です。これは二万ポンドでも手放せませんよ」
第十七章 ベルリン
グラスゴウ部長が自問自答しながら、流しのタクシーを拾い、自室へ向かった。果たして正しい選択をしたのか、最後の数時間で多くの危険を冒した。
アイダは信用できるか否か。否なら重大な判断ミスを犯したことになり、やがて壊滅的結末を招く。一方、女の性根を正確に読み切ったら、重要な役割を演じたことになる。
商売で大儲けして、新事業を手がけ、宣伝という投資が必要になったようなものだ。でもやってしまったことは、最後まで監視しなければならない。
午前二時半過ぎに自室についた。ブラインドは降りていたが、電灯は六つの部屋で煌々とついており、部下が働いていた。
グラスゴウの仕事は眠らない。電話は常時接続、電報はパリやベルリンから届き、仕事はますますきつく面倒になっていく。
上官に自慢することに、まんざら本当じゃないこともないが、全欧州を監視している。どんな政治策略や陰謀も長く隠されることはない。いま最大の事件にぶち当たった。お疲れの秘書が机から目を上げたとき、グラスゴウ部長が部屋に入ってきた。
「待たせてすまない、ロスコウ君。思ったより長くかかった。すまんがチャリングクロス駅に電話して三十分以内に臨時列車をドーバー駅まで出してくれるように手配してくれ」
ロスコウ秘書は少しも嫌がっていないようだ。
「何か突発事件ですか」
「ああそうだ。グレイ失踪のしっぽを掴んだ。グレイはさしあたり安全だし、命に別状はないようだ。紛失書類のありかも突き止めたし、これも当分そのままにしておく。時期が来たらガサ入れする場所も分った。すぐ電話しろ」
「一体この騒動は何なのですか。ちょっとばかげた恋文で、国際問題が起こるわけはありませんよ」
「ロスコウ君、まさにそこが誤りだ。もちろん、我々は膨大な時間を費やして盗まれた秘密条約文書を追いかけており、そんな文書は小説の妄想にしか存在しない。例の手紙を取り戻したら欧州が平和になるとは言わないが、もし手紙を書いた国王に手紙が戻らなければ、英国海軍にとってはいずれ重大なことになる。君は筋を立てるが好きだろ、ロスコウ君、これがそれだよ。君に解けるかな。ある統治者が青二才の頃、非常にばかげているが無害な手紙をある女優に書いた。これが最初の手がかりだ。あとを考えてみよ。ありきたりの話じゃないか。もし我が国の行政官がそんな馬鹿なこをしても大事には至らないが、暗愚政治家が宴会以外に興味がないなら、大事件になる。この手紙を入手したら使い道があとで君にも分ろう。よくあることだが、最高の愛国者が人知れず赤面する事件だ。さあ、すまんが駅へ電話してドーバー海峡のピア提督に私の専用電話をつなぎ、私が一時間半後に行くと伝え、ジプシー丸の蒸気を上げておき、すぐにオランダのフックへ渡れるように手配してくれ。私は明日の夕方までにベルリンに着かねばならないし、私がロンドンを発ったことが決して知られないようにしてくれ。タクシーに私のバッグを放り込んでくれ。サンドイッチと小瓶のブランデーも入れてくれ。ここ何日も食べていないような気がする」
ロスコウ秘書はこれらの命令を冷静に受け止めた。というのも部長が鷹のように急襲することは珍しいことじゃないからだ。
*
三十分後、グラスゴウ部長はドーバーへの途上にあり、翌日夕方七時には、ベルリンの英国大使館に現れて、提出した偽名の名刺は、ちっとも本名に似ていなかった。
玄関守衛が言うに、大使閣下はこんな遅い時間には誰にも、特に無名の私人には会われないそうだが、名刺は届ける由。守衛は名刺に暗号が書いてあることなど知らないから、大使が訪問者に直ちに面会すると聞いてびっくり。ウォルタ卿が椅子から立ち上がり、温かく握手した。
「グラスゴウ部長に会えて大変嬉しいですな。実はきみに会いたかった。これはテレパシーかな?」
「ウォルタ卿、任務ではそんな言葉は使いません。閣下に会いに来たわけは重要な事が分かり、その結果を見て閣下に動いてもらいたいのです。私と英国へ行って、つまり、とにかく明日か、あさってまでにロンドンに帰国して戴けませんか。無理なお願いだと分っていますが……」
「確信がなければそんなお願いはしないだろう。グラスゴウ部長が判断ミスをしたのは見たことがない。それにグレイの不幸な蒸発はとても心配しておる。願わくは――」
ここで、大使が不気味に中断すると、グラスゴウ部長が答えた。
「殺されていませんよ、先取りしましたが。比較的安全な部屋にいるのをたまたま知りました。望ましいとは言えませんが、暗殺は免れると思います。好きなときに数時間でグレイは救い出せます。そうしない理由はもし救出した場合、この事件を仕組んだ狡猾悪党に警戒されるからです。逆に我々がひどく混乱していると思わせ、連中には疑いが全くかかっていないと思わせたいのです」
「でもグラスゴウ部長、連中は連中のやり方をするぞ。もし連中が手紙を売ったら、我々はおしまいだ。ボーン国王は妹を絶対許さないし、妹は兄を全く制御できなくなるから、妹の広大な領地は没収されるだろう。そのとき英国の地中海港はどうなるかな」
「おっしゃることは分ります。でも連中は手紙を持っていません。『よく練った計画も失敗に終わることが多い』とか言いますが、本件は文字通りです。グレイに危険は無く、独自の方法で連中を
「もっともらしいですな。連中はとても攻撃的ですぞ。グレイのロンドン行きは全行程を有能な護衛が守っていた。でもまるで子供のようにグレイをさらった。ところであの手紙のほかに何か運んでいなかったかな」
「ハハハ、それも承知しております。信じられないかもしれませんが、連中はそれにも失敗しました。おっしゃる件は舞台用ダイヤだと思いますが」
「そういうことだな」
「でもウォルタ卿、模造品に違いありません。小箱のメモにそう書いてありました。グレイの手書きを、私が実際に確認して読みました。石を手にした連中はメモを福音書のように読み、ゴミ箱に放り投げました。だからいま安全です。この件については余り訊かずに、気になさらないように。もしご一緒に帰国されたら、手紙を渡します。手紙の有効利用はご存じでしょう」
「もちろんだとも。でもどうしてもこの一件は理解できないなあ。グレイは出発半時間前まで英国へ行くことを全然知らないのだし、半時間前まで私も命令するとは夢にも思わなかった。私が知らないのだから連中が知るわけない。例の手紙を私が持っていると危ないので、ロンドンへ持たせた。手紙が無くなったと聞いて、ひどく気分が落ち込んだ。一、二日でボーン国王が手紙を入手するだろうと踏んだ。もし国王が手紙を手に入れたら、王女の運命は広大な領地もだが、断たれる。国王は王女の仕打ちを決して許さないから、領地を没収して事実上王女を物乞いに落とすだろうな。国王の権限内であり、我々はどうすることもできない。領地を没収されたら、ルペラ男爵の採掘権もなくなるだろう。知っての通り、長い間わが英国政府は自由かつ充分に海軍用の石油供給が出来るよう段取りをつけてきた。いままで石油を安定確保出来ていなかった。米国、メキシコ、ロシアに頼ることが出来ない理由は大企業の支配下にあり、大企業は愛国者でないからだ。もし我が国が欧州戦争に巻き込まれたら、我が海軍はたちまち行き詰まる。だが一度は、この私が解決したように見えたけどなあ」
第十八章 写真
大使が興奮して話した。部屋をせかせか行ったり来たりする有様はまるでグラスゴウ部長がいないかのようだ。大使が続けた。
「世間の迷信だな、国家が国王と内閣で運営されているというのは。全然そうじゃない。すべての国家は資本家に牛耳られている。資本家は目的にかなえば、欧州大陸の地図さえ書き換えて、戦争も起こさず人命も奪わない。歴史が教えているし、有能な外交官なら知っている。時たま愛国的な資本家に出くわすこともあるが、資本家が情報を提供し続けると限らないよ、たとえば、資本家が軽視されたり、大胆な競争相手に負けている時などだ。過去何年も英国政府が警告してきたことは世界の石油供給のすべてが次第に会社か個人になってきたことだ。そこに愛国者のルペラ男爵だ。男爵だけが英国に帰化しており、英国のことを心底思っている。自堕落な英国政府の愚行を糾弾し疲れて、ついに私の所へやってきた。その理由は二つ。一つは私が困っていること、もう一つは男爵夫人がゼナ王女の親友だからだ。男爵の話によれば、王女の所有する表向き無価値で広大な不毛領地は、地中海の絶景海岸に面している。また、この荒れ地には石油埋蔵が豊富だとか。この話で君の記憶も蘇ったと思う。とにかく秘密裏に調査したところ一点の疑いなく王女の私有地は世界最大の油田であることが分った。更に価値があるのは海岸に面していることだが、これは説明の必要も無いだろう。ルペラ男爵は採掘権を持っており、極めて好意的な条件で英国政府に売却するつもりだ。だから絶対に例の手紙は取り戻さねばならない。もし手紙がボーン国王に渡ると、いちゃもんをつけるだろう。実際国王は手紙奪還のためなら何でもやりかねない。だからグラスゴウ部長、君がこの神聖な最終目的を達成するなら、喜んで英国へ帰ろう」
グラスゴウ部長が慎重に言った。
「じゃあ、そうして戴けますか。些細なことですが、一緒に帰らない方が良いでしょう。ところであるものをお見せします。信じて下さい、ウォルタ卿、一つ伺いますけど、逆質問はしないで下さい。この写真を見られたことは?」
そう言いながらグラスゴウがポケットからケースを取り出し、中から写真を抜いた。ウォルタ卿が明かりに当てて女性の容貌を慎重に調べた。不快な表情を浮かべて話した。
「あるよ。我が人生で一番悲しい場面を思い出すな。四年前不肖の息子が夢中になっていた女だ。直接この女に会ったことはないが、痛い思い出があり、ある日、息子のジェフリが来て、この女のキャビネ写真を私に見せた。美貌は否定しないよ、実に美しいし、知性も垣間見えるが、君、旅芸人だぞ。子供の頃から欧州の下層民と暮らしていた女だ。言うに事欠いて上流階級出身だと。まったくジェフリは夢中だった。息子の話では孤児で、両親はひどい争いで殺されたとか。もちろんとても結婚したがっていた。女に会ってくれと頼まれたが、もし会ったら結婚に反対できなくなることがすぐ分った。だから素っ気なく断った。代わりに息子に、もしあの哀れな女と結婚したらお前はもう私の息子じゃないと言った。息子は私の言葉を真に受けた。すぐ家を出て、以来会っていない。時々息子の噂を聞くけど、政治陰謀に深く関わり、あの女があとを追っているようだ。女は息子の邪悪な守護神だよ、グラスゴウ部長」
「結婚していないのですか」
「ああ、してない。女が狡猾すぎる。将来令夫人になっても女の野望は満たされない。だって爵位はつまらないし、お金にならないからだ。もし哀れな息子がどうなったか知っていたら、どうか教えてくれ。この二年間は音沙汰無しだ。もしかしたら死んでいるかもしれない」
グラスゴウ部長が静かに言った。
「死んでいませんよ、ウォルタ卿。いま言いましょう。写真の人物が上流階級生まれだという息子さんの話は本当です。また両親の死に様も本当ですし、子供時代何年間も旅芸人一座と欧州をどさ回りしていたのも本当です。でもいまは裕福ですし、まともにお金を稼いでいます。いままでバレリイの名前を聞かれたことは?」
「なんてことだ、まさか……」
「そうです、ウォルタ卿。女の本名はどうでもいいですが、偉大な探検家のブルン卿は実母の
「それはなんだ?」
「あなたの息子さん探しですよ。息子さんに心底惚れています。当時女は貧乏で、文無しの息子さんと結婚したかもしれないが、息子さんの政治見解と対立することを怖れました。息子さんの過激な政治思想をほとんど押さえたのですが、その最中に息子さんを見失ったのです。でもそれは女のせいじゃありません。それをやったのは反逆の悪党ハースコートであり、確か大使の親戚だと思いますが」
「残念ながらそうだ。奇妙だなあ、こんなことが複雑に絡んでいるとは。でもグラスゴウ部長、なぜこの話を私に? バレリイ嬢は現在の問題とどんな関係があるんだ? どこに絡んでいるのか」
「詳しくは言えません。でも深く絡んでいることがやがて分ります。英国へ帰国してもらいたい理由の一つがあなたにバレリイ嬢を紹介したいからです。バレリイ嬢への偏見は捨てて下さい」
「グラスゴウ部長に従うよ。でもこれで何の得があるんだ?」
「どうか忘れないで戴きたいのは、過去数年間ハースコートがゼナ王女の顧問ということです。これはまさに失踪喜劇です、ゼナ王女も失踪しました。王女がハースコートの正体を見破って逃げたのかどうかは分りません。でもこれだけは言えます。バレリイ嬢ならいつでも王女を見つけられます」
大使が椅子から立ち上がり、部屋をそわそわ歩き回った。心の中で戦っているようだ。やっと口を開いた。
「君が正しいようだ。実際確かだ。ここベルリンではいま重要案件はないから、堂々と数日留守に出来る。よければ明日早朝に出発する。邪魔が入らなければ君の事務所を明日夜、いや木曜日の夜、夕食後訪問しよう。ぜひ尽力して、不幸な息子を見つけてくれれば――」
「必ずお約束します。ただし余り私に質問しないで下さい。たぶんうまくいくでしょうが、行く手には危険と困難があります。敢えて手紙で知らせず、直接伝えに来ました。話がなければ私はもう行きます。運がよければ、明日英国へ帰れて、誰にも私がロンドンを離れたことは知られないでしょう」
*
正確に四十八時間後、ウォルタ卿はグラスゴウ事務所に現れて用件を伝えた。
真夜中近くなってから、グラスゴウ部長が出動時間だと告げた。
「これから危ないところへ行きます。少なくとも大使の安全については責任があります。いえ、拳銃は必要ありません。ですが、衣服交換が望ましくて、ちょっとがさつな衣装を用意しており、二人で船員の格好をしましょう」
「じゃあ波止場へ行くのか」
「そうです。そのあとロンドン一劣悪な場所に行きます。確実にグレイが安全、いや比較的快適なことを見てほしいのです。ご自分で確認して下さい」
「グレイを尋ねるつもりか」
「状況次第です。グレイの居場所やその他を見せたいのです。どうかこの衣装を着て下さい。がさつでみっともないかも知れませんが、きれいに洗ってありますから快適ですよ」
「道案内してくれ。準備できた。冒険気分がみなぎってきたぞ」
道中タクシーの旅を楽しみ、タクシーを降りたあと、狭く汚い道をとことこ歩いて行くと、ほとんど無人だが、時たま警官がいる。警官をグラスゴウが慎重に避けて、ついについた家は波止場の横にあった。そこは真っ暗でなく、微光で目が利いた。
ウォルタ卿が言った。
「嫌なところだなあ。まさかグレイがここにいると?」
「いままで内情を明かしてきませんでしたが、家の裏側へご案内します。以前ここへ来たので、にわか押込みをやるなら、川べりの入り口がいいですよ」
二人は慎重に家の裏側を選んだ。グラスゴウ部長が扉に触ると開いた。興奮に息を凝らし、すぐ大使にささやいた。
「いない。この家には石炭の燃えカスすらない」
第十九章 王女登場
アイダはバレリイ嬢の興奮ぶりを見て面白がった。そのように驚くのも当然だ。今夜は驚くことが次々に起こり、もしこれらの石が王冠の一部だとバレリイ嬢に教わっていれば、アイダはあれこれ悩まなかっただろう。アイダが言った。
「お嬢様に喜んでもらって嬉しいです。お嬢様のお言葉から我ながらよくやりました。面目を施したとかそんなことではありません。本物を見つけたのですか」
「アイダ、石は本物です。ぜんぶ以前見ました。何回もその宝石箱を手に持ちました。あなたを心から信用していますし、あなたも秘密を大切にして下さい。不思議なのは一体なぜその宝石をわたくしに見させたかです。あなたを信用していないというわけではありません。ピカデリまで相乗りした妙な男のことを言っているのです。誰だか大いに知りたいですね。なぜこの宝石をあなたに運ばせてわたくしに見せたのかしら。わたくしに渡すことを知っていたから? どうもワナのようね。普通の女性ならダイヤ小箱以上にすごいワナはないでしょう。用心しなければなりません。色々言いましたが、いまはこれで満足して下さいね」
「じゃあ、このダイヤの持ち主をご存じなのでは?」
「ええ。でもいまは秘密にした方が良さそうですね。このことは誰に言ってはいけませんよ。この宝石はわたくしが持っていれば安全です。わたくしの見るところ、あなたの予想通りです。あとで秘密を打ち明けましょう。わたくしやわたくしの親友に関することで、協力が欲しいのです。あなたの勇気や決断は証明済みです。あなたの読み通り、ボーン国のゼナ王女の名前は知っているでしょう」
「新聞で時々見ました」
「ではそのお方は分りますね。王女は若くて美人で夢想家です。王女は一般人と素質が違います。というのもゼナ王女が
「確かにばかげています。ひょっとして、王女がロンドンにいれば危険だとおっしゃるのですか。だれがやらせるのですか」
「兄のボーン国王です。全くためらわずにさらいかねません。わたくしがその計画の一端を邪魔しているのです。王女が失踪したあと、連中が探し回りましたが無駄でした。まさかこの家に隠れているとは思わないでしょう。そんな考えは馬鹿にするでしょう。バレリイならそれよりもっといいことを考えると思うでしょう。連中は利口すぎ、賢すぎ、勘ぐり過ぎるゆえ、王女はここが絶対安全ですから、数日滞在しておられます」
アイダが独り言を言った。
「信じられない。わずか数時間前、私はしがない無名の絵描きで一、二シリング稼ぐのに四苦八苦し、じきに宿無しになる恐れがあったのに、いまや異常な陰謀に巻き込まれ、欧州の支配者達と接触している。そのうち訳が分るだろう。もし私の手助けが欲しかったら、喜んで協力します。でも急ぎすぎておられませんか。もし召使い達に知られたら……」
「あら、わたくしの召使いはほかの所と違いますよ。幹部なのです。扉係の従僕、食器棚管理の執事はスパイ訓練を受けています。全員組織の一員です。台所女性の一人か二人は雑用に雇われているかも知れませんが、何も知りません。この邸宅で招待客の素性を知らない人は誰もいません。うちの二人が王女をここに連れてきたのですから。一緒に客間へ行って王女に会いましょう。とてもかわいらしいお方と分るでしょうし、わたくし達と同じように、たちまち
二人が客間へ入ると、すらりとした女性が炉棚の椅子から立ち上がり、熱心に読んでいた本を脇に置いた。見れば金髪の顔が暗く感じられ、澄んだ瞳が喜んだり悲しんだり、また物思いに悩んだり、くるくる変化している。
バレリイが言った。
「王女さま、お友達をご紹介します」
王女が衝動的に両手でアイダを抱き、両ほほにキスして言われた。
「大変嬉しいです。本当の親友はとても貴重です、神様からの贈り物ですから。王族に生まれたものは誠実さを見抜くことがとても大変なのです。わたくしのことは?」
「はい、バレリイ嬢が教えてくれました」
「では誠実なバレリイも信用していますね。わたくしのような事例は以前ありましたか。なぜ自分の好きにやってはいけないのですか。私が伯爵を愛し、伯爵もわたくしを愛しています、それ以上言うことはありません。なぜわたくしを放っておけないのですか。わたくしが誰と結婚しようが兄に関係ないでしょう。いやです。わたくしをさらい自国へ連れ戻そうとして失敗すると、わたくしの領地を没収すると脅す。わたくしにも武器があります。ええ、そうです。兄を欧州中の笑いものにします。兄は堅物ですから、自分は謹厳実直だと思っています。わたくしをロンドンから引き戻そうとしています。ロンドンにハースコートという友人がいます。生々しい場面が思い出されます、同氏がわたくしの面前でこう言いましたね、わたくしが小馬鹿で、言うことを聞かない駄々っ子のようで、寝かしつけた方がいいなどと。ああ、わたくしが聞いていることも知らないで。変装してそこにいることも知らず、友人のルペラ男爵がわたくしの目を覚ますためにその場を設けてくれたことも知らずに。そしてわたくしの友人だと思われていたその男は最近わたくしをこっそり海岸へ誘い出す計画をもくろみ、兄の国王のヨットに乗せようとしました。ですから友人の忠告に従って失踪しました。それでここにいます。昼夜わたくしを監視する輩がいますから、バレリイがわたくしに変装をしてくれたので外出して、追っ手をあざ笑っています。兄のスパイを通りで見ても、笑い飛ばしています。あの手紙さえ手に入れば、絶対安全なのですが。でもベルリンを脱出するときに置いていかざるを得なかった理由は、貴重な手紙を持って国境を越えられなかったからです。グレイ氏が手紙をわたくしに持ってくるはずでしたが、ああ、悲しい事故に遭われたとか。とても心が痛みます。グレイ氏がわたくしの友人であり、わたくしの安全が同氏にかかっていることを、誰か知ったに違いありません。ひとたびあの手紙がわたくしの手元にくれば、兄に最後通牒を送ります。兄にこう言います。手紙は友人が持っており、もしわたくしに何かあれば、全世界が読めるようにすると。もしわたくしの領地を没収したら、すぐさま公表すると。ですから分るでしょう、グレイ氏を見つけて、重荷から解放してあげなければなりません。でも誰ができますか。頭が痛くなるまで考えましたが、答えは出ません。あなた方、助けてくれませんか」
バレリイが思案して言った。
「そうですね。アイダと話していたときに、考えつきました。今晩アイダがアーノットという新聞記者に会いました。同氏は私を何回も助けてくれましたが、私は話したことはありません。また助けてくれようとしています、というのもハースコートの首根っこを捕まえて、やっつけるのがアーノットの目的だからです。そのためなら何もためらいません。それはさておきアーノット記者は非常に賢くて、裏政治をよく知っています。居場所を知っていますから、よろしければ電話をかけましょうか」
アイダが尋ねた。
「必要ですか。確かにグレイ氏の居場所は知っています。警察に言うだけで、数時間以内に……」
バレリイが叫んだ。
「やめて。ことわざを知っていますか。盲人、蛇に
王女が言われた。
「バレリイは素晴らしい。間違いないでしょう。あなたにすべてお任せします」
第二十章 しつこい餓鬼
アーノット記者は手が空いていたので、もしバレリイ嬢が会いたいならすぐ駆けつけるとのこと。ちょうど新聞社から帰ってきたところで、援助出来ればこの上ない喜びとか。
一〇分後に到着し客室に入ると、混乱したように立ち止まり、バレリイ嬢とアイダをしげしげ眺めた。明らかに戸惑っている。アーノット記者が言った。
「もしかして二人の女性がとても似ているせいで、今晩大失態をしたかも知れない。舞踏会で会ったのはバレリイ嬢でなかったことがいま分かりました。この失敗が悪い結果を招きませんように。でもバレリイ嬢は非常に賢いから……」
バレリイ嬢が笑った。
「ふふふ、はじめまして。実は今晩アイダ・バンストン嬢に入れ替わってもらいました」
アーノットが暗い顔になり尋ねた。
「いまバンストンと言いましたか。あなたは株式仲買人、ロバート・バンストン氏の娘さんですか」
「父です」
アーノットの額に疑惑のしわが寄るのを見て、アイダが続けた。
「どうか誤解しないで下さい。はっきり言いましょう。多くの事で父と私は衝突しました。そのため私は家出して自活しました。事実上、父と私は他人です。アーノットさん、私は今晩面白いことをたくさん経験しました。先に進む前に、私の見聞きしたことをお話した方がいいでしょう。知っておくべき理由は、もしあなたがいなかったら、冒険を乗り切れなかったからです。おそらく私をバレリイ嬢と見誤ったと思います」
手短にアイダがアーノットに今晩のことを述べて締めた。
「さあ、全部分ったでしょう」
バレリイ嬢が付け加えた。
「それに私があなたを呼んだわけも。アイダ嬢が警察に連絡すると言ったので、私が止めました、もし邪魔したら非常に繊細な仕掛けを確実に駄目にすると思いました。一般的には情報部のことですが、特にグラスゴウさんに関係します。もちろんグレイ氏が消えたことは知っているし、秘密にする深刻な理由もあり、そうしないと新聞でとっくに発表されたでしょう」
アーノットが尋ねた。
「その件についていま議論していいですか。バレリイ嬢のおっしゃることは正しいです。私が自社新聞にグレイ失踪の特別記事を書いたところ、編集長が諜報部の圧力で差し止めました。でもあなたには全部言いましょう。ハースコートと二人の仲間がすべての元凶なのです」
バレリイ嬢がきつく尋ねた。
「二人の名前は?」
アーノットが躊躇して、やっと言った。
「率直に言いましょう。エイビスとバンストンです。アイダ嬢の目の前で申し訳ありません」
「どうか
アーノットがさえぎった。
「今のところありません。バレリイ嬢が正しいです。諜報部を邪魔したら重大な過ちを起こしかねません。私にも独自の方法があります。手下を一、二人雇っています。事実、グレイが旅していた一等車で、開封済み封筒を追跡中に手に入れました。調査して一両日中に結果をお知らせします。退去前に何かご用はありませんか」
「あります。下宿まで一緒して戴けませんか。衣装交換に数分待って下さい。こんな時間に一人歩きしたくありません」
*
アイダが驚いたのはエルシが待っていたことだ、夜明け前だというのに。エルシが言った。
「こんなに心配させて。バレリイ嬢の伝言で引き留めるとは聞いたけど、時間が過ぎても帰ってこないのでいろんな事を想像したわよ。なにしてたの? なぜほほが赤くて目が輝いているの? 冒険したの? 話して」
「フフフ、千夜一夜物語です。まるでアラビヤンナイト漬けです。あなたが疲れていなければ全部話します。あなたなら話しても安全ですから」
半時間ほどエルシは夢中になって聞いた。ただアーノットという名前が出てきたときだけ、異常な関心を示した。真っ青になって、息を荒くして言った。
「とても奇妙で不思議です。あなたを驚かせた男の名前はアーノットだと言わなかった? どんなひとでした?」
「やせて陰気で、眼光の非常に鋭い男でした。黒い瞳の目が据わり、とても知的で、昔は妙な魅力があったでしょう。ひどく悩んでいました。誤審の被害者だと言っていました。でも名声を回復できる男がいるとも。その男の名前はハースコートです」
エルシが両手で顔を覆い、わっと泣きだして、言った。
「同じ人だわ。きっと同じです。何年も昔、子供の頃からあの人は新聞に投書し始めました。投書名はアーノットという名前でした。そう、遂に見つけたのね」
「とても関心がありそうね」
「ええ、それどころかアーノットは私の婚約者でした。アーノットが起訴されたとき私はパリで洋裁を学んでいました。実父が少し前に死んで、牧師館で遺産を売って借金を払ったら、手元に何も残らなかったので、故郷のデボン地区を捨てて自活しなければなりませんでした。アーノットは感受性がとても強く、収監されたとき私に手紙をよこし、二人の間は終わったから汚名をそそぐまで会わないと伝えました。刑務所へ行っても面会を拒否されました。伝言は僕のことを忘れてほかの男を幸せにしろでした。もしまだ私が独身で、アーノットが釈放され汚名が晴れたら私の所へ戻ってくるかもしれないが、望みはほとんどありませんでした。その日から今日まで会っていません。それをあなたが結びつけてくれた、本当に。アーノットを説得したいのです、何があっても私は変わりません。分らせたいのよ、アーノットは私の人生も自分の人生も投げていると。あまりに度が過ぎます」
*
翌日妙に気が抜けて何の収穫もなかったのは、前日熱狂の冒険の渦に巻き込まれたせいだ。また妙なことに二日経っても、バレリイ嬢から何の連絡も無い。
アイダがものすごく心配になり不安になったのはグレイのこと、朝刊も夕刊も詳しく読んだが、手がかりは一行もない。イブニング・ニュース新聞をいらついて放り投げようとしたとき、次の記事が目にとまった。
『今日の午後、オクスフォード通りで妙な事件が発生した。少し色あせた服装を召したご年配のご婦人と、外国商人との間にいさかいがあった。後者の商人は売り物の石膏像を頭に乗せていた。ご婦人が店の飾り窓を眺めていたとき、前述の行商人が呼び止めて、あなたはボーン国のゼナ王女かと、興奮して問い詰めた。余計なお世話ですと言われて、ご婦人に暴力を振るい、つけカツラを引っぺがしたので、群衆が面白がり、どっと集まってきた。ご婦人は警察に保護を求め、石膏売りは逃げなかったのでつかまってしまい、激しく暴れて抵抗した。警察がご婦人を探したが姿はなかった。この事件が奇妙なのは、思い起こせば同王女がロンドンにいると信じられていることと、親友や親戚から身を隠していることだ。同王女はこのような変装が好きだと言うことから、石膏行商人の言うことにも一理あるかもしれない。現在、警察が事件を調査中』
アイダが記事を二回も読み、エルシに見せようとしたとき、女宿主が扉から頭を入れて、ぶっきらぼうに言うことに、老婦人がアイダに会いたい。衣装の乱れた人物がよろよろと部屋に入り、椅子に腰掛けた。帽子、顔隠し、カツラを脱ぎ捨てると、半ば怖れ半ば嬉しそうな王女の顔が現れ、こう言われた。
「おや、もうこんな時間ですの。スパイに見つかってしまいました。わたくしの腕を掴もうとして暴力を振るったので警察に逮捕されました。グロブナー広場には戻りませんでした、監視されているといけないので。四時間ぐらいさまよいました。その時、きのうアーノット氏があなたの住所を言ったのを思い出しました。ここへはつけられておりません。すぐバレリイ嬢に私の居場所を知らせて下さい。この数日悪いこと続きのようです。グレイ氏も姿を消しました。バレリイ嬢の部下が家の近くにいましたが、もぬけの殻だそうです。みんな逃げました。始めから出直しですね」
実に驚くべき情報だ。もしグレイが川べりのあの家から連れ去られたのであれば、この数日の努力は水の泡だし、たぶん取り返しがつかない。いまになってアイダが我が身を責めたのは、あのませた子供に接触しなかったことだ。
実際、はっと思い出したのは約束を守るどころか、ダイヤの代金すら払っていない。果たして子供を見つけられるか。
そのとき部屋の扉がまた開いて、しわがれ声で言うことに、子供が通路扉の所でアイダを待っている。アイダが驚喜して年長の女の子を見た。
子供が甲高い声で言った。
「ねえちゃんはひでえ、とんだ詐欺師だ。何もいうな、一ポンド七シリング払え、けりをつけろ」
第二十一章 即決
一瞬、子供に約束を守らなかったと言われても、アイダはへこまなかった。だって、思いもよらぬ幸運だもの。女の子は怒っているが、当然のことであり、この場合当たり前、というのもアイダがきっちり約束したのに、故意に約束を破ったようにみえるからだ。
女の子の顔は怒りに震え、目が激しく燃えている。だがアイダは全く平気だった。むしろ希望に打ち震え、この浮浪児がグレイの居場所を教えてくれるのじゃないか。グレイは誰かに連れ去られ、予測しがたい複雑な状態になったが、いまこそアイダが情報を握る立場になり、それこそ外務省が大金を払ってでも欲しがりかねない。
アイダが言った。
「中におはいんなさい。えーと、お名前はなんでしたかね」
女の子が怒って言った。
「いわねえ、なんにもならねえ。でもアニーだ、なんの役にたつか。もうきくな、なんもねえ。中にはいらん。ほしいのは金貨だ、もらうまで動かん」
「じゃあここで待ってちょうだい、二階へ上がってお金を持ってくるから。ごめんなさいね、すっかり忘れてしまって。色々あったもので」
女の子が生意気にウィンクして親指を突き上げた。こりゃ、おりで暴れる小猿に似ているなあ。
「わかった、見ているから逃げられんぞ。いいきみだ、行け」
アイダが息を切らして階段を上がり、狭い居間に駆け込み叫んだ。
「大変な幸運ですよ。グレイを見つけられるかも知れません。下に子供が来ています。話した子供です、例の……」
アイダが混乱して止まった。危うくゼナ王女にダイヤモンドの話をするところだった、バレリイに堅く口止めされていた。宝石のことに関しては、エルシにも言ってはならない。
「いやあ、忘れていました。王女さまは子供のことは何もご存じないことです。子供達にずいぶんお世話になって、お金を渡す約束をしました。あのときお金を持っていなかったので、すっかり忘れてしまいました。どうやってここを見つけたのか分りませんが、子供が戸口階段の所で怒って、お金を要求しています。申し訳ありませんが、どちらからお金を借りなければなりません」
王女が言われた。
「いっぱいありますよ。大きなハンドバッグに金貨がいっぱいはいっています。アイダ、欲しいだけお取りなさい。なぜお入りなのですか」
「簡単なことでございます。この子供達の一味にグレイがからめとられています。一味は警戒して引っ越したのでございます。子供達も一緒に越したので一階にいる浮浪児に
アイダは遠慮なく王女の財布からお金を抜いて通りへ出た。きらきら光るソブリン金貨一枚と更に半ソブリン金貨を一枚、アニーの汚い手に渡した。女の子の顔が魔法のように変わった。
「ねえちゃんはワルだと思っちゃって」
と女の子がキッキッ嬉しそう。
「
「医者にきいた。医者はいい人だ。薬をとりに行くたびにいつも一ペニくれる。あんたも一シリングくれると約束したと医者にいった、あんた医者の友達だろ。医者がいってた、ねえちゃんの名前はバレリイ、グロブナー広場四五Aに住んでいる」
これにはびっくりだ。あの医者がこれだけ知っているとは実に変だ。でもこのおませな子供によけいな事を
「それからどうしたの?」
「そこへ行ったよ。ドンドン扉を叩いて、ねえちゃんを呼んだ。会ったら、そっくりだったねえ。お小遣いをもらったし、ここをおしえてもらったんだ」
「そういうことね、ふふふ。妹や弟はどうしているの? ぜひ午後に会いたいわね。えーと、住所は?」
「同じじゃない、しっ、引っ越した。夜逃げのようだったが何もきかねえ。しりすぎちゃだめだ、ねえちゃん。いいことがあればあたいがここへ来て、会えるさ」
「それが一番いいわね。ところであなた、ロンドンから田舎へ行きたくない? 小さな家に住んで、一日中ウサギやアヒルを追いかけ、いっぱい食べて、遊びたくない?」
女の子の顔がほころんだ。
「一回行ったよ。仕事でみんなと行った。最高だったねえ。ねえちゃんも一緒に遊ぼうよ。行こう」
「いまはだめ。お礼に一つか二つやってくれれば、駄賃にお金をいっぱいやるわよ。協力してくれない? 今晩九時、例のパブの外側で。グリーンマンじゃなかったっけ? 何通りだっけ?」
アニーが通りを教えた。もう警戒も疑ってもいない。
「よっしゃ。そこへ行くよ。お金が転がっているかぎり信用すらあ」
アニーは、ぱさぱさの頭をえらそうに振って、遠くに聞こえるオルガン演奏に合わせて、とっとと歩いて行った。アイダがエルシに短く事情を説明した。
「どうするつもりなの?」
とエルシが
「今晩寝る前にグレイを見つけます。あの子に午後九時に会いますが、もちろん一人で行きません。ああ、数ポンドあったらなあ。とても役に立つのですが」
すかさず王女がテーブルのハンドバッグをつかんで中身をアイダに手渡した。有無を言わせないし、アイダが一ペニでも返したら怒りかねない。四十ポンドなんて些細な金額だ。そんな金額が何だっていうの、気まぐれにそれぐらい使うのは朝飯前だ。
王女が陽気に言われた。
「これで決まりましたね。私は暗くなるまでここにいて、それからタクシーでグロブナー広場へ帰ります。勇敢なアイダはどうするつもりですか。冒険するつもりですね。目がきらきら輝いていますよ。グレイを助けに行くのですね。でもどうか一人で行かないように」
「一人では行きません。自信がありませんし、失敗するかも知れません」
およそ一時間後、王女が夜陰に紛れて家を出ないうちに、アイダは勇気を出して冷酷な女家主と掛け合った。未払い家賃を支払い、黄金色のソブリン金貨を二、三個見せたら、渋顔の強欲女に絶大な効き目があり、大満足して、下にも置かない扱いだ。
「お嬢さん、それなら何とか出来ますよ。いや絶対出来ます。一階にいい寝室と居間があります。野暮なことは
「ええ、それで決めましょう」
とアイダが納得して、また二階へ上がって行った。
「さあ、これからどうするの? 誰に相談するの?」
とエルシが
「アーノット氏とトラスコット医師も、きっと信頼できます。でもアーノット氏が適任者ですので、ここへ呼び出します。電話番号を覚えています、昨晩バレリイが電話して呼び出すのを見ていました。近くの通話所で料金を払い、連絡がつくか見てきます。いまはアーノット氏以上に頼りになる男性はいません。さあ、これからどうするか当ててごらん」
「やけくその表情ですね」
「そうよ。あの女の子に
「ここへ来るようにお願いして」
とエルシがおずおず言った。
「エルシ、もちろんです。あなたはいずれ会わねばなりませんし、アーノット氏はあなたに謝るどころじゃないでしょう。いえ、もう聞く耳は持ちません」
一時間経ってからアイダは戻って来たが、その間にアーノット氏と電話で話したばかりでなく、日刊センティナル新聞社で簡単な話もした。アーノット氏はアイダの提案に喜んで賛成し、二、三計画の上乗せをして、アイダもそれを認めた。
アイダがエルシに説明した。
「アーノット氏はすぐ来ます。どっきりの件は言いませんでした。あなたも気をしっかり持ってね」
エルシは抗議しなかったが、妙に沈んで、おとなしかった。時計が午後八時を打つと、アイダが一階へ降りてやがて、アーノットと一緒に現れてこう言った。
「こちらは私の友人エルシです。あなたの古い友人だそうですね、アーノットさん」
第二十二章 とば口
アーノットから血の気がゆっくり引き、引きつった真っ青な顔は、ふさふさの黒髪と黒い瞳に比べ、著しい対比をなした。それから恥じて薄赤くなり、アイダに向かい合った。目には、おそらく非難と怒りの気持ちがある。こう言った。
「
アイダが受けて立った。
「どうして。私を助けると同時にあなたの立場もよくなります。過日の舞踏会では率直にお話し下さったので、いま私も率直に言いましょう。あなたはいずれエルシ嬢にお会いするはずですし、この場で将来が大きく変わると思います。しかもあなたにはエルシ嬢に説明する義務があります。私は席を外しますから、どうぞ説明して下さい」
アイダが扉を閉めて、エルシとアーノットを対面させた。エルシが真っ青になり、身震いし、涙を浮かべた。だが目には決意がみなぎり、落ち着き払い、決然と相手を見据えた。
「妙な出会いだね」
とアーノット。
「妙なことになりました。あなたは別人のようです。自己
「知らない」
「そうでしょうね。私のことはよく分っているくせに。あなたは自分のことで目一杯のようで、それを胸に抱きしめて、自分と私への義務を忘れています。何の権利があって私達の人生を駄目にするのですか。あなたの言葉は覚えています、つまり私に自由を与えるが、もし名誉が回復して私の気持ちが同じだったら、私の元へ戻るって言ったわよね。そんなのまともな女性が親切だと思う? 有罪だと私が信じているとでも? 絶対信じていないことはあなたも知っている。あなたの一番悪いところは恐ろしいほどのうぬぼれです。まだ残っています。この世で無実の罪に苦しんでいるのはあなた一人ですか。あなた、稼いでいるのでしょう?」
最後の一言がアーノットの胸にこたえた。
「え、ええ。最初から稼いだよ。確実に欲しがりそうな記事を、ある新聞社に提供出来たんだ。独自の秘密情報源があったからね。ああ、金銭的な面ではたんまり儲けたさ。年間千五百ポンド、いやそれ以上稼いでいる」
「ほんとう? アーノット、私を見てごらん。見て何か分る? 前のようにきれい?」
アーノットの言葉は熱かった。
「もっときれいだよ。僕の目にはいつもきれいだ。愛せなくなったとでも……」
「いいえ、そうは言いません。そうなれば残酷な悲劇です。私を愛していますが、自分の虚栄心をもっと愛していますね。私はもう昔の私ではありません。ほほはこけ、目は充血し、色香もなくなっているのは肌の手入れをせず、不安から逃れられないからです。きっと健康は取り戻せます。また郊外へ連れて行って下さい、そうすれば新鮮な空気を吸って、女性本来の生活をして、失った若さも取り戻せます。私が厳しい戦いをしたことを知っていますか。この四年間、厳しい生活を強いられ、時には食べるものもありませんでした。私が不安で押しつぶされそうになっている時に、そばにいて守ってくれるはずの人が週に三十ポンド稼いでいるのですから。私の六ヶ月分の稼ぎですよ。途中いろいろな人に出会いましたが、ひょっとしたら……。いやそれは言いません。私が苦しんでいるのは信用と信頼が壊れ、愛を求めた人に心を捧げたのに、その人が災難に遭ったら、私に背を向けたことです。私も悲劇を感じるべきだと決めつけたのです。私に強いたでしょう、アーノット」
アーノットが頭を垂れ、返事出来なかった。葛藤の真っ最中に心がまばゆい光に照らされた。必死に
「全くきみが正しい。エルシ、僕はなんてわがままだったんだろう。いつでもきみが欲しい、何て悪だろう、言えずに。汚名をそそぐことに凝り固まっていた。心がふさがれて何も見えなかった。もし一緒になれたら――」
「ああ、それ以上言わないで。私が怒っているように見えても気にしないで。でも無駄な年月が恨めしい、ずたずたにして放り投げた年月が。それがいま……ああ、アーノット……」
エルシが震える手を差し伸べると、アーノットがしっかり受け止めた。エルシが体を倒すと、アーノットの肩に頭が当たり、まるで疲れ果てた子供のようになった。アーノットがやさしく抱いて、ささやいた。
「僕を本当に許してくれるかい? エルシ、僕はなんて馬鹿だったのだろう。きみはここから出るべきだ、きみはこの惨めな境遇にもう耐えられない。きみの欲しいものはすべて与えよう」
エルシがぬれた瞳を開けてアーノットを見た。二人の唇が合った。それからエルシが優しく体を離して、言った。
「アイダのおかげです。恩義があるので自分の幸せだけに浸れません。だってアイダも困っているもの。やるべき事がたくさんあります。アーノット、アイダを助けてくれませんか。あなただけが頼りなのです」
「全力を尽くすよ。まさか、アイダとグレイの間に何かあるんじゃないか」
「時間の無駄ですよ、そんなことを訊くのは。ほらアイダが来ました。アイダが教えるでしょう」
アイダが部屋に入る様子はしてやったり、澄まして事務的に言った。
「お話は終わったようですね。さあ、アーノットさん、今度は私を助けて下さい。して欲しいことは既に説明しました。一緒に行くとお約束してくれました。トラスコット先生も仲間に入れたいのですが、見つける方法が分りません」
「簡単です。名前がトラスコットで、ロンドン大学医学博士号を持っており、波止場近くで開業していると言いましたよね。新聞社へ私が電話すれば、医者住所録で調べてくれます。でもアイダさん、私なら絶対に行きません。私と医者に任せた方がずっといいですよ」
「それには賛成できません。第一、どうやって子供を見分けるのですか。たとえ分ったとしても、絶対に信用しませんよ。疑ってすぐに煙に巻きます。あんな見事な子役俳優に会ったことはありません。子供の口からまことしやかな嘘がぽんぽん出てくるのは衝撃的です。私抜きで行くというのはもってのほかです。私はちっとも恐くありません」
アーノットが感心して言った。
「それは確かですね。行きましょうか。タクシーを捕まえて、事務所でトラスコット先生の住所を調べましょう。それから郵便局へ行き、トラスコット先生に電話して九時半にグリーンマン・パブの外で会うよう連絡します。だが待てよ、電報を打とう。先生は少し遅れるだろうが、子供はそれまで引き留められるでしょう」
実際、九時半近くなってからアイダとアーノットがグリーンマンという派手なパブの真向かいに着いた。パブは通りの中央で
五分、一〇分過ぎても子供の来る気配がない。アイダが心配で不安になり始めたころ、ぼろ服を着た小さな影が見え、電飾を背景に主役の登場のようだ。アイダが道路を渡ってアニーの腕を捕まえた。
「来ないかと思ったわ」
子供が半分けんか腰に言った。
「九時からきてた。十五分間みてたぞ」
「じゃあ、なぜ話しかけなかったの?」
「あたいを誰だと思ってるんだい。無邪気なガキがこそっと知らせたさ。あんたは一人でくるといってたじゃねえか。向かいの道路をきどって歩く男は誰だい? 学務委員にも職業学校教官にも用はねえ。あたいは学校なんかいかねえ。読み書きなんかしたくねえ。まいにち酒場ではたらくんだ」
アイダが思わず笑って言った。
「ふふふ、約束は守っていますよ。向かいの紳士は私の友人で、職業学校とは関係ありません。田舎へ連れて行くと言ったでしょう。その前にやることがたくさんあるのよ。それで手伝って欲しいの。今どこに住んでいるの?」
「ハイドパークだ。時にはそこだ、時にはバッキンガムパレスだ。気分しだいだ。まあ、パリが好きだが」
依然として疑っており不安なようだ。アイダが向かいの道路を見ればほっと一安心、みすぼらしい無精な格好のトラスコット先生が熱心にアーノットと話をしている。
「ほら、お友達のトラスコッット先生ですよ。私を信用しなくても先生は信用するでしょう。先生がいいと言ったら私の言ったところへ案内してくれる? どうしても紳士に会いたいのよ、あなたの家で寝ていた病気の紳士よ。会わせてくれたら欲しいものは何でもあげますよ。もし危ないなら……」
「はんぱない」
と子供がつっけんどんに言った。
「まあ、危ないじゃないの」
子供がぐっと息をのんだ。汚れ顔がこわばり、真っ青になり、唇を震わせ、ささやいた。
「しっ、わかった。その気きならあんないする。こっちへこいと連中にいえ」
第二十三章 男爵の一手
グラスゴウ殿下がグロブナー広場へ大股で歩いて行く様子はこの世に悩みなどなく、人生は楽しむためにあるという風だ。礼服がぴったり合い、つやつやの帽子が陽光に輝き、完璧に折り目のついたズボンの下にはぴかぴかのエナメル靴を履いている。どうやら上流階級の紳士が単に友人と昼食するみたいだ。実はまさにそれが目的だった。
やがて立ち止まり、ルペラ男爵邸のベルを鳴らし、半時間ほど男爵夫人とたわいのない話をした。二時近くになり、ルペラ男爵が大型車でご帰還になり、遅れたことをわびた。グラスゴウ殿下が言った。
「ルペラ男爵、わびなくても。一体どうやって抜け出すことが出来るのですか。本当にすごい人ですね。一年間で自宅昼食できるシティの大物は何人いますやら」
「出来ればそうした方が良いですね。何よりこの中断が大事です」
やっと最高級の昼食が終わると、男爵夫人が優美なクロテン毛皮を召して、音楽会へ出かけ、男二人が取り残され、葉巻やコーヒーを飲みながら、男爵が珍しい酒をふるまった。時たま友人にしか出さない代物だ。面白い形をしたボトルが目の前に来たとき、グラスゴウ殿下が眉をつり上げて言った。
「男爵、二人とも忙しい午後の最中です。嘘の口実で私を誘い出し、男爵夫人がいなくなるのを
「グラスゴウ殿下、あなたの事務所ほど重要なものはなく、ここの仕事とは比べものになりません。でも、私はこれに時間をすべて
「何もありません。三日間、収穫無しです。そのうえ駐独英国大使に能なしと思われました。大使は重大事と見なしておられ、その通りです」
「じゃあ、新展開はないのですね。でも連中が手紙を持っているとは思っていないのでしょう」
「確実に持っていません。持っていたらとっくに売り払っています。手紙も得られず王女のダイヤにも触れていません。ダイヤは獲物の一部になるはずでした。お分かりのようにハースコートと株式仲買人とが結託して手紙を取ろうとしました。バンストンとエイビスはダイヤのことを知っていたが、ハースコートには言わないと決め、本件では三者の信頼はありません。私は連中に雇われた手下を知っているが、よくあることです。手紙に関しても、我々同様に手下は全く知らない」
ルペラ男爵が新品の煙草に手を伸ばしてにやりとして言った。
「それを聞いてほっとしますね。でもどうあろうと私は動きますよ。英国政府は遅れが致命的だと分っていません。私はバンストンとエイビスを追い詰める方法を考え抜いて、連中に思い知らせます、何年も記憶に残るような仕置きです。ご覧なさい、グラスゴウ殿下、大儲けのチャンスです」
目の前の大型封筒から、ルペラ男爵が大きな試し刷りを取り出した。事実上、日刊センティナル紙の第一面を飾るものだ。
「これをご覧下さい。地中海石油株式会社の設立趣意書です。一株一ポンド株式を千五百万株公募します。五百万株の優先普通株式は設立者が保有します。金融用語でうんざりさせて申し訳ない。私が停止命令を出さない限り、明日の欧州主要新聞すべてにこの設立趣意書が掲載されます。ご覧のように取締役には数人の大物の名前が載ります。大物の威力だけでも、ロンドンで四、五倍以上集まるでしょう。設立趣意書には数値がなく、最少情報だけです。大衆は名前だけを信じて投資するでしょう。さて、グラスゴウ殿下、半時間以内に私の腹心の秘書が電話をかけてきて、命令を尋ねるでしょう。私が待てと言えば遅れるし、行けと言えば進むでしょう」
「男爵は実に大胆ですね」
「シティには私ほど大胆な人はいませんよ。で、どうですか、グラスゴウ殿下」
「ええ、私の忠告が為になればいいが。男爵はこれに大金を投じていますね」
「全財産ですよ」
「もし失敗したら?」
「破産しますね。でも失敗はしません。そのうち証明しますよ」
グラスゴウ殿下があっさり言った。
「率直に言えば、私は一ペニも投資しません。まあ、気にしないで下さい。全くのギャンブルに見えます。石油埋蔵を信じておられるようですね。でもあなたの成功は手紙次第ですよ、ロンドン東部のどこかに隠されている。手紙が見つからなければ成功しません。もし手紙が見つかり敵に取られても同じ事です、新聞社に売られて世間に公表されます。逆に王女の手に渡れば、あなたの事業は大成功です。男爵は二対一で不利です。だからどう見ても私は投資しません。もし二つのどちらかに当たったら、あなたは破産します、ボーン国王はあざ笑いの的に成り下がり、妹の王女に仕返しをします。ここが重要です。ボーン国王が復讐して王女の領地を没収して、その場合あなたの優先株式は紙くずになります。ドイツに訴えても無駄です、ドイツは必ず何らかの言い訳をしてボーン国王を支持し、採掘権をドイツのものにするでしょうから」
「では私が狂っていると?」
グラスゴウ殿下が慎重に言った。
「みんな時々失敗しますよ」
男爵が試し刷りを拳でぱしゃと叩いた。口がへの字、目が点だ。ほとんどささやき声で言った。
「へまはしない。すべて考え抜いた。殿下の説を簡単に言えば、内閣か国王が権力を持ち、戦争だとか、平和だとか決めることになります。欧州にはそんなことが出来る君主は一人もいません。たとえばある君主が親類王国に軍事行動を起こしたとしましょう。英国大財閥は気に入らないし、ロンドンやパリやベルリンの金融大物も首を横に振ります。我々は
「全く、男爵が正しいですね」
「そうでしょう、グラスゴウ殿下。当然私が正しい。でもこれで終わりじゃない。ハースコート、エイビス、バンストンをとっちめるつもりです。最近連中が私をしょっちゅう負かしたので、この機会にも飛びつくでしょう。ルペラは狂っていると言いふらします。連中は例の手紙を入手できると思っています。手紙をボーン国王に高値で売りつける算段です。そうすれば私の優先株式は紙くずになります。一方、連中は新会社を立ち上げて欲しい顧客に株式を売るでしょう。十万株も売って、気づいたときは後の祭りです。連中は株式の引き渡しを求められるでしょうが、一株数シリングで売った株を一株数ポンドで買い戻しできなければ、完全に破産します。自ら墓穴を掘ったようなもので、確実に私の手に落ちます。ですからグラスゴウ殿下、二人の危険人物を排除できます。世間に名前を公表し、みんなが正体を知ります。そこで一つお
「実はそうです。アイダ嬢が私に見せました。話しましょう」
と言って、グラスゴウ殿下が手短に話して、きっぱり締めた。
「全く奇怪でしょう。この宝石は私が保管すべきでしたが保管しませんでした。アイダ嬢に戻しました。きっとバレリイに見せると思ってね」
「それで、見せたのですね」
「確かに今バレリイ嬢が宝石を持っています。ゼナ王女はそれを知りません、というのも王女がそれを知ったら質に入れかねません、ちょっと金欠ですから。男爵はダイヤを策略の道具にしますか」
「それはあとで言いましょう。さて、バレリイ嬢の所へ行って話しませんか」
第二十四章 囚人
グラスゴウ殿下が言った。
「男爵は私同様バレリイ嬢をご存じでしょう。バレリイ嬢に電話してください。在宅なら直行しましょう」
バレリイ嬢は在宅しており、男爵と殿下に会うのを楽しみにしていた。バレリイ嬢が挑戦的な目をして、グラスゴウに手を差し伸べて、こう言った。
「穏やかじゃありませんね。賢人が二人も押しかけて、どうされたのですか」
グラスゴウ殿下が応じた。
「白旗を掲げてやって参りました。バレリイ嬢は昔からの競争相手で、何回眠れぬ夜を過ごしたことやら。鮮やかな武器でいつも対戦されました」
バレリイ嬢が抗議した。
「信じて下さい、私は敵ではありません。見かけで誤解されるからです。いつか申し上げますがこの三年、私の人生最大の目的を」
「知っていますよ」
とグラスゴウ殿下がつぶやいた。
バレリイが赤面し、目が
「あなたの仕事はすべてを知ることです。当てたようですね。残念だったのはウォルタ卿に会えずベルリンへ帰られたことです。大使との会見を大いに楽しみにしておりました。グラスゴウさんが手紙や口頭で調整されたとか。ウォルタ卿を説得できたかも知れませんが、わがままは言えません。こんな感傷的なことを議論しにここへ来たのではないでしょう。ルペラ男爵のご用件は?」
「そうですね、バレリイ嬢なら簡単な質問に答えられるでしょう。グラスゴウ殿下から聞いたのですが、あなたに変装した女性のことです。その女性が石を手に入れてそれが模造品だとか。さて、今あなたが持っておられるか、本物か、おっしゃって下さい」
「私の金庫にあります。確かに高価な物です。ゼナ王女のダイヤであり、グレイ氏がベルリンから運んできたものです。王女には話しておりません。というのも、王女はとても衝動的な浪費家ですから、いずれお金が足りなくなります」
「その宝石を見せてもらえないですか」
と男爵が要求した。
「もちろん。王女は二階の寝室におられ、いま私は私用だとご承知です。邪魔はされません。宝石を持って来ます」
やがてバレリイ嬢が戻って来て、宝石箱をテーブルに置いた。男爵がよく鑑定してからバレリイ嬢にこう訊いた。
「特別なお願いがあります。バレリイ嬢、私をどの程度信用しておられますか」
「私自身と同じくらい信用しています、ふふふ。自分を差し置いてでも、あなたを信用して物事をゆだねますわ。これ以上申し上げられませんけど」
「そこまでは要求しませんよ。お願いを聞いたらきっとびっくりするでしょう。この宝石を二週間私に貸して欲しいのです。そっくりそのまま借りたいのです。お願いは極めて異例でばかげていると思われるでしょうが、この宝石を短期間私に預けて下されば、ようやくのことで大悪人を退治できます。今決断する必要はありません。一、二日よく考えて下さい」
バレリイ嬢が考えて言った。
「男爵はとても賢明なお方です。最高でしょうね。もしそうする重大な理由がなければ、決してそんなお願いはされないでしょう。良ければ宝石箱を持って行きなさい。ただし受領書は書いて下さいね」
男爵が何を考えているのかグラスゴウ殿下に興味があったにしろ、分らないだろう。というのも、もう宝石の事に触れなかったからだ。それも妙だが、もっと妙なのは男爵の次の言葉だ。
「それではみなさん、数日おいとまします。計画を進めることにします。すべて順調ですから私がシティに一、二日いなくてもいいでしょう。ここだけの話ですが、今日の午後ロンドンを離れ、ボーン国へ行きます。現地を電撃訪問します。そして戻って来たとき――」
男爵が意味深に言葉を区切り、グラスゴウ殿下に片手を差し伸べた。
*
男爵は一時間後、海辺へ急ぎ、二日後、小型漁船から殺風景な岸辺に降り立ったところが、地中海に面したボーン国だった。
しけた小屋が数棟、生気のない漁師が数人、荒れ果てた岸壁が主たる風景だ。だがルペラ男爵の心眼には、このわびしい荒れ地の将来がいろいろ見えていた。世界的天然良港として、波止場や店舗や荷下ろし場が並び、時が経てばこの小さな港が文明の辺境地で重要地になるはずだ。
今度だけ明らかに漁師達の注意を引き、数人がけだるく興味を示したのは、すごい大型自動車が村通りの先端に待機していたからだ。黒いあごひげと、鋭い灰色瞳の大男が毛皮帽子に触ったとき、ルペラ男爵が旅行バッグを持ち、車に近づいてきた。
「デントン監督、やっと着いた。どうだ、
デントン監督が近づいて答えた。
「男爵、上々です。最近労務者にいくらか不安がありました。無学な労務者は従順ですが、ばかばかしいほど迷信的です。もちろん我々の仕事が分らない連中を採用せざるを得ませんが、我々が油を取って悪いことをしているとか、特に火が出たときなんかそうですね。世界の終わりが来るんじゃないか、我々が悪霊を解き放っているんじゃないか、そんな馬鹿なことを言っています」
ルペラ男爵が言った。
「それも長くは続かないだろう。今頃欧州中が地中海石油株のことを話題にしている。広く知れ渡った。全世界から仕事にあぶれた頑強な男どもを集めねばならない。それがここへ来た一つの理由だ。慎重に進めないと食糧危機、いやもっと悪いことが起こりかねない。鉄道は三百キロ以内にないからトラック輸送を構築して、店やテントや工具はもちろんのこと、必要な機械も持ってこなければならない。だが詳細はとっくに検討済みだ。問題は労務者が続くかだ」
デントン監督が説明した。
「うまく管理しています。大規模な刑務所があって、囚人には充分な仕事がありません。定期的に五百名採用する契約を結び、まあ満足しています。一番の利点は口が重いことです。私の住居は粗末で即席ですが、男爵には寝室と食事を提供します。それに小屋はとても温かいですよ」
大型車が道路を行けども行けども無人だ。平坦で単調な田舎を突っ走ると、夜のとばりが降り、あたかも文明が消えたかのよう。やっと平屋に着いてみれば、周りにたくさんの小屋があるところに車が止まった。
平屋は一部屋しかなく、床に羊皮が敷かれ、中央にストーブがあり、真っ赤に燃えて、暖かい。デントン監督がフライパンでハムの缶詰とピータンを調理して、お粗末な料理と未熟なワインを出し、それが全料理だった。だが男爵は疲れ果てて空腹だったのでえり好みしなかった。
食事が終わると、キセル煙草を吸い、多少うとうとデントン監督の話を聞いた。しかしながら、翌朝、夜明け直後、羊皮から起き上がり、朝食前に油田へ行った。
今は巨大産業の片鱗もなく、あるのは機械が少々、小屋が並び、与えられた仕事を労務者がのろのろやっているだけ。男爵が肩をすくめた。男爵は事業家だ、このざまにいらついた。
早朝だったが、真っ黄色の服を着た労務者の一団が一キロほど離れて作業している。真剣に働いているので、男爵の機嫌が直った。労務者が何者か想像はつく、というのも六人の男が羊皮外套を着て、軍隊帽子をかぶり、目を光らせ、手にライフルを持ち、監視監督しているからだ。
男爵が独り言。
「朝食後に見に行こう。哀れな囚人が金を稼いでおる」
デントン監督も全く同じ考えだ。一時間かそこらあと、ルペラ男爵の横に立ち、囚人に囲まれて、自分の計画がうまくいっていることを誇ってにんまり。囚人は魅力的な連中じゃないが、やせ衰えて青白い顔で、男爵達にあちこちで同情を訴えた。
うつろな目をした手足の汚れていない一人の男が手押し車を押して、二人の横に寄ってきた。男は止まらず、ほとんど顔を向けなかったが、デントン監督の英語が聞こえると興奮しているようだった。
男が言った。
「私に注目しないで下さい、見ないで下さい。ここは危険です。用心して、いい武器を持たないと、安全じゃないです」
男はそれ以上言わず、ゴミ山の方へ手押し車を押していき、そこで空にした。
男爵が驚いた。
「妙だな。どういう意味だ。なんであんな英国人がここにいるんだ。間違えなければ、あれは紳士だな。ここにいよう、あの男は手押し車を空にしたら、またこの道を戻ってくる。何か情報が得られるぞ。ぜひ真相を突き止めてやる」
男が一輪車を押してゆっくり戻って来たので、直接話すために男爵が近づいて言った。
「我々ならあなたを助けられるかもしれない。名前は? なぜここへ?」
囚人が低い声で答えた。
「長い話になります。助けられないと思います。あとは名前がジェフリ、駐独英国大使の息子です」
男は一輪車と去り、残った二人の男は混乱するばかりだった。
第二十五章 秘密通路
アイダは歩道に立ちどまり、子供の心を読もうとした。確かアニーは今までそんな厳しい顔をしたことがなかった。危険があるから心構えたのだろう。
「よくわかったわ。あなたを巻き込みたくないからお姉さんが助けてあげる」
「やらん、案内せん。ばれたら、あたいは殺される。もし案内したらあした逃げなくちゃなんねえ。あんたなんかにわかるもんか」
子供の声が震え、目に涙があった。見たことのない感情を表わした。この哀れな浮浪児にバレリイ嬢が興味を持ったとしても無理はないし、もしこの子の口利きでグレイが解放されたら、アニーはそんじょそこらの浮浪児じゃない。
「お姉さんはあなたの味方ですよ。今の苦しい暮らしから救い出してあげる。ここでちょっと待っててね、あの紳士に話してくるから」
アニーが率直にうなずいた。アイダがトラスコット先生の所へ行き、紹介した。
「こちらは私の友人のアーノット氏です。私のお手伝いに来てくれました。私達の関心はあなたの患者、つまり過日の晩、川べりの家で見た紳士のことです。先生はまだ往診されていますか。と言いますのは……」
トラスコット医師が言った。
「患者の居所が分ったら、とても感謝するよ。非常に懸念しておる。いつものように往診していたが、驚いたことに最後の往診時、家は空っぽだった。全員消えていた。いろいろ訊いたが誰も何も知らなかった。忽然と消えて、聞いた限り、近所の誰も家具を運ぶのも見ていない。やましくないこともない、というのも、警察に言うべきだったからだ。あなたが戻ってこないか待っていたが、いま会えてほっとしている。アーノットさんもお分かりのように、私の立場は良くない。本来は西部で開業すべきだが、状況が許さないので貧民窟の医師になり下がった。この地域で生活するのは容易じゃない。あの不思議な患者の治療費に受け取るギニー金貨は大歓迎だった。何か疑わしかったことは否定しないし、最初呼ばれたとき、近くの交番の巡査部長に言うべきだった」
アーノットが言った。
「さあ、どうですか。警察に言ったら良いどころかもっと悪くなります。おそらく患者は身元を知られたくないはずです。かなり良く看病されています。それを友人が知ったら――」
アイダが割り込んだ。
「何人かは知っています。もう少し先生に打ち明けた方がいいでしょうね。あの患者はグレイ氏という外交官です。英国への帰路、ある文書が紛失し、私達の推測では襲われて負傷したので、襲った連中がここへ連れてきたのだと思います。ある緊急の理由で、事件は公表されませんでした。しかし連中がグレイ氏を連れて蒸発したので、更に厳しい局面になりました。もしかしたらグレイ氏は殺されたかも知れません、今晩それを確認するために来たのです。運良くあの妙な家に関係のある子供が私に会いに来ました。この子は、いつもは恐れ知らずの図々しい女の子ですが、今さっき家に案内してくれと言ったら、ひどく怖がりました。でも案内すると言っていますので、お二人も一緒に来て欲しいのです。きっともめると思います」
トラスコット医師が言った。
「その場合、力になれますよ。私はこの辺じゃ顔なじみだから、何の注意も引かずどこへでも行ける。準備良ければ取りかかろう」
アイダがアニーを手招きして、言った。
「用意できたわよ」
子供がむっつりうなずき、道案内した。アイダにはこの辺りにかすかに見覚えがあり、やがてその感覚が確実になったのは川べりにぽつんと立つ家が見えてきたときだ。
アニーがその家にずんずん向かい、扉を開けた。中は真っ暗、無人だ。あたりに人影もなく、あたかも子供が騙したかのようだった。アーノットがマッチ箱を取り出し、火を点けて、尋ねた。
「どう思う? ここに我々の尋ね人はいないようだが」
女の子が言った。
「あたいが見せてやるから。これに火をつけろ。さあ」
アニーがポケットから蝋燭の切れ端を取り出し、アーノットに突き出し、火を点けさせた。それから階段を降りて、汚い地下室へ行くと、隅に食器棚があった。棚の中はゴミが散らかり、その下に鉄輪があり、子供が指さして言った。
「これだ、だんな。これをひっぱれ。音をたてるな。いま、ばあちゃん以外だれもいない。ばあちゃんはリューマチが痛んでねてる」
「ほかの子供は?」
とアイダが
「イーストエンドのシャドウェルへ行った。おばさんが世話してる。あたいもそこへ行くことになってるけどだれも気にしねえ。あたいが一晩中うろついても心配しねえし、家に戻らんでもかまわねえ。ここは知らねえことになってる。ただ、宿替えするとだけ言った。あたいらをやっかい払いして、よういができたら戻ることになってる」
アーノットが
「この落とし戸はどこへ続いているのか。泥棒の抜け道か何かの地下道か」
「しっ、みつゆ用だ。テムズ川にそんなものはねえと思ってるかもしれんが、あるんだ。父ちゃんが生きとるときやってた。水路が別な家につうじてる。から倉庫の下にも水路があって、ボートがつないであり干潮で使う。下へおりて好きなだけやりな。あたいの知ったこっちゃねえ。金をもらえばなんもいわねえ。もしだれか戻ってきたら知らせる。ぐずぐずすんな」
アーノットがふたを持ち上げると鉄階段が現れて、石造りの暗い通路があった。記者にもってこいの冒険であり、躊躇せずはしごを下りた。医者が続き、アイダが最後だ。アイダを思い留まらせることも出来たが、アイダは有無を言わせなかった。
「いいえ、残りません。ここで待っていたらただ恐ろしいだけです。危険があるならそっちを選びます。確実な明かりが欲しいですね」
アーノットが懐中電灯を取り出してボタンを押した。まばゆい光りで見れば、三十メートルばかり通路が続いている。
天井はアーチ型石造りで、明らかに古い。どうやら教会の地下墓地のようだ、というのもあちこちに粗雑な彫刻があり、おそらく昔の修道僧の作品だろう。
アーノットが言った。
「昔は使い道があったのでしょう。通路の説明はつきます。内戦の時、逃亡者をボートに乗せてテムズを密出国させたのでしょう。おや、ここに階段と扉があります。注意しないと」
扉の下から一条の光りが暗闇に差している。アーノットが掛け金をあげて、扉を内側に押した。そこは台所、その先に通路があり、普通の居間が二室あった。誰もおらず、無人のようだ。
だがあちこちにランプがあり、アイダが辺りを見回すと、見慣れた家具が複数あった。すぐにわかったのは、あの空き家の家財道具がこの通路を使ってここに運ばれたことだ。
「少しここに留まった方がいい。アイダ嬢、上階にグレイがいると思いますか」
「いなければ大打撃です。グレイ氏に無関係だったら、こんな奇妙な夜逃げをしますか。もしグレイ氏を殺したら、元の家にいるでしょう。不思議なのは見かけ上、地域から消えたけれども、元の家のすぐ近くに引っ越し、トラスコット先生によれば近所の人も数日姿を見ていないことです」
アーノットが指さした台所の窓は、しっかり締めてあった。
「おそらくこの家の窓は全部閉めてある。さて、アイダ嬢、グレイ氏を探しますか。見つけたらどうするつもりですか。連れて帰りますか」
アイダはその時考えていなかったが、やはり連れ帰りたい。さっと階段を上り、踊り場で立ち止まった。近くからうめき声やため息が聞こえ、すぐ分ったのはリューマチ老婆の声だ。
あとの二つの扉は開いており、三番目の扉は鍵がかかっている。だが鍵は外側から閉めてあるので、こりゃあ最終目的に近い。鍵を開けて扉をそっと開けた。
部屋には明かりがつき、暖炉のそばの肘掛け椅子に一人座っている。その人物が顔を上げると、グレイだった。グレイがアイダを見たとき、嬉しいことにグレイの目は正気だ。
第二十六章 二者択一
「グレイ、私が分りますか」
グレイがよろよろ立ち上がった。疲労
「アイダ、アイダ、本当にきみか。きみ、どうやってここへ来た。ここは危険だよ。連中はきみの首を切り、川へ投げ込むぞ、もし裏切り者と思ったら」
「それほど厳しいとは思いません、ふふふ。しかも以前ここへ来ました」
「前に来たって? 何で?」
「とにかく近くの別な家です。同じ人があなたの世話をしていました。私が来たことを覚えていますか。あのときの言葉を覚えていますか」
「結局、夢じゃなかったんだ。あの晩の不思議な夢を何度も思い出そうとした。何か困っており、何か気がかりで隠し事に迫られていた。その時きみが来たのできみに渡した。上着のことでとても困っていた。旅行するときいつも着ていた鹿毛の上着だ。きみがその上着を見つけ出して、持って行った。時々夢か幻かと思うのは、その上着がどこにも見つからないことだ。もしきみの口からあの上着は私が持っていったと聞いたら非常に安心するのだが」
「絶対安全ですよ。あなたとの再会を待ち焦がれ、どんな秘密があるか知りたいです。グラスゴウ氏から聞いた……」
「えっグラスゴウ部長に会ったの? あれ以上いい友人はいない。僕の居場所を知っているの?」
「はい、でも探し当てられず困っています。なぜ引っ越して、こんな変なことをするのですか」
グレイがいらついた。
「僕に訊かないで。グラスゴウ部長が僕の居場所を知っているのに、助けに来ないとは何か特別な理由があるな。とにかくグラスゴウ部長に伝えてくれ、手紙は安全だし、時機が来たら手渡すと。だが王女は何と言われるやら、ダイヤが盗まれたと知ったら――」
「盗まれていません。私が見つけました。金庫に保管してあります。王女にいつでも返せます」
「そのうち全容を知りたいなあ。その口ぶりでは王女を知っているようだが」
「本当のことを言うべきでしょうね、ふふふ。全部聞きたいでしょう?」
グレイはアイダの急ぎ話を、口をぽかんと開けて驚いて率直に聞いていた。
「きみはすごい女性だ。とても誇りに思う。さて、何をしたい? これからどうする? 一緒に連れて行く? 連中は不親切じゃないけど、やはり僕は囚人だ。行くべきか残るべきか僕には分らない。おっと、忘れないうちにもう一つきみに渡しておこう」
そう言いながら時計のふたを開いて、非常に薄い紙を数枚取り出した。暗号が細かく書かれている。
「これをグラスゴウ部長に渡してくれ。とても重要なものだからすぐに渡すように。それを渡せば、僕がここに長く閉じ込められようが重要じゃない。お願い……」
下から音がしたのでグレイが中断した。誰かが大声で怒っている。なにか殴ったような音がすると、拳銃のパンという音がした直後、ガラスの割れる音がした。グレイがさっと部屋を横切り、ランプを吹き消し、ささやいた。
「こんなことになるんじゃないかと怖れていた。奴らが戻ってきた。おそらく悪党のエイビスがいる。バンストンというワルもいる。不思議だ、きみの名字と同じとは」
アイダは答えなかった。全身が震え、恥辱と失望と恐怖にまみれた。グレイの腕が腰に回り、ほほに唇を感じた。
「きみはここにいてはいけない。僕のことは一瞬も考えないでくれ。足手まといになるだけだ。階段を降りられるか疑わしい。どうか行ってくれ。きみに何かあったら自分が許せない。重要なことは悪党に出会わないことだ。下がどうなったか誰にも分らない。出口を知っていれば――」
アイダがグレイにひしとしがみついた。今離れがたいのは、成功が近いし、グレイが重病だし、苦しんでいるし、看病が必要だから。
下が妙に不気味に静かなので、アイダが慎重に踊り場へ出てみれば家中、真っ暗だ。難しいのは最善の行動だ。とても知りたいのが連れの二人の様子。アーノットが拳銃を撃った確率は、おそらくとても低い。二人は成り行きを見守っているだけかもしれない。
アイダがささやいた。
「おそろしい。真っ暗だから余計恐い。あの二人に何かあったら自分が許せない。逃げられないと同時に、ここにも留まれない」
グレイが片手を伸ばしアイダの腕をつかんだ。肘掛け椅子に座らせて、自分も横に座り、腕を肩に回して尋ねた。
「なぜ? アイダ、わがままかもしれないが、僕はすべて忘れてきみのそばを楽しんでいる。ここなら安心だよ。誰もここに来ない、ただし扉の外に食事を置いて、老婆が部屋の外から時々言葉をかける以外はね。実際より症状が重いと思っているから、頻繁に見に来ない。夜明けまでここにいれば脱出は簡単だよ。もうランプは点けられない、マッチがないから。しかも、もし連れが脱出していれば、まもなく救助に戻ってくるさ」
「わかりませんか、ここにいるべきじゃないことが」
「アイダ、どうして? 我々は他人じゃない。いつかは僕の妻になるのだから」
優しく、しかし、決然と、アイダは肩に回された腕をほどいて立ち上がった。ここにはおれない。たとえグレイの為とはいえ意思を強く持たないと。
「本当に私は行きます。真っ暗ですが、この家から手探りで出ます」
グレイの伸ばした腕をかいくぐった。抱かれて腰が引け、ほほにキスされた唇の感触が強さと決心を鈍らせたようだ。これじゃ何も言わずにすぐ出たほうがいい。心なしかグレイの震え声や、愛情の繰り言が聞こえたが、手すりを掴み、慎重に下へ降りて行った。
真っ暗で静か、部屋の扉は全部開いているが、物音一つしない。じりじり進んでいくと、ぶよぶよした物体に足が当たり、ため息ともうめき声ともつかない声が床からあがった。やっとの事で悲鳴を押さえた。間違いなく男が床に倒れ、傷つき意識不明だ。もしかして足元の人物は医師かアーノットじゃないかと思うと身震いした。
手足を震わせて男の周りを探ると、一メートルぐらい離れたところで足に何かがこんと当たった。ひょっとして銃か、必死に手で探った。子供時分から銃には慣れているから、銃があればいくらか安心だ。
だが震える手に持ったのは銃じゃなかった。懐中電灯だ、たぶんアーノットが持っていたものだ。自分の位置が分る危険を冒し、小さなボタンを押した。真相を知らねばならない。足元で倒れているのは敵か味方か。
ほとんど驚喜するぐらい嬉しかったのは見しらぬ男だったからだ。仰向けになった男の顔は真っ青、目を閉じ、高いびきをかいている。そのとき、低い笑い声が暗い部屋から聞こえ、静寂を破った。
「収穫があったか」
アイダが懐中電灯を持ち上げて、周辺を照らした。通路の端に扉を見つけ、そこへ走った。扉を押したら開いた。ずっと向こうに別な通路があり、下へ通じており、小さな部屋があり、床下に水があるようだ。
明らかに川に通じている、というのもボートが二
後の方で通路を降りてくる靴音が聞こえた。震える指で、もやい綱をほどき、先頭のボートに突進した。格子をしっかと掴み、ボートを力一杯引き出し、直後に飛び乗り、水面に漂うと、無力でひとりぼっち、真っ黒な流れのまっただ中にいた。何が何だか分らないうちに、二艘目のボートが追跡してきた。
光がぴかーっ、反対側の黒いガレー船から再び、ぴかーっ。
だみ声が命令した。
「誰だ。二艘とも止まれ。さもないと逮捕するぞ。こちらはテムズ警察フェリーだ」
第二十七章 逃げ道
警察
再び光りが来ないかと期待したが、あたかも巨大な黒壁が川から立ち上がったかのようで、アイダの安全が断ち切られた。
その刹那こんなことがあろうか、ボートが押し流され、巨大な不定期貨物船の横っ腹にさえぎられてしまった。巨船の下手には多数の船があり、潮たるみが形成され、その元凶の倉庫が川に突出している。
アイダに関しては、テムズ警察艇がひょっとしたら救出したかもしれない。だが後続のボートが追いついてきて、アイダのボートに船首が当たる音を感じた。
次の瞬間、肩をむんずとつかまれた。巨大な船体に隠れて真っ暗だったので、何も分らなかった。腰をつかまれ、耳元で命令が聞こえた。
「あばれるな。あばれたら川に落ちるぞ、おぼれたくないのは我々も同じだ。立て、だが注意しろ。言うとおりにすれば大丈夫だ」
ほかに方法がなく、絶対服従しかない。冷たくて真っ黒な川を思うだけで、アイダの気持ちが
よろよろ立ち上がると、自分のボートから持ち上げられ、後のボートにひょいと移され、手荒に船尾に乗せられた。
男が言った。
「それでいい。あとをつけなければどうなったやら。ところで、お前は誰だ、名前は?」
自由になったけれども、アイダは声が出なかった。声の主が分った気もしたが、もしそれが正しければ、アイダの立場はもっと惨めなことになろう。辺りが真っ暗である限り、身元を隠すことができ、運が良ければ逃げられるかもしれないが、強制されるまで自分の名前は言わないつもりだ。
「関係ないでしょう」
とアイダ。
果たしてこの男らにアイダと見透かれなかったか、どうかな。声の調子で何か伝わらなかったか。たとえ自分だけが分っていても今までの所、知られる要因はない。冷気と不安で声が震えているもの。
別な男が言った。
「まあな。ジョーンズとかなんとかでも鎌わんさ。さてジョーンズさん、二、三、
「友人と入りました」
「それは分っている。医者とアーノットと入った。しかるべき時にお前さんをどうするかだ。医者は除外だ」
アイダはその言葉に内心感謝した。どうやら医者は厳しいことにならないようだ。
男が続けた。
「だがそれはどうでもいい。どうやってここへ来たかだ。誰が教えた。たわごとは聞かねえぞ。教えろ、一番の関心だからな。名前を教えろ、そうすればすぐ岸に下ろしてやる。もし断れば、お前の処理を考えて、すぐに実行するぞ。クロロホルム綿をかがせ、大きな外套で包み、川を下り、ヨットで航海し、あることをする。イタリアのコルシカ海岸に無一文で置き去りにされたくないだろう、ええ」
耳元ですさまじく威嚇した。明らかにこけおどしじゃない。冷たい風が川面を吹き、潮がごうごう引いているのでアイダは返事しなかった。どうなろうと、あの子は裏切れない、川べりのこの家の秘密を教えてくれた子だ。
「言いません。誰にも言わせません。個人的な理由があって、この家に来ました……」
最初の男があざ笑った。
「グレイに会うためか」
二番目の男がつぶやいた。
「馬鹿言うな」
最初の男が言った。
「名前を隠しても何にもならん。誰に会いに来たのか。上で何をしていた? どうやら家の中で何か見つけたな。見つけて目的を達した。楽しむために来たんじゃねえな。お嬢さん、書類を持ってるだろう。グレイが大切にしていた書類だよ。おめえさんが行く前にもらおうじゃないか」
アイダがすっかり忘れていたのが薄い紙、グレイが託したものだ。それを思い出して衝撃を受けた。信じられないが、男らはその存在を知っている、知るはずがないのに、知っているとは。
男が続けた。
「否定しないな。黙ったところを見ると認めている。さあ、取引といこう。書類を渡せばすぐ岸に下ろしてやる。あれこれ
「あなた方には一切関係ありません。そんな扱いをされるなら渡しません」
二番目の男がかんしゃくを起こした。
「ぐずぐずして何になる。ヨットまで川をくだろう。温かい快適なところならけりがつく」
最初の男が尋ねた。
「女のボートはどうする?」
「ああ、尻についてくる。そのあと引き潮で戻る。重要じゃないからほっとけば沈むさ。隠れ家が見つかったからもう用はない」
最初の男がぶつぶつ言うと、やがてアイダの耳にオールの水しぶき音がして、ボートが動き始めた。貨物船の横腹から出ると、不意にぴかーっ、光線が濁流を照らし、花道のように三人の乗ったボートが浮かび上がった。
警察が言った。
「ついてる。お尋ね者だ。すぐオールを下ろせ、さもないと最悪だぞ。何日も見張っていた。直ちに、止まれ」
警察のボートが横付けして、三人は無造作に警察フェリーに移動させられた。アイダは隣席に大きな外套があったので、頭からかぶって、顔をしっかり隠した。発作的に感謝のため息をついたのは、やっと安全になりつつあると確信したからだ。
「誰か空ボートに一人乗り込んで、どこか近くに係留しろ」
と警察艇の指揮官が命令。
アイダを捕まえた最初の男が抗議した。
「無礼だぞ。何の罪だ。ヨットへ向かっていたらこの若い女性がオール無しで漂流していた。我々はシティの有名人だ。俺の名前はエイビス、こちらの紳士は共同経営者のバンストン氏だ」
警部補が厳粛に言った。
「そうでしょうな。少しも疑っておりません。しかし、あなた方のボートが出てきたところは秘密水路であり、これに通じる家を我々はある期間監視していたので拘束したわけであります。合理的な理由があるでしょうから署でお願いします。そういうことで全員テムズ警察署へ連行します」
アイダは外套に身をくるみ、隠れ
興奮に震えながら頭を悩ましていたのが、あの両人に聞かれずに自分の話をする方法だ。一番重要なことはこの奇妙な事件に自分が関わっていることを父とエイビスに知られないことだ。
名案がひらめいたのは白壁の小さな署内、そこで担当巡査部長が事情聴取を聞いているときだった。アイダが片手を頭に当てて、かすかにうめいて、つぶやいた。
「具合が良くありません。ボートでけがをしたようです。水を一杯下さい、話があり……」
巡査部長が即座に言った。
「女性刑事の出番のようだ。ブラウン、この女性を婦人看守室へ連れて行け。そこで面倒を見させろ」
エイビスが叫んだ。
「駄目だ。この女は他人の書類を持っている。この女はスパイ、それが正体だ、外国政府に雇われている。調べれば本当だと分る。そんなに簡単に釈放するな」
巡査部長がじろっと目を上げた。分ってきた。この案件は所轄を超えるので、慎重になってこれには答えず、こう言った。
「わかった。ブラウン、この若い女に目を光らせるように言え」
警官に腕をつかまれ、アイダが案内された部屋で、眼光鋭い女が親切に外套を脱がしてくれて、一杯の水を勧めた。女刑事の顔がわずかに変化したのはアイダの姿が現れたときだ。明らかにこんな囚人はテムズ警察署では珍しい。半時間過ぎて、担当の巡査部長が部屋に入ってきて、通告した。
「さっきあの男の言ったことを聞いたでしょう。尋問は拒否しないでしょう?」
アイダが冷静に言った。
「スパイと言いました。私はスパイです。この紙が証明します」
第二十八章 部長の出番
巡査部長が驚いてアイダを見た。目に驚きの表情があった。こんな事件に当たるとは思っていなかった。今までの経験と言えば、河川泥棒とか砂糖密輸業者の類いであり、政治犯の高飛びは伝聞で知るのみだった。
しかしながら多くの事例を読んでおり、想像通りの形で現れたアイダは国際スパイの典型のように思われた。アイダは淑女でもあり、巡査部長がかねがね信じていることだが、上流社会を世渡りする連中は秘密外交の場面に雇われる。
巡査部長が言った。
「警告しておきます。お嬢さん、何も言わないで下さい。しかし名前と住所だけはお願いします」
アイダが静かに言った。
「それも拒否します」
巡査部長が穏やかにいさめた。
「よく考えて下さい。被告人が住所を言わない場合は優しくしませんよ。ボートで一緒の紳士を見て下さい。両人とも真実を言い、それを確認したので釈放します。断定しませんが、両人は数日したら何らかの罪で起訴されるかもしれないし、シティの高い地位なので、警部補が
「ご親切にどうも。でもその種の供述は拒否します。自分がスパイだと白状して証拠を提出しました。更なる文書を探したいなら、反対しません。この紙を直ちに警部補へ持っていき、外務省と連絡を取るようにお願いして下さい」
巡査部長が残念そうに言った。
「了解しました。もちろんあなた流のやり方があるでしょう。それでは一日か二日、拘留されます」
「手続きはどうなりますか」
「明朝、判事に
巡査部長が肩をすくめる様子はそれ以上責任を追いかねるという風だ。いい判断であり、アイダはそれに賭けようと決めた。決して名前を言わない、重大な結果を招きかねないからだ。
もしかしてグラスゴウ部長の助けが期待できるかも。実際それを期待しているけれど、アイダの考えを理解してくれたらの話だ。部長への緊急手紙をお願い出来るかもしれないが、そんなことをすればもっと悪くなりかねない。
刑務所に数日監禁されたってどうってことない。おそらく友人が問い合わせをするだろうが、いずれにせよリスクはある。心身共に冷えたのは、白壁の監房に収容され、鍵の閉まる音を聞いたときだった。
一時間ぐらいあと、グラスゴウ部長の私室に来訪したのはテムズ警察署の警部補だった。
グラスゴウ部長が言った。
「グラハム警部補、何が知りたい? 電話であなたの妙な話を聞いて、ご足労戴いたが」
グラハム警部補が説明した。
「こんな具合でした。テムズ警察がしばらく監視していたのが川べりの家で、そこを巧妙な密輸業者の一味が使っておりました。秘密水路があり、昼夜監視していました。今晩、二艘のボートが出てきて、一艘目は女が一人、二艘目には男が二人乗っていました。女のボートにはオールがなかったので、逃走だと判断しました。とにかく我々は三人を捕まえて、署へ連行しました。男らは抗議をやめず、何の罪かと尋ねました。ちょっと厄介だったのは罪状が適用できなかったからです。二人は我々が追っている一味とは無関係かも知れません。でも同じ家から出てきたので、怪しかったのです。署で出来ることは両人の名前と住所を
グラスゴウ部長がのんびり言った。
「私にどう関係するか分りません。警部補はいざ知らず、私の仕事は外務省がらみです」
グラハム警部補もそう聞いているという。でもまさか諜報部の部長と話しているとは知らない。
警部補が話を再開した。
「重要なところで中断しました。女は外套にくるまっていたので、男らに顔を見られたくないのだと思いました。体調不良を口実に婦人看守室へ連れて行きましたが、本官は嘘だと思います。名前と住所は拒みましたが、外国政府に雇われたスパイだとあっけらかんに認め、素直に渡した紙には暗号が書いてあり、外務省へ持って行けと命令するのです。とても厚かましい女ですね」
「女が自分から吐いたと言うことか」
「正確じゃありませんが、女が認めました。実は一緒にいた男の一人が、女がスパイだから調べよと忠告したのです」
グラスゴウ部長が初めて興味を示した。
「おう、そうか。狙った以上の大物を捕らえたな。二人の男の名前を覚えているか」
「紙切れに書いてきました。二人ともシティの株式仲買人で、エイビス氏と、バンストン氏です」
グラスゴウ部長が思わず煙草を落とし、床を手探りしている。警部補に驚いた表情を見られたくない。警部補がもたらした情報はとても貴重であり、名前なんか些細なことだ。グラスゴウ部長が煙草を探し当て、キセルに戻す頃には素早い頭の回転で全容をつかみ、こう言った。
「まずまずだな。口外するなよ。おそらくこの清廉潔白な株式仲買人どもは独自ルートの砂糖密輸で儲けている。だから顔を見られたくなかったのだろう。女の名前は?」
「頑として名前と住所は言いませんでした」
「ほう、どんな女だった?」
グラハム警部補が描いた似顔絵を、グラスゴウ部長が認識できないわけがない。ほっとすると同時に困った。もしアイダが外務省の暗号書を持っていたとしたら、グレイ以外に入手先はあり得ない。
この数日、部長はグレイの居所がつかめていなかった。躍起になって手がかりを探しているときにアイダが見つけてしまった。
アイダにとっても、バレリイ嬢を介してグレイと接触していたらもっと良かったかもしれない。どうやら事件を自分一人で抱え込んでおり、もしそんなことをしたら、大きな危機を招き、お芝居どころの騒ぎじゃなくなる。
でも、アイダは慎重に行動している。すごい幸運というか裏技で、父とエイビスから身元を隠し通し、暗号文書を引き渡し、いずれ適正な人物に届けるだろう。
「グラハム警部補、私はたまたまこの事件を知った。時々外務省の仕事をしている。暗号文書は外務省、それとも貴官が持っているのか」
「本官は外務省へ行っておりません。外務省へ電話したら、あなたを紹介されました。ここへ来て全部話して、書類を渡すようにとのことでした。ほかに話がなければ、本官は仕事に戻ります」
*
グラスゴウ部長は一任されても困らなかった。全体を考えたかった。しばらくすると方針が見えたので、電話をつかんでバレリイ嬢を呼び出して、尋ねた。
「バレリイさんですか。今お一人ですか。少しお話したいのですが。たった今アイダ嬢が警察につかまったと聞きました。外交スパイとして逮捕され、ある書類を持っていました。実際は自発的に提出したものです。何ですか? はい、その通りです。驚きましたが、アイダ嬢はうまく立ち回ったようです。名前と住所を拒否したので数日間、拘留を余儀なくされるでしょう。そこであなたにお願いですが、問い合わせをしないで戴きたい。問い合わせをすると身元が割れて、私の仕事が非常に難しくなります。ですからどうか静かになさって、何も訊かないで下さい。一つはっきりしているのはグレイの居場所をアイダ嬢が知っていることです。事実ほかの誰からも暗号文書は得られませんから。明日午後、私が面会に行きます。支障はありません。何ですか、そう、そうです。今は辛抱と慎重ですよ、そうすればすべて解決します」
翌日の午後四時、グラスゴウ部長がアイダの独房に静かに歩いて行った。アイダは青ざめてやつれて見えた。というのも判事の尋問がほんの半時間ぐらいだったが厳しかったからだ。名前と住所をかたくなに拒否し続けた結果、警察の要請で判事が一週間の再勾留を命じた。
グラスゴウ部長が入ってくるとアイダが飛び上がって、叫んだ。
「グラスゴウさん、どうやって……」
「それはどうでもいい。あなたは良くやってくれた。あと一週間頑張って下さい、そうすれば全部解決します」
第二十九章 陰謀
政府関係書類を取引した罪で、スパイが逮捕されたという単なる発表が、大反響を呼んだ。新聞が事件を報じたのは数行だった、というのも各種証拠が提供されず、再勾留は規定通りだからだ。それでも人々は時節柄この事件を仰々しく論じた。スパイ好きが、ちまたに溢れていた。英国や欧州でも逮捕が相次ぎ、荒唐無稽な噂も流れていた。
スパイが女だという事実も騒動へ
この種の新聞が、こんなことを大々的に報ずるのは簡単だ。というのもニュースが枯渇し、おいしい記事なら何でも大歓迎なせいだ。ある夕刊紙など、スパイの扇情的な伝記と写真を掲載する始末。
グラスゴウ部長はある程度予想していたが、思った以上だった。怖れたのは告訴公聴会がどうなることやら。記者が大挙して押し寄せるだろうし、避けられないのは写真が法廷からこっそり持ち出されることだ。対策は一つしかない、発表より一日早く実施することだ。グラスゴウほどの役職であれば、これを行うことが出来るし実際、頻繁にやってきた。
アイダを収監しておく場合じゃない。弁護士に相談すると、保釈請求は警察も反対しなかった。新聞には不利だろうし、編集長も悔しがるだろうが、グラスゴウ発だから心配ない。グラスゴウ部長は大部分の新聞を天敵と見ていた。その上、かなりの保釈金が請求されるが、部長なら何とかうまくやれる。
*
もし簡易公聴会がハースコートに監視されていることを知っていたならば、グラスゴウ部長も心穏やかじゃなかっただろう。ハースコートは運悪く最高策略がおじゃんになり、ふさぎ込んだ気分で家に帰った。
でも公聴会を聞いてちっとも困らないのは、間接的にしか関わっていないからだ。当分放っておいてもいいだろう。
だがバンストンとエイビスを電話で呼び出し、重要な要請だからすぐ来いと伝えた。電話でこの件を話すことはしない。緊急だから、もし会いに来なかったら、二人にはますます不利になる。
一〇分後、両人を乗せたタクシーがハースコートの家に着いた。のんきな様子で部屋に入る態度は、現状に満足し切っているかのようだ。実際ここ数日、二人はすごく順調だった。
エイビスが陽気に尋ねた。
「どうしましたか。全くあなたを世話する以外に我々は仕事がないみたいですよ。ここにいる間、一分間あたり一〇ポンドの損失です。なぜ我々の所に来ないのですか」
ハースコートが厳しく言った。
「数分で分る。ルペラ男爵に邪魔されて、じきに痛い目に遭うぞ」
バンストンが答えた。
「危険覚悟だ。今までうまくやってきた。これが最後の獲物だ。つまり地中海石油の事だ。当然、この株は失敗する運命にある。採掘権が取り上げられるから株主は金を失う。我々は昼夜、空売りしまくっている。皆が買うまで売り続ける。なぜかって? あの手紙は紛失したし、二度と出てこないからだ。ボーン国王が権力を確実にする頃、それも間もなくだろうが、ルペラ男爵を笑い者にして、我々の儲けは神のみぞ知るだ。エイビスは二百万株も売った。一週間以内に地中海石油株を、二株につき半ペニ硬貨三枚で買い
ハースコートが陰険に笑って言った。
「メダルには
「たわごとです」
とエイビスが鼻白んだ。
「そうか? そうじゃないことを示そう。我々はまだ多少グレイの手中にあることは否定できない。もし奴が例の手紙を提出すればキミらは終わりだし、私もその件でやられる。キミらは例の手紙が紛失したと思っている。先日の夜、テムズ川のボート事件に関連して大変な目に遭ったそうだな。警察はキミらに目をつけて、そのうち起訴するかもしれないぞ」
エイビスが白状した。
「ばつが悪かった。最悪は分っています。でも砂糖密輸の重い罰金が課せられるだけでしょう、シティでは冗談と思われるぐらいでしょう」
ハースコートがいらついた。
「そんな程度ならいい方だ。密輸は単なる目くらましで、もっと重大事を隠しているのも知っている。喧嘩でファランがやられて、アーノットと医者が逃げたことを忘れているな。グレイの救出に失敗したけど。そのほかにもう一人誰かいたのを、お前ら忘れているぞ。キミがスパイだと告発した女だ」
エイビスが言った。
「あれは悪意で言ったんです。頭がこんがらかっていたので、女が重要書類を持っていると思ったのです。とにかくあの女はグレイに会っています。その後ハタと気がついて、奴は賢いから誰にも秘密は話していない。警察は女の正体をつかめないでしょう。明日になったら釈放されるでしょう」
ハースコートが厳しく言った。
「あすは釈放されない。簡単な理由だ、今日、判事の尋問があったからだ。公聴会で女が書類を持っていることを聞いた。そう言っていたぞ。実際私は法廷に行き、全部聞いた。ちょっと不安になったのはファランの連れが襲われた事件で、動機を聞いたことだ。それにしても驚いたな、女の案件が前出しされたから。明日が正規の公聴会のはずだったのに。そう長くかからず結論に達した。外務省が民衆と新聞に一杯食わせたのさ、女の身元を知られたくなかったからだ。様々なもっともらしい口実で保釈を認めるべきだと言っているが、明らかに判事も一枚絡んでいる。警察は例の手紙を軽く見ているが、逆に重要なことの裏返しだ。一瞬も疑わないのは例の手紙がグレイから女に渡ったことだ。女は追い詰められて、警察に渡し、安全を託したわけだ」
バンストンとエイビスが深刻になった。バンストンが言った。
「まずいなあ。ところで、どんな女だった? すごい美人か」
ハースコートがにやり。いわゆる友人であるこの連中はどれほど信用できるか。何回も危ない仕事を一緒にやってきたが、こと自分の儲けに関することなら、喜々として他人を裏切る連中だ。
「見るべきだったなあ」
とハースコート。
エイビスが言った。
「見えなかった。暗過ぎました。警察につかまった時、女はボートの上着をひっつかんで頭をくるみました。とても見られたくないようでした。警察署ではうまく別室へ連れて行かれました。あれ以来見ていません。これで充分でしょう」
ハースコートが意味深に言った。
「ああ充分だ。私はルペラ男爵との経済戦争に無関係だ。あんな手紙にギャンブルしない。一年ぐらい前にバンストン君の邸宅にお邪魔して、娘さんを紹介され、気品と美貌に圧倒された。それにあの顔も忘れない。ようく教えてあげるけど、あの晩、キミが追っていたのはキミの娘さんだよ」
妙な叫びをバンストンがあげ、真っ青になって椅子に座り込んで、かすれ声で言った。
「あり得ない。ハースコートさん、頭がおかしいぜ。ばかげている」
ハースコートが断言した。
「もっと変なことにも出会った。キミの話から娘さんは実家にいて、ホッケイとかゴルフに熱中していると思っていた。外交史なんぞ知りようがないだろ?」
「じ、じつは家にいないんだ。六ヶ月以上会っていない。ひどい親子げんかで家出した。正確に言えば、エイビスとの結婚を迫った。エイビスに恩義があったし、強い意向もあった。娘は聞く耳を持たなかったが、わしは引き下がらなかった。とにかく娘は家出して自活したので、それ以来会っていない。でも信じない……」
ハースコートが割り込んだ。
「バンストン君、信じなくていい、好きにすれば。私は文字通り真実を言っている。くだらなくても、私には少しもこたえない。例のスパイが
父親バンストンがつぶやいた。
「まてよ。今思い出したが、娘がある男のことを話し、外交の仕事に就いているとか言ってた。でも奴の名前はグレイじゃなかった」
「フレイザーじゃなかったか」
「おっと、そうだ」
ハースコートが勝ち誇って言った。
「今なら信じるだろう。グレイの旧姓はフレイザーだったが、遺産相続時に捨てた。ひどい話じゃないか。これからどうするつもりだ?」
第三十章 ダイヤの行方
両人は厳しく見合った。もはやハースコートの言葉を疑えない。実に驚くべき話だし、考えれば考えるほどバンストンは不安になった。
どうやってアイダがグレイを見つけたか
「我々の損失はいくらだ。何で大事な金をぶち込んだ。連日策略を仕掛けて、最後の瞬間にやられてしまった。慣例に従うしか脳のない公僕にやられた。我々は手紙を持ったグレイを捕らえ、テムズ川べりの家に連れ込み、常時監視していたのに、封筒すら見つけられなかった。手紙はかさばらないが、ダイヤモンドは……」
バンストンが困惑して止めたが、喋りすぎたことに気づいた。ハースコートが悪魔のようにあざ笑って言った。
「ヘヘヘ、続けろ。恥じる必要は無い。あるとき知ったけど、キミは一石二鳥を狙っていた。もちろん私はダイヤのことはずっと知らなかったが、全員情報を共有していると思っていた。でも何気ないエイビスの一言で、わざわざ調べに行った。近頃、私はキミらよりも川べりの家で過ごしているから二、三質問……おっとそんな必要は無い。キミらはベルリンの仲間から情報を得て、ゼナ王女の宝石をグレイがロンドンへ運ぶと知った。二人で獲物を山分けするつもりだった。だがグレイが巧妙なワナを仕掛けて、あの老婆が見事にひっかかった。グレイは用心してダイヤを模造品と表示していたので、老婆は孫に遊び道具として与えた。孫が紛失したと思ってどうやらそれで終わった。キミらにもう一つ驚くべき物を見せよう。これを見ろ」
ハースコートが金庫から取り出した赤いモロッコ小箱には王冠と組字が金色で押してあった。強欲なエイビスとバンストンの目の前で小箱を開けて、言った。
「ほらこれだ。まいったか、きんきら品だぞ」
エイビスが口ごもった。
「一体全体……」
ハースコートが続けた。
「率直に言おう。あの夜の大騒ぎのあと、ファランから手に入れた。奴は元の第一現場へ戻った。警察は川べりの第二現場を見張っていたので、捜索されそうにない場所にしばらく身を隠した。奴はあの乱闘で少しやられていたが、なんとか道を這って第一現場へ行ったら、女がベッド一台、家具を数点持ち込んでくれた。たぶん子供らが石をまた見つけて、家に持ち込んだのだろう、ダイヤがそこにあったそうだ。とにかくファランが手に入れた。私は子供達にいろいろ
バンストンが言った。
「奴に金をやっても構わん。とにかくあんたは幸運にダイヤを手に入れた。持っているつもりか」
「私はそれほど強欲じゃない。もしキミらが石の売却に責任を持てば、山分けしていい。盗品売買は私の筋じゃない。石は処分したい。エイビスがうってつけじゃないか」
エイビスが即座に言った。
「はい、ちゃんと分け前をもらえば。私に小箱を預けて下されば、ほどなく換金します。いまは時間に余裕がありません、というのも地中海石油にかかりっきりだからです。でも二週間以内にアムステルダムへ行きます、そこは盗品ダイヤ売買の最適場です。一日か二日以内に世界最高の鑑定士に石を渡せば、鑑定ミスはありません」
ハースコートが賛成したようだ。少しして二人は事務所へ帰って行った。だが両人の心は一時間前ほど安らかじゃない。ハースコートの情報によれば危険が差し迫っている。もしアイダが警察に渡した紙がゼナ王女の重要視する手紙であるならば、対ルペラ作戦は崩壊する。二人はしばらくぼう然と座り、状況を考えた。
エイビスが言った。
「娘さんは見つかりませんか。父権とかそんな物が使えませんか」
バンストンがいらっとして答えた。
「どうやって見つけるんだ。今頃娘は友人に大事に保護されて、我々は手が出せない。我々がグレイ襲撃に多少関わっていることも知っている。キミの言う父権はたわごとだ。近頃そんなものはない。アイダに機会を与えたら物にしよった。何か異常な方法で権力者に入り込み、そ、そ、それから……。ちくしょう。すべてが全くアホみたいだ。おかしいだろう、あの晩、自分の娘と対面して分らないなんて。その間、陰で笑っていた。ああ、嫌だ。エイビス」
今度だけはある意味器用で万能のエイビスも的確な提案が出来なかった。成り行きに任せるしかない、その間に昼飯を食べに行こう。
通りには大勢の新聞売り子が行き交い、口々に叫んでいた。騒音に紛れてルペラという名前が聞こえ、それから別な言葉にも引っかかったので、エイビスが売り子の肩をつかみ、新聞をひったくった。ぼう然として息もつかず、むさぼり読んだのが最新ニュース欄だった。
「バンストンさん、いいですか、運がついてきました。いまルペラはどこにいると思いますか」
バンストンが答えた。
「
「じゃあ、同紙は間違っています。ルペラはボーン国にしばらく滞在しています。さあ、いいですか、幸運は我々の方に輝いていますよ」
*
『ルペラ男爵死亡説』
『驚くべき噂が広まったのはボーン海岸村、その要旨はルペラ男爵と現場監督が農民に襲われて殺害、原因は探査方法で口論があったせい。同男爵は過去数回、採掘の可能性について同国で調査を行っており、同地の広大な領地に採掘権を所有しているとされる。農民らは無知で迷信的だから、発破作業でダイナマイトを爆発させるのに怒った。農民らの考えではあの事業に
*
エイビスが驚喜して尋ねた。
「さあ、どう思いますか。これは数日前に起こったに違いない。なぜなら電文内容に伝達遅れがあると示唆しているからです。元気を出して下さい、バンストンさん。これが真実なら怖れるに足らない。一回りして、数千株を売りましょう」
だが既に混乱が起こって、地中海石油株は全く売れない商品になってしまった。たぶん明日は回復するだろうが、その間まるで疫病神のように、シティは冒険を避ける。人々は落ち込み不安そうに歩き、グラスゴウ部長は私用で町を歩きながら、これを見て笑い、独り言を言った。
「人はなんて
グラスゴウ部長は考え込んで事務所へ戻った。自分の予想を超える速度で事態が進んでいた。こんな不祥事を聞いて本当に残念だ、だって男爵を芯から褒めていたからだ。
自室に着くと、ルペラ男爵邸の誰かが電話が欲しいとのことだった。グロブナー広場に電話するのは気が重かった。おそらく男爵夫人が電話を欲しいのだろう。この悲劇に接した嘆きや絶望は想像がつく。
しばらくして電話を掛けて自分の名前を告げると、聞こえた音声にのけぞった。
男爵が喋っている。
「はい私です。妻を除き、私が英国にいることを知っているのはあなただけです」
第三十一章 刑務所
ルペラ男爵は慎重に周りを見た。げっそり痩せた囚人が異常な告白をしても驚かなかった。人生で様々な修羅場に遭遇していたので、こんなことでは動揺しない。
見たところ、看守は成り行きに気づいていないようだし、重要なことは悟られないことだ。もしこの男が本当のことを言っているなら、もちろんルペラ男爵が信じない理由はないが、このジェフリを自由にすることが自分の義務だろう。
色々考えていると、当の囚人が手押し車を押して戻って来た。ぼう然として大儀そうで、自由の望みと願いをすべて失ったようだった。
ルペラ男爵が言った。
「私は個人的にあなたの父上を知っている。父上とは大事な関係だ。父上の名誉を傷つけていないか」
ジェフリが言った。
「僕はただの馬鹿でした。ほかの馬鹿同様に勘違いして、欧州地図を書き換える手先に選ばれたと錯覚していました。つまり、私は政治犯なのです」
ルペラ男爵が応じた。
「それを聞いて嬉しい。最善を尽くすよ。異議を申し立てたら――」
ジェフリが素っ気なく言った。
「絶対無理です。あなたの異議申し立ては認められるかもしれないが、連中の言い分は私がもうすぐ死ぬとかそんなことだろうし、審議される頃には疑いなくそうなります。奴らの
ジェフリは監視されていることを知っているので、心配して再び動き出した。そればかりか二度と戻ってこなかった。たぶん経験で知りすぎて戻れないのだろう。
「これは妙なことです。あの若い男をご存じなのですか」
とデントン監督が尋ねた。
「今日まで会ったことはない。聞いただろう、父親の名前を。昔ウォルタ卿が息子に冷酷な仕打ちをしたことは知っている。素晴らしい息子だけど、ちょっと強情で劇場型だとか。色恋話があるけど、詳しく言う必要はない。ウォルタ卿が結婚に強く反対し、両者は喧嘩別れしたと聞いている。その日から今日まで息子の消息は分らなかった。ウォルタ卿は息子の名前を誰にも言わなかったので、我々はすごい醜聞だろうなあと思った。明らかにジェフリは何らかの政治陰謀に関係して、ここへ送られてきて、おそらく正式な裁判も受けず、終身刑に服している。もっと詳しく知りたい。君はここの責任者と良い関係だろう」
「ええ、仕事柄。前に申し上げたように囚人は大いに役立ちます。向こうのポニーに乗っている男が要望にこたえられそうです。あの男は昔かなり高い社会的地位に就いており、副隊長でした。この刑務所の幹部は元々陸軍士官であり、一種の刑罰としてここへ送られて来ます。罪の重さによって任期が決まります。看守も兵士であり、懲罰のためにここへ来ています。向こうへ行って、バロフ所長と話しましょう」
大男が不機嫌な顔をして、どんよりした目でポニーから降りて、ルペラ男爵が近づくと重々しく敬礼した。嫌がっていないようで、こう言った。
「ルペラ男爵の名前はもちろん存じております。こんな有名な資本家を迎えて光栄に思います。原油埋蔵は充分あり、引き合うと見ております」
「ここは金に覆われた砂漠ですよ、バロフ所長」
「いいことを聞きました、男爵。とにかく事業と資本がここにくれば文明らしくなります。そのうち劇場を楽しめるかもしれないし、たぶん労働者にもいいことがあるでしょう」
「ここは退屈ですか」
「ああ、退屈なんて言葉は口で表現できません。究極に滅入る人生です。私がここにいる十二ヶ月の間に、四人の同僚が頭を撃ちました。五年先どうなるかは分りますまい」
「所長は五年もおられるのですか」
「さっき言ったとおり本官は一年しかいません。私はまだ若いのですが、もう中年になったような気分です。男爵は私の刑罰をご存じでしょう。私の婚約者に部隊長が横恋慕したのです。私をけしかけたのです。屈辱はそれほどひどくなかったので、我慢していたのですが、仲間に臆病だとおおっぴらにあざ笑われる羽目になりました。そのとき当然上官の思うつぼにはまったのです。上官をムチでしばたいて虫の息にしました。私にはコネがあったので、ここに昇進、つまり五年の懲役刑をもらいました」
男爵が肩をすくめて言った。
「恐ろしい。所長がつらいようですから、囚人はどんなにつらいやら。全員罪人ですか」
「必ずしも言えません。中には凶悪犯もいますが、大半は政治犯です。ここへ来たら死ぬか発狂するかです。昔の知人もいますが、もちろん口を利きません。男爵が文明をもたらして下されば、大恩人として永久に胸中の記憶に残るでしょう」
男爵はやがて立ち去ったが、憂鬱に考え込んだのも、あの惨めな囚人を考えてのことだった。ジェフリが自由になる確率は非常に低いが、一か八かの賭けでも、男爵に訴えるものがあった。
「なんとかして逃がさねば。成功するまであきらめないぞ。不幸にも自分達以外は頼れない。もしジェフリの言うことが正しければ、我々は安全じゃない。労務者の表情は好かんな。あれ以上陰気な連中に会ったことがない。デントン監督、連中は金を有り難がらないのか」
「以前より重要視しません。週末に来て賃金をさっさと受け取ります。強力な発破をしなければ何とか押さえられると思います。連中は丘が半分つぶれて足元まで崩れたら、我々が闇の魔王と結託していると考えます。労務者代表を二、三人よこしますが、もちろん私は取り合いません。連中のばかげた迷信なんて分りませんし、誰にも助けを求められません。連中はやろうと思えば私を殺せますし、本音を言っても構わなければ、最近一回や二回、刑務所で寝た方が安全と思っていますよ」
男爵が苦笑い。難しい課題だが、重要だ。あと一日か二日滞在を延ばし、労務者を管理できるかどうか確かめたい。現地の言葉が分るし、実質、母国語と同じだ。人生で指導者や支配者と会うのは慣れているし、一握りの無学労務者などひるまない。
男爵が言った。
「先んずれば人を制すだ。ライフル数丁と弾薬を幾らか持ってきたが、今は船にある。車で取りに行こう。私のやり方がうまくいけば、車があとで大いに役立つ」
二人が平屋に歩いて戻った目当ては、黒パンと目玉焼きとベーコン、デントン監督の主要な食事だ。食事をかき込んで海岸まで車で行って、ライフルと弾薬の入った箱を持って帰ってくると、ちょうど暗くなった。
車を車庫に入れたとき、小さな火矢が暗闇を飛び、男爵の帽子をかすめ、帽子が地面に落ちた。男爵がランプを消し、デントン監督と二人で車の横に伏せ、敵の次の攻撃を待った。
男爵がささやいた。
「本気のようだな。デントン監督は言わなかったが、連中は武装しとるな」
「ほんの最近です。四十年前この地区が内乱の時、農民らがライフル等を持っていましたから、何丁か残っている物と思われます。一般に、連中が危険なのは陰からであり、正面からじゃありません。でもあれは拳銃から撃ったものです。我々に敵対するものが、農民に拳銃を横流ししているようです。おそらくこれが理由でこの数週間労務者と大いにもめたのでしょう。少し前から不安が増したように思われます。妙な行商人が二人、トラックで商品を売りに来たあとです」
「分かってきたぞ。敵が何人か活動している。最近、狡猾で悪辣な一味に後をつけられて、トラブルが後を絶たない。連中が騒動を引き起こせば、オーストリアが軍隊を前線に送り込んで、口実を設けて我々の事業を一時止めるかもしれない。もちろん勘違いかもしれないが、私にはどうもそのように見える」
「そうならないように。男爵、とにかくここに一晩中おられません。たぶん連中はもう逃げたでしょう。車を中に入れて、扉を閉めましょう」
「連中が車を奪ったら……」
「男爵、連中は車には
ひやひやしながらの真っ
ランプも赤々燃え、薪ストーブも心地よく熱くなり、ルペラ男爵も旺盛な食欲で夕食にありつき、ロンドンではよそ者だったと告白した。男爵が乾燥肉をたっぷり食べて、毛皮に寄りかかり、キセルを優雅にふかした。
一時間か二時間、静かに横たわり、色々計画を考えた。デントン監督がちらと目をやり、意味深に眉毛をあげて、尋ねた。
「何か聞こえないですか。外で足音が聞こえます。近いです、男爵」
第三十二章 風の翼
ルペラ男爵がキセルを脇に置いて、立ち上がった。その時パンパンという発砲音が聞こえ、銃弾がパッパッと家屋の木材に当たった。デントン監督が笑って言った。
「好きなだけ続けろ。最悪、窓を割るぐらいでしょう。銃撃だけなら、朝まで持ちこたえられます」
ルペラ男爵が言った。
「この銃撃音は刑務所まで聞こえないな。遠すぎるからなあ」
「遠すぎます。でも私が信号弾を一、二発、持ってきますから、必要なら打ち上げます。私一人でも連中と戦えます。連中をやっつけてこっぴどい教訓にして、首謀者を撃ち殺せば、将来絶対もめません」
再び散発的に撃ってきた。ガチャンとガラスの割れる音がして、刺すような冷たいすきま風が吹き込み、ストーブがぼうっと燃え上がった。
デントンが男爵を窓正面から脇に引っ張った。割れた窓から毛むくじゃらの腕が二、三本突き出て、一斉射撃の弾が壁をぶち抜いた。射撃が一瞬止まると、しわがれ声が横柄に命令して、
「扉をすぐ開けろ」
デントン監督が尋ねた。
「パウロか。俺は考えたぞ。俺達は出て行かない、お前らも入れない。お前も皆も小屋へ戻れ、朝、お前と交渉しよう。決着がつかず残念だろ」
大勢が馬鹿にして大声で笑った。壊れた窓から十数本の腕を遠慮無く突き出し、あらゆる方向に乱射した。ほかより大胆な男が窓に頭を突っ込み発砲したので、男爵が壁の隅に逃げた。明らかにこの襲撃は発作的なものじゃない。慎重に見極めた上で、我々が丸腰と見越してのことだ。
デントン監督が厳しい顔になり、ウィンチェスター銃をひっつかんで、窓に狙いを定め、六発撃った。突き出した腕と顔が魔法のように吹っ飛び、うめき声と叫び声が上がり、断末魔の様相を呈した。続く一〇分間、物音一つしなかった。
「連中に効いたか」
と男爵。
「あの程度じゃ喜べません。正面攻撃はもうないでしょうが、別な攻撃が恐いです。あの音は」
痛いほどの静寂が破られたのは、ドンドンという足音と、突然の豪雨にも似た雨音だった。平屋の中の二人は、ぱたぱた屋根を打つ音と、ぽたぽたひさしから流れ落ちる音を聞いた。
ルペラ男爵がつぶやいた。
「変だな。抜けるように晴れていたのに。ここは雨など降らないのだろ?」
デントン監督が答えた。
「雨ではありません。怖れていたことです。臭いませんか」
「石油、原油だ。まさか連中は……」
とルペラ男爵が叫んだ。
「家に火を点けるつもりです。間違いありません。これを怖れていました。奴らは原油を一、二たる手に入れてこの家にかけています。マッチで火を点けられたら我々は外に出るか、焼け死ぬかです。家は
「どうする、デントン」
「車で突っ走るしかありません。車庫から出れば刑務所へ駆け込めます。一キロぐらいは凸凹道で、射程外に出るまで照明はつけられません。三百メートルも行かないうちに車がひっくり返る確率はおよそ六対四でしょうが、運があれば通り抜けられるでしょう」
ルペラ男爵がこの提案に乗った。
「例の信号弾はどうなった?」
「しまった、忘れていました。今なら役立ちます。無知な田舎者には何も分らないが、おびえるでしょう。ちょっとここで待って下さい、車庫の屋根裏に登って、天窓から打ち上げますから。二十分持ちこたえられれば、ここに武装看守部隊が来て、連中に鉄槌を下すでしょう」
それ以上言わず、デントンが作業に飛び出していき、男爵を残し、守らせた。相変わらず連中が石油を屋根にかけており、すきを見せない。
そのとき青い閃光が壊れた窓から入ってきて、男爵の顔が引きつった。石油漬けの家でマッチを擦った途端、爆弾のように発火するだろう。火は丸太の間を稲妻のように走るだろう。もしそうなったら車はどうなるか。エンジン始動に一、二分かかるから、いったん火がついたら、二分という時間はほかの場合に比べとても貴重だ。
男爵が吠えた。
「デントン、奴らマッチで火を点けるぞ。ほかは放っといて、エンジンをかけろ、車庫の扉を開けろ」
「二、三分欲しいです」
数分なら時間稼ぎ出来ると男爵が答えた。満
ぱっと見れば、三人の男が即席のたいまつを持っている。姿を見られないうちに三発撃った腕前は元狙撃兵仕込みだ。一番目の男は頭を打ち抜かれて前にドタン、二番目は空袋のようにへなへなと崩れ、三番目は万歳して仲間の上に倒れた。
それから無差別に乱射した。だが連中は逃げず、動じなかった。地面に伏して、男爵の方向にしつこく拳銃を撃ち続けた。弾が額をかすめ、何か生暖かいものが顔に流れるのを感じた。
そのとき、
岩陰からひゅんと音がして、火のついた
怖れていたことが直後に起こった。火が円弧を描いて六本こちらへ飛び、家に六カ所当たり、手品のように家全体が目もくらむ炎に包まれた。男爵が素早く戻ったが、家にはもう入られない。
デントンがエンジンを始動済みだったので、車庫扉を開けて発進した途端、炎が二人に襲いかかり、衣服が焦げて息苦しくなった。凸凹道を百メートルほど慎重に道を探して進むと、ごろごろの岩に阻まれた。デントンが悪態をついた。
「車の照明をつけるのは狂気の沙汰ですが、照明がないと進めません。数分は火災の明かりで見えるでしょう、黒煙がこっちへ来なければですが。と同時に、我々の位置が敵に分るため、危険です」
男爵が陽気に言った。
「そんなことは大して気にしない。車を盾に使えば良い。控えのライフルと弾がシートの下にあるだろ?」
デントンは忘れていない。油の染みた家が盛んに燃え、煙が来ないとき、三百メートル以内は昼間のように辺りが見える。連中の叫び声から分ったのは我々の最新位置を捉えており、車を激しく追っていることだ。
だが十発ばかり正確に狙って撃つと、敵は止まって、点在する
デントン監督が安堵のため息を漏らしたのは、ひづめの音を聞いたときだった。その直後、武装看守の一団が車を超えて突撃し、反乱者達を四方に蹴散らした。徒歩部隊が続き、騎馬隊の
バロフ所長が言った。
「間に合って嬉しいです、男爵。用意できる看守全員と、徒歩の優良囚人を引き連れてきました。これら囚人は大罪を犯していますが、御社の労務者です。我々の部下が反乱者を逮捕します。男爵、我々の刑務所へ来られた方が良くありませんか。あそこなら安全ですよ」
ルペラ男爵が答えた。
「ご親切にどうも。でもこれは想定内であり、反乱とか反逆じゃありません。私は出来るだけ早くロンドンへ帰らねばなりません。すぐ車を走らせます。道路に出れば照明無しでも走れますから、射程外へ出られます」
車を発進させ、二、三キロ走ってから、ルペラ男爵が照明をつけた。そのとき車の床から人影が現れ、真っ青な顔を向けた。
男爵が冷静に言った。
「ジェフリ、大歓迎します」
第三十三章 待機
扇情的な新聞ほどみだらになりがちなのは、不可思議なスパイ事件がらみの場合だ。新聞は大反響確実な事件を不当に差し止めされていた。
一般的に色恋記事は少なくとも一日に数欄が望ましいが、見よ。すべての記事がぽしゃり、ただの一枚として美人有能スパイ写真は現れなかった。
実は冒険的なタブロイド紙が一紙、淑女の肖像画と称するものを掲載したが、誰もそんな
事件の進行が早く、劇的に進むので、アイダは困惑し、途方に暮れた。試練が終わった途端に苦難が始まり、ほとんど分らないままに釈放され、誰が雇ったか知らないが、やっと弁護士が、その事実を教えてくれた。
アイダが尋ねた。
「釈放ということですか」
弁護士が説明した。
「そうです。二週間さし戻されました。その間、好きに出来ますが、ロンドンに留まる条件です」
アイダは法廷から歩いて出た。嬉しいことに誰もつけてこない。すぐにでも下宿へ戻りたかった。
通りへ足を踏み入れたとき、きちんと正装した運転手が敬礼して、こう言った。
「アイダ嬢ですね。バレリイ嬢がお車を
アイダはためらわず従った。収監中もバレリイ嬢は私のことを考えてくれていたと思い始めた。グラスゴウ部長は役目を続けることが重要だと言っていたので、そのようにしてきたからすべては間違いなく戦略だろう。
ずっと自分を犠牲にしてきたのは真実と公正を期すためであり、グレイの安全を確保するためだった。再びグロブナー広場に行くのも嬉しい。大邸宅の豪華さを満喫するだけでも楽しい。そしてもっと良いことに、グラスゴウ部長が居間でじっと待っていた。
部長が言った。
「お
アイダはグラスゴウ部長の心遣いに感謝した。父とエイビスのことだと分っていた。でもこの件については議論せず、ほかの重要案件に言及した。
「部長のお役に立ててとても嬉しいです。部長に渡した紙は重要だと思います。もちろん私には何も分りませんが」
「それなりに重要ですが期待したほどじゃありませんでした。グレイからもらったでしょうから居場所をご存じですね。まずやるべきことはグレイを見つけることです。その後ここへ運んで慎重に看病しましょう。目印をおっしゃって戴ければすぐ動きます」
アイダが説明し始めた。テムズ警察は密輸業者の隠れ家を知っていたので、急襲すれば、確実にグレイを発見できるだろう。二軒あるので両方捜査したほうがいい。
*
どうやら供述が裏付けられたようだ、というのも当日遅く、一台のタクシーがグロブナー広場の邸宅に止まり、中から外套を着た男が降りてきて、やっとの事で階段を上がってきたからだ。すぐアイダが手助けして、上階の居間に連れて行った。真っ青でやつれていたが、目は生気に溢れ、次第に手足に力が戻って来た。グレイがアイダを抱いて、優しくキスして言った。
「きみほど勇敢な女性が今までいたかな。きみ無しでは何も出来なかった。グラスゴウ部長が全部教えてくれた。途中まで僕と一緒に来た。僕のようなつまらない男の為に危険を冒して」
アイダがささやいた。
「義務です。恋人が危ないときに勇気なんて何でもありません。あることがなければ完全に幸せなのですが」
「なに、それは、アイダ?」
「厄介で不名誉なことです。父の行いに目をつぶることは出来ません。父の居場所が分れば警告するのに。あなたとお知り合いにならなければ良かったと思わざるを得ません」
アイダの涙目を見て、グレイが言った。
「どういうこと?」
アイダが途切れ途切れに、やっとのことで話した。だがそれを聞きながら、グレイの目に愛の光りが消えることはなかった。
「お気の毒に。どんなに怖かっただろう。でも僕たちにとっては重要ですか。気にする必要がある?」
「あなたの昇進を考えると」
「そんなことを考えると思う? その上どれだけの人が知っている? そもそも知りますか。僕は仕事をまじめにやってきたし、叔母の高額遺産も相続した。アイダ、きみはそのうち大使夫人になるよ。どうかその件は言わないでくれ。僕が本当にきみをあきらめると思うかい? 僕の望みはきみと結婚して、田舎へいざない、叔母の残した素敵な邸宅で暮らすことだ。きみのきれいな瞳を見ると、昇進しなくても良いと思うよ。バレリイ嬢を連れてきてくれないかい? お礼を言わなくちゃ。人前に出られるまでここに逗留させて戴き、感謝する。むかしバレリイ嬢は僕の天敵だと思っていたんだ。いまよく分ったよ。バレリイ嬢は秘密政界を泳ぐには決定的な弱点があるかもしれないが、最大の目的は僕の旧友のジェフリを探すことだ。ジェフリのことはグラスゴウ部長から聞いた。部長はルペラ男爵から聞いたと思う。バレリイ嬢にお願いがあるけど、昼食をいつもより早めて欲しい。下品なほど腹が空いている」
二、三日でグレイは著しい変化を見せた。ほぼ昔の体を取り戻した。
全員夕暮れどき、居間の暖炉の回りでそんなことを話しながら、やがてランプに火がともる頃、扉が開いて、背筋のぴんと伸びた痩せた男が出し抜けに入ってきた。
揺らめく暖炉の明かりに、顔が真っ青だ。
バレリイ嬢が口ごもった。
「だん、男爵。男爵が生きている。すごい、すごい。死んだものと思っていました。農民を罰するために王女が遠征隊の準備をしていますよ」
ルペラ男爵が言った。
「私に会えて嬉しいですか。よかった。妻とグラスゴウ殿下と召使い以外は私がロンドンにいることを知らない。一日か二日は公的に死んだことにして欲しい。ええ、あれは興奮する場面でした。反乱者達が現場監督の家に石油をかけて焼きました。向こうでも敵が暗躍しています。でも時機が来たら借りを返します。運良く武器があったので野蛮人共を食い止めていたところ、近くの刑務所から看守の一団が助太刀に来てくれました。とても助かりましたし、模範囚も鎮圧に協力してくれました。囚人らは政治犯であり、刑事犯じゃありませんが、刑務所を脱走した者はいません。いったんここへ放り込まれたら二度と出られません。ところが刑務所始まって以来、一人の哀れな男が脱走しました。連中の労役報酬は雀の涙でしょう。囚人の一人が私の車に隠れて脱出しましたが、密告するつもりはありません。その男の名前を聞いたときには――」
ルペラ男爵が射るような黒い瞳と、食いつくような顔をバレリイ嬢に向けた。バレリイ嬢が驚き震えて立ち上がったとき、血の気が失せて、ささやいた。
「わたくしの知り合いですか」
ルペラ男爵が続けた。
「そうです。自称ジェフリとか何とかいっています。私がわざわざここへ連れてきて、階下の午前の間にいます。もし――」
もう、バレリイ嬢はいなかった。
バレリイ嬢はすべてを忘れ、一目散に階下へ行くと、そこには心から愛した男が。欧州中探しまくり、むなしく年月を重ねた。この男のために荒々しい政治陰謀に身を投じ、社会的名声と命を危険にさらし、消息を求めた。死んだとは信じられず、もしや捨て鉢になっておかしな陰謀に加担して、刑務所のような所に放り込まれているかもと思っていたところ、何とそこから脱走してきた。
バレリイ嬢が自分を責めたのはジェフリに代わって政治に興味を示したことであり、激しく自分をとがめたのはジェフリと父を対立させ、ジェフリの職歴を台無しにしたことであった。そして今になって幸運が微笑むなんて、単に運命にからかわれただけか。
ジェフリが見つかり、バレリイ嬢は階段を降りながら、心は喜びと幸せに躍った。扉を開けて、目をこらし、口をぽかんと開けて見れば、やせ衰えた背の高い男が暖炉のそばに立っている。差し出された両腕に我が身を投げて、息もつけずあえぎながら、バレリイの黒い瞳は感謝の涙で一杯になった。
「ほんとに、本当にあなたなの? ジェフリ、離すべきじゃなかった。何と惨めに苦しんだことか、私のために。心から許して……」
僕こそ、とだけしかジェフリは言わず、バレリイをひしと抱いて激しくキスした。
第三十四章 見かけ
うろたえた皆にルペラ男爵が愉快そうに微笑んで言った。
「見よ、私は
「男爵、どういうことですか」
とグレイが尋ねた。
男爵が同じ調子で続けた。
「おや、グレイ君もいたのですか。グラスゴウ殿下が最近のことを知らせてくれました。お祝いを申し上げます、脱出され、賢い方法で悪党をきりきり舞いさせたとか。知らないでしょう、内幕を。知らないでしょう、脱出囚人の名前がジェフリとは」
グレイが叫んだ。
「すごい、ジェフリは運のいい男です。きっと父上が同意するときが来ます」
「グレイ君、きっとウォルタ卿は自分の間違いを認めるでしょう。少なくともグラスゴウ殿下はそうおっしゃっておりましたし、裏付け無しで論評されませんから。すべて丸く収まりそうですね。一日か二日以内に片がつき、現在のごたごたに関する限り、心配ないでしょう。その間、私はアムステルダムへ行きます。戻って来たら、みなさんに小話が出来るでしょう」
やがてバレリイ嬢がジェフリに連れられて居間へ戻って来た。ほぼ昼食時間の前にジェフリが話し終わると、男爵が急いで立ち上がり、一時の猶予もないという。なんとか皆と離れて、バレリイ嬢と一言二言、言葉を交わした。
「あした出発する前に、立ち寄ってお目にかかります。王女の宝石を返したいのです。王女の前では言いません、なぜならあなたが宝石を持っていることを王女は知らないと言われたからです。とにかくあの宝石はある目的に役立ちました。目的はやがて分るでしょう。さて、本当に行かなければなりません。昼食用に着替える時間がありませんし、アーノット記者が重要なことで打ち合わせに来ますから」
*
男爵の邸宅にアーノット記者が現れた。あまり落ち込んでおらず、いつもより調子が良さそうだ。この数日あれこれ自問して、精神状態が良くなるほどにエルシの正しさが分ってきた。アーノット記者が病的なほどの自己中心や自尊心からエルシを邪険に扱い、エルシの幸せと対立したのは、まさに当然の成り行きだった。エルシがアーノット記者の傷を癒やしてくれたのも誠実で寛大な女性ならではだ。
エルシを脇に伴い居間に戻って来たときには違った男になっていた。エルシは質素な身なりながら魅力がある。顔には苦労しわが残り、ほほはこけているが、目は幸せに溢れていた。エルシが夢見た田舎暮らしは近々実現しそうだ、というのもエルシの気持ちを察してアーノット記者が屋敷を買い、一ヶ月以内に所有すると同時に二人で入居するからだ。
楽しい夕食となったのは、男爵と男爵夫人がエルシの好きにさせてくれたからだ。だがコーヒー、お酒、煙草が提供された後、アーノット記者が男爵夫人にお礼を言い、扉を閉めたとき、男爵の表情が変わり、こう言った。
「アーノット君、仕事に戻ろうか。アムステルダムへ一緒に行ってくれないか」
「お言葉通りにします、男爵」
「それを聞いて大変嬉しいよ。私が不在のとき、連中を見張ってくれたと思う」
「私の手下が一日たりとも目を離しておりません。グラスゴウ部長を除き、私は誰よりもロンドン裏事情をよく知っています。正確にあなたの指示に従いました。まずファランを安全な場所に隔離しました。もう何でも我々に話してくれます。事実、奴は死を免れるためなら何でもやります。少し手こずった理由はバンストンとエイビスが私を知っており、私以上に警戒していたからです。あの晩、川べりの家で奴らに会うのはまずいし、つまりアイダ嬢が冒険して、警察に拘束された夜のことです。ついでにグラスゴウ部長があの件をうまくやってくれました。警察を上手に騙したばかりでなく、ある程度までエイビスとバンストンも騙しました」
「ある程度までとはどういうことか。不吉に聞こえる」
「男爵、ある程度ですよ。バンストンは何か事実をつかんでいる気がします。自分の娘がスパイになったと
「バンストンはまだロンドンか」
「いいえ、アムステルダムへ行きました。エイビスも行くはずですが、連中はお互いを信用しませんから、最後になってエイビスを同行すると決めたのです」
男爵がもみ手をして満足した様子で説明した。
「都合が良い。私の指示に慎重に従えば、二人を同時に仕留められる。失敗しないと思うが、どう?」
「失敗は最悪ですよ。私はアムステルダムに行って宝石商のイズリアルスに二回も会いました。私の要請をよく理解し、要望に合わせてくれます。おおむね金のためなら何でもします。ファランの情報をすべて仕入れて、それを言ったらすぐ乗りました。私は単なる代理人だから、雇い主がご希望の高額を支払うと納得させました。明後日の正午前、十一時にイズリアルスに会う予定です。もちろんほかに誰も来ませんし、こんなことは人数が少なければ少ないほどいいですから。イズリアルスを説き伏せて了解させました。最初不安げで、疑っていましたが、欧州一の悪党も私の誠意を認めましたので、もめないでしょう」
男爵がうなずいて認めながら、テーブルの新しい煙草に手を伸ばした。密かにアムステルダムへ行くのは難しいかもしれないが、グラスゴウ部長の力添えで、アーノット記者がやってのけた。
*
約束時間に男爵とアーノットが
やせこけた黄色い顔に大きな
挨拶もそこそこに男爵とアーノットが押し入ると、すぐ扉をぴしゃっと閉め、鍵を掛けた。ほとんど内装がされていないようだ、というのも床と階段がむき出しで、靴音がやけに響くからだ。だがイズリアルスが裏部屋へ案内すると、そこは事務所のよう、机が一台、椅子が一、二脚、それに巨大な鉄製金庫が壁に埋め込まれていた。
イズリアルスがささやいた。
「いらっしゃいませ。この家には私一人です。いつも一人です。一人で行動すれば、秘密が漏れることはありません。アーノット様のお連れのお名前は……」
アーノットが素っ気なく言った。
「こちらはスミスです。何でもよろしい」
「あ、はい、スミスさん。とても用心深いお方ですね、スミスさんは。でも売り物を買いに来られるから友人です。一蓮托生ですし……」
男爵が言った。
「分っておる。欲しいのは宝石だ。歴史的な宝石だ。多額を払うぞ。今回は私が上客だ。がらくたなら廃棄――」
イズリアルスが得意になってもったいぶり、ハゲワシに似ていなくもないが、雄七面鳥の真似をした。黄色い長爪を空中で振って言った。
「ご覧に入れましょう。ちょっと待って下さい、よだれが出ますよ。金庫に入れて、専用箱に入れてあります。私はまだ見ただけです。笑ってますね。私にうってつけの商売でしょう?」
「それに幾ら払ったのか」
と男爵。
「三千ポンドです。有り金全部です。取引成立時に、差額を払います」
男爵がいらついて言った。
「さあ、物を見よう。時間の無駄だ」
ユダヤ人が首に掛けた鎖から鍵を取り出して金庫を開けた。中から丁寧に
男爵が批評した。
「ああ、大丈夫なようだ。でも認めたくないが、君の言うダイヤはにせ物じゃないか、王冠がスタンプだぞ」
笑顔を引きつらせてユダヤ人が一個の石を掴み、ヤスリで角を削った。とたんにヤスリを落とし、怖いほど怒って叫んだ。
「悪党め、盗っ人め。ミスターとかブラウンとか言ってたが、奴らの本名はバンストンとエイビスだ。ワナを仕掛けたな。偽物に三千ポンドだ。三千枚のソブリン金貨だ」
イズリアルスは椅子に座り込み、爪を噛み、むなしく怒るだけだった。
第三十五章 仲間割れ
エイビスのお気に入り格言は、数々の痛い経験に基づき、こと金に関する限り、大衆の言動は当てにならないだとか。良いことは噂にしないが、悪いことは真っ先に飛びつく。
さて、ルペラ男爵の噂は概して良好で、地中海石油株の売り出しを六回以上行った。あの重要な手紙は実質上紛失し回収は見込めないので、エイビスとバンストンは大胆に空売りし続け、ルペラ男爵が死んだと報じられたとき、地中海石油はころっと倒れるはずだった。
だが妙なことに、一切起こらなかった。大量に売ったにもかかわらず、一般株主は相変わらず持ち続けた。株を手放さないので、週末ごろにはバンストンとエイビスも深刻に考えざるを得なくなった。
一般に土曜日はシティに出勤しないのが両人の決まりだが、当日出社し、クラブ食堂は昼食時、ほぼ貸し切りだった。
バンストンが
「好かんなあ。追い詰められた感じだ。あのダイヤでは相当儲けたけど、これを切り抜けるのは厄介だぞ。最終的にキミとアムステルダムに行くことになりそうだ。取引に参加したい」
エイビスは苦笑いしたが何も言わなかった。バンストンの心を完全に見透かしていた。コーヒーと煙草を飲みながら現状を不機嫌に話しているとき、ハースコートがあたふたと部屋に入ってきて、
「キミたちに会いに行こうと思ってたところだ。ロンドンシティの一番賢明な資本家が二人か。さて、キミたち何をするつもりか。最近私を避けるのはなぜだ。だがこれは論じない。今朝あることを聞いて驚いたので、キミたちを思い出した。滅多に間違わない男から聞いたけど、ルペラ男爵は死んでいないそうだ」
エイビスがハースコートをぽかんと見つめて尋ねた。
「いたずらということですか。ルペラが証券取引所を標的にして噂をまいたのですか」
ハースコートが不機嫌に言った。
「馬鹿もいい加減にせい。ルペラは大物過ぎてそんな汚い仕掛けは出来ない。当然新聞の誤報だ。恐らく何らかの不具合が発生し、あとは外国特派員が想像で書いたのだろう。とにかく俺は部下を信じる。もっと悪いことがあるぞ。ルペラはそんなことに手を貸さないが、誤報につけいらない理由はない。さあ、ここが重要な点だ。ルペラがロンドンに二、三日いることは奴の家族以外誰も知らない。月曜日、がさつ者のキミらは地中海石油で大弱りするだろうな」
バンストンが不安げにうなってつぶやいた。
「悪夢のようだ」
ハースコートが答えた。
「俺を信じるかどうかだ。ダチョウのように砂にくちばしを突っ込んで頭を隠せ。そうすれば誰からも見られない。俺の言ったことをもっと注意深く聞くべきだったな。テムズ岸の家にグレイはいないし、ファランと老婆はどこにも見当たらないと俺は言ったぜ。ファランと馬鹿なことをするときは何か起こるぞと俺は警告した。奴を利用したが、見捨てたあげく、敵に回してしまった。とにかく奴は逃げたし、奴が敵につかまっていなかったら逆に驚くよ。お前らがわがままじゃなかったら避けられた。お前らの計画は? 俺はアメリカへ長旅をする。英国同様に米国でも、うまくやる。今ならロンドンよりアメリカの方があう」
「泥船から逃げるネズミです」
とエイビスが皮肉った。
ハースコートが再乱入。
「もっといい比喩があるだろう。ダイヤの分け前や、俺のことは心配しなくていい。俺が警告しなかったとだけは言うなよ」
素っ気なくうなずいてハースコートはぷいと、部屋を出て行った。両人は驚いてお互いを見合った。
バンストンがささやいた。
「どうする?」
「ハースコートの警告に従う以外、何が出来ますか。ルペラのことは正しいです。心底そう思います。もう駄目です。早く行動するほどいいでしょう。もしルペラが戻って来たらチャンスはありません。ロンドンのシティで最低の債務不履行者に成り下がるほど不都合はないでしょう。出来るだけ金を集めてアムステルダムへ行きましょう。あのダイヤで数千ポンドつくって、その金でアメリカ人に思い知らせてやりましょう。知っての通り、私は一回アムステルダムに行ったことがあります。イズリアルスからあのダイヤの前金をもらいました。奴の秘密売買に、有望な買い手がおり、高額を払い、何も
バンストンがうめいた。
「難しいようだ。きのうは膨大な富を手にしたが、今日は十倍以上も損した。ここに留まって結果を見たほうがいいと思わないか」
エイビスが素っ気なく言った。
「いやです。僕たちの運用のいくつかは明らかに怪しいです。少なくとも警察はそう言うでしょう。大事件が起これば容易に隠せますが、失敗したし、ルペラの術中にはまりました。ルペラが我々の長年の悪行を知った方に、賭けます。早晩、誰が取引を邪魔していたか知るはずです。忘れていけないのはファランの件、グレイへの攻撃、川べりの妙な事件です。もしここに留まって警察を無視すれば、危険を招くだけです。しかし慎重に姿を消せば、外務省も大騒ぎしないはずです、大衆に情報源を知られたくないからです。ここでおしゃべりして貴重な時間を浪費しています。五時に会って、今晩海峡を渡りましょう」
*
翌日午後遅く、両人はイズリアルスの邸宅がある狭い通りにいた。外に突っ立って合図を待っていると、やがてダイヤ商人の黄色い顔が、汚れた窓ガラスに見えた。
目が怒りで真っ赤、爪で空気を引き裂くかのようにして、階段を降りてくる様子は歳の割に信じがたいほどすばしこかった。何も言わず、挨拶もせず、バンストンとエイビスの腕を掴み、中に引き入れた。
事務所に座ったとき、エイビスが厳しく問い詰めた。
「どうした? なんでそんな目で見る? まさかあの宝石を無くしたとか? 下手なごまかしをしたら、お前のよぼよぼの骨をへし折るぞ」
イズリアルスも詰問した。
「手前が今までごまかしたことがありますか。一緒に仕事をするようになって何年経ちますか。手前から何千ポンド受け取りましたか」
バンストンが言った。
「本来の三分の一ももらってないぞ、シャイロック。お前はあくどいだけだ。老いぼれのけちな守銭奴だし、分っているはずだ」
「危ないのはいつも手前で、あなた方じゃありません。それにあなたがたのご存じない人と利益を分配しなければなりません。今おいくらお持ちですか」
「わずかだ」
とエイビスが即答した。
嘘つき、とユダヤ人が反論した。ユダヤ人がよく冷静になるのは心底怒ったときだ。
「嘘つきね、あなた。手前が何も知らないとでも? あなた方の動きに興味ないとでも? ああ、手前の金融市場の知識には驚きますよ。ルペラ男爵に仕掛けた戦いはどうなりましたか。負けましたね、予想通りです。ロンドンその他に手前のスパイや手先がいます。あなた方は負けて、面目丸つぶれ。二度とロンドンに戻れません。例の宝石売上金の回収にここへ来て、その金を持って、よそで出直すのでしょう。有り金を全部、持っていますね。もし手前が警察へ通報すれば、もうアムステルダムからは出られませんよ。手前を騙そうとしても一銭もやりません。すぐその訳を説明します。いま三千ポンドありますか」
「それがどうした」
とエイビスが反論すると、
「認めて下すって感謝します。嬉しいですね、手前のお金がなくなりませんから。今晩いくら持っていこうとなさるんで?」
「一万ポンドだ」
とエイビスがうっかり喋った。
一万ポンドですって、とイズリアルスが素っ頓狂な声を上げた。もう怒りを抑えられなかった。
「一銭もさしあげません。逆に金を置いてもらいましょう。いいですか、手前の三千ポンドを返してもらいましょう。チョロい仕掛けで手前を騙しませんでしたか。手前に持ってきたのはダイヤですか、ハハハ、ダイヤだって。きれいなモロッコ箱に王国紋章と組文字があれば、この老イズリアルスには充分ですか」
「充分だろ。とにかく、三千ポンドの前払いはお前も了承した」
と冷静にエイビスが言ったが、意味は掴み切れていなかった。
イズリアルスが激怒して何か口走った。椅子から立ち上がって、金庫を開け、金の王冠と組文字のついた箱を取り出した。
ふたを開けて、石を一個つまみ出した。震える手でエイビスに渡し、テーブルのヤスリを指さして、しわがれ声で言った。
「盗みの経験から分るでしょう。本物の石かどうか、一般的な試験方法は。そのヤスリでどの石でも試してください。怖れている場合じゃないですよ。それ以上お釈迦にはならないですから」
陽気な笑顔がエイビスの顔から消えたのは、超硬ヤスリがチーズのように石をかじったときだ。
「にせものだ。偽物だ。一体どういうことだ」
とエイビスがうめいた。
イズリアルスが皮肉った。
「ルペラ男爵に
第三十六章 鹿毛外套
力の抜けたエイビスの手からヤスリが落ち、にせ宝石をテーブルにほっぽり出した。イズリアルスがずばり急所を突いた。余りにも劇的、余りにも急激で予想不能、余りにも面食らったのでエイビスはうめくばかりで、バンストンに助けを求める始末。
だが助けられたとしてもバンストンはエイビスよりも状況が良くなかった。あたかも男爵が空から長い腕を伸ばして、二人を万力で捕まえたかのようだった。どうやったのか。どうやってこんなことをやり通せたのか。
確かにこの小箱はグレイがボーン国のゼナ王女のためにベルリンから運んできたものだ。この小箱は外交官がドーバー駅からチャリングクロス駅までの車中で盗まれたものだ。そしてもちろん、この小箱はファランが仲間に渡したものだ。誰かが一杯食わせたか、王女が宝石を質に入れたか売り払い、偽物とすり替えたか。
イズリアルスが前払いした金は返さなければならない。偽物でも本物でも、どっちみち盗品であり、もしイズリアルスが尻をまくれば、ひどいことになろう。この裏にはまたしてもルペラ男爵の恐ろしい陰がちらついている。明らかにすべてを見通し、
「本当に全部偽物か」
とバンストンが希望をつなぐように、たまりかねて尋ねた。
「全くの屑です。舞台宝石として二十ポンドで売れます」
とエイビスが答えた。
バンストンが叫んだ。
「お前の言う通りだ。あの老婆が偽物だと言わなかったか。箱の中にそんな紙がなかったか。子供らが遊んでいなかったか。全部お前に伝えたぞ。お前が偽物か本物か分らなかっただけだ」
違う、とエイビスが断定した。
「あの家で五百ポンドの価値がある本物を見つけなかったですか。我々以上の切れ者に騙されたのです。さあ、イズリアル、いいか。我々はこれを本物として持ち込んだ。小箱と王冠と組文字に騙された。そうでなきゃここへ持ってくるはずがない。ああ、でも冷静になろう。誰がやったにしろ、普通の偽物をお前のような目利きにつかませようとして、こんちくしょうめ、お前まで騙されるとは。お前は石をろくに見ないで金庫に放り込んで、内金として三千ポンドを渡した」
イズリアルスが横柄に言った。
「そうじゃない、そうじゃない。ただ金を返してくれ」
「お前がルペラに会っていたなら――」
「手前が男爵に会ったと言いましたか。あなたは混乱し、まごつき、途方に暮れている。手前の見るところ、そんな状態です。確かにあなたはこうおっしゃった、我々は男爵に操られていると。愚かにも戦った。手前の金は一銭残らず返して下さい。反対したり、もらってないと言ったら、ますます悪くなりますよ。警察に一言いえば、大変なことになります」
エイビスが乱暴に言った。
「黙れ。我々が負けたのを知らないか。すってんてんだが、金は返す」
残酷だが、
少し経って、完敗の両人は水辺のしけたレストランで粗末な食事を取った。二人にはニューヨークへの渡航費用がほとんどなく、見込みもなかった。
「これからどうする?」
とバンストンが
「新大陸に合うのは若いか、銀行に残高がたくさんあるかですね。我々の年代で、しかも文無しで再出発するのは絶望的です。そのうえ、あの悪魔男爵が狡猾に手下を使って、地球の果てまで見張っています。我々は男爵に金を使わせ、不安にさせて、お気に入りの計画をぶちこわしてきました。唯一出来ることはロンドンに戻り、男爵の情けにすがることです。そうすれば虚栄心がくすぐられ、我々の再出発を許すかも知れません。どう思いますか」
バンストンは多言にならざるを得なかった。先々気にくわない。のこのこ虎穴に入るのは、ばかばかしいし、とりわけ男爵に会うのは嫌だ。
エイビスが冷静に言った。
「お好きになさい。以上が私の計画で、これを勧めます。お好きに」
とても嫌々ながらバンストンが計画に乗った。エイビスを信じていないし、良心の呵責が無かったなら、裏切ったかもしれないが、自分一人取り残されることを考えると怖くなって、うめいた。
「キミの考えで行こう。キミはいつも賢すぎる。キミの悪知恵のおかげで、大混乱だ」
*
ルペラ男爵はアムステルダム旅行とワナに満足して英国へ帰国した。ワナをエイビスとバンストンにしかけた。今や二人をあらゆる意味で支配し、完全に押さえ込み、警察へ一言いえば、これから何年も悪さは出来ないだろう。
ルペラ男爵はこの状況下、報復したいとは思わなかった。なぜならすぐ分ることだが、アイダに気配りしなければならないからだ。醜聞や有害な噂から守ってやろう。後で連中と妥協して、国外追放すれば、アイダはもう悩まされない。
あの重要な二人組が早晩接触してくることは確かだ。でもほとんど予想していなかったが、面会したいと翌日の朝食直後にきて、エイビスが召使いへ渡したメモが届いた。
「あなた、なにか嬉しそうですね」
と男爵夫人が言った。
男爵がメモを読みながら、妻へ言った。
「確かに嬉しい。事件の前段はもう説明したよな。こんなに早く悪人どもを屈服させるとは思わなかった。連中はロンドンに再び顔を見せるのは怖かっただろうなあ。あすはシティで連中への問い合わせがひっきりなしだろう」
男爵夫人が言った。
「厳しすぎてはいけませんよ。関係者の一人はあのアイダの父親なのですから」
男爵がまじめに答えた。
「父親は救出しよう。やり方は分っている。実に長い作戦だった」
男爵が陽気に口笛を吹きながら事務室に降りた。恥じて待っている二人に、親友並の気さくな挨拶をした。
「望外の喜びですね。お二人ともロンドンへ戻られましたか。アムステルダムへのご旅行はお変わりなかったでしょう。イズリアルスの豪邸では楽しまれたか。おもてなしは時々高くつきます。そうでしょう」
エイビスは椅子でもじもじ、バンストンは憂鬱に下を向いて最悪を予想していた。この会見で良いことが起こるなんて思ってもいない。
エイビスが勇気を奮い起こして、言った。
「三千ポンドかかりました。実質的にチャラになりました」
男爵がすかさず言った。
「心配ないでしょう。悲しむ必要ないでしょう、自分のお金じゃないのだから。もし自分のお金だったら――」
男爵が意味深に肩をすぼめて、続けた。
「私の情けにすがりに来ましたね。手前勝手ですが、あなた方の心はよく分りますよ。たぶん賢い判断をされました。認めても構いませんが、長い間あなた方に大いに苦しめられたのは最近のあなた方の苦しみと同じです。腰を据えて問題解決にあたり、誰が私の邪魔をいつもしているか分りました。はしょりますと、徹底的に調べた結果、あなた方の方法にたどり着きました。とても良い方法ですね。ただ残念なのは根拠となるものが盗難文書と、国際スパイ情報、それに盗難宝石、言うまでもありません。それなりに良かったのですが、そんな武器ではおおっぴらに戦えないし、長期戦にならざるを得ません。今あなた方は財産も評判も無くして、シティに再び顔出しできません。でもそれだけでは不十分です。窃盗の罪で投獄したいぐらいです。投獄出来ることはお分かりでしょう、投獄されたらここへ来られません。盗んだのが本物か偽物かは問いません。バンストン氏は知りたそうですね。残念ですが、説明はしません。説明できるまで巧妙な仕掛けはあいまいにしておきます。もう一度同じ手を使うかも知れませんから。ここの金庫から金王冠と組文字付きのモロッコ小箱を見せましょう。これこそあなた方とファランが探している物であり、あなた方が自分の所有物だと主張するものです。これこそが、諸君、本物のダイヤであり、ボーン国のゼナ王女の物です。よくご覧あれ。よだれを垂らさないように。知りたくないですか、どうやって安全にここへ来たか、グレイから盗む計画を慎重に立てたのに。これに関してもあなた方の好奇心は満たしません。手の届かない所にあることで充分でしょう。エイビスさんはある手紙に興味があるでしょう? 匿名の国王が数年前、有名な女優に書いた手紙ですよ。恥じることはありません。これらの手紙で私の石油会社を破滅させようとした。手紙は失われたとあなたは考えた。あの金庫の中に、長い鹿毛の上着がぶら下がっていますから、それを取って、私に渡して下さい。どうも。前に見たことは?」
エイビスが仏頂面で言った。
「グレイの持ち物のようだ。ああ、襟の内側に奴の名前が書いてある。でもどうして……」
男爵が言った。
「言いましょう。この上着は文字通り百万ポンドの価値があります。説明しましょう」
第三十七章 手紙
ルペラ男爵が対面の二人をじっと見た。標本を顕微鏡で見るようなそぶりは、さながら著名な科学者が新種を調べるが如し。男爵が尋ねた。
「どう、今までこの上着を調べたことは?」
エイビスが黙って肩をすくめたが、一方のバンストンは質問の意味が分らないようだ。
男爵が続けた。
「請け合います。率直になった方がずっと得ですよ。あなた方はあの手紙をとても見つけたがっている。手紙の内容をよくご存じで、その使い道も心得ており、もしその手紙をボーン国王に持って行けば、指し値で売れます。そのあと私の石油採掘権は取り上げられて、地中海石油への攻撃は大成功するでしょう。恐らくあなたが採掘権を手に入れるでしょう。そのためにはもちろん手紙が必須です。ドーバー駅とチャリングクロス駅の間でグレイを捕まえたときはうまくいったと思われた。だが残念ながら手紙はどこにも見つからなかった。大打撃だったがあきらめず、紛失手紙を必死に探した。三回も、あなたと片割れの誰かがグレイ氏の個室をあちこちしらみつぶしに探した。いつでも幸運が舞い込む機会はありました、グレイ氏を囚人状態で捕まえていたからです。あなた方は知らないと思うが、ある人がグレイ氏の居場所を突き止め、わざとそのままにして、あとで逮捕する方針にしました。あなた方を泳がせて、騙す作戦、つまり嫌疑がかかっていないと思わせたのです。あなた方が手紙を持っていないことは分っていました。持っていればすぐ動くからです。二、三日経ってこの上着を手に入れたとき、推論が確信に変わりました。みなさんはこの上着をもっと慎重に調べるべきでした」
エイビスがぶつぶつ言った。
「やった。何もなかった」
男爵が笑った。
「ハハハ、それじゃ私が単に劇的効果を狙って話しただけのようですね。二人とも何と哀れでしょう、偉大な推理作家エドガー・アラン・ポーの『盗まれた手紙』を読んでいないとは。そこには素晴らしい訳ありの教訓があり、一番良い隠し場所は一番ありふれた場所だと言うことです。エイビスさん、せめて上着のポケットを探り、裏当てに手紙がないか調べるべきでした。当然、反論としてグレイ氏は貴重品をそんなぼろ上着には入れない。大事な物がかかっていますからね。王女の領地、私の石油採掘権そして大げさに言えば英国海軍の未来もです。あまつさえ英国の運命がこの手紙にかかっています。これを知っているのはグレイ氏、ウォルタ卿、外務省、秘密諜報部長です。さて、あなたの目で確かめて下さい、外套の右側に大きなポケットがあるでしょう。中を探って、何があるか言って下さい。妙な物がありますか」
「そういうことか」
とエイビスが納得した。
「天然ゴムが裏当てされているでしょう。ポケットのふたにはボタンがあり、グレイは煙草を入れてました。極東の旅人は多くがそうします。手がかじかんだときに大いに助かります」
「でもそんな物はありま……」
男爵が笑ってさえぎった。
「ハハハ、まさにグレイ氏の狙い通りです。そのポケットをひっくり返してくれませんか」
エイビスが渋々従った。ひっくり返すとポケットの天然ゴムがそっくり出てきた。煙草入れの大きな袋になるし、丈夫な天然ゴムだ。男爵に言われてエイビスが袋を握りつぶした。
男爵が言った。
「さあ出てくるぞ。なにか気づきませんか。気づかない? じゃあ、私に貸して下さい」
男爵が袋を手にとって、更に裏返した。裏返すと、同じ材質の裏張りがもう一枚出てきて、その中に薄い洋紙に書かれた手紙が出てきた。バンストンがうめいて言った。
「我々はなんて馬鹿なんだ」
ルペラ男爵が愉快げに言った。
「そうは思いません。分るでしょう、二重ゴムなら手紙が破れません。薄い紙に書かれていますから、袋のかさが増えず分りません。隠し場所がいいですから探せなくて当然です。さあ皆さん、この手紙こそがすべての混乱と煩悩の元凶です。手紙はわずか四枚、長文じゃありませんが、欧州で一番貴重な文書のようです。英国の富の半値でも安いくらいです。でも売り物じゃありません。ある条件で書いた人へ戻すことになりましょう、そうすれば私の勝利は確実です。さて、あなた方には心付けを差し上げましょう。あなた方は手持ち金も信用もありませんが、アメリカなら簡単に乗り越えられるでしょう。これから何を見聞しようが、地中海石油は世界一素晴らしいものになるでしょう。なにしろ英国政府が保証人となり、国家権力が後についているのですから。慎重に考慮の上、これをお伝えしました。でも私は不愉快ではありません、その理由は、あなた方から非常に難しい問題を提起され、挑戦したからです。その両方が好きなのです」
エイビスが何事かつぶやいたのは感謝のようだった。素早く頭を回転させ、もう将来を見据えている。結局この会談は思ったほど面目丸つぶれじゃなかった。エイビスが言った。
「ありがとうございます。どうぞ続けて下さい。まだ終わっていません、男爵」
ルペラ男爵が答えた。
「では早速。敢えて言いますが、あなたの印象では私が親切心を欠いて、がっかりさせた。決してそんなことはありません。良くあることですが、悪党も減刑される場合があり、それは悪党に依存する無実の人を害する場合です。たとえば妻であったり、子供だったり。この場合子供、つまり娘です。バンストンさん、分りますか」
バンストンがぱっと赤面して訊いた。
「私の娘のことか」
男爵が厳粛に言った。
「そうです。全く偶然に身元を間違われ、あなたの娘さんは陰謀に巻き込まれてしまい、私がこの半時間で解放しました。娘さんはこの世で頼る人も無く、家出理由が嫌な結婚から逃げるためでした。娘さんの口から直接聞きました。そしてエイビス氏の感情を害することなく、うまく逃げました。娘さんは強い信念と美貌、知性と高潔、それに大胆な勇気を持っています。我々はどれだけ借りがあるか計り知れません。まさしく娘さんがグレイ氏を見つけました。娘さんがこの上着を川べりの家から持ち出しました。娘さんが命を危険にさらし再度グレイ氏を発見しました。バンストンさん、せめて娘さんの恋人が同時に見つかって喜ぶべきですね。奇遇ですが娘さんとグレイはずっと昔に知り合っています。奇妙なことに、あなたが多くの無実な人々や私を破滅させようとしている最中、あなたの娘さんが神の先兵に選ばれて、あなたをやっつけて全財産を奪うように行動したことです。私がこれを言うのは娘さんの将来が幸せになると確信してのことです。グレイ氏は高く評価されています。外務省で出世するでしょうし、今は裕福です。この話であなたが喜ぶかどうかは分りません。父性本能があれば喜ぶべきでしょう」
バンストンが恥じてうなだれた。エイビスより大恥をさらした感じだった。つぶやいた。
「分った。ほかに言うことがなければ――」
ちょっと待って下さい、と制した男爵の顔は厳粛で、目が光っている。
「まだ終わっていません。二人とも勘違いして退去させたくありません。アメリカではまっさらな経歴で出直しされると思ったら間違いです。長い間、諜報部のたんこぶがあなた方であり、英国諜報部だけでなく欧州諜報部もそうです。あなた方は愛国心という点で、良心の呵責に悩むことはないし、網にかかる奴は間抜けとみています。自らの利益になれば自国を平気で裏切り、長年成功してきました。シティの事務所は巧妙な目くらましであり、手下を使う手法には賞賛します。でも疑惑の指を差されるのは避けられません。何ヶ月もずっと諜報部員が見張っていました。同じ部屋で昼食や夕食をした人物に諜報部長がおり、まったく気づかれていません。慎重に行動し、あなた方に対抗してきたと言えば充分でしょう。あなた方の悪業は未遂なので、法廷で立証できないでしょう。でも法廷に引っぱり出さない理由はほかにもあって、それこそあなた方の運というものです。そのうえ私も妻も、娘さんが大好きなので出来るだけ心痛を与えたくありません。さてお二人はニューヨークかどこかへ行かれるとか。ちっとも構いません。どこへ行こうが追跡され、秘密警察が調べます。昼夜監視され、年を取って悪さが出来なくなるまで続けます。身ぎれいに生活している限り、安全です。もし――」
書斎の扉が開いて召使いが入ってきて、告げた。
「紳士がお見えでございます。お約束だそうで。ハースコート様とおっしゃいました」
第三十八章 大団円
エイビスの口元に笑みの陰がちらついた。エイビスの心にハースコートが何回もよぎったのは会談の最後の時だった。心に引っかかったのは、ハースコートが現在の不快な立場に何か関わっているらしい。もしそうなら、俺の出番が間違いなく来る。
男爵が言った。
「キミらの友人だと思う。けさ電話してこの時間に来るようにお願いした。幸いにも来てくれたが、米国へ長期旅行する段取りだとか」
ハースコートがさっそうと部屋に入ってきたが、顔が曇り驚いたのはバンストンとエイビスを見た時だ。
「お、お邪魔かな。男爵の話では仕事の打ち合わせだったが、ほかの機会に……」
「今をおいてほかにありませんね。あなたはすぐにでもアメリカへ行かれますから」
と男爵。
「初耳ですな」
とハースコート。
「本当ですかね。なぜお宅の美しい芸術家具を処分されたのですか。なぜ木曜日にリバプールを発つ予約をされたのですか。なぜニューヨークで旧友のバンダヌープに会う電報を打たれたのですか。今日はぼけていますね」
ハースコートが真っ赤になり、激怒しているものの、少しも動揺せず、椅子にどっかと座った。
男爵が言った。
「ええ、その方がよろしい。なぜハースコート氏を呼んだか知って欲しいのです。エイビスさん、ここに来られたあなたの友人に、最近起こったことを説明して戴けませんか。ハースコートさんが自分で話す必要はありません。私も煙草を吸いながらエイビスさんのお話を聞きましょう。では、どうぞ」
決して楽しい話じゃなかったが、エイビスが何とかやり抜いた。
空恐ろしい復讐となったのは、用心深いハースコートを網に捕らえて、この先確実に訪れる運命を伝えたことだが、ただし同氏がこれ以上国際政治に手を突っ込んだ場合だ。
男爵が煙草の端を指で弾いて、言った。
「すばらしい。すばらしい。私はそんなにうまく説明できません。バンストン氏とエイビス氏はこれ以上引き留めません。ベルを鳴らして召使いに案内させます。ハースコートさんはまだ行かないで下さい。決着をつけなければなりませんので」
ハースコートもついて行きたかったようだが、心変わりして座り直した。
男爵が説明した。
「ぜひ分ってもらいたいのです。エイビス氏の説明を聞いたでしょう。幸い、エイビス氏とバンストン氏は簡単に行かせる訳がありますが、あなたには適用できません。多くの点で三人の中で最悪です。あの二人には勇気があります。あなたが直ちにこの争いを中止して、改心しなければ同じ定めになると警告しておきます。
「本当は何が欲しいのか」
とハースコートが不機嫌に訊いた。
「アーノットの身の
*
それから二日か三日経った晩、男爵と令夫人が限定夕食会を開催した。上流階級の貴人はいない。そして仕事の話は高尚な場ではしない。
でも一座に欠かせないのは、当然ながら高貴で寛容なボーン国・ゼナ王女、駐独英国大使・ウォルタ卿閣下、諜報部長・グラスゴウ殿下だ。
その他の出席者は、バレリイ嬢とジェフリ、アイダ嬢とグレイ、エルシ嬢とアーノットだった。
大騒ぎもせず、派手なパーティーでもなかったが、それぞれが満足し、三組の輝かしい瞳が幸せに輝いていた。
給仕達が退出し、デザートが食卓に上がり、
「アーノット君、今こそチャンスだよ。今こそ君のような新聞記者にとってはチャンスだ。英国大衆に何を訴える?」
アーノットが笑って言った。
「男爵、書きませんよ。もちろん公表する必要が生じれば対処します。でもないでしょう」
ウォルタ卿が言った。
「むしろ不公平じゃないか。ここにいるかわいいスパイの肖像画が、なぜ社交新聞に載らないのかな」
アイダ嬢がグレイを見て控えめに言った。
「全く同感ですわ。最近は多くのスパイがいますのに」
「でも女性はいませんよ」
と男爵夫人が応じた。
会話がばらけたので、男爵夫人が腰を折って、何事かアイダ嬢の耳にささやいた。
アイダ嬢が意味深に見返して、つぶやいた。
「ええ、父には会っていません。私がやらなくてもまあ同じ結果でしょう。やっと私の正しいことが分ったみたいで、幸せを祈るとか書いてよこしました。本音だと思います。たぶんいつか数年以内に……」
アイダの声が消え入って、一瞬横を向いた。ウォルタ卿が再開して、議論をふっかけた。
「さあ、グラスゴウ殿下、君は仕事でいろんな怪奇事件を見てきただろうが、この数週間の出来事のような劇的な舞台は作れまい。結果だけを考えたまえ。英国を救ったのは主に男爵のおかげだ。私も二度と会えないと思っていた息子を取り戻した。かてて加えて、ある魅力的な女性が、とんだ政治陰謀家から、素敵な未来の義理の娘に変身して、願わくは――」
バレリイ嬢が笑って言った。
「ふふふ、公平じゃないし、正確じゃありません。ウォルタ卿のせいで私は危険な陰謀世界に封じられました。ウォルタ卿へ話す機会もなく、私が最善を尽くしていたのは愛する人を……」
ゼナ王女が割り込まれ、銀鈴のように笑われた。
「おほほ、みなさん身勝手ですこと。自分のことしか考えていない。誰かさんのダイヤは偽物ですって。男爵がわたくしの宝石を巧妙にすり替えたとか。なんて巧妙な芸当ですこと、男爵は」
男爵が申し上げた。
「王女さまには本物の宝石が戻りました。どうかご用心下さいませ」
王女が乳白色の肩を無造作にすぼめて、質問された。
「重要ですか。私には領地がありますから、これっぽっちの宝石なんか重要じゃありません。見なさい。兄の国王が正気に戻りました。今晩聞きましたが、もう差し押さえはしないそうです。兄は私から手を引きました。最愛のルドルフと婚約したとき、祝福の言葉を与えて、結婚式に出席するそうです。例の手紙を兄に戻しても、後で何も起きません。ですから、わたくしも自分本位ですね。だって、魅力的で素敵な若者の特権じゃないでしょう。グラスゴウさんにお
グラスゴウ殿下が言った。
「どうか何も
男爵夫人が椅子から立ち上がりながら言った。
「グラスゴウ氏はとても謙虚ですね。気持ちを尊重しましょう」
パーティーの男達はたばこやコーヒーに執着しなかった。豪華な居間には、へこみ空間がいくつかあり、そこには花々が飾られており、その一つにアイダとグレイがすぐしけ込んだ。しばらく無言で座っていた。完全に理解しあっての無言だ。二人の世界に浸りきり、お互いの目を見つめ、これからの希望と幸せを考えた。グレイがアイダを引き寄せて、唇を熱く重ねて、つぶやいた。
「なんて素敵なひとときなんだろう。なんてうまくいったことだろう。わずか数日前はきみの居場所さえ知らなかった。バレリイは依然として恋人を探していたし、エルシは若さと展望もむなしく、貧しさと闘っていた。そうしたら、きみが大きな変化を起こしてくれた」
アイダが反論した。
「そうじゃありません。見えざる運命にほかなりません。個人的な理由でコベントガーデンを出たときはあなたを見つけるなんて夢にも思わなかったし、白状しても構わないけど、とても怖かったのよ。戻る勇気さえありませんでした。でも、もし……」
アイダが言葉を止めて、グレイの顔を見上げた。目には幸せの涙が流れ、唇は震えている。グレイがひしと抱きしめて、ほほを寄せて、ささやいた。
「戻ってはいけない。きみは勇敢に突き進み、僕たちの幸せを見つけ、全員を幸せにした」
これが真の総括であり、誰も否定できまい。
完